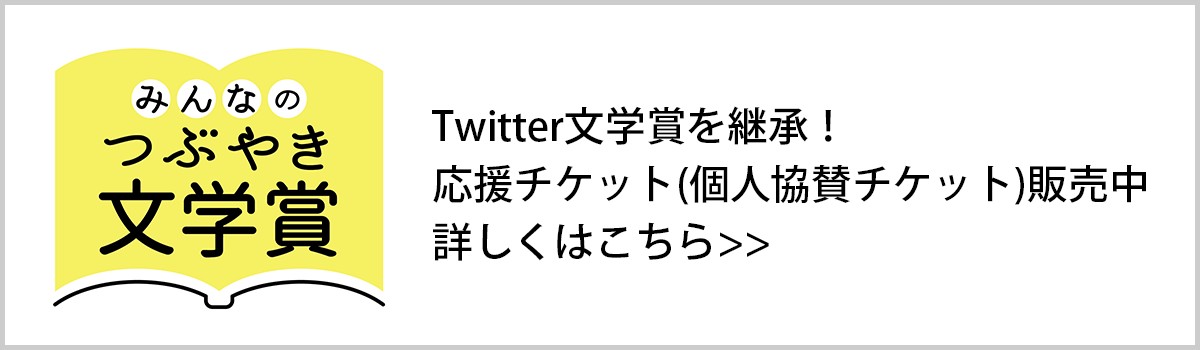『路上の陽光』(書肆侃侃房)
聖なる都、ラサにうず巻く欲望と恋心。山の麓に放牧された羊の番人たちが点在する、牧歌的な情景。中央と地方を両眼で見つめながらチベットの〝現在〟を映し出す、気鋭の小説家の短編集を前にそっと耳をすませば、変わりゆく瞬間の蠢きの音がそこかしこから聞こえてくる。
表題作に描かれているのは、日雇い労働者たちによる不器用な恋愛模様だ。ラサの一角にかかる橋で仕事を待つ、ランゼーという若い女性の赤い帽子が川に落ちた。彼女の恋人、プンナムは拾うそぶりすら見せない。彼にはじぶんの金で帽子を買い与えたいという想いがあるからだ。だが、貧富の格差が激しいラサにあって、彼の想いは空回りする。結果、ある富豪に見染められ、彼の経営するナイトクラブで働くことになったランゼーは、欲望の魔の手に堕ちる。ラサの街に資本の力で作られた新たな権力関係が、人間の純心を濁らせる、そんな悲しみを歌い上げる物語である。
こうした権力関係は、続編にあたる「眠れる川」でよりはっきりとかたちになる。政府の脱貧困政策により三輪タクシーの運転手となったプンナムに新しい恋人ができた。変化しようとする社会にしがみつく男女のかぐわしい恋が、情感豊かな文章で描かれる。だが、彼の三輪タクシーが前作に登場した富豪のBMWと衝突すると、そこに権力の優劣関係が具現化されてあらわされていく。作者の代表作『雪を待つ』同様、近代化の波の最果てで、ラサに生きる人々の内側にどんな変容が見られるのかを伝える作品たちだ。
激しい変化に呑まれながらチベットの人たちは何を感じるのか。寄宿舎を舞台に、父権的な力の権化である独裁者みたいな同級生に対し、臆病でひ弱な主人公が決闘を挑む「川のほとりの一本の木」や、20年前、社会的な条件のなかでそれぞれ就職した結果、別離を経験した元恋人同士が40歳になって再会する「四十男の二十歳の恋」。あるいは、もう羊飼いは辞めようという父に抗う少年の嘆きが轟々と響く「最後の羊飼い」。過去を過去として眺め、その上でチベットの〝現在〟を捉えるしなやかな筆力がこの小説家の魅力だ。
それを突き詰めれば、社会という共同体の喪失が生む孤独に行き着くのかもしれない。最後の作品「遥かなるサクラジマ」はチベットにルーツ持つ、移民として日本に暮らす女性が同郷出身の留学生と恋に落ちる。故郷を失い、移動をし続けた家族の過去。彼女の夫である日本人の暴力的な振る舞い。孤独を慰めてくれたチベット人男性との別れ。この世界に根無し草として生きる彼女の途方もない苦しみを描き上げたこの短編は、文句なしの大傑作だ。ここから長編が紡がれたとしてもおかしくないほどの、重厚で濃密な物語となっている。
ラシャムジャという名前を覚えておいて絶対に損はない。チベットから世界に出るべき作家の神髄を、ご堪能あれ。
週刊金曜日 2022年6月24日号
わたしたちにとって大事なことが報じられていないのではないか? そんな思いをもとに『週刊金曜日』は1993年に創刊されました。商業メディアに大きな影響を与えている広告収入に依存せず、定期購読が支えられている総合雑誌です。創刊当時から原発問題に斬り込むなど、大切な問題を伝えつづけています。(編集委員:雨宮処凛/石坂啓/宇都宮健児/落合恵子/佐高信/田中優子/中島岳志/本多勝一)