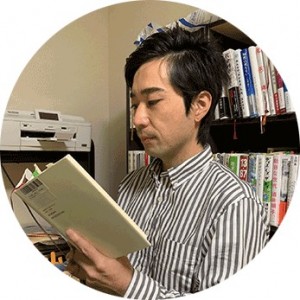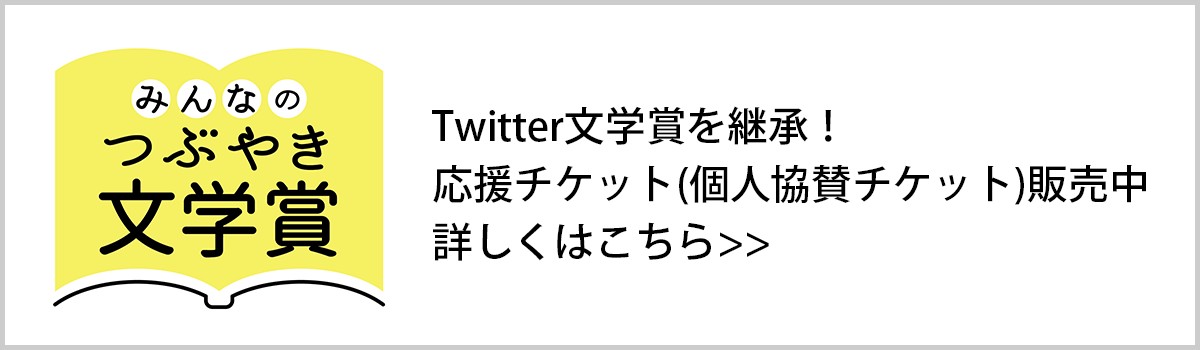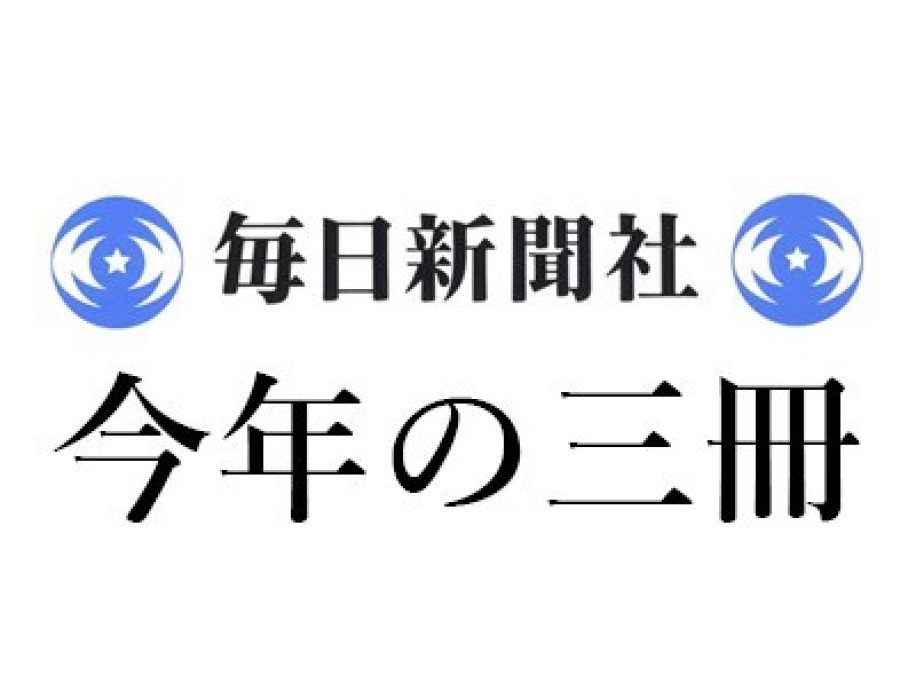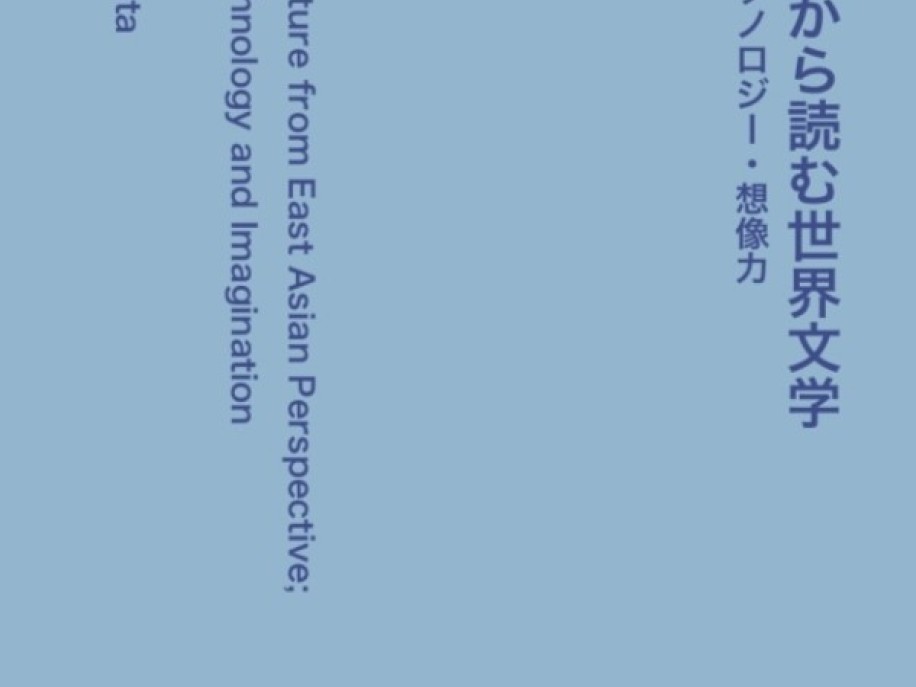書評
『少年が来る』(クオン)
アジア文学への招待(1)
去年(※本稿執筆は2023年)、韓国の大学に特別講義のために招かれたときのことです。議論が「文学と慰霊」に及ぶと、ある学生が不意に手を挙げてこう言いました。「梨泰院で亡くなった人々は、私だったかもしれないと思うんです」と。梨泰院ではその年、群衆の雪崩事故が起き、大勢の死傷者が出た。彼女の発言はどこか不思議な当事者意識を感じさせるものでした。講義後、その言葉が気になり、僕は梨泰院へ。重々しい空気を感じながら街に立つと、息を呑む光景が広がっていました。街の壁一面には、おびただしい数のメッセージカード。死を悼む言葉が、真新しい痛みを引き受けている。死者の側に立つことの意味を、その光景は語っていました。
あのとき死んだ人々は私だったかもしれない。そう考えることから始まる鎮魂とは何か。
ハン・ガン『少年が来る』はそのことを問う小説です。この作品が描くのは1980年に起きた光州事件。軍事政権に対し蜂起した民衆を暴力で弾圧したあの事件では、多数の無辜(むこ)の市民が殺されました。韓国が民主主義に向かう契機となった光州事件を、作者は緻密な調査によって作中に甦らせます。
中心となるのはトンホという少年です。〈とても平凡で誰とも混同しそうな顔〉の彼は軍の暴力の犠牲となった。本作は、いまなお癒えない社会の傷痕を物語に象るために、死者へ/からの語りの「声」を物語のなかで再生していきます。
第一章では、トンホに対する〈君〉という呼びかけのもと、彼を含む多くの人々が虐殺されたあの日の情景が立ち上がる。トンホは同じ敷地に住むチョンデを探しているうちに市民組織の一員になります。遺体を管理する二人の〈姉さん〉を手伝いながら、彼はチームのリーダーと親しくなる。濃厚な死の気配が立ち込めるなかで、闘いの果てにある希望と空虚さがせめぎ合う。〈君〉と語りかける声は、そんな空間にたたずむ無垢な少年が世界の残虐性と出会う瞬間をまざまざと映し出すのです。
トンホが命を落とした事実は次の章で、既に殺されていたチョンデの語りによって告げられます。魂となった彼の声は死んだ人々の肉体の物質性を生々しく描写する。死者の語りは腐乱する死体を見つめながら、その声でしか表出しえない怒りを響かせていく。
では、生き残った者たちは? 続く章では、闘いの生存者が以後を生きる苦しみを語る。軍から受けた地獄のような拷問。心と身体を破壊され続けた日々。子宮を破かれ、肉体を憎悪するようになった人生。作中に轟(とどろ)く「声」が問いかけます。
人間は、根本的に残忍な存在なのですか? 私たちはただ普遍的な経験をしただけなのですか? 私たちは気高いのだという錯覚の中で生きているだけで、いつでもどうでもいいもの、虫、獣、膿と粘液の塊に変わることができるのですか? 辱められ、壊され、殺されるもの、それが歴史の中で証明された人間の本質なのですか?
彼らは決して雄弁に語りはしない。証言することの葛藤に煩悶し続けながら一人ひとりは「声」を振り絞り、そして、耳を傾ける作者は語らせることのためらいのなかで言葉を紡ぐ。そこで生まれる語りの澱みが、痛みを引き受けることの難しさを突きつけるのです。
なぜ作者はそんな困難に挑むのか。実はこの語り手(そして、作者自身)はトンホの家にかつて住んでいたと言います。彼女の引っ越しと同時に入居したトンホは、つまり、あり得たかもしれない自分だった。この死者を悼む物語は、その気づきから始まったわけです。
あのとき死んだ人々は私だったかもしれない。梨泰院の痛ましさを我が事としたあの学生も、メッセージカードも、この小説も、死者との同一化という不可能性に身を置くことで乾かぬ傷口にそっと手を伸ばしている。弔いの可能性を求めて。
悲しみ。痛み。苦しみ。社会に刻まれたそれらを引き受けること。鎮魂は、その先にある。街に物語に響く無数の「声」がそのことを教えてくれるのです。
初出メディア
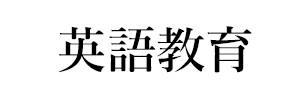
英語教育 2023年10月号
ALL REVIEWSをフォローする