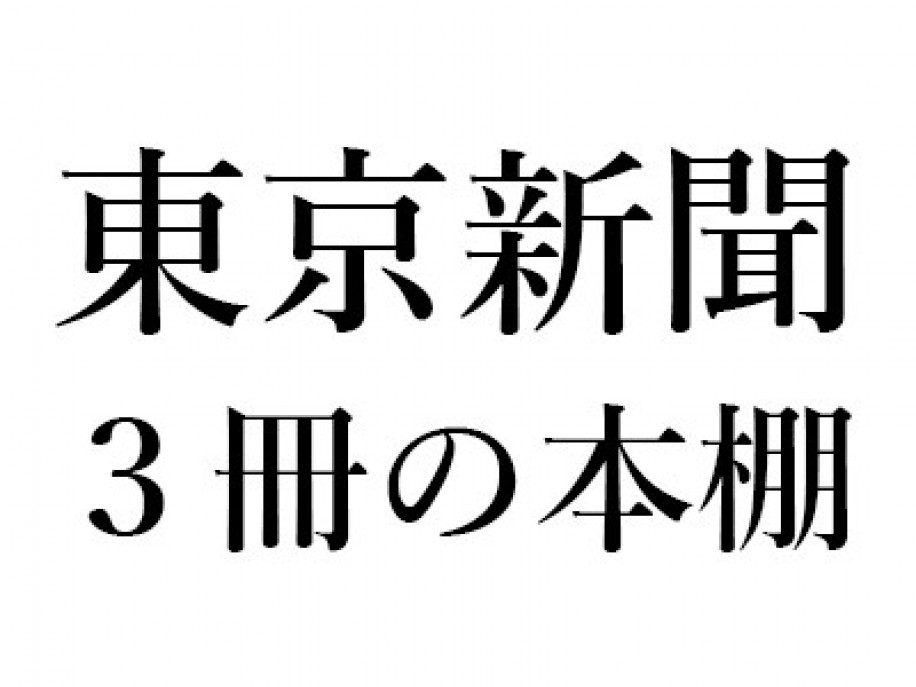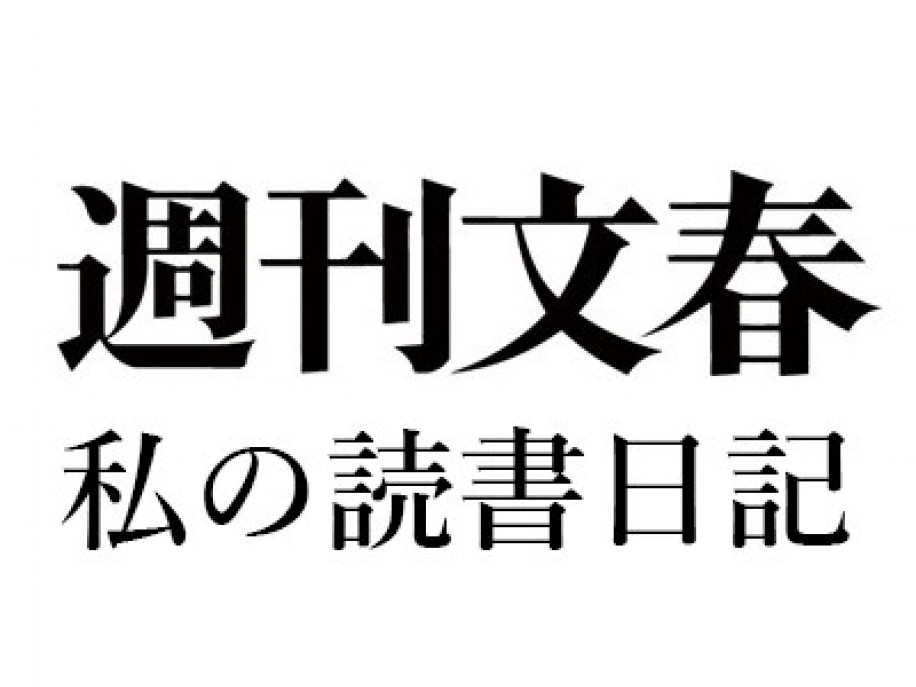書評
『街場の芸術論』(青幻舎)
「共同的な場」から生まれる作品論
不思議なものだ。内田樹を読むといつの間にか身体を使っている。目で字を追っているだけなのに、言葉と出会い、行が替わり、論が展開する過程で骨や関節に負荷がかかる。身体が「あ」とか「う」とか、言っているような気がする。もちろんこれは、著者がそういうふうに書いているのである。説得し、うんと言わせるためには、頭だけでなく身体も巻きこんだほうがいいと著者は知っている。私たちは文章を読みながら、書き手の運動や呼吸やときには休息や溜息にまで引き込まれるのだ。
こうした語りの方法は、本書の序章におさめられた二つのエッセイで内田がしようとしていること、言おうとしていることの実践でもあるだろう。
なぜ「表現の自由」は守るに値するものなのか?
残念ながら、その問いに対する答えは憲法本文には書かれていない。(中略)その答えは国民が自分の頭で考え、自分の言葉で語らなければならないことだからである。
(「民主主義をめざさない社会」傍点ママ)
まず、この傍点の多さに注目しよう。内田はしれっと素知らぬ風を装って語る人ではない。しっかりとこちらの目を見て語る。冗談を言うときもいさぎよく「どうだ、おもしろいだろ」という顔をする。彼は「人が語る」という振る舞いそのものにこだわっているのだ。だから、私たちにも「読む人」「聞く人」であることを期待する。この傍点の多さは、<語る人/聞く人><書く人/読む人>という関係性をきっちりピン止めしようとする姿勢の表れなのである。
「自分の言葉で語らなければならない」という考えも、こうした前提を踏まえて受け取った方がいい。内田によれば「自分の言葉で語ること」が可能になるためには、その言葉を差し出す相手がいる。語るとは、見知らぬ相手に自分の言葉を査定する権利を「付託する」ことなのだ。だからこそ、語るための「共同的な場」も必要となる(「言論の自由についての私見」)。
「自分の言葉で語る」というと、まずは"自分で思いついたこと""人の受け売りではないこと"といった面に注意が向きがちだが、それと劣らず重要なのはそれが行為であることなのだ。内田の言う「共同的な場」が想定するのは、言葉が"実際に言われていること"なのである。だから、タイミングも大事になる。必要とあれば何度でも言う。間違っていたら直す。語ることは継続的な作業となる。おそらくそうした場には独特の感触があり、抵抗感があり、一か八かとでもいう緊張感も生まれるだろう。
このような内田のこだわりは、"街場シリーズ"の一冊である本書の芸術論全般にも明確に出ている。著者は宮崎駿、小津安二郎、村上春樹、大滝詠一の作品を取り上げ、明確に「ファン」の立場を標榜する。たとえば村上春樹について語る前に著者はこんな宣言をする。「僕の関心事はもっぱら『村上春樹の作品からいかに多くの快楽を引き出すか』にあります。ですから、僕が村上春樹の作品を解釈し、あれこれと仮説を立てるのは、そうした方が読んでいてより愉しいからです」。
本書には、このように語るという行為を通して体感される"愉しさ"があふれている。小津映画の魅力を語る文章では、鬱屈した青年期をすごしていた内田がにわかに身を乗り出して作品に引き込まれた様子の描写に、著者の背筋の動きまで追体験できそうな気になる。宮崎駿への熱いオマージュには、解きほぐそうとしつつも解きほぐしきれないことを、むしろ喜んでいるそぶりがある。先の引用箇所を含む淡江大学での村上春樹についての講演はとりわけ力のこもったものだが、ここでも対象を"やっつける"ことが眼目なのではなく、著者と読者とが一緒になって村上の不思議さに目を見張るのである。
文学を含め、芸術作品について語るのは簡単なことではない。すでに作品にはそれ自体のロジックがあり、そこに下手に介入すれば、作品の持ち味を損なってしまう可能性もある。しかし、内田樹はあの手この手で作品を語るための「場」を作りだし、私たちの身体を聞き手/読み手として物理的に引きこむことで作品語りを可能にする。本書のキーワードである「成長」は、そんな読書を通して読者の身体が微妙に変化し、今までと違う状態に至ることも示唆しているのではないかと思ってしまうのである。
ALL REVIEWSをフォローする