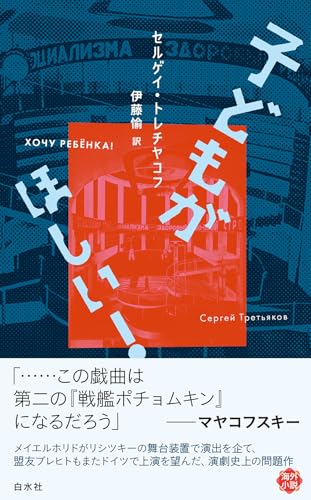書評
『ハルムスの世界』(白水社)
理知のむこうを探求する試み
ソ連初期のダニイル・ハルムスという奇妙な作家の作品集である。二〇一〇年に刊行された本の増補改訂版。ハルムスはもともと一九二〇年代末にレニングラード(現サンクトペテルブルク)でオベリウという、未来主義の流れを汲む前衛芸術家グループを率いて活動していたのだが、やがてこのグループの活動は事実上禁止され、三〇年代には出版のあてもなく、不思議な超短編小説のようなものを書き続けた。例えば、ある「赤毛の男」を描いた「青いノート №10」は、「その男には眼もなかったし、耳もなかった。髪の毛もなかった。だから、仮に赤毛と呼ばれているだけだった」と始まる。「赤毛」と言いながら、髪の毛がない? いったいこれはどんな男なのかと怪訝に思って読み進めると――
その男は話すこともできなかった。と言うのも、口がなかったからだ。その男には鼻もなかった。 それどころか、腕もなかったし、脚もなかった。それに腹もなかったし、背中もなかったし、背骨もなかったし、内臓もなかった。その男には何にもなかったのだ! だから、誰の話をしているのか、よくわからない。 もうこの男の話をするのはやめた方がよさそうだ。
あきれたことに話はこれで終わりだ。読者は啞然とするしかないだろう。言語の約束事を突き詰めると、究極的には無に辿り着かざるを得ないということだろうか。
そうかと思えば、ある行為や出来事が無意味にひたすら繰り返される場合もある。ある老婆たちは好奇心にかられて窓から身を乗り出し、立て続けに六人も窓から落ちて死んでしまう。いったいこれには、何の意味があるのだろうか? ハルムスはこの「落ちていく老婆たち」とは別の作品で、こう説明している。「私たちもこんなふうに、到達した高みから転落し、われわれの未来という名の、気の滅入るような監獄にたたきつけられるようなことがある」
ハルムスの作品では因果関係のない事象が次々に衝突したり、異常事態が理由もなく繰り返されたりして、ごく日常的な普通の世界が俄然グロテスクで不気味な様相を帯びる。そして、最終的には言語によって何かを物語るという行為そのものの土台が切り崩されてしまう。一見可笑(おか)しくて、じつはかなり恐ろしい世界観である。
このような過激な作品を書く者が、スターリン時代のソ連で容認されるはずもなかった。ハルムスは一九四一年八月に密告に基づいてスパイ容疑で逮捕され、翌年の二月に刑務所の精神病棟で亡くなった。第二次世界大戦のさなか、ちょうどレニングラードがドイツ軍に完全包囲され、おびただしい凍死者と餓死者を出した冬のことだった。
実に不可解な作家だが、ペレストロイカ後のロシアで再発見され、ブームになって、今では広く読まれている。理性を超えた不条理の感覚が現代人にアピールするのだろうか。ちなみに、最近は日本でも、小澤裕之氏によって『理知のむこう ダニイル・ハルムスの手法と詩学』(未知谷、二〇一九年)という本格的な研究書さえ書かれている。これは先行研究の徹底的な調査と作品の緻密な読解に基づいて、ハルムスのナンセンスな言語実験を、「理知のむこう」を果敢に探求する試みとして詳細に分析したものである。
ALL REVIEWSをフォローする