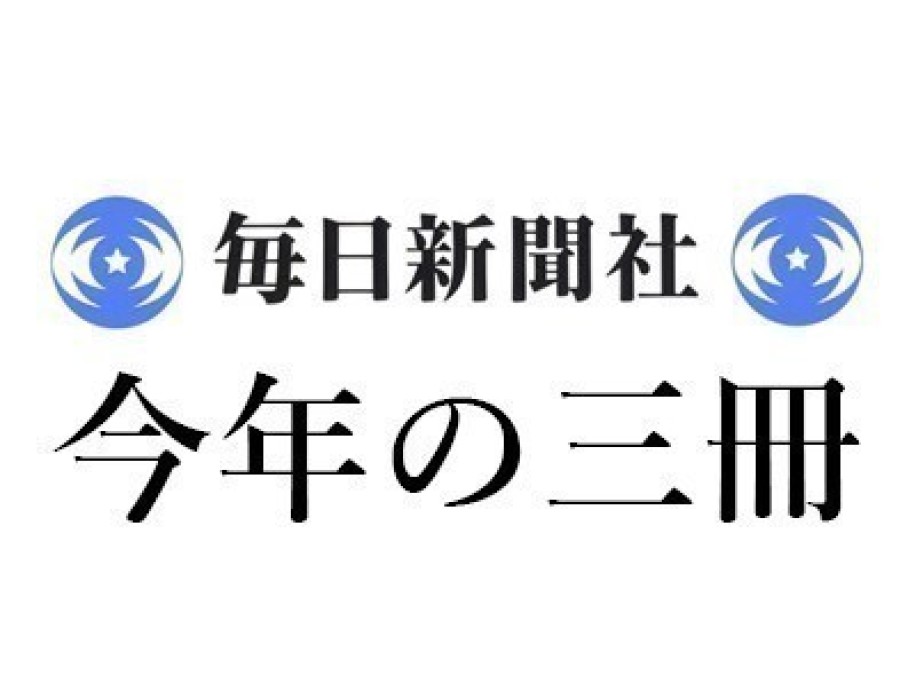自著解説
『PKOの思想―その実践を紡ぎだすもの―』(名古屋大学出版会)
紛争から平和への移行を包括的に支援する平和維持活動(PKO)。その名前は知っていても、どこか自分とは縁遠い活動のように感じている人も多いのではないでしょうか。
PKOはそもそもなぜ、何を目指して行われるのか? 国際政治学が専門の山下光先生は、こうした根本的な「問い」に立ち返って考えることが必要だと語っています。2月に刊行された著書『PKOの思想』について、書き下ろしの自著紹介を寄稿していただきました。
もちろん、一方が他方の政体を崩壊ないし降伏させ、その後占領統治するようなケースがないわけではない。2003年のイラク戦争はこれに近いだろう。だがその他ほとんどの場合、国際機構、地域機構あるいは第三国が間に入った形で何らかの停戦がまず合意され、その後和平交渉が進められてきた。この「合意による終戦」は、ひとつの国際規範になっていると言えるのである。
ただし、問題はその後である。紛争当事者が「合意による終戦」に沿った行動をしていたとしても、紛争が再発しないとは限らない。停戦が「合意」されているのであれば「維持」する必要があり、その国ないし国家間が再び武力紛争に陥らないようにする必要がある。また、紛争後の社会はさまざまな、そして膨大な復興ニーズを抱えてもいる。そうしたニーズに応えつつ、紛争後社会の復興を支援することも国際社会には期待されている。「合意による終戦」と、その前後にわたる国際支援とはセットなのである。
停戦直後から展開され、紛争から平和への移行を包括的に支援することが多い平和維持活動(PKO)は、こうした国際支援に欠かせない一部である。したがって、現代の国際社会が「合意による終戦」を規範とする限り、PKOが本質的な意義を失うことはないと私は思う。それは、PKOへの関心を持ち続けることの意味でもある。
しかし、こうした意義をPKOに認めるとしても、PKOにはどこか疎遠な印象を持っている人が多いのではないだろうか。その疎遠さとは、PKOをどこかで誰かがやっている類の、したがって自分にはとりあえずのところ関係のない活動と捉えるような感覚のことである。
この感覚は、活動地域の遠さ、派遣される要員の多くが軍事要員であること、国連や地域機構の機能への懐疑心など、さまざまな要因に由来する。確かに、PKOミッションの展開地域(その多くはアフリカ大陸に位置する)も、軍事組織や軍人も、また国連の機能や意思決定も、多くの人にとってそれ自体で身近なものではないかもしれない。
他方で、この疎遠さには、PKOの普段の論じられ方も関係しているように思われる。PKOが論じられる場合、実際に行われているミッションを取り上げ、その設立経緯、活動内容や実施上の課題を分析することが非常に多い。もちろん、そうした議論や研究はPKOのあり方や運営に示唆を与えるので重要ではある。だが、PKOをそもそも疎遠と思っている人には、ミッションの詳細が論じられているものはあまりピンと来ないのではないだろうか。
こうした疎遠な感覚を軽減するためには、その前の段階の、より根本的な議論が必要だと思う。すなわちPKOはそもそもなぜ行われるのか、そして何を目指して行われるのか、といった議論である。こうした「そもそもの問い」をもう少しじっくりと考える余地も必要もあるのではないか。そう考えたのが、本書を執筆したきっかけである。
そして、これら「そもそもの問い」を考えるために、本書ではPKOを国際場裏でおきる現象ないし出来事としてとらえる見方を取っている。PKOという活動があり、実際に行われていることを前提として議論を進めるのではなく、どうしてそうした活動=現象が生じるのかを考えるのである。そしてそのように捉えると、現代の国際関係におけるいくつかのアクターが、ある目的のために、あるやり方によって協働することで発生する活動としてPKOを見ることが可能になってくる。本書の骨子をなす「協力」「国家」「平和」という概念を深堀りすることにしたのは、PKOにこうして参画するアクターの思考の中で、それらの概念が躍動しているように思えたためである。
最後に、本書のタイトルとなっている「思想」という言葉について少し記しておきたい。先にも述べたように、本書における思想の意味は、特段難しいものではない。国際政治のアクターが何かを行う時に、その行動を方向づけたり動機づけたりする実践的な概念とその運動を集約的に表現するのに、「思想」という言葉を使っているだけのことである。
したがって、本書における「思想」は、例えば政治哲学や社会思想などで使われる際のような重厚な含みを持っているわけではないし、思想家や哲学者の議論をとりたてて引き合いに出しているわけでもない。だが、少なくとも私にとっては、PKOのような極めて実践的・政策的な活動分野の中で生き生きと動いている「協力」「国家」「平和」をめぐる思考の総体は、「思想」として取り上げるに足る価値があるように思われるのである。
そうした「思想」の視点からPKOをめぐる「そもそもの問い」にアプローチすることで、PKOとそれを考えるわれわれとの間の距離感も変わってくるように思う。そうすれば、もしかしたらアフリカも、国連も、軍事組織も、それまでとは違ったものとして見えてくるかもしれない。さらに言えば、「国家」が変貌し、「協力」や「平和」とは逆の方向に赴きつつあるように見える国際関係の流れについても、考察を深めることにつながるかもしれない。本書がそうしたきっかけになればと思う。
[書き手]山下光(静岡県立大学国際関係学部教授)
PKOはそもそもなぜ、何を目指して行われるのか? 国際政治学が専門の山下光先生は、こうした根本的な「問い」に立ち返って考えることが必要だと語っています。2月に刊行された著書『PKOの思想』について、書き下ろしの自著紹介を寄稿していただきました。
PKOをめぐる「そもそもの問い」を考える
戦争の終わりと国際支援
現代の戦争のほとんどは何らかの合意によって終わる。例えば、レバノン(2024年11月27日)やガザ(2025年1月15日)で停戦が合意されたのは、本書の作業が最終段階を迎えていた時期であったし、ウクライナ・ロシア間の停戦交渉もさまざまなルートで試みられてきた(2025年1月末現在)。周知のとおり、これらに関係する紛争当事者のうち、少なくとも一部は敵のせん滅に向けた意思を明らかにしている。その意味でいえば、停戦に向けた動きがあることは意外にすら映るかもしれない。もちろん、一方が他方の政体を崩壊ないし降伏させ、その後占領統治するようなケースがないわけではない。2003年のイラク戦争はこれに近いだろう。だがその他ほとんどの場合、国際機構、地域機構あるいは第三国が間に入った形で何らかの停戦がまず合意され、その後和平交渉が進められてきた。この「合意による終戦」は、ひとつの国際規範になっていると言えるのである。
ただし、問題はその後である。紛争当事者が「合意による終戦」に沿った行動をしていたとしても、紛争が再発しないとは限らない。停戦が「合意」されているのであれば「維持」する必要があり、その国ないし国家間が再び武力紛争に陥らないようにする必要がある。また、紛争後の社会はさまざまな、そして膨大な復興ニーズを抱えてもいる。そうしたニーズに応えつつ、紛争後社会の復興を支援することも国際社会には期待されている。「合意による終戦」と、その前後にわたる国際支援とはセットなのである。
PKOをめぐる「そもそもの問い」
停戦直後から展開され、紛争から平和への移行を包括的に支援することが多い平和維持活動(PKO)は、こうした国際支援に欠かせない一部である。したがって、現代の国際社会が「合意による終戦」を規範とする限り、PKOが本質的な意義を失うことはないと私は思う。それは、PKOへの関心を持ち続けることの意味でもある。しかし、こうした意義をPKOに認めるとしても、PKOにはどこか疎遠な印象を持っている人が多いのではないだろうか。その疎遠さとは、PKOをどこかで誰かがやっている類の、したがって自分にはとりあえずのところ関係のない活動と捉えるような感覚のことである。
この感覚は、活動地域の遠さ、派遣される要員の多くが軍事要員であること、国連や地域機構の機能への懐疑心など、さまざまな要因に由来する。確かに、PKOミッションの展開地域(その多くはアフリカ大陸に位置する)も、軍事組織や軍人も、また国連の機能や意思決定も、多くの人にとってそれ自体で身近なものではないかもしれない。
他方で、この疎遠さには、PKOの普段の論じられ方も関係しているように思われる。PKOが論じられる場合、実際に行われているミッションを取り上げ、その設立経緯、活動内容や実施上の課題を分析することが非常に多い。もちろん、そうした議論や研究はPKOのあり方や運営に示唆を与えるので重要ではある。だが、PKOをそもそも疎遠と思っている人には、ミッションの詳細が論じられているものはあまりピンと来ないのではないだろうか。
こうした疎遠な感覚を軽減するためには、その前の段階の、より根本的な議論が必要だと思う。すなわちPKOはそもそもなぜ行われるのか、そして何を目指して行われるのか、といった議論である。こうした「そもそもの問い」をもう少しじっくりと考える余地も必要もあるのではないか。そう考えたのが、本書を執筆したきっかけである。
そして、これら「そもそもの問い」を考えるために、本書ではPKOを国際場裏でおきる現象ないし出来事としてとらえる見方を取っている。PKOという活動があり、実際に行われていることを前提として議論を進めるのではなく、どうしてそうした活動=現象が生じるのかを考えるのである。そしてそのように捉えると、現代の国際関係におけるいくつかのアクターが、ある目的のために、あるやり方によって協働することで発生する活動としてPKOを見ることが可能になってくる。本書の骨子をなす「協力」「国家」「平和」という概念を深堀りすることにしたのは、PKOにこうして参画するアクターの思考の中で、それらの概念が躍動しているように思えたためである。
なぜ思想なのか?
最後に、本書のタイトルとなっている「思想」という言葉について少し記しておきたい。先にも述べたように、本書における思想の意味は、特段難しいものではない。国際政治のアクターが何かを行う時に、その行動を方向づけたり動機づけたりする実践的な概念とその運動を集約的に表現するのに、「思想」という言葉を使っているだけのことである。したがって、本書における「思想」は、例えば政治哲学や社会思想などで使われる際のような重厚な含みを持っているわけではないし、思想家や哲学者の議論をとりたてて引き合いに出しているわけでもない。だが、少なくとも私にとっては、PKOのような極めて実践的・政策的な活動分野の中で生き生きと動いている「協力」「国家」「平和」をめぐる思考の総体は、「思想」として取り上げるに足る価値があるように思われるのである。
そうした「思想」の視点からPKOをめぐる「そもそもの問い」にアプローチすることで、PKOとそれを考えるわれわれとの間の距離感も変わってくるように思う。そうすれば、もしかしたらアフリカも、国連も、軍事組織も、それまでとは違ったものとして見えてくるかもしれない。さらに言えば、「国家」が変貌し、「協力」や「平和」とは逆の方向に赴きつつあるように見える国際関係の流れについても、考察を深めることにつながるかもしれない。本書がそうしたきっかけになればと思う。
[書き手]山下光(静岡県立大学国際関係学部教授)
ALL REVIEWSをフォローする