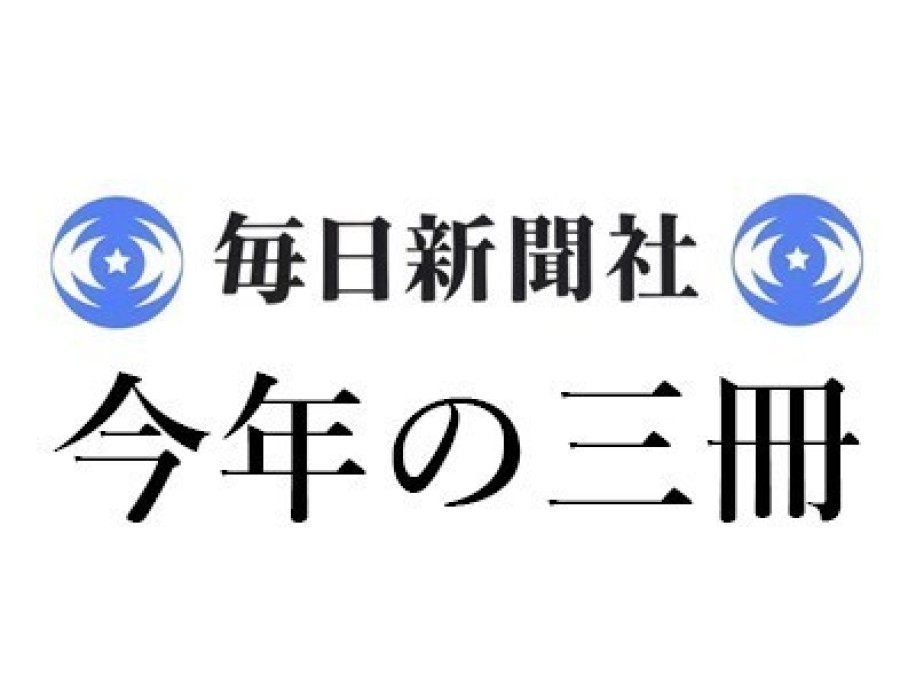自著解説
『善意の帝国―イギリスのフィランスロピーと南アフリカ―』(名古屋大学出版会)
社会的弱者に救いの手を差し伸べる「善意」と、奴隷や先住民らを抑圧し搾取する「帝国」――一見相反する言葉が組み合わされたタイトルに込められた意味とは? 移民政策や多文化共生という課題に世界が直面する今、私たちは歴史から何を学ぶことができるのでしょうか。昨年12月に刊行された『善意の帝国』の著者・大澤広晃先生による書き下ろしの自著紹介を特別公開いたします。
「人道」という言葉について、最近では、イスラエルに侵攻されたガザで、戦火に苦しむパレスチナ人に食料や医療を提供する「人道支援」がマスメディアでよく取り上げられる。苦境にあって自らを守ることができない「弱者」を保護し、その生命を救おうとする企ては、概して好意的に評価される。こうした行為、およびそれらに通底する心構えは、「人道主義(humanitarianism)」と呼ばれる。
対照的に、「帝国」という語は、もっぱらネガティヴな意味で用いられる。私たちは、帝国主義や帝国支配という言葉から、強者による弱者の抑圧や搾取を連想するだろう。こう見てゆくと、「帝国の人道主義」とは、相反する言葉を組み合わせた、形容矛盾ともいうべき表現であるように思われる。本書はこの、イギリス帝国における人道主義を考察するものである。
私がこのテーマに関心をもった理由は、支配と保護の逆説的関係に魅了されたことに加え、人道主義という言葉に「捉えどころのなさ」を感じたからである。人道主義の定義は国語辞典にも載っているが、その説明はいかにも抽象的で、どうも腑に落ちない。ひとつの理由は、この言葉が翻訳語だからであろう。人道主義は、近代西洋社会で育まれた独自の感性に由来する思想・行為であり、日本社会で日本語を母語として育ってきた者(少なくとも私)には本来馴染みがない。そのような言葉の意味を直観的に捉えるのは難しい。ましてやそれが帝国という文脈で使用されるとなると、なおさらだ。
戸惑いながら史料を読んでいくと、あることに気がついた。現代の歴史家が人道主義と呼ぶ思想や行為が、史料のなかでは、(少なくともある時期までは)「フィランスロピー(philanthropy)」という言葉で表されているのである。フィランスロピーとは、類似語であるチャリティとともに、民間による社会的弱者(貧民など)の救済を意味し、近現代イギリス社会を下支えする重要な役割を担っていた。フィランスロピーが広く福祉に関わる事柄であることを踏まえ、私は、イギリス帝国における人道主義という問題を、当時の福祉やそれと関連するさまざまな思想・運動との関係で考えてみようと思い立った。このような視点からの分析は、これまで十分になされてこなかった。そして、自分自身の問題意識を明確にするために、人道主義に代わりあえて「帝国フィランスロピー」という用語を使い、イギリス帝国の「善意」とされるものの実相を明らかにしようとした。
分析の対象は、19〜20世紀転換期から20世紀前半にかけての南アフリカである。この時期の南アは、後のアパルトヘイトにつながる人種隔離の制度化が進み、支配される側のアフリカ人は差別や貧困に苦しんでいたのだが、帝国フィランスロピスト/人道主義者は、まさにそのようなアフリカ人の境遇に強い関心を寄せていた。本書では、「アフリカ人の労働」を主題に据え、イギリスと南アそれぞれに拠点を置くフィランスロピー団体――イギリスを拠点とするのは、今日の反奴隷制インターナショナルである――の動向にそくして、帝国フィランスロピーを検討した。その際、両団体もその一部であるところのトランスナショナルな人道主義者のネットワークに注目し、問題をグローバルな文脈にも位置づけながら分析した。
本書で明らかになるのは、帝国フィランスロピーが、同時代のイギリスにおける福祉およびそれに関連する思想・運動(例えば、労働運動、ニュー・リベラリズム、社会主義など)に規定される部分が実際に大きかったこと、そして、アフリカ人を救済しようという試みが人種隔離と密接に関係していたということである。後者について言葉を足すと、帝国フィランスロピストたちは、白人による労働搾取からアフリカ人を保護するためには両者の居住空間を分離する必要があると主張し、人種隔離イデオロギーの形成に大きく貢献した。むろん、その主張は時代とともに変化したが、アフリカ人労働者の居住や移動を制御しようとする姿勢は、その後のアパルトヘイトにも通ずるものがあった。「善意」=帝国フィランスロピーは、植民地支配を批判するものであるとともに、それを補完する役割も担っていたのである。
さらに、南アを対象とする帝国フィランスロピーの歴史は、日本のこれからを考えるうえでも有益だ。帝国フィランスロピストたちはある時期まで、植民地南アで白人(支配者)とアフリカ人(被支配者)が安定的な関係を取り結ぶための方策として、人種隔離とアフリカ人の移動の管理を提言していた。違う角度から見てみると、この問題は、移民管理と多文化共生という今日的課題と相似形にあることに気づく。移民と多文化共生はいまやグローバル・イシューであり、昨今の欧米諸国における政治変動の一因ともなっている。これは、対岸の火事ではない。いまや「移民国家」となった日本もまた、この問題を真剣に検討すべき時期に来ている。その際、「弱者」に対する「善意」が人種隔離/アパルトヘイトに帰結した歴史は、多くの示唆を与えてくれるだろう。「いま、ここ」も念頭に、本書をお読みいただけると幸いである。
[書き手]大澤広晃(法政大学文学部史学科准教授)
弱者救済と帝国支配の切り離せない関係 英と南アの歴史から考える
帝国の人道主義?
近年の歴史研究で大きな関心を集めるテーマのひとつに、「帝国の人道主義」がある。とくにイギリス帝国史研究においては、このテーマをめぐって活発な議論が展開されているが、「帝国」の「人道主義」という言葉の組み合わせには、戸惑う人もいるのではないだろうか。「人道」という言葉について、最近では、イスラエルに侵攻されたガザで、戦火に苦しむパレスチナ人に食料や医療を提供する「人道支援」がマスメディアでよく取り上げられる。苦境にあって自らを守ることができない「弱者」を保護し、その生命を救おうとする企ては、概して好意的に評価される。こうした行為、およびそれらに通底する心構えは、「人道主義(humanitarianism)」と呼ばれる。
対照的に、「帝国」という語は、もっぱらネガティヴな意味で用いられる。私たちは、帝国主義や帝国支配という言葉から、強者による弱者の抑圧や搾取を連想するだろう。こう見てゆくと、「帝国の人道主義」とは、相反する言葉を組み合わせた、形容矛盾ともいうべき表現であるように思われる。本書はこの、イギリス帝国における人道主義を考察するものである。
人道主義に福祉の視点から切り込む
イギリス帝国における人道主義とは、具体的に何を指すのか? 代表的な事例は、18世紀後半から興隆した奴隷貿易や奴隷制への反対運動である。その後、19世紀に入ると、帝国内外で、主に白人の手により抑圧や搾取を受けた非白人たちの保護を訴える運動が登場してくる。これらも人道主義と呼ばれる。私がこのテーマに関心をもった理由は、支配と保護の逆説的関係に魅了されたことに加え、人道主義という言葉に「捉えどころのなさ」を感じたからである。人道主義の定義は国語辞典にも載っているが、その説明はいかにも抽象的で、どうも腑に落ちない。ひとつの理由は、この言葉が翻訳語だからであろう。人道主義は、近代西洋社会で育まれた独自の感性に由来する思想・行為であり、日本社会で日本語を母語として育ってきた者(少なくとも私)には本来馴染みがない。そのような言葉の意味を直観的に捉えるのは難しい。ましてやそれが帝国という文脈で使用されるとなると、なおさらだ。
戸惑いながら史料を読んでいくと、あることに気がついた。現代の歴史家が人道主義と呼ぶ思想や行為が、史料のなかでは、(少なくともある時期までは)「フィランスロピー(philanthropy)」という言葉で表されているのである。フィランスロピーとは、類似語であるチャリティとともに、民間による社会的弱者(貧民など)の救済を意味し、近現代イギリス社会を下支えする重要な役割を担っていた。フィランスロピーが広く福祉に関わる事柄であることを踏まえ、私は、イギリス帝国における人道主義という問題を、当時の福祉やそれと関連するさまざまな思想・運動との関係で考えてみようと思い立った。このような視点からの分析は、これまで十分になされてこなかった。そして、自分自身の問題意識を明確にするために、人道主義に代わりあえて「帝国フィランスロピー」という用語を使い、イギリス帝国の「善意」とされるものの実相を明らかにしようとした。
分析の対象は、19〜20世紀転換期から20世紀前半にかけての南アフリカである。この時期の南アは、後のアパルトヘイトにつながる人種隔離の制度化が進み、支配される側のアフリカ人は差別や貧困に苦しんでいたのだが、帝国フィランスロピスト/人道主義者は、まさにそのようなアフリカ人の境遇に強い関心を寄せていた。本書では、「アフリカ人の労働」を主題に据え、イギリスと南アそれぞれに拠点を置くフィランスロピー団体――イギリスを拠点とするのは、今日の反奴隷制インターナショナルである――の動向にそくして、帝国フィランスロピーを検討した。その際、両団体もその一部であるところのトランスナショナルな人道主義者のネットワークに注目し、問題をグローバルな文脈にも位置づけながら分析した。
本書で明らかになるのは、帝国フィランスロピーが、同時代のイギリスにおける福祉およびそれに関連する思想・運動(例えば、労働運動、ニュー・リベラリズム、社会主義など)に規定される部分が実際に大きかったこと、そして、アフリカ人を救済しようという試みが人種隔離と密接に関係していたということである。後者について言葉を足すと、帝国フィランスロピストたちは、白人による労働搾取からアフリカ人を保護するためには両者の居住空間を分離する必要があると主張し、人種隔離イデオロギーの形成に大きく貢献した。むろん、その主張は時代とともに変化したが、アフリカ人労働者の居住や移動を制御しようとする姿勢は、その後のアパルトヘイトにも通ずるものがあった。「善意」=帝国フィランスロピーは、植民地支配を批判するものであるとともに、それを補完する役割も担っていたのである。
「いま、ここ」を考えるために
「帝国の善意」は、さまざまな遺産を残した。イギリスでは20世紀後半以降、発展途上国への援助に対する関心が高まっていくが、それは帝国フィランスロピーの伝統に部分的に依拠している(ゆえに帝国支配の過去と切り離せない)。南アでは1990年代にアパルトヘイトが崩壊し、アフリカ民族会議(ANC)が政権を握った。だが、ANC政権がネオリベラリズムを受け入れた結果、経済格差は縮まらず、いまだに多くのアフリカ人が貧困と失業にあえいでいる。そうしたなかで、ANC指導者たちは国民に対して勤労精神と自助努力を説いているが、その根底には、帝国フィランスロピーをひとつの媒介として広まった近代イギリスの福祉思想があるように思われる。さらに、南アを対象とする帝国フィランスロピーの歴史は、日本のこれからを考えるうえでも有益だ。帝国フィランスロピストたちはある時期まで、植民地南アで白人(支配者)とアフリカ人(被支配者)が安定的な関係を取り結ぶための方策として、人種隔離とアフリカ人の移動の管理を提言していた。違う角度から見てみると、この問題は、移民管理と多文化共生という今日的課題と相似形にあることに気づく。移民と多文化共生はいまやグローバル・イシューであり、昨今の欧米諸国における政治変動の一因ともなっている。これは、対岸の火事ではない。いまや「移民国家」となった日本もまた、この問題を真剣に検討すべき時期に来ている。その際、「弱者」に対する「善意」が人種隔離/アパルトヘイトに帰結した歴史は、多くの示唆を与えてくれるだろう。「いま、ここ」も念頭に、本書をお読みいただけると幸いである。
[書き手]大澤広晃(法政大学文学部史学科准教授)
ALL REVIEWSをフォローする