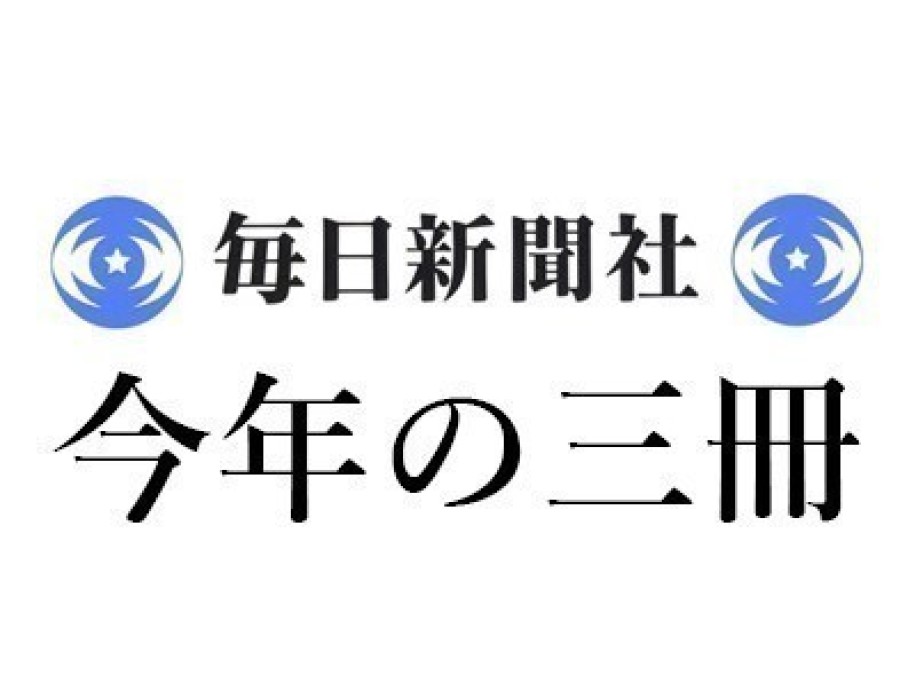後書き
『グローバル・ヒバクシャ』(名古屋大学出版会)
アメリカ史、科学史、核の文化史を専門とし、広島平和研究所(広島市立大学)で長年研究・教育に携わってきたロバート・A・ジェイコブズ。その集大成である著書『グローバル・ヒバクシャ』の日本語版がこのたび刊行されました。英語版(2022年)はすでに欧米で話題となり、ヨーロッパの映像作家たちによってドキュメンタリーも準備されています。この本の読みどころを、竹本真希子氏の「訳者あとがき」からご紹介します。
ジェイコブズはグローバル・ヒバクシャが生まれていく背景や、核保有国が被害者を選定した論理を、科学や軍事、そしてヒバクシャのコミュニティのそれぞれから丁寧に追う。本書の各所に登場する、マーシャル諸島民、アボリジナル、福島の住民、サーミ、ナバホ族、カザフスタンのポリゴンや仏領ポリネシア、ネバダなどの核実験場近郊に住むヒバクシャたちに実際に会って聞き取ったオーラル・ヒストリーも貴重なものである。原発事故を「スローモーションの核戦争」と位置づけた前著『ドラゴン・テール』(凱風社、2013年)にすでにこの問題意識は見られるが、その後、広島で多くの被爆者と議論を重ねた経験と、世界各地のヒバクシャのコミュニティでのフィールドワーク、そしてとりわけ2011年の東京電力福島第一原子力発電所での事故を日本で経験したことが、彼に核の植民地主義的特徴をあらためて確信させたことは、著者自身が述べているとおりである。本書は、科学史、軍事史、環境史の先行研究を広く参照しながら、現代社会のあり方に対する鋭い感覚と長年にわたるフィールドワークの成果に基づき、グローバルかつ複合的に冷戦史を捉え直している。そして放射性廃棄物を生み出し続け、この負の遺産を未来世代に残すことになった我々に対して、その自覚と責任を問うているのである。
原書については、2022年に出版されてから多くの書評が書かれており、とくに「限定核戦争としての冷戦」という視点に対する評価は高い。そしてジェイコブズ自身が精力的に世界各地のメディアに登場し、広島からヒバクシャについて発信しており、本書はとくに欧米で話題になっている。現在、この書をもとにしたドキュメンタリー番組がヨーロッパの映像作家たちによって準備され、2025年夏に放映される予定だという。日本被団協の平和賞受賞によりヒバクシャに対する関心が高まっている中、ジェイコブズの研究はより一層関心をもって読まれることになるだろう。
[書き手]竹本真希子(広島市立大学広島平和研究所准教授)
広島・長崎だけではない? 不可視化されてきた世界のヒバクシャの実態
限定核戦争が行われた時代
本書『グローバル・ヒバクシャ』の最大の特徴は、冷戦期を「限定核戦争が行われた時代」と位置づけた視角にある。多くの人々は広島と長崎への原爆投下以来、戦時下での核兵器使用は起きておらず、第三次世界大戦は回避されてきたと考えている。だが、二千回以上の大気圏内核実験やウラン採掘、原発事故、そしてこれらから生まれた放射性廃棄物から発生する放射線や放射性物質は、冷戦期を通じて世界各地で多くの人々に危害を加えてきた。その被害者は核保有国が勝手に選んだ人々、つまりそれぞれの国における少数民族や政治的発言力の弱い人々、旧植民地の人々など、「周縁」にいると見なされた人々である。彼らはその身体が放射線を受けただけでなく、居住地付近の生態系も汚染され、多くの場合、強制移住を余儀なくされた。そして彼らのコミュニティは分断され、伝統や文化も破壊されていった。彼らは広島と長崎の人々と同様にヒバクした人々、つまりグローバル・ヒバクシャである。こうしたヒバクシャを生み続ける核開発は、いわば自国民を対象とした限定核戦争だったのだ。ジェイコブズはグローバル・ヒバクシャが生まれていく背景や、核保有国が被害者を選定した論理を、科学や軍事、そしてヒバクシャのコミュニティのそれぞれから丁寧に追う。本書の各所に登場する、マーシャル諸島民、アボリジナル、福島の住民、サーミ、ナバホ族、カザフスタンのポリゴンや仏領ポリネシア、ネバダなどの核実験場近郊に住むヒバクシャたちに実際に会って聞き取ったオーラル・ヒストリーも貴重なものである。原発事故を「スローモーションの核戦争」と位置づけた前著『ドラゴン・テール』(凱風社、2013年)にすでにこの問題意識は見られるが、その後、広島で多くの被爆者と議論を重ねた経験と、世界各地のヒバクシャのコミュニティでのフィールドワーク、そしてとりわけ2011年の東京電力福島第一原子力発電所での事故を日本で経験したことが、彼に核の植民地主義的特徴をあらためて確信させたことは、著者自身が述べているとおりである。本書は、科学史、軍事史、環境史の先行研究を広く参照しながら、現代社会のあり方に対する鋭い感覚と長年にわたるフィールドワークの成果に基づき、グローバルかつ複合的に冷戦史を捉え直している。そして放射性廃棄物を生み出し続け、この負の遺産を未来世代に残すことになった我々に対して、その自覚と責任を問うているのである。
「唯一の戦争被爆国」とグローバル・ヒバクシャ
個々の研究の蓄積がある一方で、グローバル・ヒバクシャについての日本社会での認知度はいまだ低いのも事実だ。広島や長崎においてでさえ、「唯一の戦争被爆国」が強調されるとき、在外被爆者に思いが至っても、原爆以外の核技術の被害者を同じヒバクシャと捉える視点をもつことはそう多くなかったと言える。この問題が強く意識されるきっかけになったのは、言うまでもなく2011年の福島での原発事故であり、ヒロシマ・ナガサキに加え、フクシマでのヒバクシャを生んでしまったことだった。さらなるヒバクシャを生むことへの危機感は、多くの被爆者にそれまで以上に自らの経験を語らせることになった。2017年の核兵器禁止条約の成立は、核兵器をもたない中小国と核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)などのNGOの尽力により達成されたものであったが、グローバル・ヒバクシャの連携もこれを後押しすることになったと言えよう。ICANが同年にノーベル平和賞を受賞したのは周知のことである。そして2024年には、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を受賞した。ウクライナ戦争開始後のロシアや、ガザをめぐる紛争でのイスラエルによる核の脅しに対する危機感が、その背景にあるのは明らかである。新たなヒバクシャを生まないために、いまこそグローバル・ヒバクシャが生み出された歴史を振り返る必要がある。本書はそのために必ず参照される重要な文献となるであろう。原書については、2022年に出版されてから多くの書評が書かれており、とくに「限定核戦争としての冷戦」という視点に対する評価は高い。そしてジェイコブズ自身が精力的に世界各地のメディアに登場し、広島からヒバクシャについて発信しており、本書はとくに欧米で話題になっている。現在、この書をもとにしたドキュメンタリー番組がヨーロッパの映像作家たちによって準備され、2025年夏に放映される予定だという。日本被団協の平和賞受賞によりヒバクシャに対する関心が高まっている中、ジェイコブズの研究はより一層関心をもって読まれることになるだろう。
[書き手]竹本真希子(広島市立大学広島平和研究所准教授)
ALL REVIEWSをフォローする