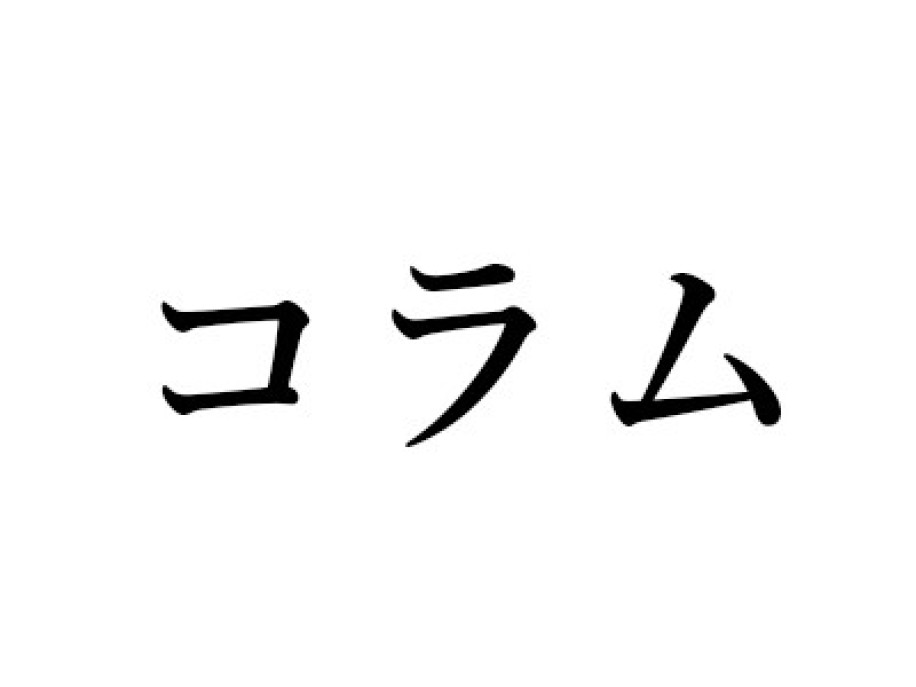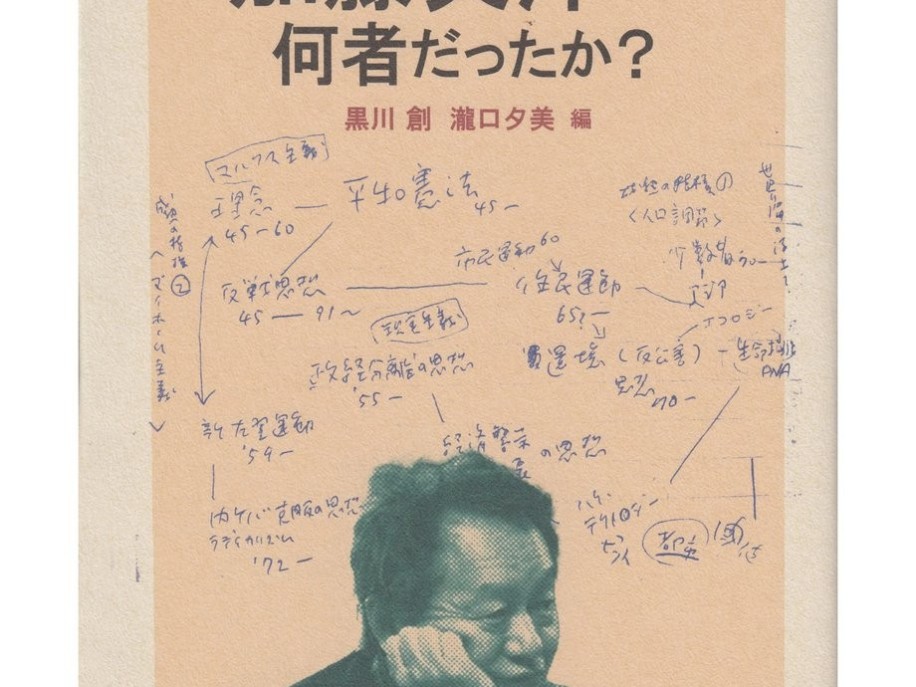書評
『近世近代小説と中国白話文学』(汲古書院)
日本の近世小説と中国文学の関係についての研究は底力の要る作業だ。ニカ国の言語に精通し、浩瀚な文献を辛抱強く読みこなす能力が欠かせない。著者はその領域における稀有な研究者の一人だが、前著『日本近世小説と中国小説』(青裳堂書店)に続いて、本書でも中国小説の受容について数々の発見と新しい知見を披露した。
典籍を広く渉猟し、テクストの異同を手堅く実証する手法は、本書でも思う存分発揮されている。馬琴『塩梅余史』と鈴木桃野(とうや)『反古のうらがき』の材源考はその好例である。粉本の沈起鳳『諧鐸』は清朝の筆記小説で、中国でもほとんど知られていない。茫洋とした文献の海から底本にたどりつくまでには、粘り強い資料調査はもちろん、日頃の博覧のほうがものを言ったのであろう。
比較文学の盲点は、実証を重視するあまり、作家論作品論という文学研究の本質をかえって疎かにすることだ。本書はたんに典拠探しに終わるのではなく、たとえば馬琴による中国小説の翻案が、読本(よみほん)作家になる過程においてどのような意味があったかもきちんと検討されている。『月氷奇縁』の考証も作家の方法意識が芽生えた時期を特定するのに役立った。『八犬伝』の戦闘描写、幸田露伴における元曲受容の論考はいずれも創作方法の考察を射程に入れたものである。
ここ二十年来、江戸時代の日中比較文学研究は長足の進歩を遂げた。その中で著者の地道な努力がいかに大きな力を発揮したかは、本書を読んで改めて思い知らされた。
【この書評が収録されている書籍】
典籍を広く渉猟し、テクストの異同を手堅く実証する手法は、本書でも思う存分発揮されている。馬琴『塩梅余史』と鈴木桃野(とうや)『反古のうらがき』の材源考はその好例である。粉本の沈起鳳『諧鐸』は清朝の筆記小説で、中国でもほとんど知られていない。茫洋とした文献の海から底本にたどりつくまでには、粘り強い資料調査はもちろん、日頃の博覧のほうがものを言ったのであろう。
比較文学の盲点は、実証を重視するあまり、作家論作品論という文学研究の本質をかえって疎かにすることだ。本書はたんに典拠探しに終わるのではなく、たとえば馬琴による中国小説の翻案が、読本(よみほん)作家になる過程においてどのような意味があったかもきちんと検討されている。『月氷奇縁』の考証も作家の方法意識が芽生えた時期を特定するのに役立った。『八犬伝』の戦闘描写、幸田露伴における元曲受容の論考はいずれも創作方法の考察を射程に入れたものである。
ここ二十年来、江戸時代の日中比較文学研究は長足の進歩を遂げた。その中で著者の地道な努力がいかに大きな力を発揮したかは、本書を読んで改めて思い知らされた。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする