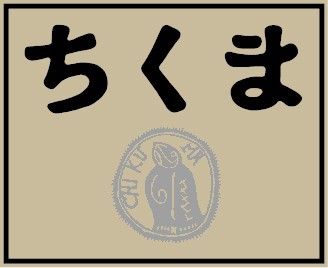対談・鼎談
『大菩薩峠』中里介山|鹿島茂+中野翠の読書対談
花は散りてもは咲く――『大菩薩峠』愉しみ
ニヒリストと怪人物たち
鹿島 僕らの世代で「大菩薩峠」というと、片岡千恵蔵の映画を一番最初に見たかなあという感じですね。それから(市川)雷蔵の三本。机竜之助「音無しの構え」というのは子供のころのチャンバラの必須アイテムの一つという感じでしたね。
僕は思うのだけど、『大菩薩峠』って読まれるのに十年ぐらいの周期があるんじゃないかな。僕らの間で『大菩薩峠』がちょっとしたブームになったのが七一、二年。学生運動で留置場に入れられて戻ってきたやつらが、大学でドロップアウトしてやることなくて『大菩薩峠』を読んでたという時期がある。左翼にありがちな、典型的な日本的なものへの揺れ戻しといえなくもない。僕もそのとき角川文庫でちょっと読んだ。ただ、読んだつもりになってたけど。後がこんなにあるとは思ってなかった(笑)。
中野 私はもうちょっと後、七三、四年とかそれぐらいだと思うんですけど、失業してて(笑)、なんか暇にしてて、家にあったからクロス張りの黴臭い本で読んでたわけ。
それでね、昔は私、もっとシリアスな人だったみたいなのね(笑)。だからなんかシリアスに読んでたような気がするの。それであんまり面白くないと思って、竜神の巻あたりでやめちゃった。今回読んだら、こんなおかしな小説だったのかと驚いた。要するに昔読んだとき、私は市川雷蔵の印象がすごく強くて、なんか二枚目の話だという固定観念にしばられていたのね。ニヒリストのね。そしたらその周辺の怪人物というか、おかしな人たちの話がすごく面白くて。ところどころはほんとにスラップスティックみたいなドタバタや……こんな小説だったのかとものすごく驚いた。
鹿島 映画に撮ると、剣豪が戦う場面が中心になるからシリアスにならざるをえない。
だけど、よくよく読んでみると、机竜之助が強豪と戦ってるというのはほとんどない。
中野 文庫版でいうと三冊目ではすっかり姿を消しちゃうでしょう。で、最後のとこにちょこっとまた出てくる。忘れてるわけじゃないんだからね、みたいな感じでまた出て来るの。剣豪の話といっても伝説とかエピソードみたいな感じで出てきたりで、机竜之助自体は別にあんまり戦ってない。一騎討ちみたいなのはないのね。強い人同士のは。
鹿島 だって新撰組と島田虎之助との死闘だって竜之助は横で見てるだけなんだから。
机竜之助が本当に戦ってるというのは、最初の宇津木文之丞との戦いと、文之丞の門下生が攻めてくる――。映画ではそこが結構メインになってるけど、小説の中には実際に戦ってる場面はないでしょう。竜之助は、新撰組に入ったって、新撰組では全然戦わないんだもん。後で辻斬りに走ると、もうこれは完全に淫乱殺人になるから(笑)。
ユニークなキャラクター
鹿島 面白いのはやっぱりキャラクターの創造がユニークだということ。例えば神尾主膳なんて映画だとちょっとした悪殿様ぐらいのイメージでしか出てこない。ところが小説では、後のほうになるとこいつなかなか面白い男に描かれている。
これ気に入ったね、神尾主膳っていうの。
中野 神尾主膳に関しては最初からわりとうまく書いてる。完全にワルじゃなくて、やっばりお坊ちゃんの愛敬とか、女好きするところとか、なんかちょっといいとこもあるのよ。いいとこっていうか、かわいいっていうかね。悲しいとこも、わりと最初からちゃんと書いてて、完全な悪役でもないっていう。
鹿島 大長篇の悪いパターンというのは、最初に悪者だったやつが最後のほうになるといい者になるところだけれどそれがないね。それがないからいいんだ。神尾主膳は最後まであんまりいいやつにはならないんだけど。酒乱のところを除くと、これはけっこう僕の性格に近い感じ(笑)。「金というのは使い方を知らないやつのところばかりに行って、俺のような使い方を知っている奴のところには来ない」ってうそぶくけれど、これなんかわがことのように読んだね。
中野 でも、女の人がけっこう悪いのがいろいろ出てくるでしょう。お絹とかお角とか。悪くはないんだけど、なかなかやり手の女の人とか。最初の机竜之助の相手の「悪縁の女」お浜とかね。けっこう複雑なキャラクターを書いてて面白いな。お銀様が出てきたときはほんとに私、うれしかった。
鹿島 うれしかったね。遂に出たって感じで(笑)。
中野 ロマンチックだなと思って。
鹿島 これはほんとゴシックロマンだな。
中野 出たーっ!ていう感じよね(笑)。
鹿島 そう、最後のほうになるとお銀様が主役になっちゃうのね。
中野 ユートピアみたいのをつくるでしょう。できる女だったんだ、っていう。
鹿島 それとお銀様って顔はケロイドだけど、ナイスバディなんですよね。後のほうになると米友を誘惑するところがある。米友が暗闇から覗いていると……お風呂になやましい女人の後姿がぼっかり浮かんでいる。米友は死んだお玉のイメージがあるから、お玉が生き返ったと思う……。ところがそれがお銀様で、「私の背中を洗ってちょうだい」なんて言ってね。最後には、私と寝なさいって言って命令を出す。「これは命令です」って言って。お銀様は気に入っちゃったな、もう。
中野 お銀様はいいよ。名前といい、思い詰め方といい、もうすごいんだ。
鹿島 腕を刺して血で写経をするとか。
中野 そうそう、激しい人なの(笑)。
鹿島 あれはほんと少女漫画の、僕らが読んでたわたなべまさこのゴシックロマンとかね。
中野 そうそうそう。わたなべまさこの感じ。
三巻目で駒井能登守とお君の悲恋が出てくるでしょう。駒井能登守は、これは消すには惜しいキャラクターだと思ったわけ。そしたらちゃんと後で出てきて、かなりの主要なキャラクターになってゆく。
鹿島 軍艦つくったりする。
中野 すごいよね。悲恋のときはそこまで際立った個性じゃない。それが、すごい科学者になっていっちゃうのね。
鹿島 その意外な感じで思いだしたけれど、時代劇って時代がいつだかよくわからないでしょう。『大菩薩峠』も、幕末だっていうことが最初はそんなにわからない。
ただ、よく考えてみれば、神田のお玉ヶ池とか、道場とか、剣豪というのが出てきたのは幕末なんですよ。要するに武士階級以外の人間が剣道をやり始めることで道場っていうのが成立する。
旗本八万騎が二百年たつうちにだんだん官僚化していって、神尾主膳みたいな遊び人ばっかりになってきたので、代りの暴力装置というのが必要になる。それを下のほうの階層から調達しなきゃいけないから、それが幕末に新撰組とかそういう形になる。竜之助もその階層の一人だ。ただ、理屈ではわかってても、そこの部分と、時代のー要するにもう黒船が来てるっていうことがなかなかイメージの中で重ならない。
中野 だってこれ、たいして何年もたってないわけでしょう。最初に三年ぐらいたっちゃうけど、トータルしてそんなに経過していないんじゃない。
鹿島 机竜之助の息子の郁太郎が四歳にしかなってない。で、最終的にも四歳なんだよ。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする
ちくま 1995年12月
筑摩書房のPR誌です。注目の新刊の書評に加え、豪華執筆陣によるエッセイ、小説、漫画などを掲載。
最新号の目次ならびに定期購読のご案内はこちら。