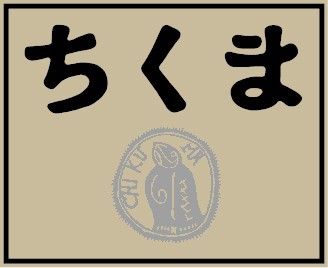対談・鼎談
『大菩薩峠』中里介山|鹿島茂+中野翠の読書対談
ユートピアとフォークロア
中野 でもほんと、その時代の感じっていうのはあんまりないですね。
鹿島 それは文章が思ったよりもはるかに論理的だからじゃないかな。介山は相当に英語が読めた人じゃないかという気がした。
中野 アメリカにも行ったことがある。
鹿島 これ、読んでてすごく文章がモダンな感じがするでしょう。
中野 なんか突然マドロスが出てきたり……(笑)。
鹿島 マドロス――外人が出てきちゃって、カンツォーネか何か歌うんだよね(笑)。
中野 中国人がその前に出てくるのね。
鹿島 金推ね。金推が聖書読んでる。「マタイ伝」なんか読んでる。
中野 そう。どんどん変なふうになっていくの(笑)。
鹿島 ユートピア建設とかあるでしょう。フーリエニズムとかサンシモニズムとかいう空想科学主義的なユートピア思想って、昭和の最初に、われわれが思っているよりもはるかに紹介されてるのよ。「世界大思想体系」とか戦前に出たものが古本屋なんかに転がってる。介山は、そういうのをけっこう読んでた。それと、この人、フロイトも読んでるね。例えば無意識とか下意識とか、そういう概念で語ってる。それが基調音として隠されてるところが面白いな。
中野 竜之助が出てくると必ず夢の場面になるのよね。
鹿島 あとはどういうキャラクターがよかったですか。
中野 道庵先生とか(笑)。
鹿島 道庵先生(笑)。
中野 道庵先生をめぐって変な民衆運動みたいなのがあるじゃない。ところが民衆運動っていうほどちゃんとしたもんじゃなくて、ものすごくいい加減なものでしょう。勝手に商店に入り込んじゃってごはん食べちゃう、おかゆか何か食べちゃう、ただそれだけっていう貧窮組。それで書いてる介山が、民衆のいい加減さみたいなものをちゃんと書いてるわけ。民衆は素晴らしいみたいに讃美は全然していなくで、民衆のずうずうしさとか、飽きっぼさとか、ずるさとか、馬鹿馬鹿しさみたいなものを書いている。そういうところなんか、おやっ、この人は信頼できるなと思うのね。
関西のほうに行くわけじゃない、西のほうに。そうすると歌舞伎のいろんな……その土地にまつわる歌舞伎の話みたいなのが直にはあんまり書いてないけど、これは「伊勢音頭(恋寝刃)」の話だなとか、これは「道成寺」の話だなとかわかる。いろんなことを知ってる人なら、二重三重に楽しめる感じで。
あと仏教説話だか何だか知らないけどフォークロアとか、そういうのがごちゃごちゃいっぱい入ってる。歌も入ってるし。そういうのがすごくこくを出してるっていう感じね。変なインチキな名前の歌舞伎の芝居が村であるじゃない。
鹿島 海土蔵ね、海老蔵じゃない(笑)。
中野 海老蔵じゃなくて海土蔵っていうのね。そこから「勧進帳」の話をひとくさりしたりとか、急に評論家みたいになっちゃって。私はそういうところが面白かったんだけど、ストーリーを読みたい人はああいうとこがちょっと面倒くさいかもね。
鹿島 脱線は脱線として楽しんでゆっくりと読むというのがいいんじゃないかと思うな。
中野 弁信のおしゃべりなんかも、何にもたいしたことは言ってない(笑)。言ってないんだけど、そのしゃべりが彷彿とするようなね。節まで聞こえてくる。
鹿島 あれ、完全に落語だね。圓生か林家正蔵って感じ。
中野 声とか調子まで聞こえてくるような感じなんだよね。
鹿島 この人、音楽がわかった人かどうか知らないんだけども、文章の音韻がいいなという気がしたな。
手紙文なんか――例えばお雪ちゃんが弁信に手紙出すでしょう。あすこなんか声出して読むとすごくいい。
あと僕は、サブ・キャラクターだけど忠作っていうのが気に入っちゃった。
中野 小さな資本主義者でしょう。私もけっこう好き。あれ、言うことがリーズナブル(笑)。少年金貸しで、お絹だったっけ? 組んだのが。ガキのくせして、やり手のお絹を手玉にとってしまう。
鹿島 忠作は、後のほうで薩摩屋敷の前のところのそば屋の丁稚になって、武器を佐幕と勤皇の両方に納入する死の商人になるの。その後は、武器じゃ限界がある、貿易を考えなきゃいけないと。それで絹の納入業者になって。異人さんの資本主義のノウハウを全部学ぶんだね。
誘惑する女たち
鹿島 女の人はどうですか。僕はファム・ファタル願望が強いからお絹が一番よかったな。
中野 お絹? でも読んでて、この人はいったい何歳なんだと(笑)。神尾主膳の父親の愛人だったのが、その息子と……。坊っちゃまの子守してました、とか言いながら愛人になっちゃうから、そうすると三十八ぐらいなのかなあ。江戸時代にしては、女としてすごく長持ちしている。五月みどりタイプっていうか……。
鹿島 介山は娼婦的な女を書くの、うまいですね。お蘭とかね。お蘭というのは竜之助とお雪ちゃんが飛騨高山に行くと、そこの悪代官の姿で出てくる。このお蘭というのがまた天性の娼婦で、男と見れば誘惑してみないと気がすまない。その反対に清く正しいキャラクターっていうのは――。
中野 華々しくすぐ散ってほしいなっていうね。お君なんかほんとにいいけどね。
鹿島 お君はいいね。これぞ正統派の悲劇のヒロイン。
中野 いい女の人は、やっばりあんまり長く引っぱらないでサッと散って、悪い女がいつまでもいた方が面白いよね。あれがおかしいのよね、お銀様っていうのとお角というのが……。お角って気の強い女なんだけど、どうもお銀様は苦手みたいで。
相互にあの人には弱いっていうのがあるのよ。米友は道庵に弱かったり。
鹿島 三すくみ、四すくみになってる。
それと、『大菩薩峠』がここまで続いたのはすれ違いを基本としてるメロドラマだからかな。
中野 しかしすれ違いすぎるよね(笑)。
鹿島 宇津木兵馬と竜之助のすれ違いって、これはちょっと異常としか言いようがない。なにしろ、隣の部屋にいるのに気づかないんだから。
中野 そのわりにはほかの人はすぐ会っちゃう。偶然、宿が隣の部屋だったとかさ。人口が江戸三十人、全国で百人ぐらい(笑)、みんなつながってるっていう、そのぐらいの感じなのに、あの二人だけはどうしても会わない。
鹿島 これ、会っちゃいけないんだな。宇津木兵馬といえばこいつも清く正しい男だと思っていると……。
中野 わりと崩れちゃう。女にまどわされたりする(笑)。駒井能登守も洋服になっちゃうのよね。髪の毛を断髪にして、ズボンをはいて上は羽織なのね。それで切った髪の毛先をちょっと巻き上げてるって書いてあるから、どうなるのかなと思って。鏝(こて)かなんかかけてるのかな、なんて。私は本のすみに絵を描いてみた。こうなってるのかな、なんて。けっこう、アヴァンギャルドなファッションよ。
鹿島 それから、この小説、ある意味で頭巾が主役でしょう。竜之助は辻斬りに行くとき頭巾被ってるし、お銀様は一貫して頭巾で。最後のほうになると頭巾についての解説まで付いてくる。だから頭巾小説でもあるな。
中野 私、与八っていうのもけっこう好きよ。
鹿島 与八、いいねえ。水車番の与八ね。
中野 与八の考えてることが全部モノローグで書かれてるのね。頭に浮かんだことも全部。
あれ読んでると、ほんとに心が洗われる。すごくのどかな、いい気持ちになる。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする
ちくま 1995年12月
筑摩書房のPR誌です。注目の新刊の書評に加え、豪華執筆陣によるエッセイ、小説、漫画などを掲載。
最新号の目次ならびに定期購読のご案内はこちら。