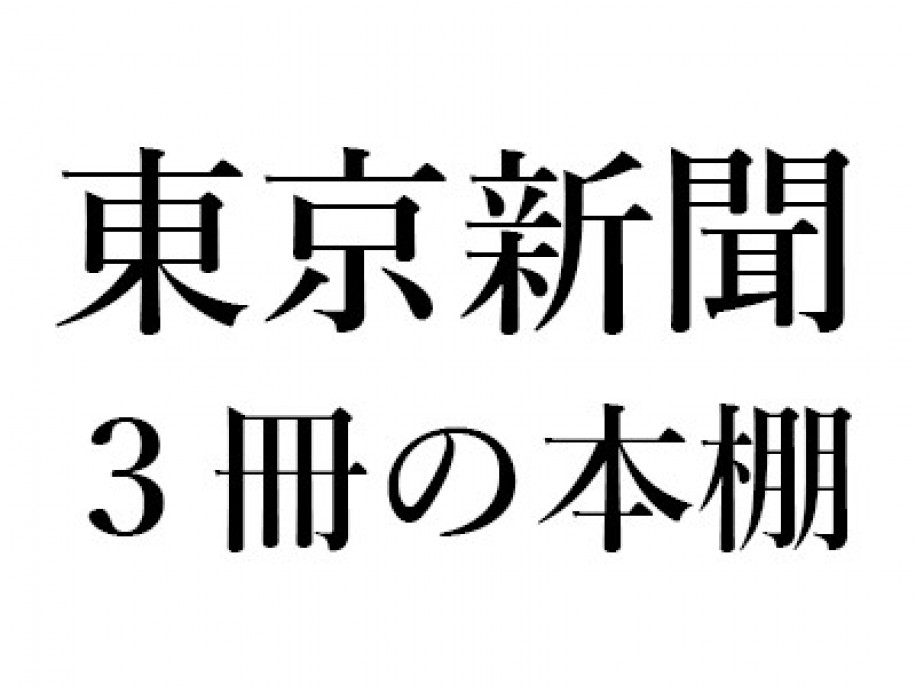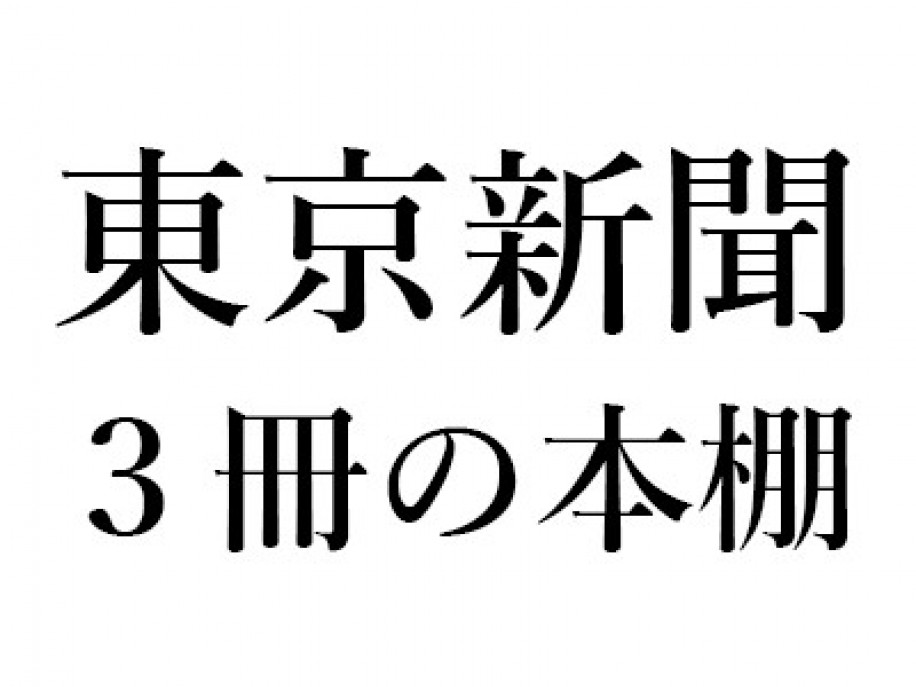対談・鼎談
『キリストの誕生』遠藤周作|丸谷才一+木村尚三郎+山崎正和の読書鼎談
木村 わたしは、日本のクリスチャンの書くものは、一般に好きになれないんです。独特のくさみがあるものが多いですから。でも、この本にはそれがない。わたしのように、キリスト教を全然信じない人間でも、素直に読んでいけるんですね。この本は全体がきわめて知的な誠実さで貫かれていて、著者自身、わからないことは最後までわからないといっているからです。
イエスが十字架にかかったあとの使徒たちの悩み、つまり、なぜ神は救わないのか、なぜ再びキリストは現われないのかといった疑問は、使徒たちの疑問であったと同時に、おそらく遠藤さんご自身の疑問でもあるのじゃないか。その悩みとか疑問を、最後まで正直に出しているところに、共感をおぼえました。
ところで、この本は小説なんでしょうか。たしかに、ポーロの最期を書きとめなかったルカの心境が述べられているところなどは、小説的な心理描写のように見える。しかし著者は『聖書』を隅から隅まで読み、様々な学術的研究を参照した上で書いているわけで、個人の一方的な思いこみで書かれているものではないと思うんです。
丸谷 ちょっとごめんなさい。小説というのは、個人の一方的な思いこみで書くものじゃないんですよ(笑)。
木村 あ、なるほど。そうですね。ですがわたしのいいたいのは、この本には、学術書と呼んでもそうおかしくない知的な誠実さがあるということです。歴史学者には往々にしてイマジナティブ・パワーがなく、木で鼻をくくったような叙述が多い。しかし個々の片々たる事実をつなぎ合わせてゆくには想像力が不可欠なはずで、この本はその点でも一つのいいサンプルだと思うわけです。
山崎 犠牲とその復活という観念は、悲劇の根底にある考え方だ、とたいていの人類学者がいっています。つまり、偉大な生命力を葬ることによって死んだ古い年を弔って、新しい年の復活に期待をかける。この考え方は、根本的に循環史観というんでしょうか、つまり、永遠の繰り返し……。
丸谷 永劫回帰の考え方ですね。
山崎 それに対してユダヤ的な考え方では、最後の裁きに向かって一直線に歴史は進行するものである。これはマルクス主義にまで繋がっている直線型、発展型、あるいは終末型の歴史観でしょう。
そういうユダヤ教の地盤に立っているキリスト教の中に、具体的に東方の思想の接触があって復活の思想が入ってくるという説明はたいへんおもしろいですね。
丸谷 この本の主題は、ユダヤ民族の一宗教にすぎなかったキリスト教が、どうして人類全体の宗教になることができたかということでしょう。ユダヤ民族の宗教が、ヨーロッパ人の宗教に転化した。と同様にヨーロッパ人の宗教が東洋人の宗教にもなるはずだという見通しが、根底にあると思う。
山崎 しかも、キリスト教が真のキリスト教になったのは、他民族の文化や思想を受け入れたときである、と遠藤さんはいっている。あとでギリシャ系のユダヤ人が多神教的な明るいものをキリスト教の中にもちこんだと、非常に大胆な推定をしているんですが、このあたりの遠藤さんの志は非常によくわかるんですね。
木村 しかし、一方でヨーロッパの伝道者たちが日本に布教する際、一方的に自分たちの考えを押しつけたことに対して、遠藤さんはきちんと批判しておられる。ですから遠藤さんは、日本人もふくめたキリスト教の普遍化を、この中で一所懸命に考えているんですね。
山崎 著者はあくまでポーロの立場に立ちたいんですよね。そのときに、もしもポーロの思想がキリスト、つまり、個人イエスと無関係だといわれると困るわけです。ポーロを充分に自家薬籠中のものにしておいて、さて、ポーロがこういう解釈をなし得るためには、その素材となったイエスの中に、その解釈を許すようなものがなければならない。こういわないと、キリスト教の再解釈としての筋が切れちゃいますからね。そういう論理の運びだと思う。
丸谷 正統性がなくなってしまうということでしょう。でも、立派な批評を書けば、その批評家は正統的なものを、元の作品に対してもっちゃうわけね。
山崎 もちろんそうですけれども、遠藤さんとしては、キリスト教の有力メンバーの中で、自分の味方になり得る人物を一人つかまえたわけでしょう。そこで、根を切られては困るから、次の手続きとして、その人物こそ正統である、という論理的手続きをしておかないといけないんだうと思う。
木村 そのポーロがアテネで嘲笑されたわけですよ。〈神々の世界とただ一つの神の世界が激突した瞬間である〉と書かれてありますが、そこにまた日本人が重なり合ってくるんですね。
〈ギリシャ人と違った形であるが汎神的な世界に生き続けてきた日本人の我々が一神論のポーロ神学を実感をもって理解することが、いかにむつかしいか。いかに長い時間がかかったか〉
つまり、日本人と、一神教としてのキリスト教のあいだに今日なお存在する違和感というものを、遠藤さん自身、たいへん強く感じておられる。その意味で、この本は高級な布教の書かもしれません。
(次ページに続く)
イエスが十字架にかかったあとの使徒たちの悩み、つまり、なぜ神は救わないのか、なぜ再びキリストは現われないのかといった疑問は、使徒たちの疑問であったと同時に、おそらく遠藤さんご自身の疑問でもあるのじゃないか。その悩みとか疑問を、最後まで正直に出しているところに、共感をおぼえました。
ところで、この本は小説なんでしょうか。たしかに、ポーロの最期を書きとめなかったルカの心境が述べられているところなどは、小説的な心理描写のように見える。しかし著者は『聖書』を隅から隅まで読み、様々な学術的研究を参照した上で書いているわけで、個人の一方的な思いこみで書かれているものではないと思うんです。
丸谷 ちょっとごめんなさい。小説というのは、個人の一方的な思いこみで書くものじゃないんですよ(笑)。
木村 あ、なるほど。そうですね。ですがわたしのいいたいのは、この本には、学術書と呼んでもそうおかしくない知的な誠実さがあるということです。歴史学者には往々にしてイマジナティブ・パワーがなく、木で鼻をくくったような叙述が多い。しかし個々の片々たる事実をつなぎ合わせてゆくには想像力が不可欠なはずで、この本はその点でも一つのいいサンプルだと思うわけです。
山崎 犠牲とその復活という観念は、悲劇の根底にある考え方だ、とたいていの人類学者がいっています。つまり、偉大な生命力を葬ることによって死んだ古い年を弔って、新しい年の復活に期待をかける。この考え方は、根本的に循環史観というんでしょうか、つまり、永遠の繰り返し……。
丸谷 永劫回帰の考え方ですね。
山崎 それに対してユダヤ的な考え方では、最後の裁きに向かって一直線に歴史は進行するものである。これはマルクス主義にまで繋がっている直線型、発展型、あるいは終末型の歴史観でしょう。
そういうユダヤ教の地盤に立っているキリスト教の中に、具体的に東方の思想の接触があって復活の思想が入ってくるという説明はたいへんおもしろいですね。
丸谷 この本の主題は、ユダヤ民族の一宗教にすぎなかったキリスト教が、どうして人類全体の宗教になることができたかということでしょう。ユダヤ民族の宗教が、ヨーロッパ人の宗教に転化した。と同様にヨーロッパ人の宗教が東洋人の宗教にもなるはずだという見通しが、根底にあると思う。
山崎 しかも、キリスト教が真のキリスト教になったのは、他民族の文化や思想を受け入れたときである、と遠藤さんはいっている。あとでギリシャ系のユダヤ人が多神教的な明るいものをキリスト教の中にもちこんだと、非常に大胆な推定をしているんですが、このあたりの遠藤さんの志は非常によくわかるんですね。
木村 しかし、一方でヨーロッパの伝道者たちが日本に布教する際、一方的に自分たちの考えを押しつけたことに対して、遠藤さんはきちんと批判しておられる。ですから遠藤さんは、日本人もふくめたキリスト教の普遍化を、この中で一所懸命に考えているんですね。
山崎 著者はあくまでポーロの立場に立ちたいんですよね。そのときに、もしもポーロの思想がキリスト、つまり、個人イエスと無関係だといわれると困るわけです。ポーロを充分に自家薬籠中のものにしておいて、さて、ポーロがこういう解釈をなし得るためには、その素材となったイエスの中に、その解釈を許すようなものがなければならない。こういわないと、キリスト教の再解釈としての筋が切れちゃいますからね。そういう論理の運びだと思う。
丸谷 正統性がなくなってしまうということでしょう。でも、立派な批評を書けば、その批評家は正統的なものを、元の作品に対してもっちゃうわけね。
山崎 もちろんそうですけれども、遠藤さんとしては、キリスト教の有力メンバーの中で、自分の味方になり得る人物を一人つかまえたわけでしょう。そこで、根を切られては困るから、次の手続きとして、その人物こそ正統である、という論理的手続きをしておかないといけないんだうと思う。
木村 そのポーロがアテネで嘲笑されたわけですよ。〈神々の世界とただ一つの神の世界が激突した瞬間である〉と書かれてありますが、そこにまた日本人が重なり合ってくるんですね。
〈ギリシャ人と違った形であるが汎神的な世界に生き続けてきた日本人の我々が一神論のポーロ神学を実感をもって理解することが、いかにむつかしいか。いかに長い時間がかかったか〉
つまり、日本人と、一神教としてのキリスト教のあいだに今日なお存在する違和感というものを、遠藤さん自身、たいへん強く感じておられる。その意味で、この本は高級な布教の書かもしれません。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする