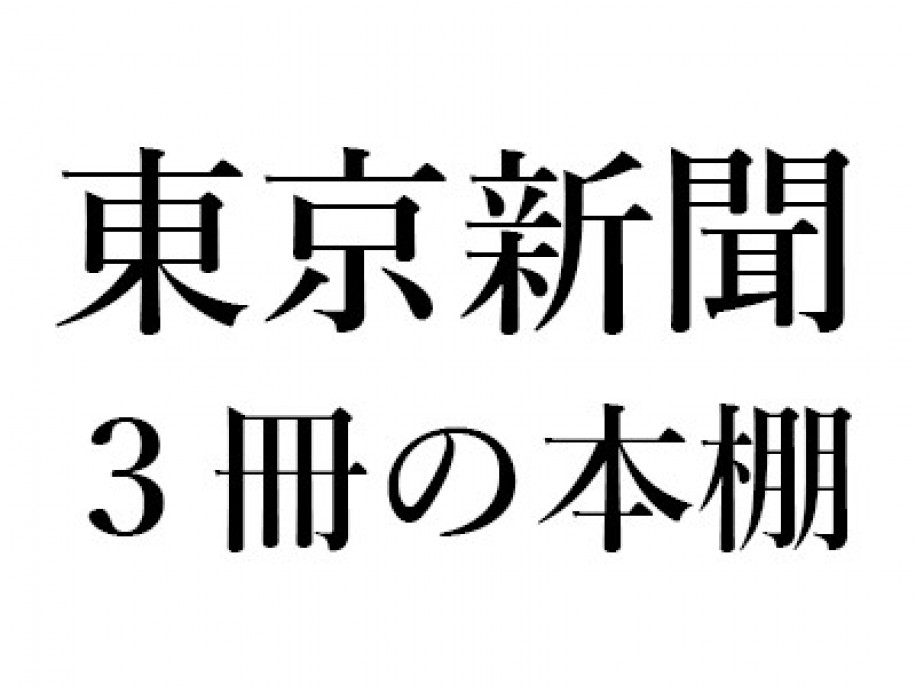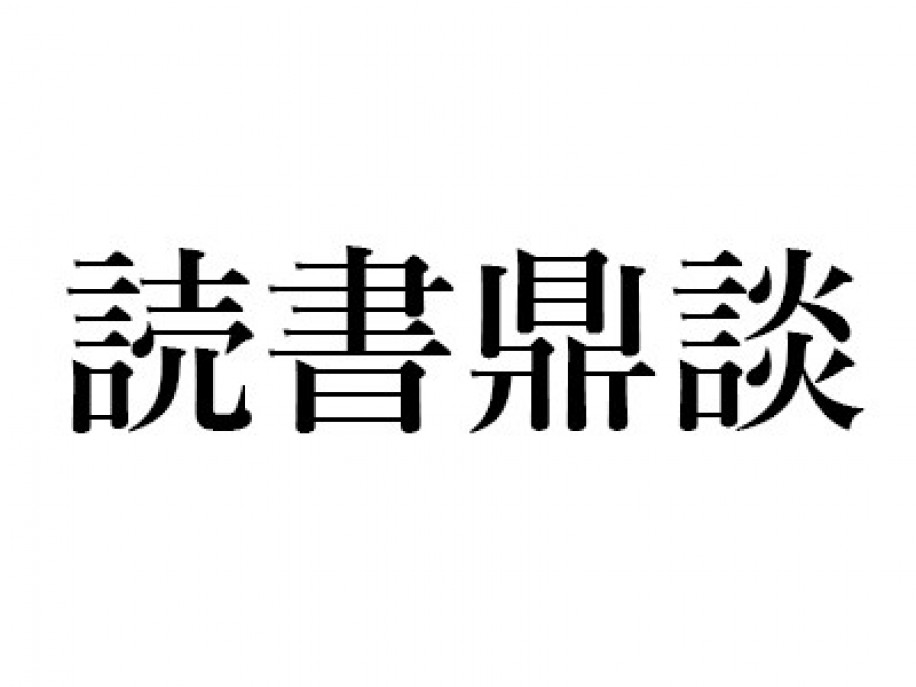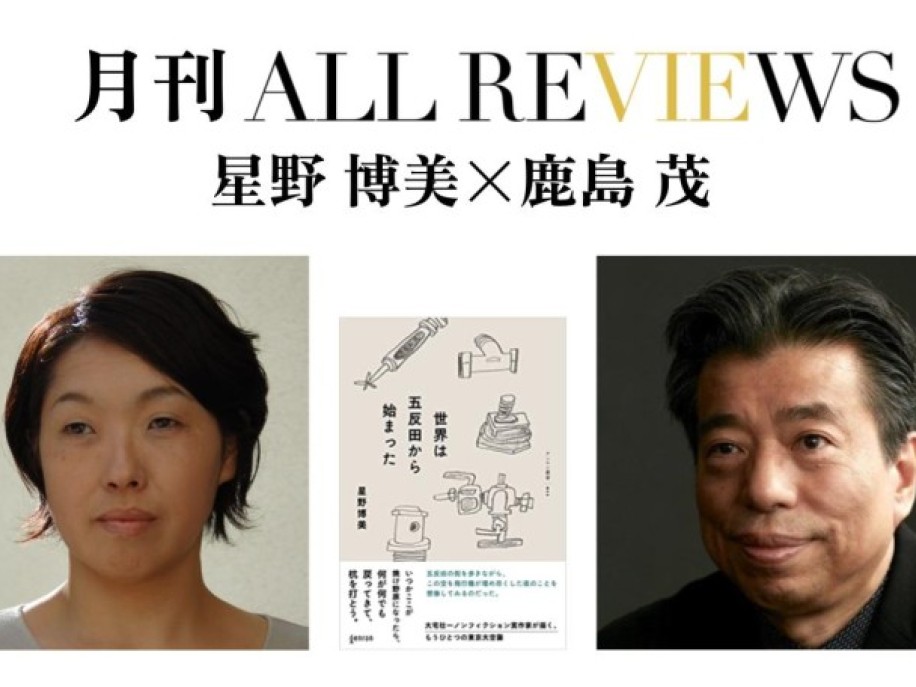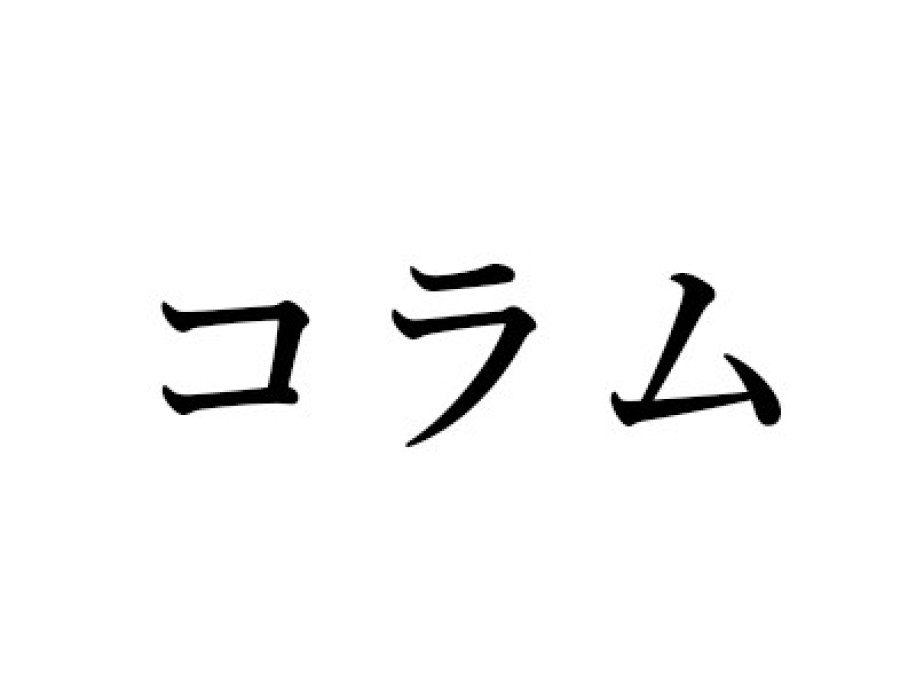読書日記
遠藤周作『人生の踏絵』(新潮社)、星野博美『みんな彗星を見ていた-私的キリシタン探訪記』(文藝春秋)、米田彰夫『寅さんとイエス』(筑摩書房)
遠くて近いキリスト教
スコセッシ監督の映画「沈黙」をみて、原作を久しぶりに読み返した私。さらに原作の著者である遠藤周作の講演録<1>『人生の踏絵』(新潮社・1,512円)を手に取ると、そこには「沈黙」執筆時の心境が記されていました。遠藤が長崎で踏み絵を見た時、そこには脂足で踏まれ、くたびれ果てた中年イエスが。それが「沈黙」執筆のきっかけとなりました。キリスト教徒の家に生まれた遠藤は、幼児洗礼を受けています。子供の頃からの“許嫁(いいなずけ)”が「バタ臭い顔」をしていたのだ、と。やがて“女房”となったキリスト教。みそ汁も作れないその妻を「愛している」かは定かでないけれど、相手を懸命に理解しようとする遠藤がそこにはいます。
このように遠藤は、自信満々の信者ではありません。踏み絵を踏む信徒。棄教する宣教師。弱い者に寄り添う姿勢がそこにあるのは、遠藤自身もまた一人の弱い人間としての自覚があったからです。
しかしなぜ、かつての日本で大量のキリスト教信者が生まれたのか。神父達はなぜ、命を賭けて日本まで来たのか。そんな疑問は残るわけですが、<2>星野博美『みんな彗星(すいせい)を見ていた-私的キリシタン探訪記』(文芸春秋・2,106円)は、今を生きる著者が数々の疑問の中に飛び込んでいった書。
著者は、キリスト教系の学校で学んだ折、日本のキリスト教界に対する強い違和感を覚えていました。
日本人がキリスト教に熱狂した時代に対する興味の背景は、そんなところにもあるでしょう。
キリシタンゆかりの地を巡り、膨大な資料を読み、やがて宣教師達の故郷であるスペインへ。そこで待っていたのは、感動の出会いでした。文化は違っても、同じ神を信じることはできる。また文化は違っても、信じる対象が異なれば殺し合いになる。
人間の可能性と愚かさを、同時に感じさせられる一冊です。
キリスト教はその後、日本で盛んにはなっていません。やはり「バタ臭さ」故の相性の問題がありそうですが、<3>米田彰男『寅(とら)さんとイエス』(筑摩選書・1,836円)を読めば、今もキリスト者達は、日本人に合ったキリスト教の解説に腐心していることがわかります。
フーテン性やユーモアのセンス等、寅さんとイエスの間に共通項を見出した著者は、神父。
寅さんという意表をついた補助線の登場によって、イエスが少し、身近に思えるのでした。
ALL REVIEWSをフォローする