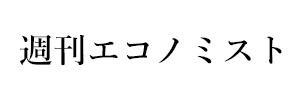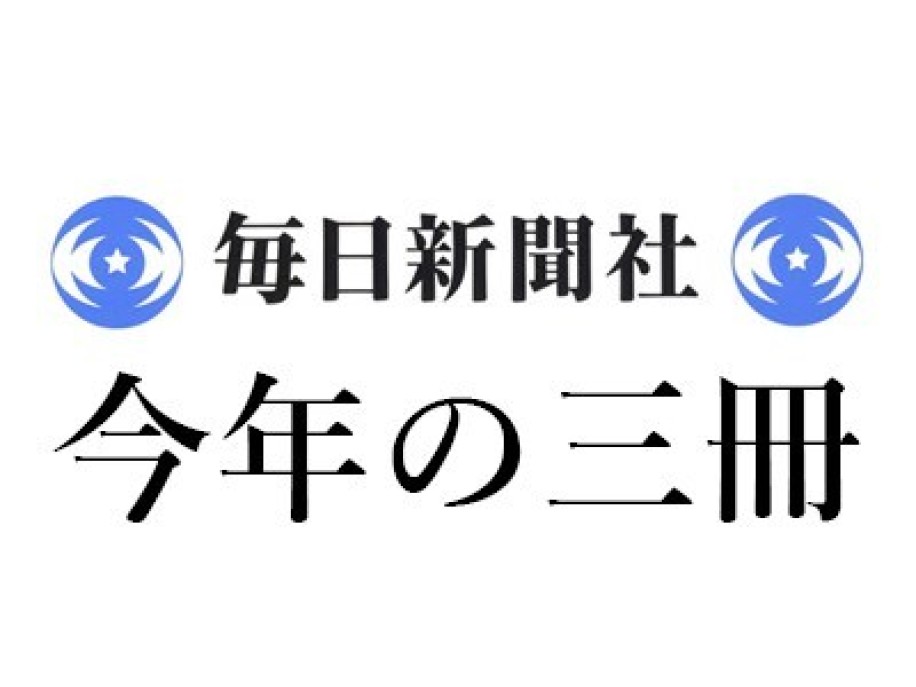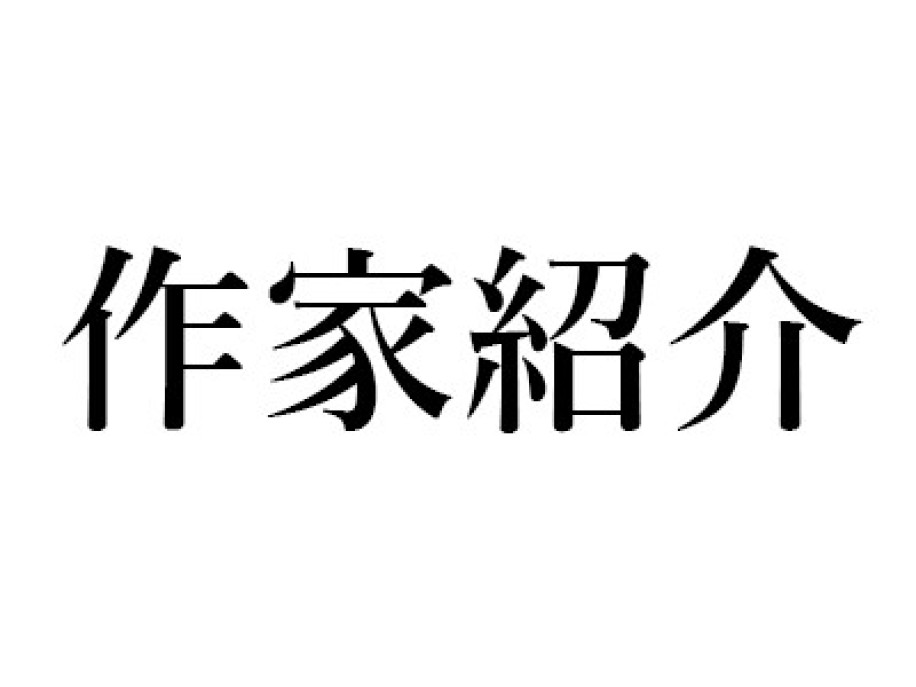読書日記
町田康「読書日記」週刊エコノミスト2016年9月6日号|『東海道四谷怪談訟』『丸山眞男の敗北』『北山十八間戸』
猛暑で思考力が低下 本に涼を求めてみれば…
このところ気温が高く、ものを考える力(これを業界では思考力と呼ぶ)がドシドシ低下していくのが自分でもわかったので、少しでも涼しくしようと思い、『東海道四谷怪談』(鶴屋南北著、岩波文庫、900円)を読んだら極度におもしろかった。どんなところがおもしろかったか。思考カが低下しているので、うまく説明できないが、まずは芝居に登場する人が思うこと、感じることがおもしろかったし、そのうえで言うことすることがおもしろかったし、その結果、どんどん土壺(どつぼ)にはまっていく成り行きがおもしろかった。
というと、芝居に出てくる人が特異な性格、特殊な感情の持ち主のように聞こえるが、そうでもなく、やっていることそのものは意外に合理的であったりする。もちろん決定的に非合理なところもあるのだけれどもそのところには必ず怪異が介在する。
ということはその怪異がおもしろいのかというとそうでもなく、じゃあどこがおもしろいかというと、好き放題に振る舞って個人的に土壺にはまって半泣きになっている方が実は理性的・抑制的なのではないか、と逆説ではなく思えてくるようなところである。
というのはでも思考カがほとんどない状態で考えたことだし、それに肝心の怪異の部分があまり怖くなかったので所期の目的を達することができないというか、人間の業、のようなものをみて余計に暑苦しくなり、ますます思考力が低下していく。
そこでこういうものを読むと少しは涼しくなるのではないか、と思って手に取り読み始めたのが、『丸山眞男の敗北』(伊東祐吏著、講談社選書メチエ、1700円)で、どうだったかというとまったく涼しくはならなかったがたいへん勉強になった。というのも恥を忍んで言うのだが私はこれまで戦後最大の知識人と言われた丸山眞男に関連する本を一行も読んだことがなかったからで、この本は、丸山眞男の思想を戦後の日本人の生き方と重ね合わせて考えることによって、いまの私たちの社会がある有り様の根本をそこに見出すようなことをしていて、題名に「敗北」とある通り、作者はある時点で、それはどこかで敗北したと見なしていて、敗北というと言葉は厳しいのだけれども、行き詰まってそれ以上先あるに考えが進まなくなった、或いは、論理の堤があちこちで決壊して修復ができなくなった、というようなことなのかも知れぬが思想家にとってはその方が厳しい。けれども一般の生活者、市井の働(はたら)き人(ど)にとってはそっちの方が楽で、そこが互いに干渉してしまったということなのだろうか。思考がないのでわからない。
詩人が翻訳する理由
私がもっとも思考が破壊されてルククと歌ったのは、丸山眞男と死者の関係を書いたところで、丸山眞男はそれを弔っているようで怨霊化してしまっている、というところで、ルクク、じゃったら戦後詩とかどうなるんだろうか、と思ったら、作者は石原吉郎を例に出して、それとは別の感じ感があると言っている。それでいよいよ思考はなくなっていくし、暑いしどうしようかな、と思って読んだのが詩つながりで、『北山十八間戸』(荒川洋治著、気争社、1850円 事務局注:取扱書店なし)で、戦後71年ということでいうと、例えば、「アルプス」という詩で、詩はいろんなものを置き換えて進むが、その戦後の時間も詩に取り込んだうえで別のもの、例えば衣服が揺れてできる小さな円弧の揺らぎのようなものにも置き換えて進み、というのはなぜかというともちろんこれが詩であるからであるが、戻ったり立ち止まったり、飛び上がったり、飛び落ちたりする。
いったいぜんたいなんのためにそんなことをするのかというと、詩の言葉というのはいい気なもので、詩人が好きなように書くとすぐに格好つけて歌い出し、俺は死人を代表している。俺は死人の代理人だ。歴史や物語にアクセスしたければ必ず俺を通せ、と言って事態を混乱させるからで、それを防止するために、言葉を二重三重に翻訳し、ルクク、と歌うことによって生じる酔いとその後の二日酔いを防止しているように感じたら、「東京から白い船が出ていく」にまた8月のことを感じて、なぜか涼しく、思考力はついにゼロとなった。ごめんな。
ALL REVIEWSをフォローする