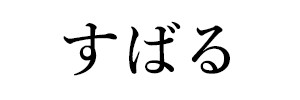作家論/作家紹介
宇能 鴻一郎他『水蜜桃―ポルノの巨匠傑作選』(祥伝社)、宇能 鴻一郎『鯨神』(中央公論新社)、『味な旅 舌の旅』(中央公論新社)、他
わたし、おののいたんです――宇能鴻一郎私論
エロの秋波はやっぱりただごとではない。いや官能の熱波というべきでしょうか。書店の文庫本の棚のまえで横並びの背表紙をつぎつぎ目で追っていたら、視線をがっちり捉えられて急停止。
「『ラブシーンの言葉』荒川洋治(あらかわようじ) 新潮文庫」
読みそこねていた本にこうしてあらたな縁ができたときは、ほんとうにうれしい。急いで棚から抜きだし、カバーを眺める。にやり。まったりとした卵いろ一色もうれしはずかし、題字のとなりで二体の熊がひしと抱き合ってラブシーン中。
とるものもとりあえず最初の一ページをめくる。
まずは〈ハーレクイン・イマージュ〉の濡(ぬ)れ場から見ていこう。
大富豪の御曹司(おんぞうし)が「女性にも性の衝動はあるんだよ」と囁(ささや)いてヒロインの頬をなでたそのとき、給仕長が現れたせいでワインを何にしようかという話になってしまう。足踏みさせられた荒川さんは書く。
せっかくの濡れ場も、これで中断。こちらの期待も中断。
でも、こちらは歓喜に沸く。たった二行で手ごたえじゅうぶん。鼻息を荒くしながらレジのおねえさんに差し出し、そのまま近所の喫茶店になだれこんだ。
ポルノ小説、日記や手記、辞典、教科書、通販カタログまで現代詩作家が熟読。一語一文一節、足どりしずかに立ちどまりながら、おじさんのエロごころを全開にして言葉を、官能描写を、じっくり鑑賞し尽くすのである。荒川洋治さんならでは、切れ味するどく、熱く、熟れた玩味(がんみ)ぶりに目を開かされ、官能と言葉の睦(むつ)みあいに光が当てられるさまに息を呑む。わたしの鼓動は高まるばかりだ。章扉の熊さんカップルのラブシーン四場面も花を添える。「できあがったばかりの二体の熊の立体を相手に、あーでもないこーでもないとAV監督さながらに演技をつけて撮影」(新潮文庫編集部・古浦郁氏後日談)しただけのことはあります。
刮目(かつもく)させられる箇所は数かぎりないが、わたしがとりわけ反応したのは、このくだり。
〈とっさに松吉は、そこに口をつけていた。散った墨を舌先で丹念になめ取った。ひんやりとした、なめらかな触感を心ゆくまで盗み、味わった。墨の香りに混った玉枝の体臭はいちだんと強く、松吉は水から上った犬のようにあえいで、身を震わせた〉 夏の終わりの風が部屋のなかを通りぬけていく。布団に顔を伏せる玉枝、絵筆を走らせ、針を刺していく松吉。この世は、二人だけである。 宇能氏の文章の静けさが、すばらしい。その一針、一針に息をのむ。
わたしも喫茶店のかたすみで渇いた喉にごくり、すっかり水滴に濡れたグラスの水を流しこむ。宇能鴻一郎(うのこういちろう)「刺青綺譚(いれずみきたん)」(昭和四十六年)。この一編を取りあげた荒川さんが「宇能氏」と書き分けるところに敬意を汲(く)みとる。
なまなましい感情が湧いてきた。
宇能鴻一郎。
なんという強烈なインパクト。自分の内なる場所でこの五文字がいぜん効力を持ちつづけていることにもおどろく。宇能鴻一郎、やっぱりただものではない。
数年まえまで、スポーツ紙や夕刊紙でしじゅう名前を見ていた記憶がある。電車の席に座ると、目のまえに立ったおじさんがスポーツ紙をがさごそめくる。すると、そこに宇能鴻一郎の連載官能小説。なんの興味もないふりをしながら、急いで読む。改行も句読点も多いからあっというまに読めるのだけれど、かならず冒頭一行めでさらわれる。
「あたし、レイコ。人妻看護婦なんです」または、こういうの。
「課長さんたら、ひどいんです」つまり、こういうの。
「あたし、濡れるんです」
「あたし、」と書くだけでアナザーワールドに連れてゆく天才、宇能鴻一郎。でも、そもそも芥川賞作家ではなかったか。じつは、ほんとうのところをよくは知らない宇能鴻一郎。がぜん読んでみたくなった。
書店を探し歩いてもなかなか見つからないときは、ネット書店がはやい。さっそく検索。著作は七百冊を超えるとも聞くのに、どの本もこの本も軒並み絶版である。芥川賞受賞作『鯨神』の文庫本が難なく見つかったから、さっそく中古で買いもとめる。値段は八百円。つづけて、いま出版されている数少ないうちから「祥伝社文庫」の一冊をクリックしてみると、わわ。いきなり画面にでました。
「警告 このストアは、アダルト商品および18歳未満の方には不適切な表現内容が含まれる商品を取り扱っています。18歳未満の方のアクセスは固くお断りします。あなたは18歳以上ですか?」
はいはい太古のむかしです。そそくさとクリックして進み、まず『水蜜桃(すいみつとう) ポルノの巨匠傑作選』あたりに目星をつけてみることにした。かつて「ポルノ御三家」と呼ばれた宇能鴻一郎、川上宗薫(かわかみそうくん)、富島健夫(とみしまたけお)をはじめ、田村泰次郎(たむらたいじろう)、梶山季之(かじやまとしゆき)まで揃えたアンソロジーである。
クロネコが敏捷(びんしょう)にも即日届けてくれたので、さっそく手に取る。収録されているのはいずれも昭和四十年代の作品なのだが、うち宇能作品は「寝巻(パジャマ)パーティ」。初出は「問題小説」昭和四十六年十二月号。アナクロ感ただようタイトルに一瞬ひるんだけれど、つべこべ言わず読んでみた。そして、納得。
冒頭にはすでに後年の宇能文体の萌芽(ほうが)があった。
「女って、つくづく欲ばりだ、と思います。もちろん、男のひとだってそうですけれど、でも何だか、可愛(かわい)げがあるみたい」
耳もとでこっそり告白を聞かされている気になるところからして、勝負あり。フィクションをたちまち忘れさせる一人称独白体の威力だ。夫婦ふたりで深夜の「寝巻パーティ」になだれこんだのち、心理(妻の、です)をむだなく描写してぐんぐん没入させるスピード感がすばらしい。出会った相手をこっそり思い起こすつぶやきが締めくくり。
「ジョーイの小瓶を指にはさんで、そう申しながらあたくし、心の片隅で、
(あたしはまたするわ。きっと) と考えていたのでございます」
夫、かたなし。こちらは、ずきり。
宇能鴻一郎は昭和九年生まれ。東京府士族の鵜野二弥と佐賀県士族の綾(あや)とのあいだに生まれる。北海道札幌市(さっぽろし)出身。父の転勤にともなって各地を転々としながら育ち、三十年、東京大学文科Ⅱ類に入学。三十四年卒業。同年大学院進学。三十六年学位論文「原始古代日本文化の研究」で文学修士。同年「光りの飢え」が芥川賞候補になる。三十七年「鯨神」で第四十六回芥川賞を受賞。四十年代前半に性をテーマに据える小説家として位置を確立。嵯峨島昭(さがしまあきら)の別名で推理小説も執筆。そののち官能を描く大衆娯楽小説に進み、独自の文体と作風によって一世を風靡(ふうび)する。
――これが、宇能鴻一郎の道すじのあらかたである。しかし、そのすがたはおぼろげだ。たしかに一世は風靡したけれど、実像が極端にうすい。かの山本夏彦は「週刊新潮」連載「夏彦の写真コラム」第六百三十一回、一九九二年一月二・九日合併号に宇能鴻一郎を取りあげ、こんなふうに書いている。
「宇能鴻一郎は名のみ高く、その姿を見たものがない唯一の文士である。きっと写真ぎらいなのだろう。それも尋常一様のきらいではない。宇能の読者は何十万人いても、その肖像を見たものはまあ一人もない」「顔を知られてないからどこに出向いてもあれが宇能だと言われる気づかいがない。明朗には見えるがその底には何がひそんでいるか分らない」
見出しは「声はすれども姿は見えぬ」。読めばだれもが一行めで作者は宇能鴻一郎だとわかるのに、実像は茫洋(ぼうよう)としたままなのだ。いやもちろん、それはそれでかまわないのです。ただ、『鯨神』と「あたし、濡れるんです」のあいだにはどんな距離が横たわっているのか、いないのか。もしそこに奥行きや幅があるなら、ほんのすこしでも指を触れてみたい。『ラブシーンの言葉』と『水蜜桃』に刺激されて、痛烈に思ったのである。
風に舞う桜の花びらがついえたころ、郵便受けにすとんと茶封筒の包みが落とし入れられていた。裏をかえすと個人書店の名前が記してある。胸を弾ませて封を切ると、はたしてそこには『鯨神』(中公文庫 昭和五十六年刊)が、ていねいにハトロン紙でくるまれていた。
その夜、仕事を早めに切りあげて夕食をすませ、さっそく『鯨神』を手にとった。収録された四篇はいずれも昭和三十六~三十七年発表、二十七歳ごろの作品である。くじらがみ、と読む。なじみのない響きのなかにざらつきが潜んでいるのを感じながら、居間のかたわらの椅子(いす)に腰を落ち着けてゆっくり読みはじめる。
ここに一巻の古い鯨絵巻(くじらえまき)がある。中央には背美鯨(せみくじら)だと思われる巨鯨が血を噴いて荒れまわり、何隻かの赤・白・黒にぬりわけた鯨小舟(くじらこぶね)がそれをとりまいて銛(もり)を投げつけている。
「わたし」が、旧家の当主が所有する絵巻にまつわる鯨神の言い伝えを聞くところから、小説ははじまっている。舞台は明治初期の肥前平戸沖(ひぜんひらどおき)。そもそも十七世紀の日本には、各地の沿岸で武士を中心に据えた捕鯨の大集団、鯨組があった。なかでも紀州太地(たいじ)とならんで、江戸から明治にかけて全国に名をとどろかせたのが長崎県生月島(いきつきしま)を拠点に網取り式捕鯨をおこなう「益富組(ますとみぐみ)」。宇能鴻一郎は、その史実を知って着想を得たにちがいない。さらに鯨は、古来から日本人にとって豊饒(ほうじょう)をもたらす経済資源であり、畏敬や崇拝の対象、つまり霊的な存在でもあった。大学時代からすでに作家を志し、水上勉(みずかみつとむ)、北杜夫(きたもりお)、佐藤愛子(さとうあいこ)、川上宗薫(かわかみそうくん)らとともに同人誌「半世界」へさかんに寄稿しながら、土俗的な世界を果敢に描きだそうとしていた宇能鴻一郎は、かっこうの題材として鯨組を捉えたのである。さらには土地の方言、隠れキリシタンの祈り、呪詛(じゅそ)、唄をさかんに小説に取り入れ、言葉のエネルギーを充塡(じゅうてん)する。
……ああやっぱり。しだいに背中が熱くなってきた。なにしろ濃いんです。猛(たけ)って、滾(たぎ)って、ものすごく濃い。こういう芥川賞受賞作があったのか。はあはあ。動悸(どうき)がしてくる。黒い島のように巨大な鯨神と、かつて鯨神に祖父と父と兄を奪われた若い羽指(はざし)(鯨捕りの花形。鼻を切り開いて綱を通し、瀕死(ひんし)の鯨を仕留める役目を担う)、シャキ。この小説こそ、宇能鴻一郎の文学の血脈のみなもとだった。なんと、荒れ狂う大海で壮絶な死闘を繰りひろげる巨大鯨と人間に、恍惚、忘我、畏怖、賛美、称揚、ありったけの官能を注ぎこんでいたのだ。びっくりしてしまいました。
いよいよ死闘の場面に進むと、筆致は気迫をみなぎらせる。ついに海上に現れた鯨神が網に追いこまれ、そそり立つ黒い壁肌に突き刺さる無数の銛。荒れ狂う海面。降りそそぐ飛沫に混じる鯨神の返り血。尾に叩き潰されてこっぱみじんに散るセコ船。シャキは網を足がかりによじ登り、海中の鯨神の急所をテガタ包丁でえぐりつづける。
死闘のすえ鯨神を仕留めたシャキは、自分にも訪れた死を受け容れ、今際(いまわ)のきわ、鯨神と一体に溶け合う幻想に身をゆだねて恍惚とする。
おれのふきあげるしぶきは、大空の虹とはりあうもうひとつの虹をおれの頭上にかかげ、鳥どもはやかましい讃嘆(さんたん)のさえずりをかわしながら虹をくぐって飛びかった。なんと豪奢(ごうしゃ)な海であり、なんと豪奢なおれであり、なんと豪奢なおれの生だったことだろう。
相まみえて性愛の絶頂感のうちに果てる男女のすがたも、すでにここにある。
白波をくだいておれのすすむところ、おれのまわりは、明け方は薔薇(ばら)いろの褥(しとね)となり、まひるには一めんにかがやく金ののべ板の大広間となり、夕暮れどきには蒼穹(そうきゅう)をおおって真紅の天蓋(てんがい)が垂れこめ、夜には、ながながと曳(ひ)かれたおれの航跡はすべて、月の光りをあびて蒼白(あおじろ)くかがやく練り銀の波うつ裳裾(もすそ)とかわった。
くらくらしてきます。筆のさきで官能がうねっている。
ただし、世間はなかなかきびしいわけです。芥川賞選考委員の選評のうち、もっとも好意的な内容はこんなふう。
井上靖(いのうえやすし)
八篇の中では宇能鴻一郎氏の『鯨神』が、私には際立って面白かった。この作品を読み終った時、すぐこれを推そうという気になった。 構成の上にも難はあるし、細部にわたって見れば指摘できる欠点は幾らでもあるが、そうしたところがさして気にならないくらい野性的なエネルギーに満ちた作品で、芥川賞授賞作にふさわしい新風と言っていいだろうと思った。
戦慄(せんりつ)が走るのは、この選評だ。
丹羽文雄(にわふみお)
宇能鴻一郎君の『鯨神』には、その豊かな描写力は、ひとを驚かすに足る。筆が走りすぎて、文章が上すべりしているところがあるが、前回の『光りの飢え』に比較すれば、格段のちがいである。吉村昭君の場合は、私達と共通の場でその将来性が考えられるが、宇能君はどんな風になっていくのか、私達とあんまり縁のないところへとび出していくような気がする。
予言的中。「私達とあんまり縁のないところへとび出していく」と見抜く文士の炯眼(けいがん)におそれ入る。なにしろほんとうに宇能鴻一郎は文壇を「とび出して」いくのだから。
「あのう、さらにこんなものまであるのですが」
電話のむこうのカワサキさんの声が動揺している。
「ごぞんじでした? 昭和三十七年大映作品、田中徳三監督『鯨神』。もちろん原作は宇能鴻一郎。主演は勝新太郎と本郷功次郎。それでもって脚本は新藤兼人(しんどうかねと)」
芥川賞受賞の翌年、そんな映画まであったのか。それにしてもやっぱり濃い。配役がすでに濃厚すぎます。シャキ役は本郷功次郎、紀州の流れ者が勝新太郎。鯨名主・志村喬(しむらたかし)、その娘トヨ・江波杏子(えなみきょうこ)、シャキの嫁・藤村志保。カワサキさんがさっそく取り寄せたDVDのカバーには、まがまがしい赤い宣伝文句が躍っていた。
「鯨神はおれが倒す! 大海原を巨鯨の鮮血で染め上げた、海の男の一大叙事詩!」
かなり暑くるしい。
さっそく上映会が開催された。参加者はDVD発見者のカワサキさん、同僚のアキヤマくん、わたしの三人である。じつはこの映画は公開当時、鯨の特撮が話題を呼んだ注目作でもあった。巨大なプールに高さ七メートル、重さ三トンのセミ鯨の頭部の模型を入れて操るという時代の最先端をゆく撮影技術が駆使された。時代劇が行き詰まったとみた大映にとって、特撮路線は起死回生のこころみだったのだ。
で、さっそく観てみました。いやまいった。本編百分、まったく飽きなかった。それどころか、緊迫につぐ緊迫。モノクロ画面に勝新の黒光りする肌がてらてら、本郷功次郎の筋肉がりゅうと盛りあがる。鯨神征伐に名乗りを挙げたふたりの乱闘場面(しばしば鯨はそっちのけ、男同士の肉弾戦がしつこく展開)のはげしさときたら、声もない。これはもう「漢(おとこ)」の映画。先頭に立って鯨組を率いる志村喬もまた、「用心棒」「椿三十郎(つばきさんじゅうろう)」と同時期ならではの精悍(せいかん)ぶり。妖気(ようき)ふりまく江波杏子、可憐(かれん)な藤村志保、ふたりの女優の初々しさ。
3D映画まで登場したいま、当時話題の特撮シーンはたいそうかわいいのです。冒頭、模型バレバレの鯨の咆哮(ほうこう)に思わず「ぷ」と吹きだした三人だったが、しだいに膝を乗りだして画面に見入った。
「真剣なんだ……すごい」
目をまるくしてつぶやくアキヤマくんに、カワサキさんもわたしも無言でうなずく。それもそのはず、役者のその後の活躍ぶりはもちろんのこと、田中徳三監督は勝新太郎主演「悪名(あくみょう)」シリーズ、市川雷蔵(いちかわらいぞう)主演「眠狂四郎」シリーズ、田宮二郎主演「犬」シリーズと人気作をつぎつぎ手がけ、大映は「鯨神」ののちガメラや大魔神など特撮路線に活路を見出(みいだ)してゆく。音楽の伊福部昭(いふくべあきら)は、あの不滅のゴジラのテーマの作曲者だ。東京オリンピックの二年まえ。土俗的なテーマを原作に選びながらも日本の映画人がエネルギーを燃やして未知の可能性に挑む、「鯨神」はその奔流のただなかで生まれた映画なのだった。
画面いっぱい「終」のエンドマークののち、部屋の灯(あか)りをつけながらアキヤマくんがぽつりと言う。
「かんがえてみたら、鯨はただ海を泳いでるだけだから、わざわざちょっかい出さなきゃ死人も争いごとも起こらず、世間は平和なわけですよね?」
そうなのよ。そこなのよ。人間は、人智(じんち)を超えたものに向かって渾身(こんしん)のちからを奮いながら挑んでゆく。愚かしくとも、それが栄光であっても。メルヴィル『白鯨』が描きだす復讐(ふくしゅう)の悲劇も、つまり人間が背負った運命のありようなのだ。または、アントニオ・タブッキ『島とクジラと女をめぐる断片』。ある夏、ポルトガル沖合に浮かぶアソーレス諸島で過ごしたタブッキは滅んでゆくクジラに隠喩(いんゆ)をもとめて幻想的な掌篇を書き継ぎ、いっぷう変わった一冊に編んだ。作家にとっても詩人にとっても、鯨は東西をとわず文学的存在でありつづけてきた。さらに貪欲(どんよく)にも官能の輝きを希求した作家、それが宇能鴻一郎なのだった。
丹羽文雄の予言どおり、『鯨神』以降の宇能鴻一郎は独自の世界に足を踏み入れてゆく。昭和四十年代前半、性と死、サディズム、フェティシズム、同性愛、異形(いぎょう)のエロスを探求しながら『獣の悦(よろこ)び』(昭和四十一年)、『魔楽』(昭和四十四年)、『切腹願望』(昭和四十五年)……おびただしい数の作品を中間小説誌に発表する。タイトルだけで脳震盪(のうしんとう)を起こしそうな「べろべろの、母ちゃんは……」(昭和四十四年)は、母親がつくった「微妙な艶(つや)をたたえて、蒼(あお)ぐろい淵(ふち)のようによどんでいる」桶(おけ)のなかのこんにゃくにフェティシズムを投影した奇譚だ。『楽欲(ぎょうよく)』を論評した澁澤龍彦(しぶさわたつひこ)は、「おそらく、日本で獣姦(じゅうかん)小説を書いたのは、宇能鴻一郎が最初であろう」(『澁澤龍彦全集6』)と、さすが見逃していない。その特異な作品世界に刺激を受けた作家はたくさんいたが、栗本薫(くりもとかおる)もそのひとりだった。
ALL REVIEWSをフォローする