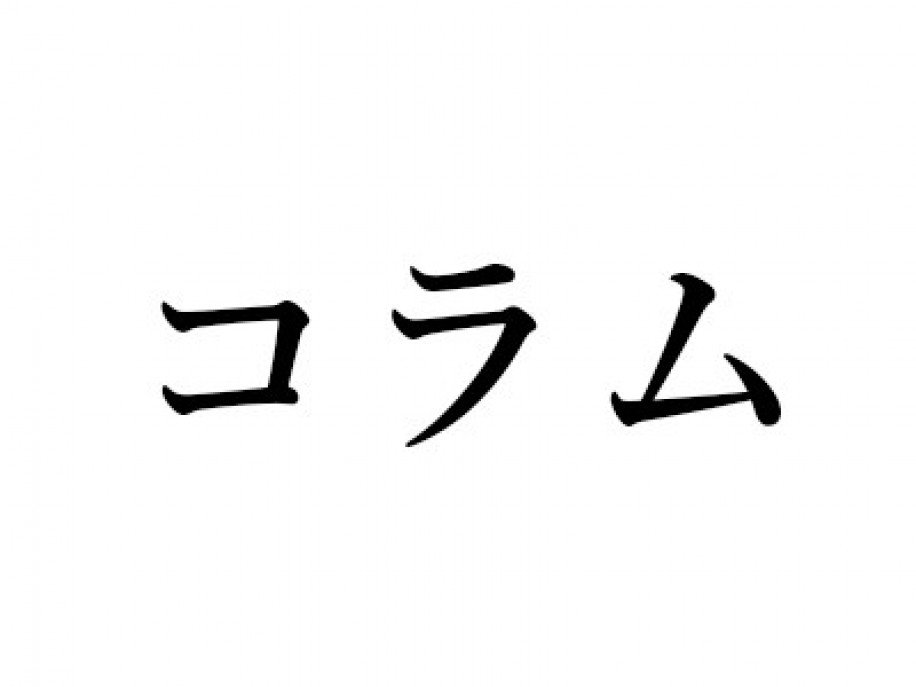書評
高平哲郎『高平哲郎スラップスティック選集(別巻)』、出久根達郎『幕末明治異能の日本人』
人名がおもしろい本
筒井康隆さんが、昔、人名で自分史年表のようなものを書いた。つまり3歳で覚えた人名、4歳で覚えた人名というふうに、架空実在を問わずに列記した人名リスト。この人名のリストを見るだけで、成長の様子や、趣味や知識のつみかさなりや変化が見える。いわば脳ミソをのぞくようなおもしろさだ。
高平哲郎さんの新著『私説人名事典』をパラパラと見ていて、この筒井さんのリストを思い出したのは、形式の発明という共通点だ。
人名事典を、たった一人の人間の視点で作るというのが発明だ。そもそも人名事典というのはNHKの放送みたいに「偏らない」「無名性の」「客観的な」いわば「人間的でない」文章で書かれてあるものだ。
だが、それはあくまで表向きなので、事典の項目の書き手は、そこに何かをこめて書いているはずだ。そうであるのだったら、はじめから私見を全面的に展開した「偏った」「主観的」で「人間的」な「人名事典」を作ってみたらどうか。
果たせるかな、ものすごくおもしろい本になった。高平さんが、人と出会うたのしさや、人に憧れるよろこびや、なじめなかったり、反発したり、こじれたり、友情を感じたりする、人と人との関係のおもしろさが、まるごと一冊になった。
はじめのうち、知った名前を拾い読みしていたが、もう一度はじめから通読してみると、これがそのまま起伏のある読み物になっている、のに気がついた。
つまり、どのページのどの項目にも高平さんがいるのだ。会ったこともない昔の人も、その偏った人選に入っているところに意味がある。
イエス・キリストの項に「面識」はないとあったりするおちゃめもあって高平さんらしい。
出久根達郎さんの『幕末明治異能の日本人』も、人名の本である。古書店主でもあった著者の目が、人名と人名を、脳の神経繊維のようにつないでいって、意外なところで出会っていく。たくさんの書物によって人名があちこちでつながって、実人生のリアリティーが感じられる。
私はかつて、二宮金次郎や清水次郎長になったつもりで、ゆかりの場所に旅して、ゆかりの場所に立ち、本人として記憶をたどる、という奇妙な実験をしたのだったが、その時に、覚えた人名は不思議に頭に入っている。
名前を知れば、その人は知人である。知人の消息を見るように興味はひきつけられる。興味が人名によってむすばれていく。
幸田露伴と二宮金次郎、二宮金次郎と勝海舟、勝海舟と山岡鉄舟、山岡鉄舟と清水次郎長。という具合にそれぞれ単独に知っていた人名が、実はむすびついていて、たがいにからみあってくる。
読書家というのは、こういう本の読み方をするらしい。一冊の本に出てきた人名が、次なる本を呼び、その本に新たにみつけた人名が、さらに次の本へつながっていくという具合だ。
この『幕末明治異能の日本人』は一冊で、この本読み巧者のたのしみを味わえる。豊かで実物大の人生を感じるようだ。
ALL REVIEWSをフォローする