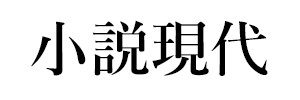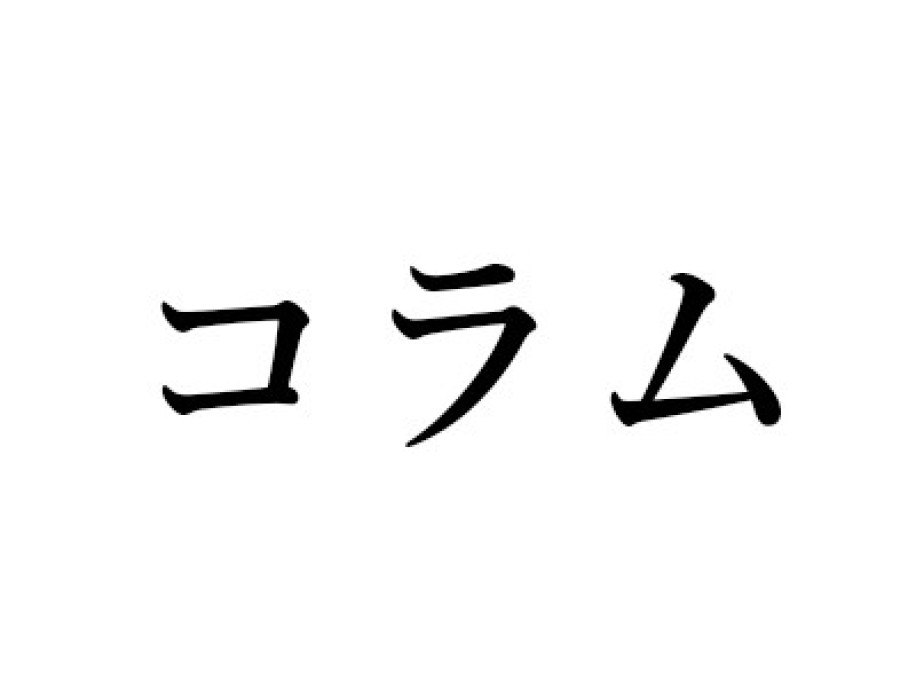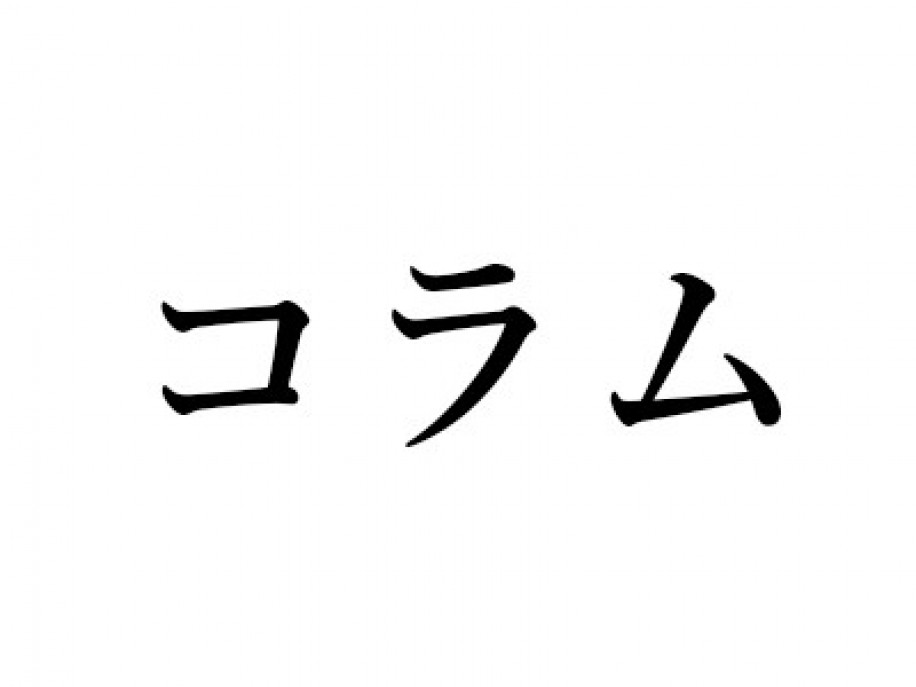読書日記
大佛次郎『猫のいる日々』(徳間書店)、内田百閒『新編ノラや』(福武書店)、群ようこ『鞄に本だけつめこんで』(新潮社)ほか
猫好きにはかなわない
近所の道を歩いていたら、向こうから、底の分厚いサンダルにミニスカートの若い女性が、やって来た。私のすぐ前で、突然棒立ちになったかと思うと、「いやーん」と道のまん中ですっとんきょうに叫ぶではないか。何ごとかとあっけにとられる私のそばを通り過ぎ、ポストの前で、パンツが見えそうなくらいにしゃがみ込む。
「かっわいーい。よしよし」
ポストの下に腕を伸ばし、そこで昼寝をしていたらしき猫の腹を、ぐにゅぐにゅとさわっている。
(また、猫好きか)と横目で見る。
あのポストの下にはよく猫がいるが、私が遭遇する猫好きは、彼らに向かって「よしよし」と目でうなずくだけでは飽き足らない。必ずや手を出し、撫で回すのである。
猫の方もまんざらではないのか、自ら体を裏返し、ときには乳首までさらすという、あられもない姿で喜んでいる。あれが嬌態でなくて、何であろう。
梶井基次郎には、そのものずばり「愛撫」なる題の小説がある(新潮文庫『檸檬(れもん)』に収録)。飼い猫の耳をひっぱったり、つまんだり、嚙んでわざと悲鳴を上げさせたりと、いちゃつきぶりが、臆面もなく綴られている。猫好きでない私には、あの愛情表現はどうも理解しがたい。人前で抱き合うカップルを睨む頑固おやじではないけれど、
(なんという慎みのなさか)
と思ってしまう。
猫とみれば相手構わず「かわいい」を連発し、いじくり回す人間も人間だが、ポスト猫の方だって、他の人の愛撫にも同じように嬉々として応えるところを、しょっちゅうここを通りかかる私は、何度も目撃している。
「不実だ」
というのが、猫に対する私の印象。嫌いというほどでもなく、事実、わが家の庭を通行するのは黙認しているが、「どちらかを飼え」と言われれば、犬の方を選ぶだろう。
小学校の頃住んでいた家の角ひとつ向こうが、大佛次郎の家で、常時多数の猫が出入りしていた。子どもたちの間では『鞍馬天狗』の作者としてより、猫の方で有名だった。
たまたまその頃、「スイッチョねこ」という童話を読んだ。あくびをした猫のロから虫が飛び込み、腹の中でスイッチョ、スイッチョと鳴くという話。「大佛次郎・作」とあり、「あの猫屋敷の人の本か」と合点がいった。あり得ないことなのに、リアリティーを感じさせるのは、猫を日々観察している人だから、しぐさなどの描写がひとつひとつそれらしいためだろう。
『猫のいる日々』(徳間文庫)には、猫をめぐるエッセイとともに「スイッチョねこ」もおさめられている。多くの小説を書いてきた著者が「私の一代の傑作はほんとうは」あの童話だと、同じ本の中で打ち明ける。
エッセイによると、大佛家で飼った猫は、延べ五百匹以上になるそうだ。著者は少なくとも文章上は、居候どもを猫かわいがりはしていない。むしろ少々持て余し気味のふうでもある。
連れ合いは、もとは大の猫嫌いだったのに、いつの間にか夫をしのいでしまった。十五匹以上になったら別居する旨、著者は妻に申し渡した。あるとき並んで皿に首を突っ込んでいるのを数えると、十六匹いる。
「一匹多いぞ。おれは家を出るぞ」
女房すかさず、
「それはお客さまです。御飯を食べたら、帰ることになっています」
猫自慢に溺れない軽妙な文章が、読んで楽しい。例えば、泥棒に入られたときの話。捕らえてみれば、かつてよく届けにきていた魚屋で、なるほど猫が驚き騒がなかったわけだと。
飼い猫のいる人に聞いたところ、
「猫は犬と違って、誰が侵入しようと知らんぷりよ」
魚屋だからなびいたわけではないだろう、と。にもかかわらず、話のオチをそこでつけるあたり、小説家の著者、エッセイにおいても、「仕事」をしているなと感じる。
内田百閒の『新編ノラや』(福武文庫)は、猫のいる日々ではなく、「いない日々」がメインである。行方知れずになってから、なぜか愛しさが爆発して、あたり構わず号泣し、ご近所をはばかる妻がたしなめても、ふとしたきっかけに「思い出し、又泣いて制する能わず」といった日々だった。
新聞に折り込み広告を出すこと四たび、子どもや外国人にはわからないかも知れないと、それ用のチラシも刷る。「みなさん ノラちゃんという猫をさがしてください!」「Inquiring about a Missing Cat」。全文が、エッセイに掲載されている。
しまいには、これだけ探しても出てこないのは、皇居に迷い込んだからではないかと考えるにまで至る。
悲嘆のうちのおかしみを計算しての構成か。激情のさなかにある人間というのは、ぶざまであり、激情の内容が真であるか否かにかかわらず、そうなのだということを、自らの姿を通して描いたのでは、と読める。その意味で、これもやっぱり、大人の仕事だ。
「今となって思うに、その時ノラは死んだのだろう」と十数年が過ぎてから、ようやく死を認める記述が出てくる。失踪後間もない朝、ふいの嗚咽(おえつ)に涙が枕をしとど濡らしたことがあった。著者が言うに、あれは「ノラが私の枕辺にお別れに来た事に間違いない」。
群ようこ著『鞄に本だけつめこんで』(新潮文庫)にも、二、三日帰らなかった飼い猫が、ひょっこりとお別れを言いにくるシーンがある。家に上がらず、庭に「おすわり」の姿勢でいた。「体をさすってやると首から下はなぜかひんやりしていた」。
「トラちゃん、今までありがとう」、著者の母親が声をかけると、どこへともなく去っていったという。
猫は「不実だ」との認識を、私は改めざるを得なかった。犬とは違うしかたで、人間との関係を取り結んでいる。
森銑三の「猫が物いう話」(『ちくま文学の森 動物たちの物語』に収録)では、飼い猫がうっかり人間の言葉を喋ってしまう。ナンセンス話を、短い文章で、ごく自然なエピソードのごとく仕上げるうまさに、驚く。
似たような昔語りは、大佛次郎のエッセイにも出てきていた。たしかに、犬ではなく猫でこそ、この話は、ほんとうらしく成立する。それだけ猫は人間にとって、身近で、かつ謎めいた存在なのだろうか。
ALL REVIEWSをフォローする