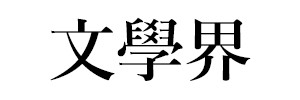コラム
社交する人間の文学 丸谷才一さんを悼む
丸谷才一さんを悼む
丸谷才一さんと私の仲が歴史に残るとすれば、それは二人が百回を超える対談、鼎談を活字にしたという記録によってだろう。第百回目はついに「対談的人間とは何か」という題の対談になって、このときだれかがこれはギネス・ブックものだと言ったのを覚えているが、その後も二人は何回も話し合っているので、ほんとうの回数は今ではわからない。最初はもう四十年も昔、河出書房の『文藝』に載ったものだが、初対面の話題が何であったかは往時茫々のなかに霞んでいる。その後しだいに私たちは昵懇を深め、中央公論社の『歴史と人物』などで連載対談をするようになっていたが、何といっても二人を百回に及ぶ会話の醍醐味に開眼させたのは、半藤一利編集長の『文藝春秋』であった。
このときは木村尚三郎さんを加えて「鼎談書評」と題し、毎月一回、三人が交替で選んだ三冊の本を批評するという企画だった。当時、丸谷さんと私はすでに対話の芸というものにも目覚めていて、話を面白くするために喧嘩のふりをする悪智恵も身につけていた。第一回の冒頭から丸谷さんの推奨する本に私が酷評を下し、激論で初参加の木村さんを狼狽(ろうばい)させるという気の毒なこともした。
また後の回で木村さんが推薦した本を今度は丸谷さんが攻撃し、有名なあの大音声でまくし立てたものだから、私が「そんな大きな声を出しても活字にはなりませんよ」と言うと、「ここはゴチにしろ」と一層の大声が返ってきたのは、単行本になった記録にも残っている。もちろん木村さんもたちまち雰囲気に慣れ、結局、企画はまず一年半つづいて「文藝春秋読者賞」を受賞することになった。
これに味を占めたか、半藤さんは同じ書評集をさらに二冊分も作ったうえ、やがて『くりま』の編集長に移ると丸谷さんと私を旅に誘った。北は北海道から南は九州まで、二人が好きな町を訪ねて対談による紀行を出そうというのである。二つ返事で引き受けた二人は、おかげで一泊二日の旅を八回も楽しみ、互いに一層の親密を深めることになった。
半藤さんが町の芸者を総揚げするというので期待していたら、集まったのは平均年齢七十余歳の老妓(ろうぎ)ばかりだった小樽。昔、天皇をお迎えしたという老舗に宿をとったところ、部屋係の老女が靴下の履き替えまで手伝うと言うので二人が恐縮した長崎。それに丸谷さんから私が初めて連句の手ほどきを受けた松江など、あの旅の思い出は尽きない。
四〇年の交遊を振り返って思うことは、丸谷さんが生来の「社交する作家」であり、対談の精神はその文学活動の中核をなしていたのではないかということである。対談に欠かせない人をそらさぬ気遣い、「淡きこと水の如し」、また「親しんで狎(な)れず」といわれる人との距離感、その均衡をみごとに貫いたのが丸谷文学だった。
本来、社交には規律と遊び心という矛盾する姿勢が必要だが、丸谷さんはその二つを過不足なく備えていた、規律といえば、この人はかつて対談の時間に遅れるということがなかった。いつも私よりも早く会場に着いていて、私に忸怩(じくじ)たる思いをさせた。酒は好きで陽気に飲んだが、この人が泥酔する姿を見たことがない。その反面、先に触れたように演技力も豊かで、会話を盛りあげるためにあえて怒声を発することも厭(いと)わなかった。
対談にはまた、知的な運動神経とでもいうべきものが欠かせず、何を聞かれても当意即妙に答える才能が求められるが、その点でも丸谷さんはとりわけ俊敏であった。この背景には日ごろの好奇心の格別の柔軟さと、森羅万象にわたる広い知識の用意があったことはいうまでもない。そしてそのすべてが、この人の文学の独創性を支えたのだった。
丸谷さんがみずから俳句を嗜み、連句に遊んだことは有名だが、この二つが日本の伝統を飾る社交の文学だったことは広く知られている。一座を結んで「歌仙」を巻く連句はもちろん、席題に応じて人まえで一句を発する俳句も、いわば詩的な対談だといえる。またおびただしい随筆は丸谷文学の重要な一ジャンルだが、ここで作者が「です、ます」調を交えた独特の文体を造ったことも、注目しておきたい。「です、ます」調は話し言葉の文体であって、対話の情調を湛えていることを作者が意識していなかったはずはない。
さらにこの人が本業とした小説であるが、かねて丸谷さんの小説では登場人物が具体的な職業を持ち、実社会のなかに確かな身許証明を持っていることに、私は注目してきた。この人の小説にはいわゆる無頼の徒は登場せず、社会や家庭にたいして無責任な「私」という存在も現れない。『笹まくら』の主人公のように徴兵を忌避し、戦前社会に反旗を翻(ひるがえ)した人物でさえ、逃亡中は砂絵師という職業に就き、戦後は学校の事務員という職務を果たして、実直な生活を貫くのである。
後年の『たった一人の反乱』『裏声で歌へ君が代』『女ざかり』『輝く日の宮』『持ち重りする薔薇の花』のような長編はいうまでもなく、珍しく作者と主人公の重なりを思わせる『樹影譚』ですら、主人公はけっして内に籠もって実社会に背を向ける「私」ではない。官僚あり会社員あり、女性の新聞記者や大学教師あり、はては元経団連会長と弦楽四重奏団の団員まで、すべてが身辺の人間関係に責任を負う人物ばかりである。彼らは国家といった傲然として縁遠い社会には反抗しても、家族や隣人、同僚や友人との絆を失わない「社交する人間」なのである。
しかも見落としてはならないのは、これら多彩をきわめる人物を描くにあたって、作者はそのほとんどに直接の取材をしていることである。ご本人からその旨を聞いたこともあるし、作品を読むだけでも資料のみによる創作にはありえない現実性が感じとれる。ということは丸谷さんはこれだけの社会人に会って胸襟を開かせ、つぶさに暮らしぶりを語らせたことになるが、これはとても狷介(けんかい)な旧文士風の作家にできることではあるまい。
丸谷才一という文学者の歴史的な意味は、日本近代文学の二つの病弊、甘ったれた無頼性と不機嫌な「私」とを一気に打破し、文学を知的社会の開かれた地平に置いたことであった。この社交の達人に導かれたことが至福だっただけに、この人に去られたことは私にとって痛切な悲しみである。しかし日本文学が喪ったもののそれ以上の大きさを思い、現状から見てその穴を埋めることの困難を思うと、無念はさらにさらに耐え難いのである。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする