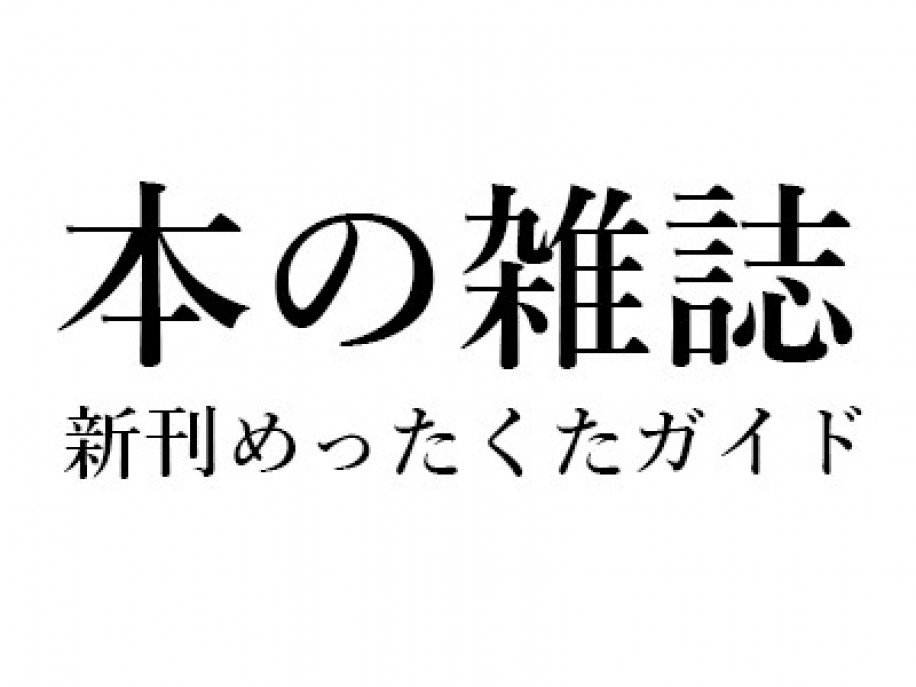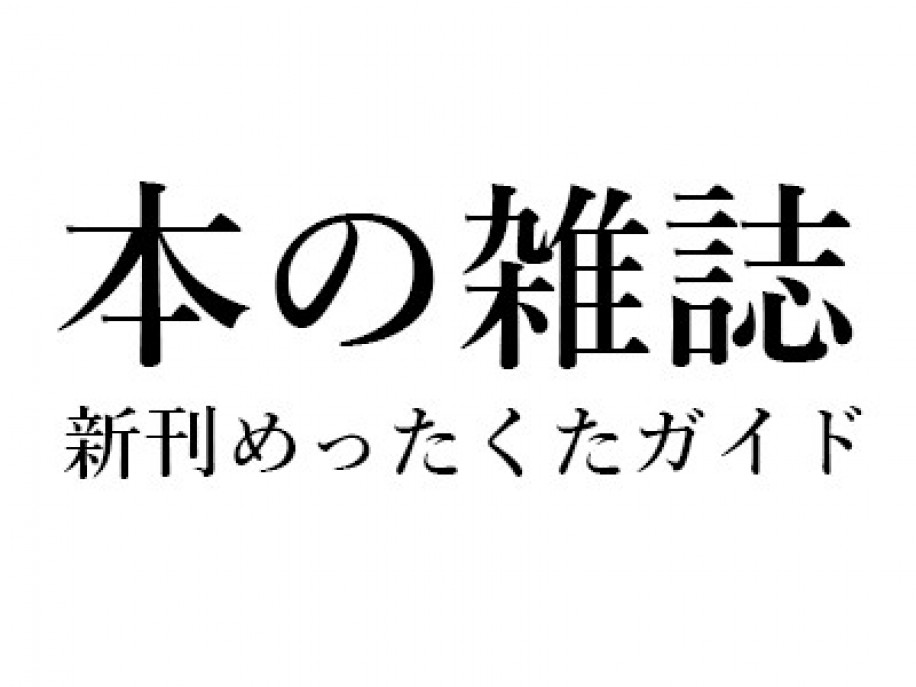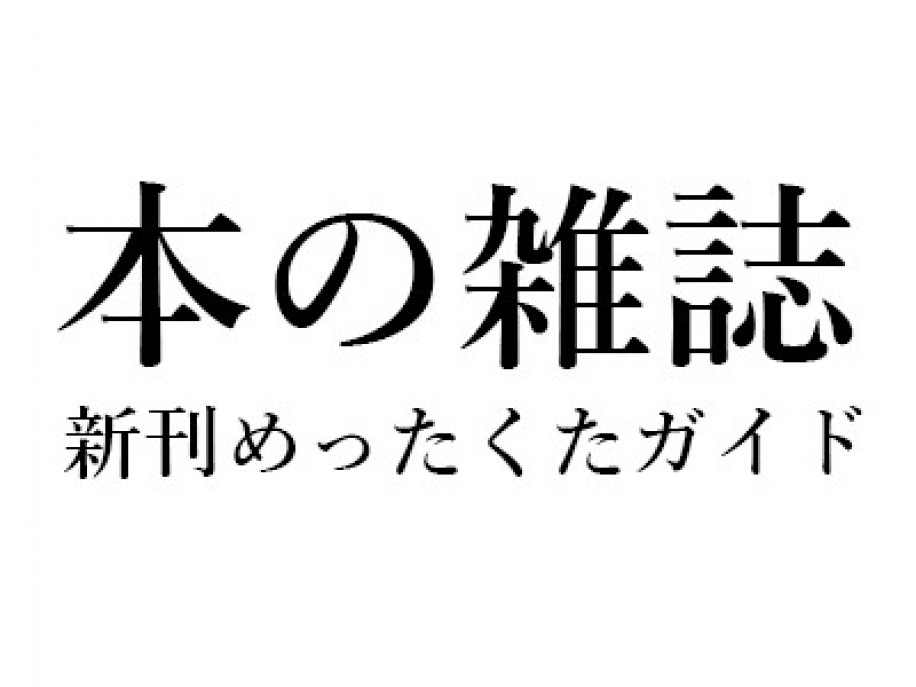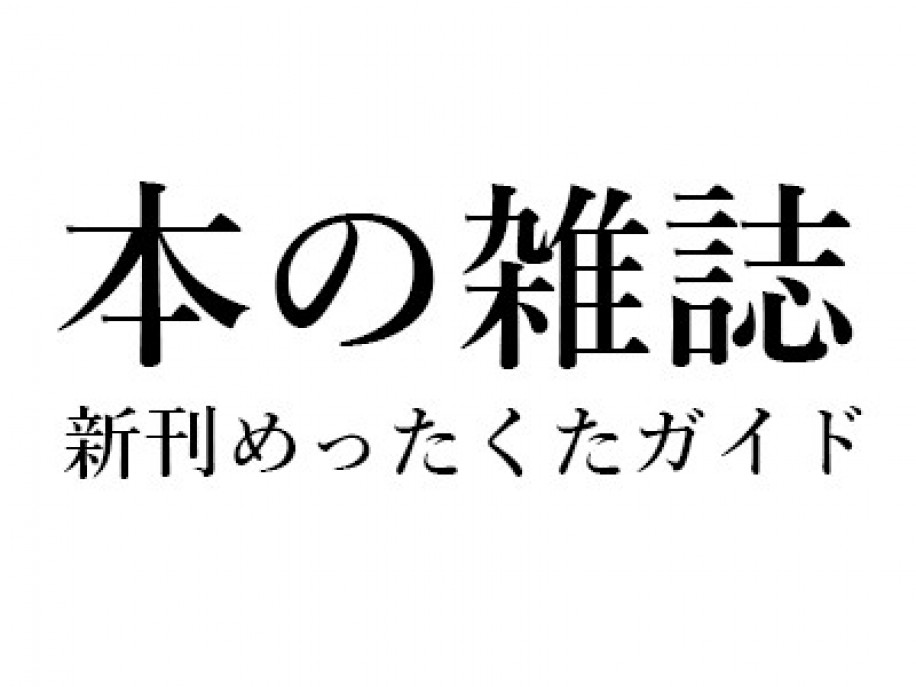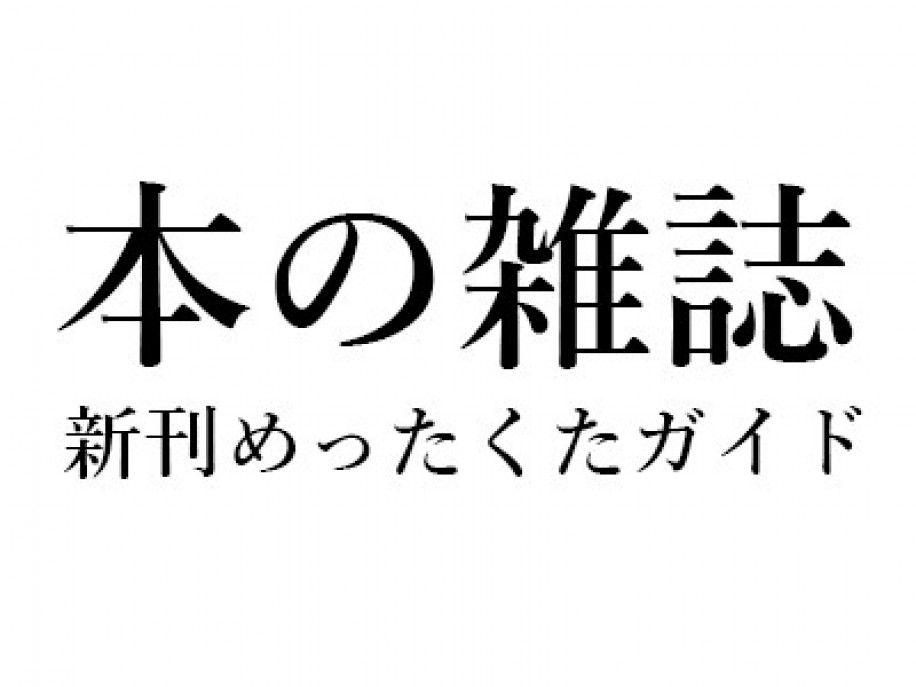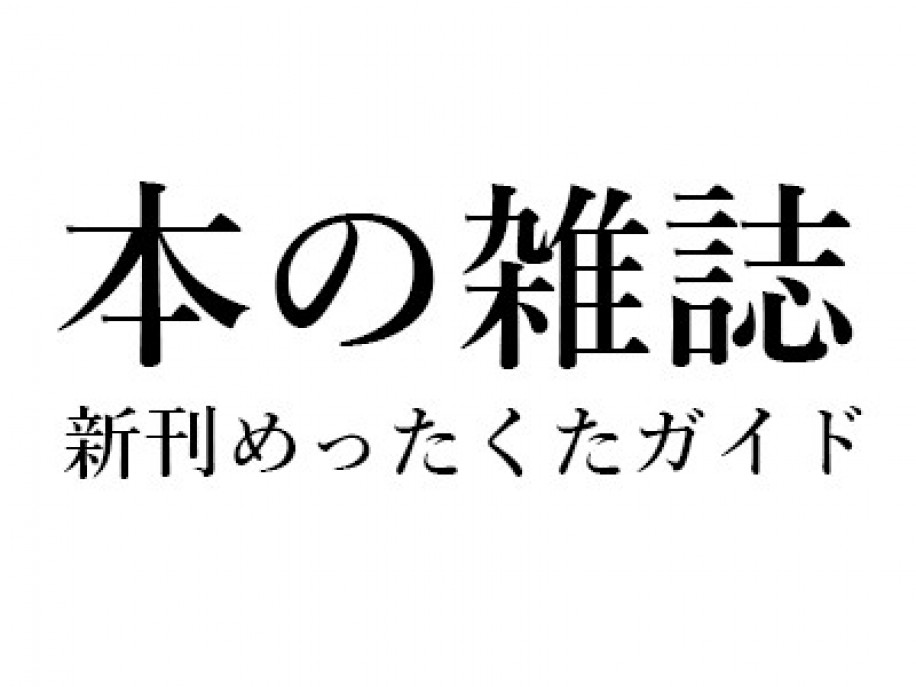読書日記
馬渕哲・南條恵『人は「動き」だ! なりたい自分を演出する40の方法』(日本経済新聞社)、渡部信一『ロボット化する子どもたち』(大修館書店)ほか
馬渕哲・南條恵『人は「動き」だ! なりたい自分を演出する40の方法』(日本経済新聞社/一四〇〇円)は、マジメなハウツー本だと思う。さまざまなシーンにあわせて、〝伝えたいことを正しく伝えるために不可欠な動き方の例を、イラストを使ってわかりやすく解説〟した指南書である。
禿頭に毛が三本、むかし流行ったレンズの大きい眼鏡、上のボタン二つ外したラフなワイシャツ姿、そんな男がイラストで、動きの実例を示している。
たとえば「穏やかに相手をけん制するときの動き方」のイラスト解説は、こんな感じだ。
なんなんだ、これは。
なにしろ、これで「穏やか」なのだ。こんなことを、こんな人に、こんな動きで言われる世界を想像する。それは、コントだ。
次の「穏やかに相手を攻撃するときの動き方」は、こうだ。
指さされて犯罪だと指摘され、さらにほほえまれた時、どうすればいいんだろう。読んでると、どうしても「この動き方を練習しよう」じゃなくて、こんな動きでこんなこと言われたらどうしようと考えてしまう。あたふたしても「犯罪を指摘された人のリアクションの仕方」の項はない。
他も、すごい。お金持ちらしい笑い方、堂々としたお茶の飲み方、気になる男性をさりげなくたたく方法、美女! のはずかしがり方(見ないでって言ってうなじを強調)、相手のバカな話に対するコケ方、面白い人が「大きいもの」を表現するときの動き方、面白い人の万歳の仕方など。なんなんだ、どういう場合なんだ、とツッコミを入れながら読んでしまう。「ツッコミながらクスクス笑ってしまうときの動き方」の大特訓をさせていただいた。
知人が、実際に社内で数人に本を見せると、「激しく怒ったときの机のたたき方」などが一時的に大流行。普通の会話でも、怒りのジェスチャーで問いかけて互いにアゴを上げてみたり。たいした連絡ではないのにおおきく振りかぶって指さしたり。果ては、ちょっとした会話でも、どの身ぶりが飛び出すかと身構えるようになって、動きがロボットみたいにぎこちなくなったとか。大いに楽しんだようである。コント好き必読、へんてこ本好き必読。
渡部信一『ロボット化する子どもたち』(大修館書店/一八〇〇円)というタイトルだけを見ると、デタラメなデータと主観だけで子供が危ないと主張し、親の不安を煽るタイプのインチキ本みたいだけど、内容はまったく違う。
ロボット研究者は、七〇年代まで「簡単なことから複雑なことへ系統的にひとつひとつプログラムする」ことでロボットを人間に近づけていこうとした。が、行き詰まってしまう。実験室では成功しても、実験室の外に出てしまうと、予想外の出来事があまりにも多くてロボットは対応できなくなるためだ。あいまいで複雑な日常に対応するために、ロボット工学はパラダイムシフトを強いられる。ロボット自身が環境の中で試行錯誤し、自らが学習していくように設計する方向へ進み始めるのだ。
そして著者は、それは人間にもまったく同様に当てはまると考え、「学び」について考察する。また自閉症の子供と向き合ってきた体験から、「簡単なことから複雑で難しいことへ系統的に教えていきましょう」という障害児教育で(いや、一般の教育現場でも)受け入れられている方法に疑問を投げかける。
"狭い枠組みのなかでのみ検討を進めてしまいがちな人間の「学び」探求に対し、ロボットの「学び」という視点と自閉症児の「学び」という視点を取り入れることによって"、将来の「学び」の方向性を探る刺激的な内容なので、「無根拠デタラメ脅迫本」っぽいタイトルに呆れずに読んでみて欲しい。同じ著者の本で、自閉症の晋平君がどのように育っていったかを軸にした『鉄腕アトムと晋平君 ロボット研究の進化と自閉症の発達』(ミネルヴァ書房/一九〇〇円)もオススメ。
数々の宮沢章夫のエッセイで、笑った。真剣なコードから逸脱するすっとんきょうを掬い上げる手腕に踊らされ、ゲラゲラと笑った。驚くことに『「資本論」も読む』(WAVE出版/一六八〇円)では、見い出されたすっとんきょうが「『資本論』の新たな読み」に繋がっているのだ。『資本論』を読んだことのない私が偉そうに「新たな読み」とか言っても説得力がないが、(弱気な瞳で)きっと繋がっていると思う。というか、『資本論』を読む宮沢章夫を読む本である。読むことは読む人の読みであるということを読む本である。『チェーホフの戦争』(青土社/一六八〇円)で、「チェーホフ」を読む宮沢章夫を読むのも楽しかった。
宮原諄二『「白い光」のイノベーション』(朝日新聞社/一二六〇円)は、太陽にできるだけ近い無色透明な光を手に入れるためのイノベーション(社会や産業構造を変えていく過程)について書かれた本だ。虹はなぜ七色に分類されたのか、昔の工場はなぜギザギザしたノコギリの刃のような屋根をしていたのか、人はどうやって色を感じるのか、などの疑問を次々と解説していく第一章からぐいぐいひきこまれる。
漫画は、八巻が出て本編が完結した芦原妃名子『砂時計』(小学館/四一〇円)を紹介。第五〇回小学館漫画賞受賞。十二歳冬から始まって、二十六歳の冬+αまで、少女が背負った重い現実を受け入れるまでの心の変化を全八巻かけてじっくりと描いた純愛物語。米光が泣いたのは、一巻、五巻、八巻。で、八巻を読んだら一巻を読みたくなって読み返し、また泣きました。伏線の張り方がめちゃくちゃ巧い。あと二冊、番外編が出るそうです。楽しみだ。
【この読書日記が収録されている書籍】
禿頭に毛が三本、むかし流行ったレンズの大きい眼鏡、上のボタン二つ外したラフなワイシャツ姿、そんな男がイラストで、動きの実例を示している。
たとえば「穏やかに相手をけん制するときの動き方」のイラスト解説は、こんな感じだ。
"いずまいを正し、穏やかに相手を見る"
「そうですか」
"遠いところを見る" 見上げる角度を示す点線つき。
「それならこちらにも」
"身体を少し傾ける"
「考えがありますよ」。
なんなんだ、これは。
なにしろ、これで「穏やか」なのだ。こんなことを、こんな人に、こんな動きで言われる世界を想像する。それは、コントだ。
次の「穏やかに相手を攻撃するときの動き方」は、こうだ。
"やや前傾し、真面目な顔で、相手をじっと見る"
「それは」
"ゆっくり手を上げ相手を指さす 指さしたまま一秒静止"
「犯罪ですよ」"
身体の力を抜いてほほえむ"
指さされて犯罪だと指摘され、さらにほほえまれた時、どうすればいいんだろう。読んでると、どうしても「この動き方を練習しよう」じゃなくて、こんな動きでこんなこと言われたらどうしようと考えてしまう。あたふたしても「犯罪を指摘された人のリアクションの仕方」の項はない。
他も、すごい。お金持ちらしい笑い方、堂々としたお茶の飲み方、気になる男性をさりげなくたたく方法、美女! のはずかしがり方(見ないでって言ってうなじを強調)、相手のバカな話に対するコケ方、面白い人が「大きいもの」を表現するときの動き方、面白い人の万歳の仕方など。なんなんだ、どういう場合なんだ、とツッコミを入れながら読んでしまう。「ツッコミながらクスクス笑ってしまうときの動き方」の大特訓をさせていただいた。
知人が、実際に社内で数人に本を見せると、「激しく怒ったときの机のたたき方」などが一時的に大流行。普通の会話でも、怒りのジェスチャーで問いかけて互いにアゴを上げてみたり。たいした連絡ではないのにおおきく振りかぶって指さしたり。果ては、ちょっとした会話でも、どの身ぶりが飛び出すかと身構えるようになって、動きがロボットみたいにぎこちなくなったとか。大いに楽しんだようである。コント好き必読、へんてこ本好き必読。
渡部信一『ロボット化する子どもたち』(大修館書店/一八〇〇円)というタイトルだけを見ると、デタラメなデータと主観だけで子供が危ないと主張し、親の不安を煽るタイプのインチキ本みたいだけど、内容はまったく違う。
ロボット研究者は、七〇年代まで「簡単なことから複雑なことへ系統的にひとつひとつプログラムする」ことでロボットを人間に近づけていこうとした。が、行き詰まってしまう。実験室では成功しても、実験室の外に出てしまうと、予想外の出来事があまりにも多くてロボットは対応できなくなるためだ。あいまいで複雑な日常に対応するために、ロボット工学はパラダイムシフトを強いられる。ロボット自身が環境の中で試行錯誤し、自らが学習していくように設計する方向へ進み始めるのだ。
そして著者は、それは人間にもまったく同様に当てはまると考え、「学び」について考察する。また自閉症の子供と向き合ってきた体験から、「簡単なことから複雑で難しいことへ系統的に教えていきましょう」という障害児教育で(いや、一般の教育現場でも)受け入れられている方法に疑問を投げかける。
"狭い枠組みのなかでのみ検討を進めてしまいがちな人間の「学び」探求に対し、ロボットの「学び」という視点と自閉症児の「学び」という視点を取り入れることによって"、将来の「学び」の方向性を探る刺激的な内容なので、「無根拠デタラメ脅迫本」っぽいタイトルに呆れずに読んでみて欲しい。同じ著者の本で、自閉症の晋平君がどのように育っていったかを軸にした『鉄腕アトムと晋平君 ロボット研究の進化と自閉症の発達』(ミネルヴァ書房/一九〇〇円)もオススメ。
数々の宮沢章夫のエッセイで、笑った。真剣なコードから逸脱するすっとんきょうを掬い上げる手腕に踊らされ、ゲラゲラと笑った。驚くことに『「資本論」も読む』(WAVE出版/一六八〇円)では、見い出されたすっとんきょうが「『資本論』の新たな読み」に繋がっているのだ。『資本論』を読んだことのない私が偉そうに「新たな読み」とか言っても説得力がないが、(弱気な瞳で)きっと繋がっていると思う。というか、『資本論』を読む宮沢章夫を読む本である。読むことは読む人の読みであるということを読む本である。『チェーホフの戦争』(青土社/一六八〇円)で、「チェーホフ」を読む宮沢章夫を読むのも楽しかった。
宮原諄二『「白い光」のイノベーション』(朝日新聞社/一二六〇円)は、太陽にできるだけ近い無色透明な光を手に入れるためのイノベーション(社会や産業構造を変えていく過程)について書かれた本だ。虹はなぜ七色に分類されたのか、昔の工場はなぜギザギザしたノコギリの刃のような屋根をしていたのか、人はどうやって色を感じるのか、などの疑問を次々と解説していく第一章からぐいぐいひきこまれる。
漫画は、八巻が出て本編が完結した芦原妃名子『砂時計』(小学館/四一〇円)を紹介。第五〇回小学館漫画賞受賞。十二歳冬から始まって、二十六歳の冬+αまで、少女が背負った重い現実を受け入れるまでの心の変化を全八巻かけてじっくりと描いた純愛物語。米光が泣いたのは、一巻、五巻、八巻。で、八巻を読んだら一巻を読みたくなって読み返し、また泣きました。伏線の張り方がめちゃくちゃ巧い。あと二冊、番外編が出るそうです。楽しみだ。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする