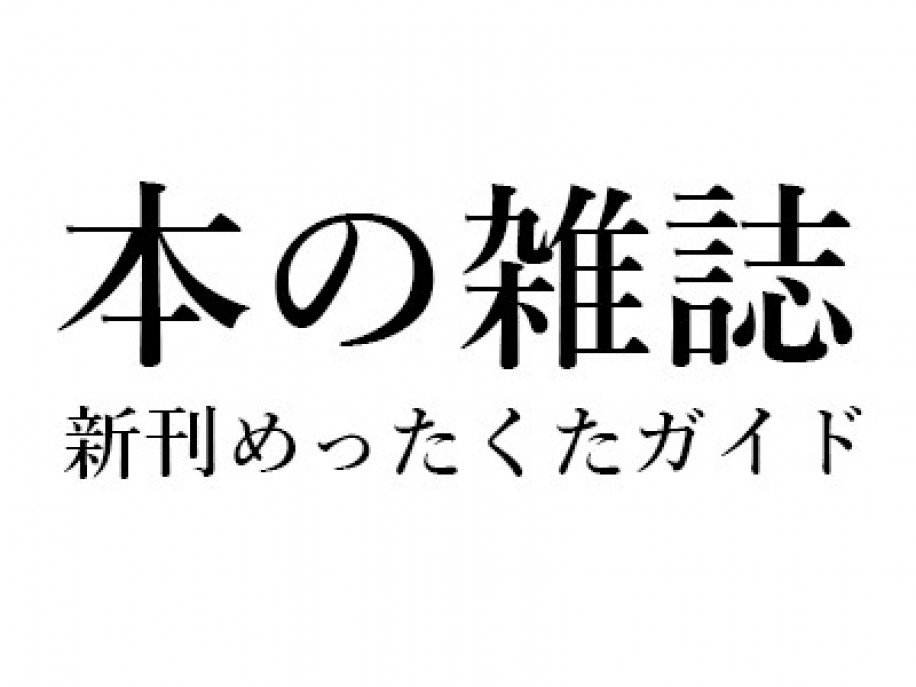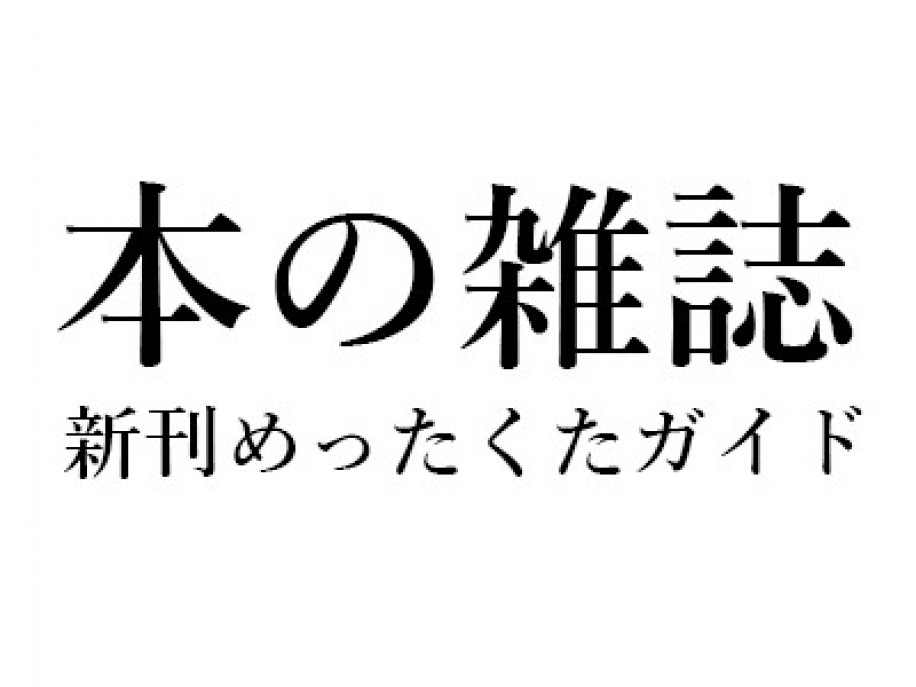読書日記
和田伸一郎『メディアと倫理』(NHK出版)、木原善彦『UFOとポストモダン』(平凡社)、野沢和弘『わかりやすさの本質』(NHK出版)ほか
戦地。子供が酷い怪我をしている。異国の言葉で泣きながら訴える父親。それをテレビ画面で見ている自分。ぬくぬくとした「お茶の間」で。だらしなく寝ころがって。おやつを食べながら。
でも、誰にも責められない。逆に、姿勢を正して真剣に見ても、その子が救われるわけでもない。という現実に対する無力感。
和田伸一郎『メディアと倫理 画面は慈悲なき世界を救済できるか』(NTT出版/二三〇〇円)は、そんな倫理的ジレンマを出発点としたメディア論だ。
叢書コムニスといういかめしいネーミングのシリーズ一冊目で、帯の文句は〝画面メディアは世界からの存在論的「退きこもり」を現実化する。その行き着く先に救済は見出せるか――気鋭の俊英による新しいメディア批判のアプローチ〟。「簡単な本じゃないよオーラ」が放出されている。
読まぬ。普通だったら読まぬ。読まぬというより、そんな難しそうな本は読めないだろう、この締め切り直前のタイミングで!
が、この連載を始めてからは、本屋で新刊を見つけたら、とりあえず何でも最初の数ページは読んでみる癖がついてしまっている。読むと、あれよあれよと読み進め、あわわわ面白いわこれと即購入。
世界の悲惨な出来事そのものではなく、何もできずただ見ているだけという状態でテレビ画面を通じて出来事と対峙していることが、現代的な悲惨であると著者は指摘する。「お茶の間」とテレビが作り出す気楽な場に逃げ込むこと、インターネットによるさらなる孤立への撤退を批判する。逆に、そうした流れに抗う新しい映画の動きを、『誰も知らない』『エレファント』『ヴァンダの部屋』といった作品を具体例に語る。
論旨が明瞭で、おもしろくて一気に読んでしまった。刺激的で、(意外にも)読みやすい本なのでオススメ。
木原善彦『UFOとポストモダン』(平凡社新書/七二〇円)も、おもしろくて一気読み。UFOについての本だけど、空飛ぶ円盤やエイリアンの存在の真偽を検証するというスタンスではない。
UFOと宇宙人についてのおびただしい言説を三つの時代に大きく区分けし、検証し、そこから見え隠れする考え方と、それぞれの時代の考え方を照合していくスリリングな論考だ。
たとえば、社会が進歩していけば人類は幸福になるという楽観的な考え方がまだ十分に信じられていた時代には、UFO神話は、進歩した幸せな文明を持つものの象徴として語られる。ところが、ベトナム戦争が終わり、そういった直線的な進歩が信じられなくなった時代になると、エイリアンによる誘拐事件、UFO墜落事件、エイリアンと政府との共同陰謀説など、天空の理想ではなく、地上的な悪に内容が変移していく。
荒唐無稽だと思えるようなUFO神話でも、その要素が文化的・歴史的な文脈に支えられてはじめて、受容され、流行する。ということが、はっきりと解って、読んでいて興奮した。UFO神話から、世界の歴史が見えてくる感じがしてくるのだ。
野沢和弘『わかりやすさの本質』(NHK出版/七〇〇円)は、新聞記者と知的障害者がともにつくる新聞「ステージ」の制作を通じて問われ続ける「わかりやすさとは何か」についての本。「ステージ」の記事と、一般の新聞記事を比較して語られる「わかりやすさの技法」は、単純な文章術にとどまらず、伝えるということはどういうことかを考えるきっかけになる。
柳沢小実『リトルプレスの楽しみ』(ピエ・ブックス/一六〇〇円)は、たくさんの「リトルプレス」をフルカラーで紹介した本。リトルプレスというのは、企画から制作まですべてが手作りで、大手の流通を通さずに発行販売している本のこと。八角形だったり、クリップで束ねられてるスタイルだったり。内容も多彩で自由で。眺めてるだけでも楽しい(むずむずと作りたくなってくる)。
林雄司『小エロのひみつ WEBやぎの目研究発表』(イーストプレス/一一九〇円)は、ゆる系情報サイト「デイリーポータルZ」のウェブマスターとしても有名な著者のおもしろネタ本。ロフトプラスワンというトークライブ居酒屋で行われたイベントの一部を再現した本だ。基本は、テーマにもとづいて、写真を見せて、語る。
テーマは、「小エロのひみつ」「中二のひみつ」「ブルジョワのひみつ」「人んちのひみつ」といった日常をちょっと違った視点で眺めるというもの。「小エロのひみつ」の章では、「救命胴衣の説明をするスチュワーデス」「昼休みの白衣」といった小エロ初心者にもわかりやすいネタからはじまって、「ライトアップされたイトーヨーカドーの看板」「ひなたのアイス」という難易度の高いものまで、さまざまな小エロを、写真とゆるゆるした会話で紹介する。「小エロ」というフィルターを通すことによって、なんでもない写真が微妙な味わいを帯びる楽しさ。
IT系技術書で有名なオライリージャパンから出たトム・スタッフォード/マット・ウェッブ『MIND HACKS 実験で知る脳と心のシステム』(夏目大訳 二九四〇円)は、脳をハッキングしちゃうぞ本。っても怖くない。簡単な実験をして、脳の不思議を体験する解説本だ。目や耳の制限を脳がどのように修正改変しているか等、WEB上の映像や音声を使ったりして、いろいろな実験ができる。目を閉じていると「バ」に聞こえるのに、映像とあわせて聞くと同じ声が「ダ」に思えてしまう実験とか。
漫画は、ぎゃーーー文庫で復刊したよしましたよジョージ秋山『アシュラ』(幻冬舎文庫/上巻六四八円・下巻六〇〇円)!! ぼくの三大トラウマ本のひとつ(残り二大は『毒虫小僧』と『デビルマン』だ)。飢饉。人を殺し、その肉を食う狂女。彼女が産み落とす赤ん坊。そして、餓えに苦しむ狂女は「食べられるのはおまえだけ……」とつぶやいて、赤ん坊を火の中に放り込む! というショッキングな始まり。それでも、その赤ん坊は死なず、餓えと死体と血の世界を、生き延びていく。繰り返される「うまれてこないほうがよかったギャア」という叫びは、忘れられない。こ、これが「少年マガジン」に連載されてたことに驚く。改めて読んでも、すさまじい。
【この読書日記が収録されている書籍】
でも、誰にも責められない。逆に、姿勢を正して真剣に見ても、その子が救われるわけでもない。という現実に対する無力感。
和田伸一郎『メディアと倫理 画面は慈悲なき世界を救済できるか』(NTT出版/二三〇〇円)は、そんな倫理的ジレンマを出発点としたメディア論だ。
叢書コムニスといういかめしいネーミングのシリーズ一冊目で、帯の文句は〝画面メディアは世界からの存在論的「退きこもり」を現実化する。その行き着く先に救済は見出せるか――気鋭の俊英による新しいメディア批判のアプローチ〟。「簡単な本じゃないよオーラ」が放出されている。
読まぬ。普通だったら読まぬ。読まぬというより、そんな難しそうな本は読めないだろう、この締め切り直前のタイミングで!
が、この連載を始めてからは、本屋で新刊を見つけたら、とりあえず何でも最初の数ページは読んでみる癖がついてしまっている。読むと、あれよあれよと読み進め、あわわわ面白いわこれと即購入。
世界の悲惨な出来事そのものではなく、何もできずただ見ているだけという状態でテレビ画面を通じて出来事と対峙していることが、現代的な悲惨であると著者は指摘する。「お茶の間」とテレビが作り出す気楽な場に逃げ込むこと、インターネットによるさらなる孤立への撤退を批判する。逆に、そうした流れに抗う新しい映画の動きを、『誰も知らない』『エレファント』『ヴァンダの部屋』といった作品を具体例に語る。
論旨が明瞭で、おもしろくて一気に読んでしまった。刺激的で、(意外にも)読みやすい本なのでオススメ。
木原善彦『UFOとポストモダン』(平凡社新書/七二〇円)も、おもしろくて一気読み。UFOについての本だけど、空飛ぶ円盤やエイリアンの存在の真偽を検証するというスタンスではない。
UFOと宇宙人についてのおびただしい言説を三つの時代に大きく区分けし、検証し、そこから見え隠れする考え方と、それぞれの時代の考え方を照合していくスリリングな論考だ。
たとえば、社会が進歩していけば人類は幸福になるという楽観的な考え方がまだ十分に信じられていた時代には、UFO神話は、進歩した幸せな文明を持つものの象徴として語られる。ところが、ベトナム戦争が終わり、そういった直線的な進歩が信じられなくなった時代になると、エイリアンによる誘拐事件、UFO墜落事件、エイリアンと政府との共同陰謀説など、天空の理想ではなく、地上的な悪に内容が変移していく。
荒唐無稽だと思えるようなUFO神話でも、その要素が文化的・歴史的な文脈に支えられてはじめて、受容され、流行する。ということが、はっきりと解って、読んでいて興奮した。UFO神話から、世界の歴史が見えてくる感じがしてくるのだ。
野沢和弘『わかりやすさの本質』(NHK出版/七〇〇円)は、新聞記者と知的障害者がともにつくる新聞「ステージ」の制作を通じて問われ続ける「わかりやすさとは何か」についての本。「ステージ」の記事と、一般の新聞記事を比較して語られる「わかりやすさの技法」は、単純な文章術にとどまらず、伝えるということはどういうことかを考えるきっかけになる。
柳沢小実『リトルプレスの楽しみ』(ピエ・ブックス/一六〇〇円)は、たくさんの「リトルプレス」をフルカラーで紹介した本。リトルプレスというのは、企画から制作まですべてが手作りで、大手の流通を通さずに発行販売している本のこと。八角形だったり、クリップで束ねられてるスタイルだったり。内容も多彩で自由で。眺めてるだけでも楽しい(むずむずと作りたくなってくる)。
林雄司『小エロのひみつ WEBやぎの目研究発表』(イーストプレス/一一九〇円)は、ゆる系情報サイト「デイリーポータルZ」のウェブマスターとしても有名な著者のおもしろネタ本。ロフトプラスワンというトークライブ居酒屋で行われたイベントの一部を再現した本だ。基本は、テーマにもとづいて、写真を見せて、語る。
テーマは、「小エロのひみつ」「中二のひみつ」「ブルジョワのひみつ」「人んちのひみつ」といった日常をちょっと違った視点で眺めるというもの。「小エロのひみつ」の章では、「救命胴衣の説明をするスチュワーデス」「昼休みの白衣」といった小エロ初心者にもわかりやすいネタからはじまって、「ライトアップされたイトーヨーカドーの看板」「ひなたのアイス」という難易度の高いものまで、さまざまな小エロを、写真とゆるゆるした会話で紹介する。「小エロ」というフィルターを通すことによって、なんでもない写真が微妙な味わいを帯びる楽しさ。
IT系技術書で有名なオライリージャパンから出たトム・スタッフォード/マット・ウェッブ『MIND HACKS 実験で知る脳と心のシステム』(夏目大訳 二九四〇円)は、脳をハッキングしちゃうぞ本。っても怖くない。簡単な実験をして、脳の不思議を体験する解説本だ。目や耳の制限を脳がどのように修正改変しているか等、WEB上の映像や音声を使ったりして、いろいろな実験ができる。目を閉じていると「バ」に聞こえるのに、映像とあわせて聞くと同じ声が「ダ」に思えてしまう実験とか。
漫画は、ぎゃーーー文庫で復刊したよしましたよジョージ秋山『アシュラ』(幻冬舎文庫/上巻六四八円・下巻六〇〇円)!! ぼくの三大トラウマ本のひとつ(残り二大は『毒虫小僧』と『デビルマン』だ)。飢饉。人を殺し、その肉を食う狂女。彼女が産み落とす赤ん坊。そして、餓えに苦しむ狂女は「食べられるのはおまえだけ……」とつぶやいて、赤ん坊を火の中に放り込む! というショッキングな始まり。それでも、その赤ん坊は死なず、餓えと死体と血の世界を、生き延びていく。繰り返される「うまれてこないほうがよかったギャア」という叫びは、忘れられない。こ、これが「少年マガジン」に連載されてたことに驚く。改めて読んでも、すさまじい。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする