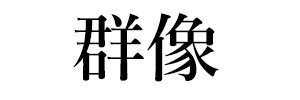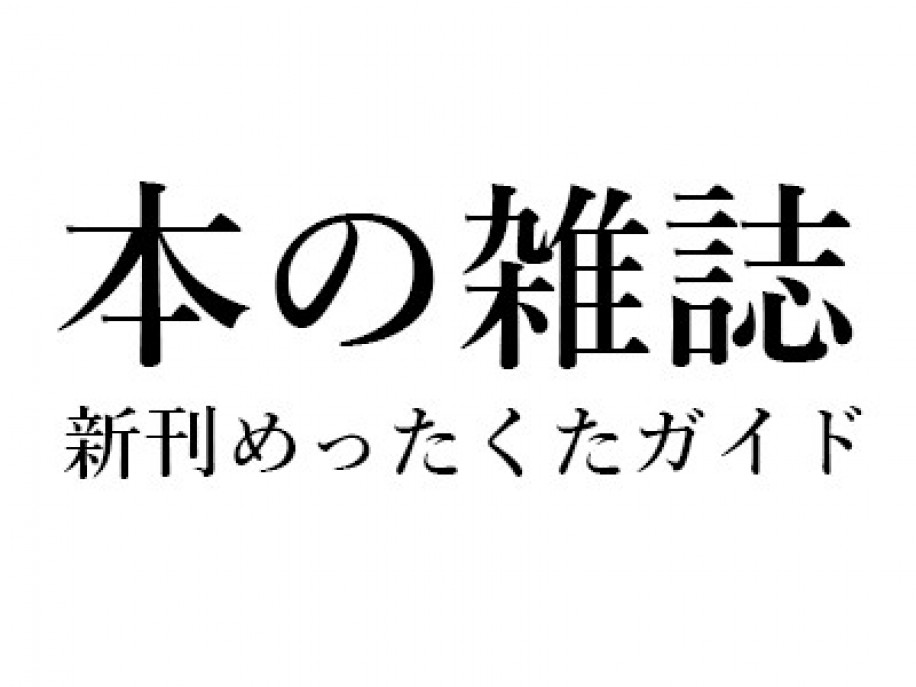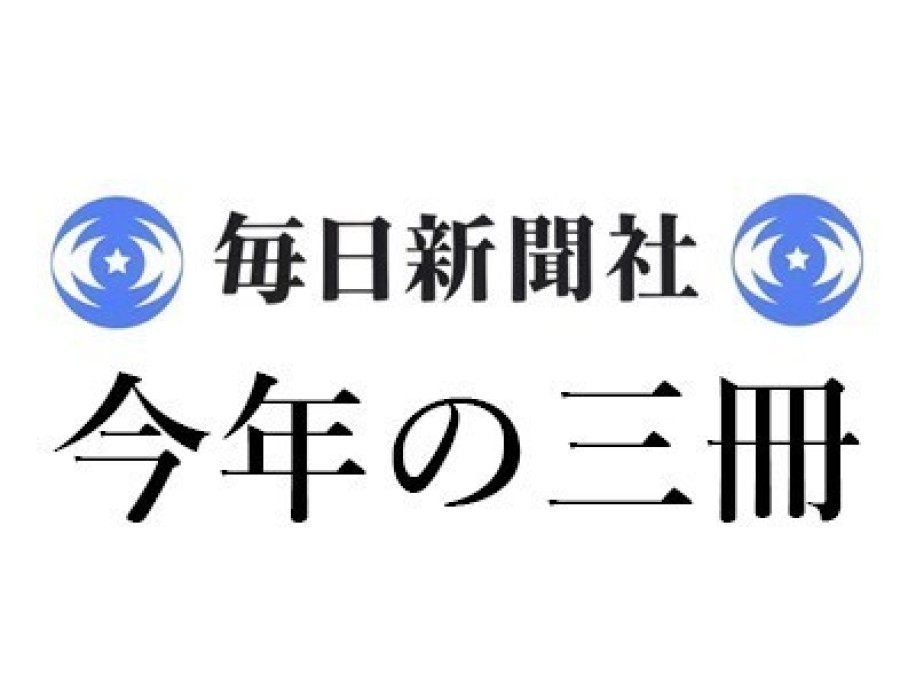書評
『アイロニーはなぜ伝わるのか?』(光文社)
単線的な目的論(テレオロジー)に抗うアイロニー
言語習得とは、ある環境において、ものをどう考えるかの根っこのレベルで「洗脳」を受けるようなことなのです。これはひじょうに根深い。言葉ひとつのレベルでイデオロギーを刷り込まれている、これを自覚するのはなかなか難しいでしょう。だから、こう言わねばならない。言語を通して、私たちは、他者に乗っ取られている。(千葉雅也『勉強の哲学――来たるべきバカのために』33-34頁)
アイロニーの本を評するのに、言語のイデオロギー機能についての引用から始めるのは飛躍しすぎではないかと思われるかもしれない。しかし、もしこのアイロニーが他者による自己の乗っ取りを可能にする「言語」から逃れ、疾走しつづけるための一つの媒体であるとしたらどうだろう。また、本書が議論の核心部分で『勉強の哲学』に言及していることにも留意したい。言語の本質にまで敷衍しようとするのが筆者の狙いだとすれば、言語使用者がそのイデオロギー性に自覚的であることの重要性とアイロニーの反逆性は通底するのではないだろうか。
本書が詳らかにしようとする種類のアイロニーは、ある特定の文化に特徴づけられるような狭義の意味に限定されるものではない。具体例には、朝寝坊をした人に対してわざと「早起きですね」と反対のことをいうお馴染みの英国風の皮肉はこれに相当するかもしれない。勿論このような皮肉は広辞苑で定義されるより普遍的(ユニバーサル)な用法とも結びつく。
第1章では、「表現面と真に表したい事とをわざと反対にし、しかも真意をほのめかす表現」としてのアイロニーが(格率(ルール)に則っているかどうかという)言語学的関心に沿った形で多角的に論じられる。これだけでも充実した内容という印象だが、本書の新しさはむしろ従来の理論に縛られない、自由で多声性(ポリフォニー)に開かれたアイロニー論に見いだせる。第3章で論じられる「開かれた」アイロニー論を下支えする語彙(ボキャブラリー)の定義は、第2章で入念に行なわれている。たとえば、メンタル・スペースのなかの《現実》と《期待》の空間などである。現実の天気はあまりよくないが、「今日はお出かけ日和だ」というアイロニー発話によって、日差しを楽しみたいという「期待スペース」が脳内に構築される。この「期待スペース」は「現実スペース」に「従属するスペース」として固定されるのだという。
ところが、「現実」と「期待」の間に結ばれるこの主従関係さえ、まさにアイロニーの内破性によって足元から崩れることがあるという。ここで千葉雅也氏の「自己破壊」の比喩が援用されていることは重要であろう。本書のナラティブが、じつはアイロニーのもつ脱構築的メカニズムによって駆動しており、従来のアイロニー論を見事に内側から壊している痛快さを秘めている。自己破壊される過程で、乗り越えられていくものは、「行為の『目的的・共同的な方向づけ』」である。「神」「理性」「科学」のような「終極の語彙」、いわば単線的な目的論(テレオロジー)を徹底して疑うこともアイロニーの範疇にあるという考えが提示されている。
アイロニーが、「共同的な行動規範や価値判断」を疑って批判するツールとして力を発揮することを余さず示しているのが第3章である。本書の最も優れた点は、哲学者リチャード・ローティを始めとする皮肉屋(アイロニスト)らの著書や文学作品の鮮やかなテクスト分析である。たとえば、シェイクスピアの『ジュリアス・シーザー』では、ブルータスに殺害されたシーザーをアントニーが擁護すべく(ただし、ブルータスを咎めないという条件で)追悼演説を行う場面が紹介される。アントニーが「ブルータスは公明正大な人物だ」と反復するアイロニーによって、市民(読者)の心の中の「現実スペース」と「期待スペース」にあるブルータス像に揺さぶりがかけられるという議論が展開され、じつに刺激的である。
また、ジョナサン・スウィフトの「ささやかな提案」で活用されるアイロニーがアイルランドの貧困を引き起こした宗主国イングランドへのあてつけでもあるという論も明解である。「貧民の赤ん坊を豊かな人たちの食物にしてしまえばよい」というのは、イングランドは突き詰めればこのような悲惨なことを《期待》しているのだと暴露している。このような反逆性もまたアイロニーの醍醐味であると読者は気づかされる。
さらに、「寝たい」と思っている時に相手は「寝たくない」と思っているマーティン・エイミスの恋愛のすれ違い論も、自分が気に入るものは他人のものであるというサミュエル・ベケットの『ワット』で用いられるアイロニーも、単線的な目的論を裏切っている。いずれの場合も「自分のものでなくなる可能性がある」ときに顕在化する人間の矛盾に満ちた欲求を表す。本書はアイロニーをめぐる格率(ルール)の議論に終始するのではなく、アイロニー発話に伴う認識の変化が「必ずしも究極の真実へと向かうわけではな」いという人間の複雑さを鋭く捉えているのである。
ただ、女性作家のアイロニーにもっと言及してもよかったのではないかということは頭をよぎる(オースティンはその数少ない一人)。本書におけるジェンダーの不均衡は、筆者の選択によるものなのか、あるいはアイロニー自体が男性作家の専売特許なのか。この問いは今後議論されてもよいだろう。とはいえ、その不足を補って余りあるほどの魅力が本書に備わっていることは強調しておきたい。
ALL REVIEWSをフォローする