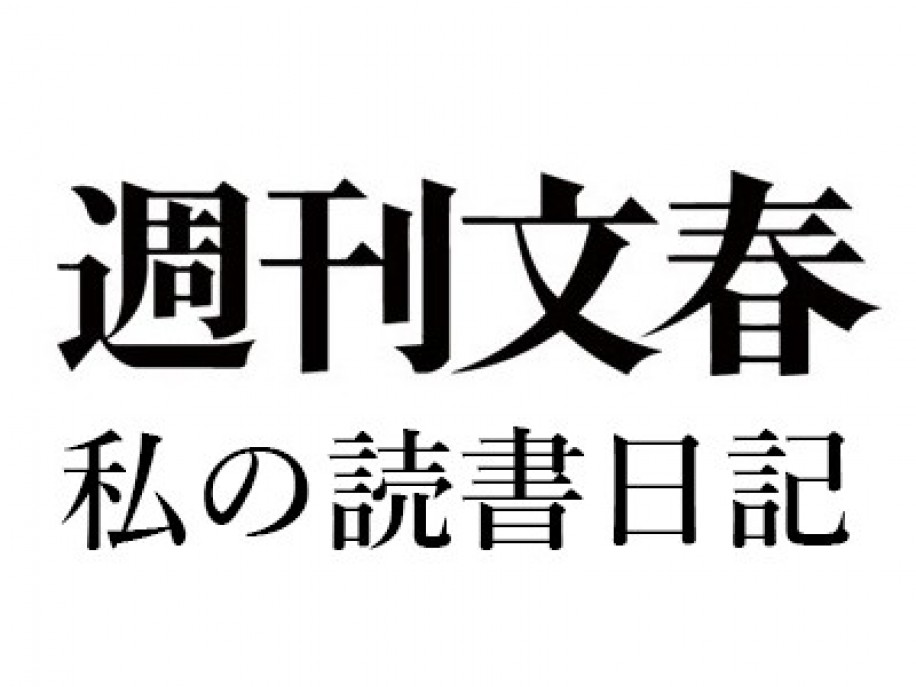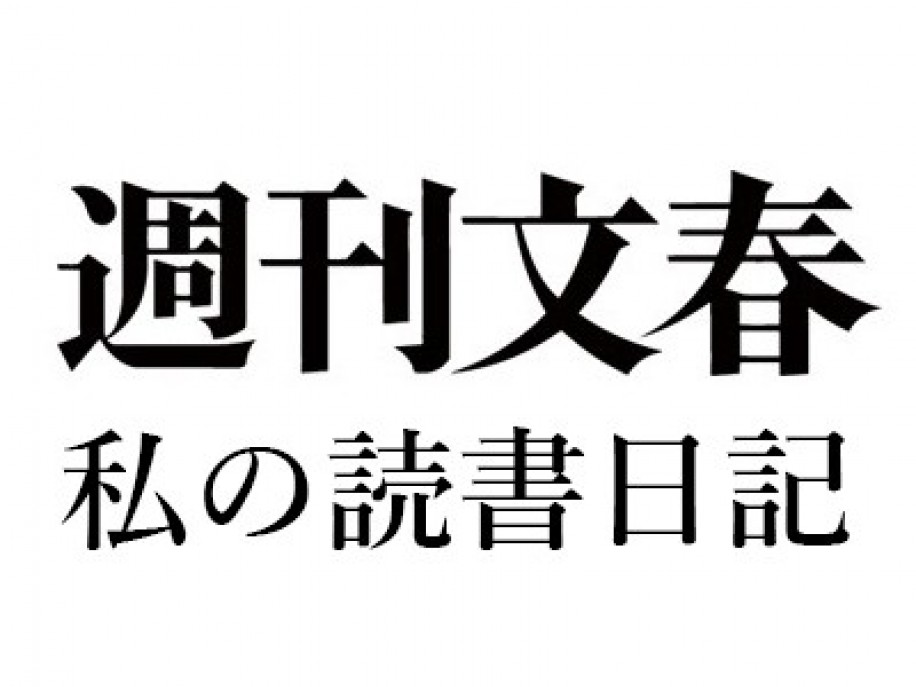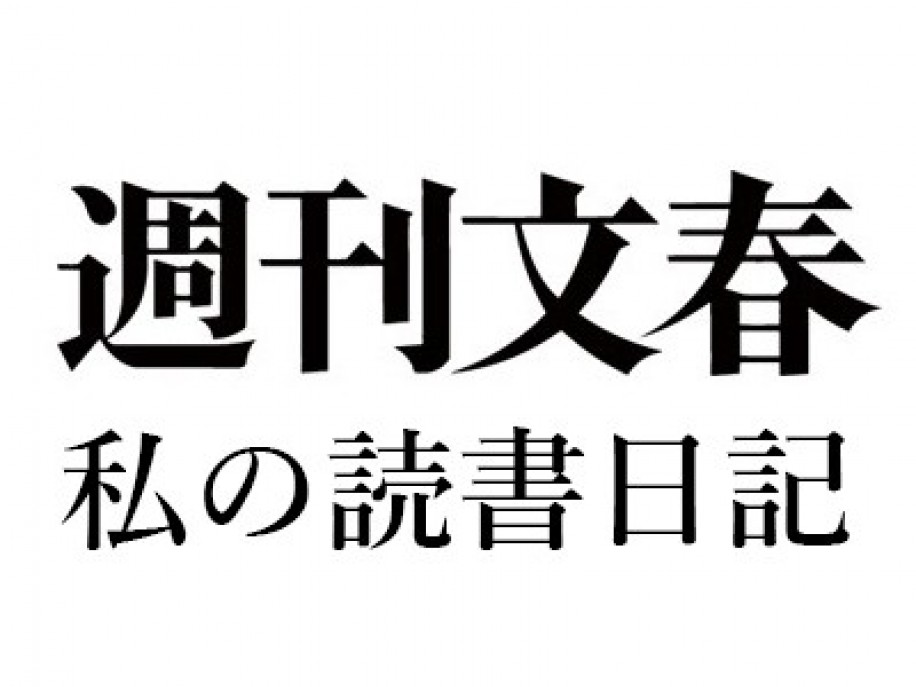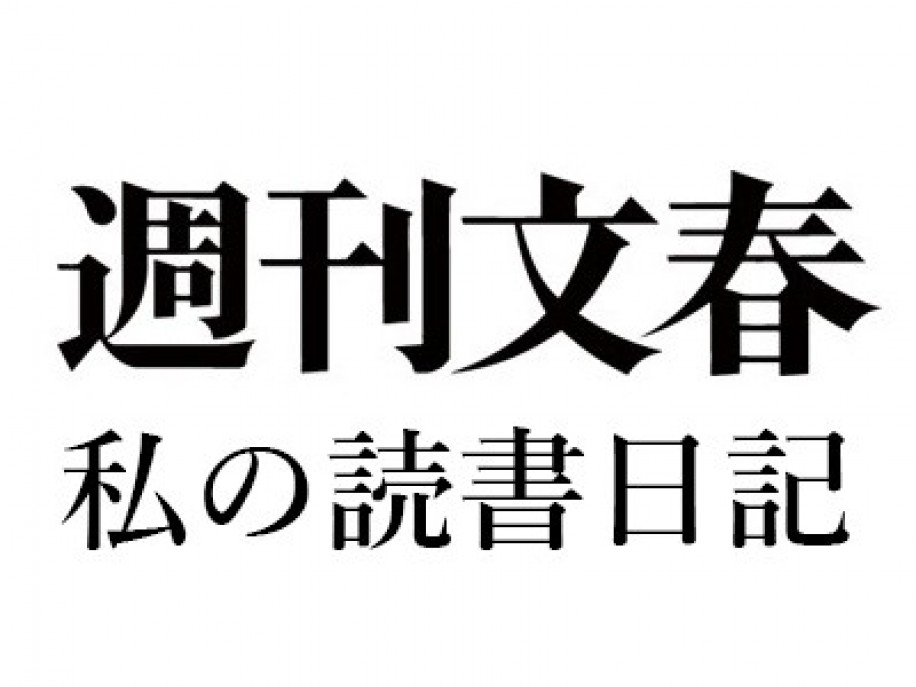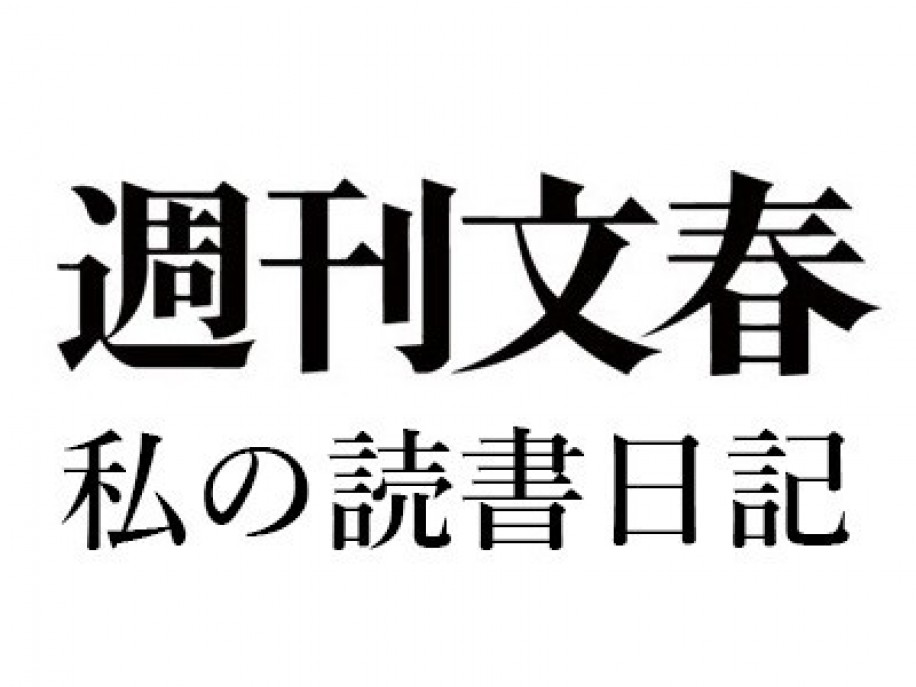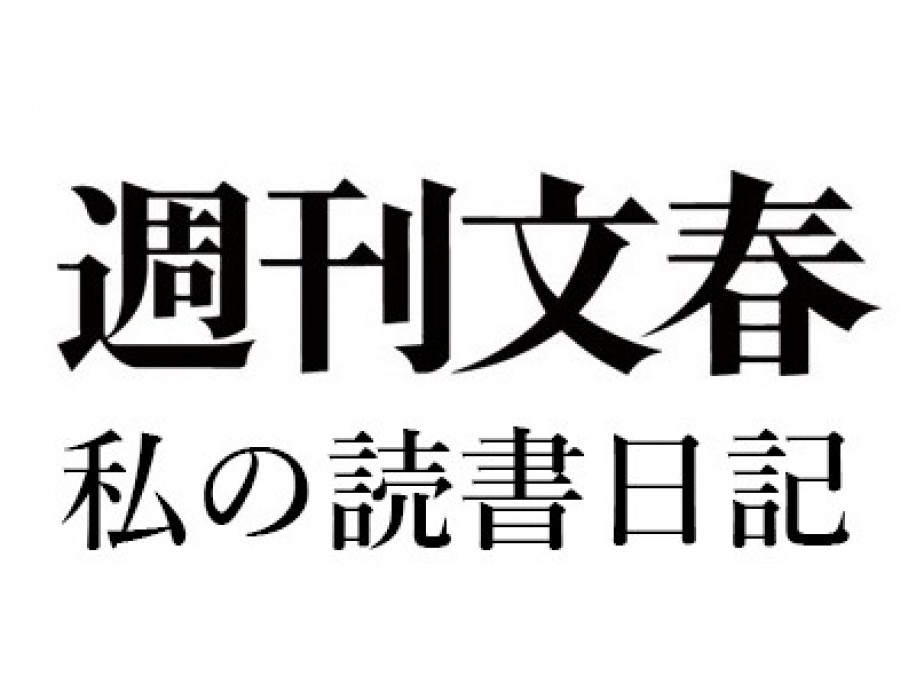読書日記
ロナルド・シーゲル『パラノイアに憑かれた人々』(草思社)、ジョン・ディ・セイント・ジョア『オリンピア・プレス物語 ある出版社のエロティックな旅』(河出書房新社)
パラノイドとエロと前衛と
×月×日
明日の朝までに五枚の書評を書かなければと思いつつ、夜中にテレビをつけたら、そのとたん、ニューヨークの世界貿易センタービルに旅客機が突っ込んだ瞬間の映像が映し出された(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2001年9月)。これはえらいことになったと、ザッピングでチャンネルを変えているうちにどんどん時間がたってしまったので、意を決して机の前に座り、書評を書きあげる。どんなときでも、たとえ世界が崩壊しそうなときでも、〆切は守らなければならない。物書きはつらいよ。テロの黒幕と目されているビン・ラディンをパラノイアだとは決めつけることはできないが、パラノイア的思考の人物(これをパラノイドという)が世界史を変えるとてつもない事件を引き起こしたことは、ヒトラー、スターリンを始めとして枚挙に暇がない。なぜなら、パラノイドは、自分こそ世界を変革しうる崇高で全能な予言者であると強く信じているため、ときには一つの国や文明までがその強靭な論理に引きずられるからである。さらに、そうしたパラノイドは、他者は全員、自分に敵意を持ち、陰謀を企てていると確信しているから、パラノイア思考が高まると、敵の組織を全滅させるために攻撃に出ることがある。この先制攻撃が多くの悲劇を生むのだ。
ロナルド・シーゲル『パラノイアに憑かれた人々(上) ヒトラーの脳との対話』『パラノイアに憑かれた人々(下) 蟲の群れが襲ってくる』(小林等訳 草思社 上 1600円+税、下 1800円+税)は、UCLAの精神医学行動科学科准教授がパラノイドに密着取材し、そのパラノイア的思考の内側にまで入り込んで、その因って来たるところを解き明かそうと試みた興味深いレポートである。
著者によれば、あらゆるパラノイドの思考に共通しているのは、強い猜疑心である。
パラノイドは疑惑の正体を確認する手がかりを得ようとして、あらゆるものを調べる。(中略)つまらないことに飛びつき、過大評価し、独自の論理体系のパターンに組みこむのだ。
パラノイドの第二の特徴は敵対心。世界は悪意に満ちていると思い込む。その結果、周囲の人々の反感を買うことになり、本当に迫害される。これがよけいに確信を強める。
そして、そこから第三の特徴である投影が生まれる。「私が彼らを憎んでいるのではなく、彼らが私を憎み、殺したいと思っているのだ」
この投影が強くなると、それは妄想を作り出し、最後には先制攻撃に出るというわけだ。
取り上げられている症例で興味深いのは、航空宇宙企業に勤める科学者で、個人監視用人工衛星の妄想に憑かれたエド・トールマンのケースである。
トールマンは通勤時や就寝時にまずブザーのような音が聞こえ、次に地獄から送られてきたような図像の「はがき」が見えると言い張る。そして、それは敵対企業が個人監視用人工衛星(POSSE)から送ってくる電磁波だと断定する。これだけなら、典型的なパラノイドだが、トールマンがすごいのは、その断定をすべて「科学的」に証明して見せることである。すなわち、あらゆる科学論文に根拠を求め、個人監視用人工衛星を実証的に「解明」する。それどころか人工衛星の設計図まで描いてしまう。
彼は自分で体験したことに意味と秩序を与えるため、解答を求め、最終的に、人工衛星が自分を追跡し悩ませているというPOSSE理論を構築した。
著者は、トールマンと行動を共にし、ついに、入眠時のノイズは歯軋りの音、通勤時のブザー音はトンネルのノイズ、また「はがき」はかつてエドが観た『エル・トポ』という不気味な映画の場面だったと突き止めるが、エドはそんなことはまったく信ぜず、より強固なパラノイアの陣地に立てこもってしまう。
これを読んで思い出すのは、私の知っているパラノイドのケースだ。そのパラノイドはこちらの指摘に常にこう答えた。「それはわかっています。だから、不思議なんです」。これに対抗できる論理は正常の側にはない。
×月×日
残暑厳しいある夜、ふと、物書き業界の中だけで通じるジョークを考えついた。良心的出版社として知られるX社の社長がある作家についてこんなことを言った。「あいつはなんだ。金のことしかいわない。俺を見ろ、金のことなんか一度だって口にしたことがない」
このジョークは、およそ契約という概念がない日本の出版界でのみ通じるものと思っていたが、どうやらそうでもないらしい。ジョン・ディ・セイント・ジョア『オリンピア・プレス物語 ある出版社のエロティックな旅』(青木日出夫訳 河出書房新社 3400円+税)を読むと、可能性を秘めた無名作家の前代未聞の作品を出版する勇気ある出版社として二十世紀の文学史にその名を刻むオベリスク・プレスとその後身であるオリンピア・プレスが、印税をなかなか支払わず、作家の怨嗟の的になっていた事実があきらかになる。
第一次世界大戦で英米からパリにやってきたロスト・ジェネレーションの一人にジャック・カハンというイギリス人青年がいた。青年はフランス娘のマルセル・ジロディアスと結婚、四人の子供をもうける。カハンは自らエロ小説を書いた後、出版に手を染めた。エロ本を英米人相手にパリで英語で出版し、それで儲けた金で知られざる天才の大胆な傑作を出版するという野心を抱いたのである。
後者の路線の最初の本がジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』の一部「ハヴス・チルダーズ・エヴリウェア」で、以後、ラドクリフ・ホール『孤独の泉』、フランク・ハリスの『わが生と愛』と続いて、ついにヘンリー・ミラーの『北回帰線』で当て、さらにアナイス・ニン『近親相姦の家』、ロレンス・ダレル『黒い本』を出す。このラインナップはまことに壮観で、二十世紀のエロスの前衛文学は確かにオベリスク・プレスから生まれたといえる。しかし、その内実はというと、これが案外みみっちいもので、カハンは絶対に損をしないように印刷費を作家やその友人たちに払わせていた。たとえば、『北回帰線』と『黒い本』はアナイス・ニンに、『近親相姦の家』はダレルに印刷代を負担させたのだ。
彼は、その奔放で魅惑的な自伝が伝えているほど、勇敢でもなければ鋭くもなかったのである。
ジャック・カハンはドイツがポーランドに侵入した翌日に死んでしまう。
息子のモーリス・ジロディアスは父の唐突な死の後、エディシオン・デュ・シェーヌという高級挿絵本の出版社を興した。父の名前を名乗らなかったのはナチ占領下だったためである。ジロディアスはユダヤの血がまじっているにもかかわらず、うまく立ち回って戦中を生き延びるが、戦後、事業に失敗し、父の築いたエロと前衛という二本立て路線を継承することを決意する。これがオリンピア・プレスである。
ジロディアスはヘンリー・ミラーの『プレクサス』とベケットの『ワット』それにサドの『閨房哲学』でオリンピア・プレスをスタートさせるが、サドの翻訳者として加わったオーストリン・ウェインハウスらの雑誌『マーリン』同人に目をつけ、彼らにエロ小説を大量に書かせ、これをトラヴェラーズ・カンパニオン・シリーズと称して経営の安定を図る。この伝記の優れたところは、これまでオリンピア・プレスの研究では無視されていたこれらのエロ本の作者を突き止め、彼らの功績にも光を当てたことである。オリンピア・プレスは、前衛文学だけではなく、エロ文学のほうでも一流であったのだ。
やがて、ジロディアスの前に父にとってのヘンリー・ミラーのような存在が現れる。イギリス在住のアメリカ人作家J・P・ドンレヴィーである。ドンレヴィーはすべての出版社で『赤毛の男』を拒否され、ジロディアスの扉をたたく。『赤毛の男』はオリンピア・プレスから一九五五年に出版されるが、ドンレヴィーはそれがトラヴェラーズ・カンパニオン・シリーズの一冊として世に出たことに仰天し、ジロディアスとの長い闘争に入る。これに英米での出版契約という厄介な問題が加わる。どちらも、版権は自分にあると主張したのである。この戦いは最後にドンレヴィーに軍配があがる。オリンピア・プレスが破産したとき、ドンレヴィーは株を競売で買い取って復讐を遂げたのだ。
ナボコフの『ロリータ』の場合もほぼ同じだった。『ロリータ』を出す勇気のある出版社はオリンピア・プレスしかなかったが、ナポコフは後に自作がオリンピア・プレスから出たことを恥じるようになり、英米での版権をオリンピア・プレスから奪おうと画策する。
その後、オリンピア・プレスは『キャンディ』『O嬢の物語』『裸のランチ』と文学史に残るエロスの前衛文学を次々に出版するが、そのたびに著者と悶着をおこす。その理由はほとんどが金だった。
ジロディアスの金払いは最悪だった。意図的か偶発的かの差はあるものの、作家たちへの支払いは常に遅れるか、少ないかであり、忍耐強いウィリアム・バロウズがアメリカの印税を待ち続けた時のように、まったく払わないことも頻繁にあった。「個人的なレベルでは、彼はとても魅力的な人物だったよ」とディック・シーヴァーは語る。「だが彼は、まったく恥知らずの男だった。印税を払わないんだからな」。
性の前衛出版社を巡る「栄光と悲惨」あるいは壮絶な「人間喜劇」。『O嬢の物語』のポーリーヌ・レアージュがジャン・ポーランの秘書で愛人だったドミニク・オーリであることが証明される部分も興味深い。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする