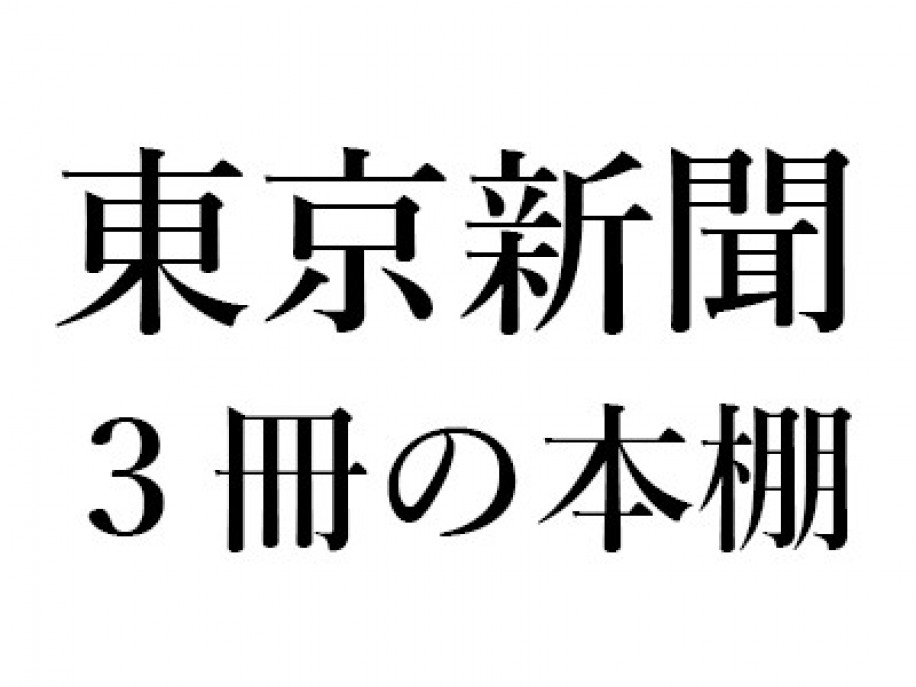読書日記
西村 賢太『どうで死ぬ身の一踊り』(講談社)、『一私小説書きの日乗』(KADOKAWA)
半歩遅れの読書術――破滅型作家が放つ私小説、ルーティンに透ける凄み
人と人の世の中、とりわけその基底にある論理を知りたい――この興味関心からして、読書はノンフィクションに偏る。フィクションだとやりたい放題になるので、ロジックを追えない。抜群に面白い小説であればその世界にトリップできる。しかし、そこまでの作品はそうそうない。たまにはその時々に絶賛されている小説に手を出してみるのだが、「それほどかな……」と思うことが多い。根が想像力に欠けているのかもしれない。例外は私小説だ。完全なノンフィクションではないにしても、僕の貧困な想像力でも人間のリアルな本質に接近できる。現役作家でいえば、大好物は西村賢太。
どれを読んでもきっちりと面白い。西村作品はそのほぼすべてが特定少数のテーマの変奏である。悪く言えばワンパターン(登場人物がすべて著者その人なのだから当たり前)、よく言えば安定感抜群。芥川賞受賞作の『苦役列車』(新潮文庫)もいいが、僕にとっての最高傑作は初期の短編集『どうで死ぬ身の一踊り』(講談社文庫)に収録の「一夜」。ラストシーンには鳥肌が立った。私小説に固有のパワーに心底感動した。
西村賢太の日記『一私小説書きの日乗』(角川文庫)シリーズは小説に輪をかけて面白い。判で押したように同じルーティンを繰り返す日々。それが何年も続く。確立された生活と仕事の様式。錬度の高いルーティンに氏のプロとしての凄(すご)みが透けて見える。
運が良ければ一発ホームランは打てる。しかし、素人はその後が続かない。プロとアマの最大の違いは持続力にある。コンスタントに質の高いアウトプットを継続して出す。これがプロの条件だ。仕事の成果は日々の生活の中からしか生まれない。「生活第一、芸術第二」、菊池寛の名言だ。詩人は泣きながら詩は書かない。持続力の基盤にはその人に固有の練り上げられた生活ルーティンがある。
数多くの失敗とたまに訪れる成功を積み重ねていく中で、自分だけのルーティンを錬成していく。そこに仕事生活の醍醐味がある。私見では、創造的な仕事をしている人ほどルーティンを大切にしている。仕事がダイナミックで非定型的だからこそ、変わらず安定した土台が必要となる。
西村賢太はしばしば「無頼派」「破滅型」と評される。確かにその言動や私小説に描かれる思考と行動は刹那的で衝動的に見える。しかし、この人にこそ練り上げられたプロフェッショナルのモデルを見る。
ALL REVIEWSをフォローする