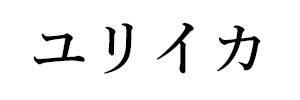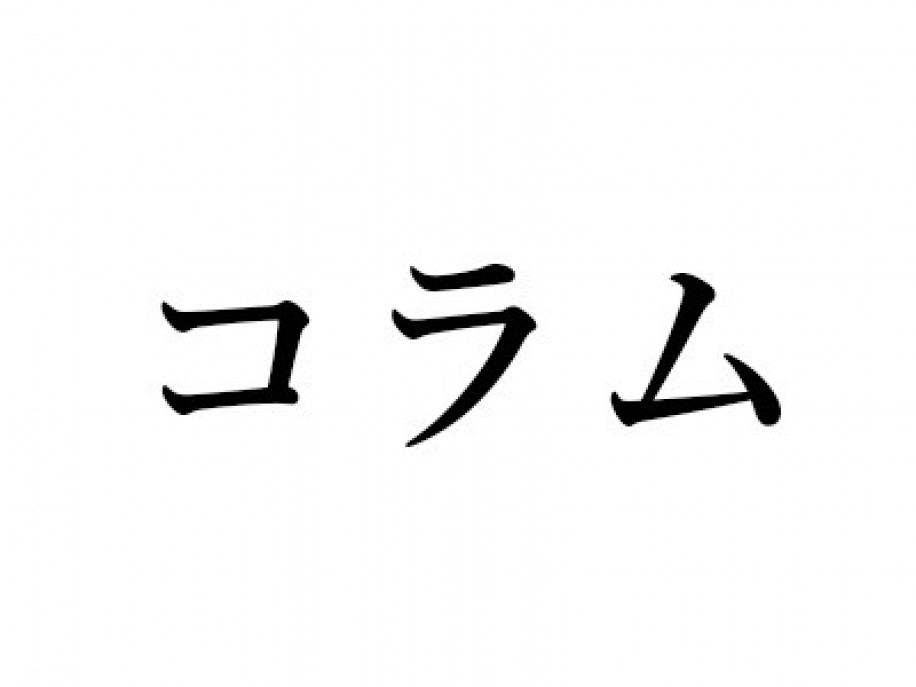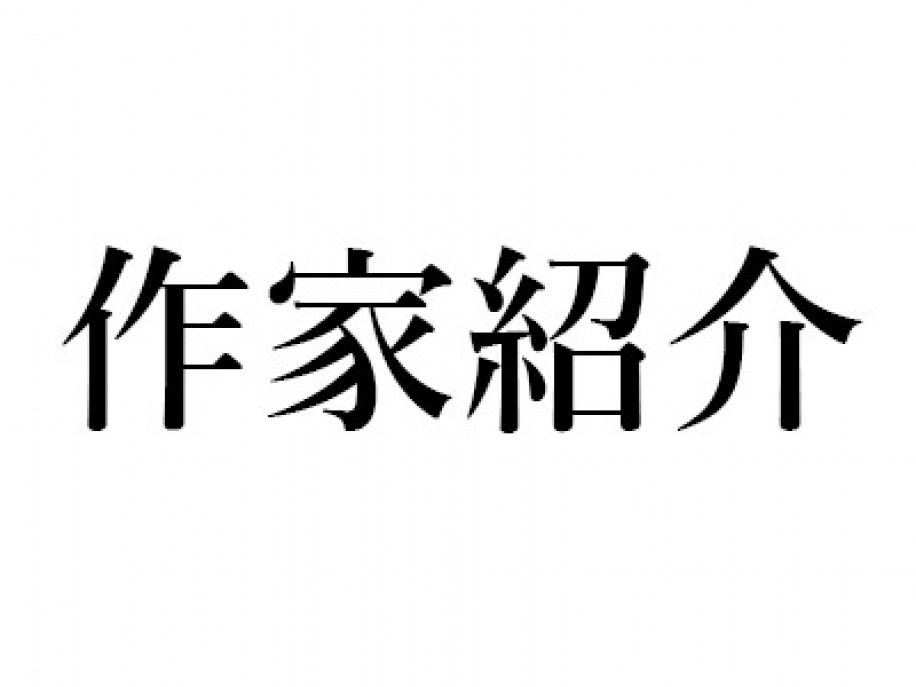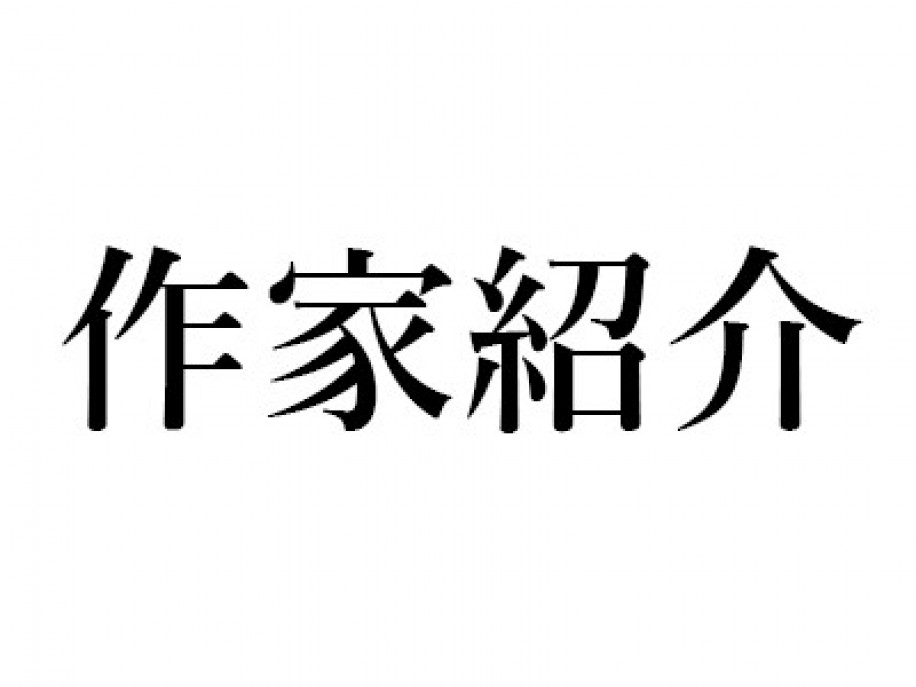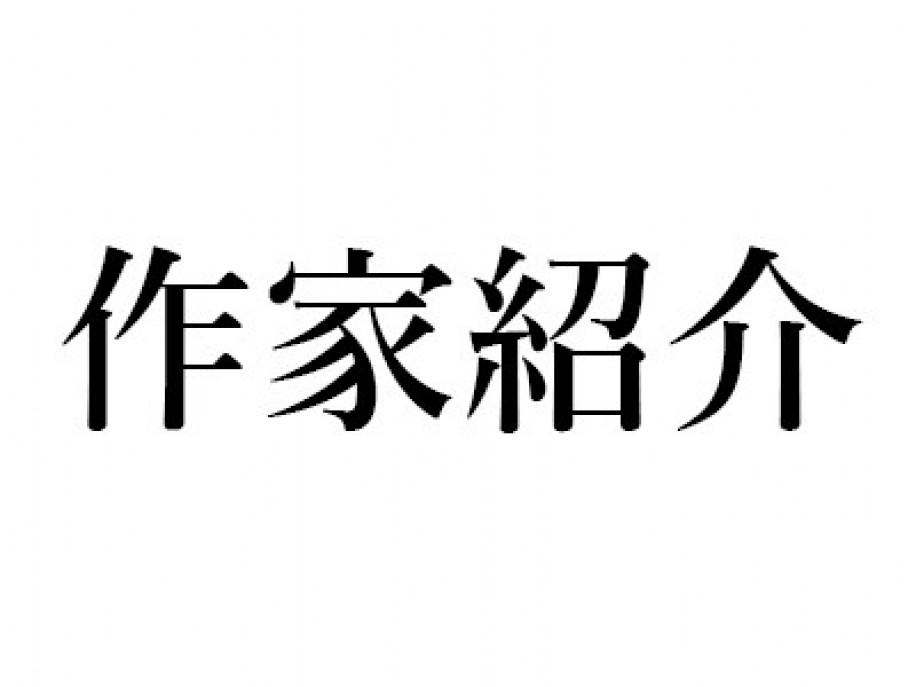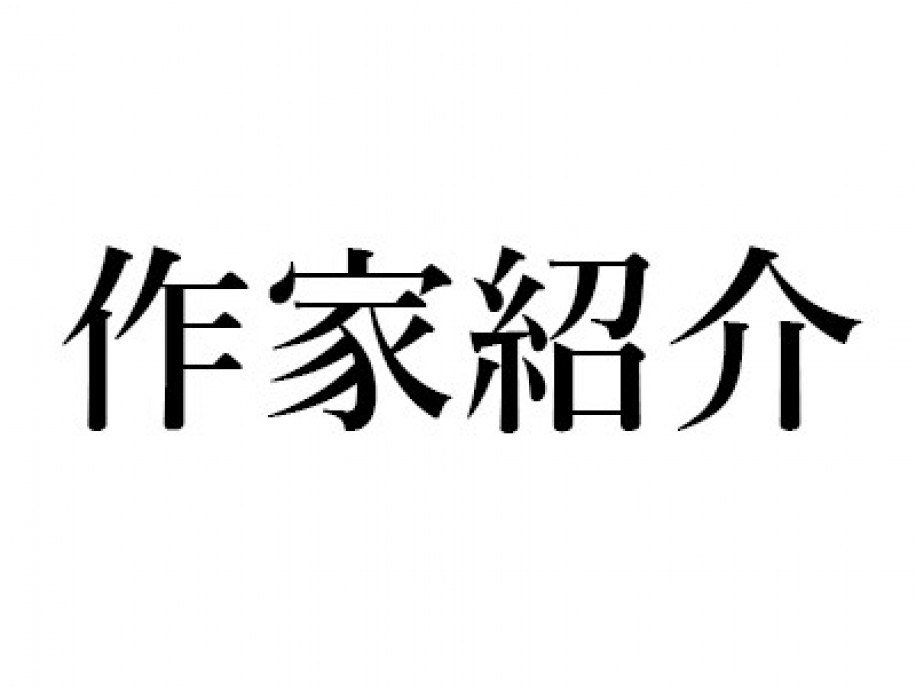作家論/作家紹介
【ノワール作家ガイド】船戸与一『非合法員』(講談社)、『神話の果て』(同左)、『猛き箱船』(集英社)ほか
一九四四年、山口県生まれ。出版社勤務ののち、ルポライター、漫画原作者などを経て、長篇「非合法員」で作家デビューする。第一作以来、先進国の帝国主義に抵抗する民族/国家の問題を、冒険小説の手法で描きつづけている。「伝説なき地」で日本推理作家協会賞、「山猫の夏」「猛き箱船」で日本冒険小説協会大賞を受賞するなど、ミステリの分野でまず高い評価を受け、のちに「砂のクロニクル」で山本周五郎賞を、「虹の谷の五月」で直木賞を受賞し、名実ともに日本のエンタテインメント界を代表する作家となった。
評論の分野でも、その洞察と独特の視座が高く評価されている。
船戸与一の作品は、一般的に、冒険小説のカテゴリーに入れられている。たしかに物語はたいてい、世界の辺境たる土地で展開され、勃発する闘争は戦争行為と言えそうなほど大規模だ。都市小説でありミクロな力学を描くことの多いハードボイルド/ノワールとはまったく別種のものに属するように思われる。
だが、船戸与一は、自分の作品をハードボイルドと規定している。秀逸なハードボイルド論「ハードボイルド試論 序の序」において、船戸与一は、帝国主義の一断面をあざやかに切り取ってみせた小説こそが優れたハードボイルドなのだ、と結論しているが、この定義は、ぴったりと自身の作品に重なり合う。つまり船戸与一は、自覚的にハードボイルドを書いている作家だということになる。
船戸与一が激烈なチャンドラー否定論者であること、また前記評論が、ダシール・ハメットの『赤い収穫』を主なテキストとしており、また船戸与一がハメットをとりわけ高く評価していることなどから、船戸与一がいうハードボイルドが、主にハメットを指し、またチャンドラーの影響をつよく受けているいわゆる「正統ハードボイルド」を排除していることが推察できる。このハメット/チャンドラーの差異を端的に言うなら、そこにヒロイズムがあるかないか、絶対的正義があるかないか、といったところになるだろう。チャンドラーがハードボイルドに持ち込んだ最大のものが、探偵フィリップ・マーロウに象徴されるヒロイズム/ロマンティシズムであったからだ。船戸与一はそれを否定しているとみていいだろう。つまりは「正義」の存在の否定、あるいは相対化。
船戸与一作品においては、先進諸国の論理=正義が、それに対立する開発途上国の論理=正義によってラディカルに転倒される。それは処女長篇『非合法員』で、すでに描かれている。CIAの非合法活動を遂行する日本人工作員が、彼を密殺せんとする追っ手から逃れるためにメキシコからアメリカを北上してゆくというのが本作の主軸だが、主人公が赴き、身を隠す場所は、すべてがアメリカ少数民族のもとなのである。言ってみればこの作品は、「アメリカ」が体現する大国の論理に抵抗する別の論理を巡礼してゆく物語であり、主人公を含む非アメリカ的なるものが、冷徹に踏み潰されてゆく物語なのだ。
一方、南米における少数民族の抵抗を主題とする「南米三部作」の二作目『神話の果て』では、やはりアメリカの非合法工作員が、ゲリラ活動の首領の暗殺を命じられる物語だが、ここでは主人公がアメリカ覇権主義の「触手」として活動し、それがラストで明かされる意外かつ皮肉なツイストによって、完璧に敗北するさまが描かれる。
たしかに物語の枠は大きい。舞台も狭い都市ではない。これらをノワールと呼ぶのはいささか無理があるだろう。けれど、ここには明らかにノワールと同質の空気がある。
それがより濃厚なのが、おそらく船戸与一の代表作であり最高傑作であろう長篇『猛き箱船』だ。この作品の第三部のひえびえとした質感、暗い絶望のひびきは、まさしくノワールのそれだ。脳天気なマチズモを憧憬する主人公が、傭兵となり凄惨な体験を経て、憎悪と呪詛の権化のような存在となるさまを濃密に描くのが『猛き箱船』だが、船戸与一の主題たる「帝国主義の断面を切り裂く」ことが、もっとも切実なかたちで見事に結実したのがこの作品だと言っていいだろう。「帝国主義/資本主義国家」の維持のために用いられる手段の醜悪さを、漫然とそれを享受してきた男が認識し、それに激烈な憎悪を抱くまでを描ききっているからである。
船戸与一においては、すべての巨大な対立は、渦中にある人間の生理に置き換えられて語られる。世界的規模の価値観の衝突が、僻地において勃発する紛争を戦う者たちに仮託されて語られる。そして最終的に物語が行き着く悲劇は、巨大な構図のなかで徹底的に非力な個人を浮き彫りにする。憎悪と呪詛を抱えて破滅するしかない人間の姿を。
対抗し得ないほど肥大化したシステムのなかで圧殺されようとする人間たちのデスペレートな抵抗。正義の相対化。こうした大枠において、船戸作品とノワールとは等号で結べることになる。むろん、船戸与一の凝視する地点がいまだ近代社会の網の目が完成していない辺境であるがゆえに、展開される「抵抗/闘争」は、よりドラスティックなものとなる。だが、そこにノワール的な構図を限りなく拡大したものを見ることは可能だろう。
ノワールが撃とうとしているのは、理性による支配が完成した現在における人間の「自然」の疎外である。ここでいう理性が近代西欧の思想であり、またその安定と繁栄が、帝国主義の遂行の上に築かれたものであることは論をまたない。船戸与一作品と同様に、ノワールもまた、帝国主義の一断面を切り裂こうとする文学であることは間違いあるまい。
【必読】『非合法員』(講談社文庫)、『神話の果て』(同左)、『猛き箱船』(集英社文庫)
評論の分野でも、その洞察と独特の視座が高く評価されている。
船戸与一の作品は、一般的に、冒険小説のカテゴリーに入れられている。たしかに物語はたいてい、世界の辺境たる土地で展開され、勃発する闘争は戦争行為と言えそうなほど大規模だ。都市小説でありミクロな力学を描くことの多いハードボイルド/ノワールとはまったく別種のものに属するように思われる。
だが、船戸与一は、自分の作品をハードボイルドと規定している。秀逸なハードボイルド論「ハードボイルド試論 序の序」において、船戸与一は、帝国主義の一断面をあざやかに切り取ってみせた小説こそが優れたハードボイルドなのだ、と結論しているが、この定義は、ぴったりと自身の作品に重なり合う。つまり船戸与一は、自覚的にハードボイルドを書いている作家だということになる。
船戸与一が激烈なチャンドラー否定論者であること、また前記評論が、ダシール・ハメットの『赤い収穫』を主なテキストとしており、また船戸与一がハメットをとりわけ高く評価していることなどから、船戸与一がいうハードボイルドが、主にハメットを指し、またチャンドラーの影響をつよく受けているいわゆる「正統ハードボイルド」を排除していることが推察できる。このハメット/チャンドラーの差異を端的に言うなら、そこにヒロイズムがあるかないか、絶対的正義があるかないか、といったところになるだろう。チャンドラーがハードボイルドに持ち込んだ最大のものが、探偵フィリップ・マーロウに象徴されるヒロイズム/ロマンティシズムであったからだ。船戸与一はそれを否定しているとみていいだろう。つまりは「正義」の存在の否定、あるいは相対化。
船戸与一作品においては、先進諸国の論理=正義が、それに対立する開発途上国の論理=正義によってラディカルに転倒される。それは処女長篇『非合法員』で、すでに描かれている。CIAの非合法活動を遂行する日本人工作員が、彼を密殺せんとする追っ手から逃れるためにメキシコからアメリカを北上してゆくというのが本作の主軸だが、主人公が赴き、身を隠す場所は、すべてがアメリカ少数民族のもとなのである。言ってみればこの作品は、「アメリカ」が体現する大国の論理に抵抗する別の論理を巡礼してゆく物語であり、主人公を含む非アメリカ的なるものが、冷徹に踏み潰されてゆく物語なのだ。
一方、南米における少数民族の抵抗を主題とする「南米三部作」の二作目『神話の果て』では、やはりアメリカの非合法工作員が、ゲリラ活動の首領の暗殺を命じられる物語だが、ここでは主人公がアメリカ覇権主義の「触手」として活動し、それがラストで明かされる意外かつ皮肉なツイストによって、完璧に敗北するさまが描かれる。
たしかに物語の枠は大きい。舞台も狭い都市ではない。これらをノワールと呼ぶのはいささか無理があるだろう。けれど、ここには明らかにノワールと同質の空気がある。
それがより濃厚なのが、おそらく船戸与一の代表作であり最高傑作であろう長篇『猛き箱船』だ。この作品の第三部のひえびえとした質感、暗い絶望のひびきは、まさしくノワールのそれだ。脳天気なマチズモを憧憬する主人公が、傭兵となり凄惨な体験を経て、憎悪と呪詛の権化のような存在となるさまを濃密に描くのが『猛き箱船』だが、船戸与一の主題たる「帝国主義の断面を切り裂く」ことが、もっとも切実なかたちで見事に結実したのがこの作品だと言っていいだろう。「帝国主義/資本主義国家」の維持のために用いられる手段の醜悪さを、漫然とそれを享受してきた男が認識し、それに激烈な憎悪を抱くまでを描ききっているからである。
船戸与一においては、すべての巨大な対立は、渦中にある人間の生理に置き換えられて語られる。世界的規模の価値観の衝突が、僻地において勃発する紛争を戦う者たちに仮託されて語られる。そして最終的に物語が行き着く悲劇は、巨大な構図のなかで徹底的に非力な個人を浮き彫りにする。憎悪と呪詛を抱えて破滅するしかない人間の姿を。
対抗し得ないほど肥大化したシステムのなかで圧殺されようとする人間たちのデスペレートな抵抗。正義の相対化。こうした大枠において、船戸作品とノワールとは等号で結べることになる。むろん、船戸与一の凝視する地点がいまだ近代社会の網の目が完成していない辺境であるがゆえに、展開される「抵抗/闘争」は、よりドラスティックなものとなる。だが、そこにノワール的な構図を限りなく拡大したものを見ることは可能だろう。
ノワールが撃とうとしているのは、理性による支配が完成した現在における人間の「自然」の疎外である。ここでいう理性が近代西欧の思想であり、またその安定と繁栄が、帝国主義の遂行の上に築かれたものであることは論をまたない。船戸与一作品と同様に、ノワールもまた、帝国主義の一断面を切り裂こうとする文学であることは間違いあるまい。
【必読】『非合法員』(講談社文庫)、『神話の果て』(同左)、『猛き箱船』(集英社文庫)
ALL REVIEWSをフォローする