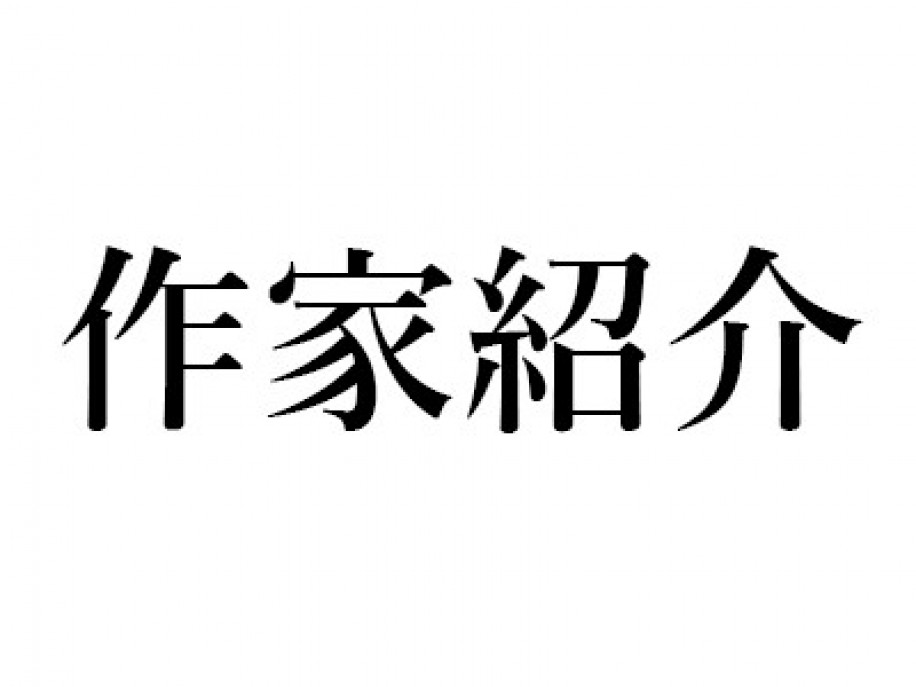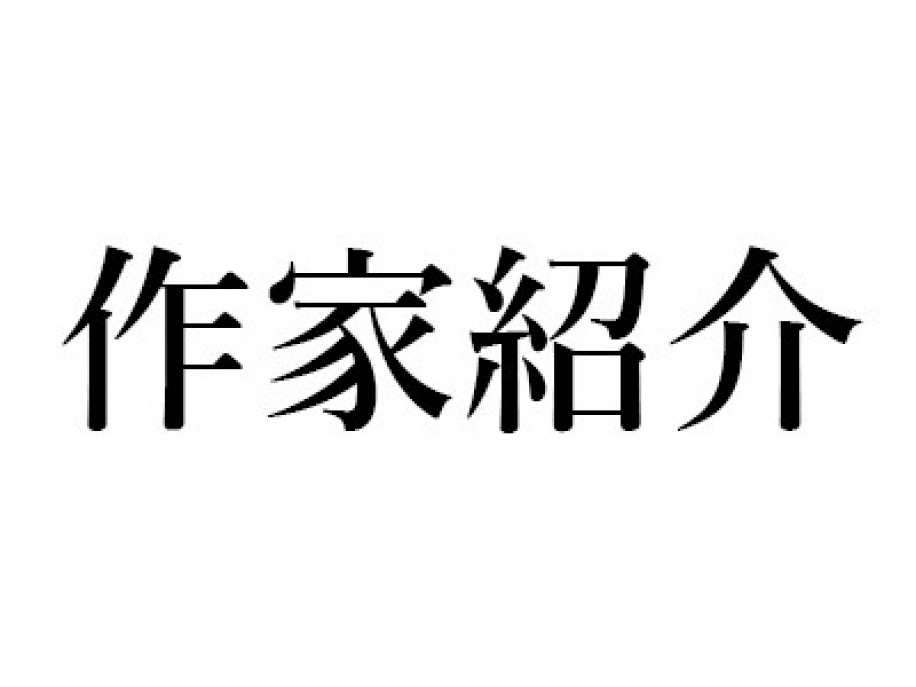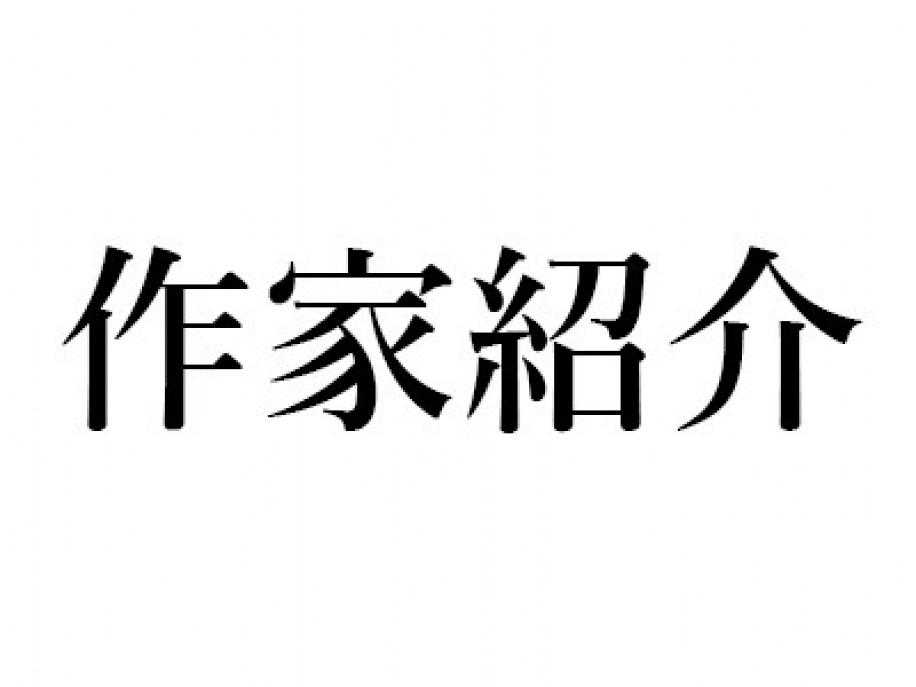コラム
ハードボイルドは裏切りの文学か
ここ一、二年の間にわたしは長編『百舌の叫ぶ夜』と『カディスの赤い星』、短編集『クリヴィツキー症候群』と『水中眼鏡の女』を世に出した。
この四冊にはたまたま、わたしの書く小説のいくつかのジャンルがうまく配分されている。つまり、『百舌』は警察官を主人公にしたハードボイルド小説であり、『カディス』はスペインを舞台にした冒険小説、『クリヴィツキー』は同じくスペインをテーマにした蘊蓄(うんちく)小説、そして『水中眼鏡』は精神病理を扱ったサスペンス小説という次第である。もっとも、意識して書き分けたわけではない.それらは一つの幹から枝分かれした兄弟にすぎない。その幹とは《ハードボイルド》の精神である。
わたしはハメット、チャンドラーに代表されるハードボイルド小説の、熾烈な洗礼を受けて育った世代に属している。そもそも《ハードボイルドとは何か》という議論は永遠の命題であって、その定義はハードボイルド作家の数と同じだけあるといってもよい。時代や国柄によって、概念が異なったり変化したりもする。一九七〇年代以降の《ネオ・ハードボイルド派》と呼ばれるものにいたっては、ハードボイルドという名を冠するのもはばかられるくらい、非ハードボイルド的な色彩を帯びている。
試みに日本の状況をみてみよう。
北方謙三さんは、日本では銃の使用があまりなじまないところから、主に肉体と鉄拳によって暴力の世界を描く試みをしている。北方さんはヘミングウェイの乾いた簡潔な文体を、日本語という情緒的な言語に移し替えることに、みごとに成功した。それだけではない、例えば「棒。」とただ一語書くことによって、読む者にその棒で殴りつけられたような衝撃を与えた。そうした斬新な文章表現の発見に、独特の感性と嗅覚が感じられる。
また彼はあるとき、自分の描くハードボイルド小説の源流を、かつての日活のアクション映画に求めると語った。アメリカに生まれたハードボイルドの概念を、日本の特殊な風土に移植しようとするとき、それはある意味で必然的な帰結だったかもしれない。
船戸与一さんは、作家になる決心をするまで、小説のたぐいを読んだことがないと豪語する、型破りの人である。船戸さんの原点が、ハメットにあることははっきりしている。何年か前、彼が『非合法員』でデビューしたとき、処女作にしてすでに自分のスタイルを確立していることに、羨望に近い驚きを感じた覚えがある。そのスタイルは、わたしの目には明らかに、ハメットのそれを志向しているように思われた。のちに語ったところによれば、彼は小説なるものを書くにあたって、ハメットやチャンドラーの作品を徹底的に分析したという。そして躊躇なくハメットのスタイルを選んだばかりか、チャンドラーこそハードボイルドを堕落させた張本人である、と喝破した。
船戸さんは「優れたハードボイルド小説とは帝国主義の断面を完膚なきまでに描いてみせた作品をいう」と定義している。彼の作品は間違いなく、その定義を体現しようとする努力の連続といえる。
志水辰夫さんも冒険小説、ハードボイルド小説の旗手の一人とされるが、北方さんや船戸さんとはまた一味違う趣を秘めている。志水さんの文章には、日本の風土や自然といったものに対する強い畏敬の念があり、それらと折り合いをつけながらハードボイルド小説を書こうとしているように思われる。彼の描き出す豊かな地方色、綿密な風景描写は、このジャンルの他の作家に見られないきわだった特徴である。彼が描こうとしている闘いは、人間対人間というよりも、人間と自然のぶつかり合いといった方が適切かもしれない。
かつてアメリカの評論家アンソニー・バウチャーは、《ハメット・チャンドラー・マクドナルド・スクール》と称して、これら三人の作家に正統ハードボイルド派のお墨付きを与えた。今にして思えば、この括(くく)り方はかなり乱暴なものであった。三人ともまったく資質の異なる作家であり、作風も違えば文体も違う。共通点といえば、私立探偵を主人公にした小説を書いたということだけである。同様に、北方、船戸、志水の三氏も、共通点より相違点の方が多い。彼らを一つのラベルで括ることは、文学史的な観点からは便利であろうが、作家としての本質を見誤る恐れがある。
わたし自身もまた、作品のタイプがいくつかに分かれているため、一つのラベルで括りにくい作家の一人といえるだろう。わたしはそれでいいと思っているし、まして自分から××作家などと看板を掲げるつもりは毛頭ない。アメリカの作家ディーン・クーンツが言うように、一度貼られたラベルをはがすにはたいへんな努力がいる。今あげた三人の作家もわたしも、通奏低音としてハードボイルドの精神を堅持しているし、そのほかこの分野で活躍する若手の作家にも、同様の気概を秘めた人が何人かいる。ラベルは別々でも、志は同じである。手垢がついて久しい《ハードボイルド》という言葉に、いまだにある種の神通力が存在すると信じる同志がいることは、まことに心強い。
(次ページに続く)
この四冊にはたまたま、わたしの書く小説のいくつかのジャンルがうまく配分されている。つまり、『百舌』は警察官を主人公にしたハードボイルド小説であり、『カディス』はスペインを舞台にした冒険小説、『クリヴィツキー』は同じくスペインをテーマにした蘊蓄(うんちく)小説、そして『水中眼鏡』は精神病理を扱ったサスペンス小説という次第である。もっとも、意識して書き分けたわけではない.それらは一つの幹から枝分かれした兄弟にすぎない。その幹とは《ハードボイルド》の精神である。
わたしはハメット、チャンドラーに代表されるハードボイルド小説の、熾烈な洗礼を受けて育った世代に属している。そもそも《ハードボイルドとは何か》という議論は永遠の命題であって、その定義はハードボイルド作家の数と同じだけあるといってもよい。時代や国柄によって、概念が異なったり変化したりもする。一九七〇年代以降の《ネオ・ハードボイルド派》と呼ばれるものにいたっては、ハードボイルドという名を冠するのもはばかられるくらい、非ハードボイルド的な色彩を帯びている。
試みに日本の状況をみてみよう。
北方謙三さんは、日本では銃の使用があまりなじまないところから、主に肉体と鉄拳によって暴力の世界を描く試みをしている。北方さんはヘミングウェイの乾いた簡潔な文体を、日本語という情緒的な言語に移し替えることに、みごとに成功した。それだけではない、例えば「棒。」とただ一語書くことによって、読む者にその棒で殴りつけられたような衝撃を与えた。そうした斬新な文章表現の発見に、独特の感性と嗅覚が感じられる。
また彼はあるとき、自分の描くハードボイルド小説の源流を、かつての日活のアクション映画に求めると語った。アメリカに生まれたハードボイルドの概念を、日本の特殊な風土に移植しようとするとき、それはある意味で必然的な帰結だったかもしれない。
船戸与一さんは、作家になる決心をするまで、小説のたぐいを読んだことがないと豪語する、型破りの人である。船戸さんの原点が、ハメットにあることははっきりしている。何年か前、彼が『非合法員』でデビューしたとき、処女作にしてすでに自分のスタイルを確立していることに、羨望に近い驚きを感じた覚えがある。そのスタイルは、わたしの目には明らかに、ハメットのそれを志向しているように思われた。のちに語ったところによれば、彼は小説なるものを書くにあたって、ハメットやチャンドラーの作品を徹底的に分析したという。そして躊躇なくハメットのスタイルを選んだばかりか、チャンドラーこそハードボイルドを堕落させた張本人である、と喝破した。
船戸さんは「優れたハードボイルド小説とは帝国主義の断面を完膚なきまでに描いてみせた作品をいう」と定義している。彼の作品は間違いなく、その定義を体現しようとする努力の連続といえる。
志水辰夫さんも冒険小説、ハードボイルド小説の旗手の一人とされるが、北方さんや船戸さんとはまた一味違う趣を秘めている。志水さんの文章には、日本の風土や自然といったものに対する強い畏敬の念があり、それらと折り合いをつけながらハードボイルド小説を書こうとしているように思われる。彼の描き出す豊かな地方色、綿密な風景描写は、このジャンルの他の作家に見られないきわだった特徴である。彼が描こうとしている闘いは、人間対人間というよりも、人間と自然のぶつかり合いといった方が適切かもしれない。
かつてアメリカの評論家アンソニー・バウチャーは、《ハメット・チャンドラー・マクドナルド・スクール》と称して、これら三人の作家に正統ハードボイルド派のお墨付きを与えた。今にして思えば、この括(くく)り方はかなり乱暴なものであった。三人ともまったく資質の異なる作家であり、作風も違えば文体も違う。共通点といえば、私立探偵を主人公にした小説を書いたということだけである。同様に、北方、船戸、志水の三氏も、共通点より相違点の方が多い。彼らを一つのラベルで括ることは、文学史的な観点からは便利であろうが、作家としての本質を見誤る恐れがある。
わたし自身もまた、作品のタイプがいくつかに分かれているため、一つのラベルで括りにくい作家の一人といえるだろう。わたしはそれでいいと思っているし、まして自分から××作家などと看板を掲げるつもりは毛頭ない。アメリカの作家ディーン・クーンツが言うように、一度貼られたラベルをはがすにはたいへんな努力がいる。今あげた三人の作家もわたしも、通奏低音としてハードボイルドの精神を堅持しているし、そのほかこの分野で活躍する若手の作家にも、同様の気概を秘めた人が何人かいる。ラベルは別々でも、志は同じである。手垢がついて久しい《ハードボイルド》という言葉に、いまだにある種の神通力が存在すると信じる同志がいることは、まことに心強い。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする