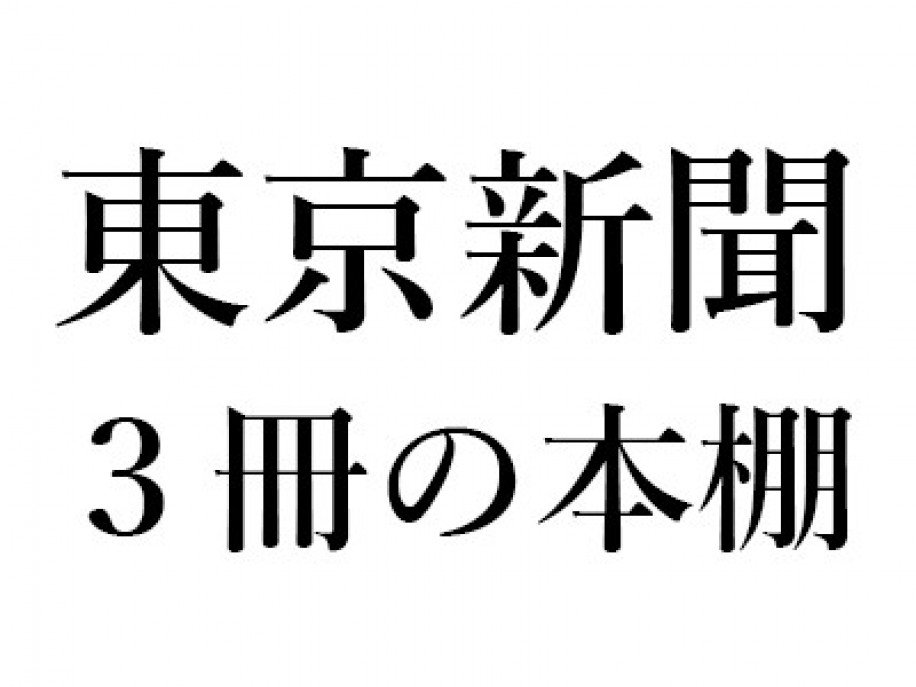笹山 久三『四万十川』(河出書房新社)、宇江 敏勝『さらば学舎』(求龍堂)、松村 みか『タイ、水牛のいる風景』(勁草書房)、林 真理子『ミカドの淑女(おんな)』(新潮社)、北山 龍二『ココリアの残紅』(影書房)
主婦の読書
十年前までシュフという言葉をわりあい無自覚に使っていたように思う。結婚して家庭を持ち、子供がいる女である自分が主婦と呼ばれるのも、それほど嫌でなかった。
でも、私は結婚してこのかた、一度も仕事を休んだことはなく、亭主に扶養されたこともない(したことはあるが)のに、「主婦=外での仕事を持たない女」であるように思われるのはどうもおかしいと思った。
地域で雑誌をはじめてみると、じつに「地域にいる人=主婦」の面ばかり強調され、「主婦のタウン誌、下町情緒」といった妙なレッテルをはられるのは困った。マスコミは言葉を消費し、変なニオイをつけるのはお手のもので、主婦作家、主婦連、主婦売春は申すにおよばず、主婦というとカルチャーセンター、教育ママ、不倫、パートに市民運動、バーゲンセール、オバタリアン、といったものと勝手に結びつけてくれるのである。そのうち『主婦と生活』も廃刊になった。『主婦の友』もリメークされた。「婦人」と同様「主婦」の命運も尽きかけているようである。ま、その辺のことを詳しく考えるには、上野千鶴子編『主婦論争を読む』を読んだ方が良い。
とりあえず、主婦というのは対概念がないこと(主夫とはいうが市民権のある言葉とはいいがたい)、有職、無職を両方含むこと、また一家の家事をつかさどる女性という意味では樋口一葉の妹くにとか正岡子規の妹とか、映画『東京物語』の夫と死別した原節子だって主婦なので、定義しにくいことだけ述べておく。
私自身は、離婚したり、あまり家事をしてないせいもあって、自分が主婦といわれるのには面映(はゆ)い感じ、また肩書きを勝手に「主婦」とされるのはうんざりする感じ、結婚していない女性エッセイストなどがステロタイプな主婦批判をくり返すのには向っ腹が立つ感じ、主婦というだけでプロに対するアマ、世間知らず、台所感覚などばかり強調され貶しめられた感じなど、複雑な感情を持っている。
一方、幸田文や向田邦子、沢村貞子、大村しげの各氏のエッセイを読むと、主婦本来のつつましく温かく、生活を手放さないで生き抜く心構えに魅かれ、ふたたびひらき直って、主婦を名乗るのも悪くはないという気がする。古い革袋に新しい酒である。
いや呼称にモノの本質は現われるというから、できるだけ主婦というあいまいな言葉は自らはつかわないようにはしたい。しかし、専業主婦が外での仕事を持たないゆえをもって不当に差別されているときは、私は彼女たちを代弁することが多かった。
夫に扶養される立場に安住し、不勉強で無神経で、子どものしつけもなってなくて、不倫や賭事にうつつを抜かしている主婦などというものは、マスコミで過大視されるほどいない。人間はすべてさまざまな事情と都合で生きているもので、老親の介護、夫の転勤、体が弱い、障害児がいる等々の理由で、働きたくとも家庭に居ざるを得ない女性はじつに多い。三十五歳をすぎると就職口もいたって少ない。
本の話からそれてしまった。何が言いたいか。レッテルはりという点では本屋にいくとかならずある〈主婦コーナー〉、これが困る。料理に編物、受験に勝ち抜いた母の体験談、占い、皇室物、女性作家による軽いエッセイが並ぶ。主婦がこうした噛みごたえのない本ばかりを喜ぶと書店や出版社が思っているのは、ずいぶん、私の実感とずれている。
私の身近にいる主婦たちは有職、無職を問わずバリバリ本を読む。『本の雑誌』にたまに本が三度の飯より好きな主婦が登場するが、あの程度の猛者はごろごろだ。
障害児をもつAさんも子どもの施設の送り迎えや病院通いで忙しいが、図書館で逢坂剛、宮部みゆき、佐々木譲、山田詠美、中島らも、藤沢周平といったところはことごとく読破、帚木蓬生が次作を出すのが待ち遠しいという人である。生協活動に熱心なKさんは六十代だが、村上春樹、吉本ばななは全部読んでいる。さらっとかりっとしたとこが好きなそうだ。老母の介護でいっしょに飲んでても七時には家に帰るSさんは、みすず書房のファンで私は中井久夫や辻まこと、神谷美恵子、シモーヌ・ヴェーユについて彼女にいろいろ教わった。大阪市立東洋陶磁博物館が面白かった、といったら、あなたが持ってた方がよさそうね、と淡交社の『小林太市郎著作集』をポンとくれた。安宅コレクションを集めた人だそうだ。彼女はいま岩波の『学海日録』が届くのを楽しみにしている。
ときどきイラストを描くIさんは女性史関係なら何でも読んでいる。「青鞜」の発起人の一人、自分と同郷の保持研子を調べはじめ、お墓参りをしてバッタリ遺族と出会い、その支援も得て現在、資料をあつめ研究中。七十代のMさんは夫の死後、夫の家系史を残すことから、その生活とかかわりのある島崎藤村、谷崎潤一郎、明治女学校を調べてやみつきとなり、全国を踏査している。ご自身が会津出身なので若松賎子についても大変詳しい。大阪のHさんは主婦の立場で飲み水にかかわっているうち、水問題に深入りして書物を読破し、ついに水に関する本を数冊出してしまった。彼女の説明は年号と人名とデータが淀みない。
こんな主婦はごく一例である。
ある日、森岡由起子さんという「主婦」の方が「虫喰草紙」という個人書評紙を送って下さった。このB5版八ページの書評の面白さ、闊達さよ。私はずいぶん、多くの本を教えてもらった。手書きのミニコミを引用するのは悪いけど、こんな風。
「あつよし少年がまた少し大人びてきた。……もうひ弱な感じはしなくなって、みずみずしくたくましくなってきた。彼の成長につき合って、年輪の曖昧な私は擬似脱皮をしようとしているのかも」――『四万十川』(笹山久三、河出書房)
「学舎、……ああ、こんな言葉があったんだなあ、と懐しくほろ苦い。モノクロームの写真はこわれた時計みたい。和歌山県下の休廃校を取材した作品であるのに、私は自分の出た小学校と中学校をこの中に捜した。今はもう無い。名前も残っていない学校を」――『さらば学舎』(中川秀典写真、宇江敏勝文、求龍堂)
「タイ各地の自然、文化、人々の暮しの観察もさることながら、タイという彼女にとってはこだわりのある国で、彼女が苦しみ、悩みつつ自立してゆくところが興味深い。とりわけ不倫ぽい恋愛の記録という点でも読める。だってこの題名で恋に身を焼く乙女の日記『バンコクの哀愁』なんて内容が想像できる? でもその後みかさんは彼とどうなったの! あとがきに書いてほしかったよね」――『タイ、水牛のいる風景』(松村みか、勁草書房)
「林氏は売文を生業としておられるので、……商品として下田歌子はなかなかよい素材であったろうと思う。編集者からこの素材を料理してみんかね? と言われるまで下田歌子のことは何も知らず、資料も全部、編集者が集めて来てくれて、あーよく勉強したもんだ、とあとがきにあった。林氏の正直さに涙すべきか呆れるべきか」――『ミカドの淑女(おんな)』(林真理子、新潮社)
「ココリアが何か、ケケリアが何か説明することはできない。一人でそっと声を出して読んでみた。初めて読むのに、言葉がスルスルと次の言葉を引き出すようによどみなく続く。静かで生暖かいような不思議な世界が、むこうから扉を押し開けてやって来るような、一読は百見にしかず」――『ココリアの残紅』(北山龍二、影書房)
的確にキマっている、本を読む彼女がはっきり見えてくる。私はここに出てくる本はほとんど全部よみたくなって手帳にメモした。既読ベスト3に入るのが『ある明治人の記録――会津人柴五郎の遺書』というのは握手したくなった。
私の全く不得意な〈児童文学〉について、「子どもが読めることを第一目的としているけれど、大人の鑑賞に耐え十分読むことのできる本を〈児童文学〉とか〈子ども向け読物〉と呼ぶのはやめよう」と彼女は提案する。じゃあ何とよぶか。「New J Land」だってさ。彼女、ニュージーランドに行ってきたばかりなのね。Jは単語数が少ないけれどJoy Join Jump Joke Jowel Jeans、身近な親しみやすい単語が多いんだよ、もちろんJuniorもあるしさあ、と簡単明瞭だ。
彼女の「ニューJランド・独断ベスト19」とその短評にはまいりました。一位マゴリアン『おやすみなさいトムさん』二位フュアマン『少年ルーカスの遠い旅』三位林多加志『ウソつきのススメ』四位ハリス『フランセスの青春』……から十九位後藤竜二『九月の口伝』まで、よくもまあ。これだけ徹底して読者の目で読んで実感溢れる、権威ある「ベスト・ガイド」はないのではないか。私はこの「虫喰草紙」にショックを受けた。
主婦といったら怒られるな。森岡さんは伊那の惠文堂という本屋の店員でもあったといいますが、……やっぱり主婦はスゴイ。
【このコラムが収録されている書籍】