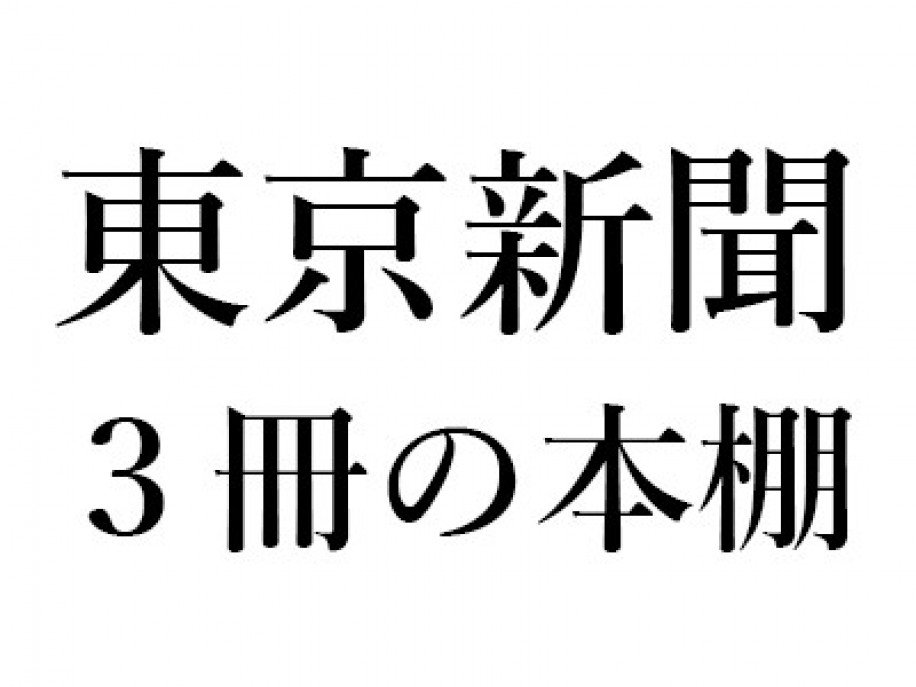書評
『女文士』(集英社)
真杉静枝という女流作家を記憶している人は、たぶんほとんどいない。なぜあえて二流、いや三流の作家の評伝なのか。そこにすでに著者の批評精神が込められているのだ。女流と呼ばれることへの自嘲(じちょう)とそう呼ぶ文壇人たちへのいくばくかの軽侮、ほかにも……、それは最後に触れよう。主人公にとってライヴァルは同じ女流の林芙美子、平林たい子、吉屋信子、宇野千代であった、といえば読者にも彼女の生きた時代の見当がつく。
真杉静枝は台湾で育ち、親の取り決めた見合いで平凡で退屈な男と結婚した。それでもまだ見ぬ世界の広がりだけは、漠然と予感した。やがて夫から淋病を移された。「ひとつの希望をかなえるためには、大きくてつらい代償が必要なのだ」と、家出する。植民地という周縁で人知れず咲いて散るだけであったはずの人生は、ひょんなことから大きく転換した。幾つかの職を経るうちに独特の運気で大阪毎日新聞の嘱託となったことから、白樺派の作家で「新しき村」の創設者・武者小路実篤のところへ取材に行く機会を得る。
蝉(せみ)が鳴く夏の午後、初対面の彼女にこの理想主義者は「あなたは西洋女のような顔をしている」と口説く。武者小路の愛人として過ごすうち結婚願望がむくむくと湧(わ)く。男からみれば潮時の徴候である。捨てられついでに歳下の文学青年・中村地平と知り合った。強引な結婚は長続きせず、彼女の空虚は拡がり結婚願望はいっそう募るばかりだった。今度は芥川賞作家で売れっ子の中山義秀へ近づき目的を成就した。だがこれも二年ほどで破綻(はたん)する。のちに中山義秀は自分の年譜から真杉との結婚歴を削ったほどだ。「醜聞に汚れきった女」としての“実績”が重ねられていくからである。
著者は自分のなかの女の部分に愛着以上に辟易(へきえき)とするものを感じているようであり(それは著者に両性具有の、男の視線も備わっているということだが)、極端に誇張されたモデルを通じてそれを描くことができたら、と考えたのだと思う。その試みは成功したのではないか。
真杉静枝は台湾で育ち、親の取り決めた見合いで平凡で退屈な男と結婚した。それでもまだ見ぬ世界の広がりだけは、漠然と予感した。やがて夫から淋病を移された。「ひとつの希望をかなえるためには、大きくてつらい代償が必要なのだ」と、家出する。植民地という周縁で人知れず咲いて散るだけであったはずの人生は、ひょんなことから大きく転換した。幾つかの職を経るうちに独特の運気で大阪毎日新聞の嘱託となったことから、白樺派の作家で「新しき村」の創設者・武者小路実篤のところへ取材に行く機会を得る。
蝉(せみ)が鳴く夏の午後、初対面の彼女にこの理想主義者は「あなたは西洋女のような顔をしている」と口説く。武者小路の愛人として過ごすうち結婚願望がむくむくと湧(わ)く。男からみれば潮時の徴候である。捨てられついでに歳下の文学青年・中村地平と知り合った。強引な結婚は長続きせず、彼女の空虚は拡がり結婚願望はいっそう募るばかりだった。今度は芥川賞作家で売れっ子の中山義秀へ近づき目的を成就した。だがこれも二年ほどで破綻(はたん)する。のちに中山義秀は自分の年譜から真杉との結婚歴を削ったほどだ。「醜聞に汚れきった女」としての“実績”が重ねられていくからである。
著者は自分のなかの女の部分に愛着以上に辟易(へきえき)とするものを感じているようであり(それは著者に両性具有の、男の視線も備わっているということだが)、極端に誇張されたモデルを通じてそれを描くことができたら、と考えたのだと思う。その試みは成功したのではないか。
ALL REVIEWSをフォローする