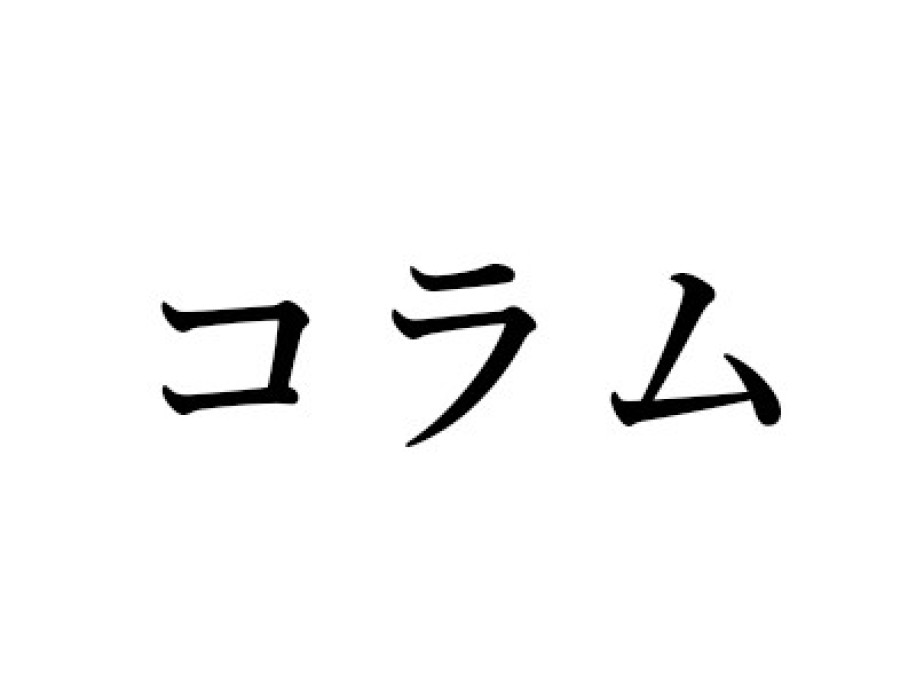書評
『必然の出会い―時代、ひとをみつめて』(影書房)
紡がれた言葉
一つの体は一つの心しか持てない。一つの心は一つの体にしか宿らない。どうしても想いを届けたいとき、それが心底つらい。言葉にすると嘘になる。言葉にしたらツマラナイ。それでも人は言葉を頼む。伊藤ルイさんの『必然の出会い』(影書房)は言葉がじつによく響いてくる本である。
たとえば、冒頭にこんなおばあさん。村のバス停で、みんな石のように押し黙ってバスを待つ。そこに「どなたも、おはようございます」という声がかけきれる人。「ひろびろとどこまでもひろがる『どなたも』といえる心を、なんのために、どうやって失わされてしまったのか」とルイさんは考えこむ。
ルイさんは一九二二年生まれ。博多で長く人形の彩色職人として生きてきた。そしていまは反戦、反原発、自然保護、死刑廃止その他の運動にかかわって全国を歩き、それをまた書くことによって伝えている。
その旅のさなかで鳥取の徳永進医師(『死の中の笑み』著者)に会う。さまざまな縁が重なりながら、会えずにいた。しかし「想いつづけていれば、時が満つれば、やがては会える」と文中にある。さて、別れて徳永夫人から手紙が届く。「今は亡き人たちがなお人に与える影響力を持っているのも確かですが、生きている者同士でしか感じ合うこともできない影響力というものがお互いのなかにある、というのも確かなことだと思います」。これをルイさんは「私が伝えたくて言いきれなかった言葉」だという。そんな「必然の出会い」が本書には数多く語られている。
この場合、前段の「今は亡き人たちがなお人に与える影響力を持つ」というところも大事なのだ。伊藤ルイは大杉栄と伊藤野枝の四番目の娘である。二歳のとき関東大震災が起こり、無政府主義者である両親は、憲兵隊によって火事場泥棒的に虐殺された。このことをはじめに紹介したくなかったのは、ルイさんを「大杉・野枝の遺児」とだけレッテルを張るのはあまりにも愚かしいことだからである。
しかし物心つかないうちに殺された両親の存在とその苦難を深く受けとっているからこそ、ルイさんは、在日外国人の指紋押捺拒否を支援し、国家権力の「人を殺した者は死刑にする」という論理に憤り、獄中の人を励ましているにちがいない。
本の中に、墓や碑をたずねるくだりが多い。名古屋の日泰寺には、大杉と共に殺された甥の橘宗一の墓が発見された。石には父親が刻ませたものか「犬共ニ虐殺サル」とあった。なんというすごい言葉であろう。かくのごとく、石にすら想いは言葉として結晶する。必然の出会いといえばもう一人、異父兄辻まことの墓を、福島県の長福寺にたずねてもいる。
生前の兄とはたった五回しか会わなかった。それはいつも楽しかった。辻まことが父辻潤を評す。「おやじ自身、一個の芸術作品であった」「おやじ自身は自由ではなかったとしても、おやじの行為と表現は、私のそして多くの人々の精神の願望の犠牲のように思われる」。同じことをまさに、妹は辻まことに感じる。「人を取り除けてなお価値のあるものは、作品を取り除けてなお価値のある人間によって作られるような気がする」という兄の言葉、「ルイちゃん、才能はね、それを資本化しながらのばしていかなくちゃあね」という最期のベッドからのメッセージをルイさんはぐっと握りしめて生きている。
いま、戦後の労働運動、ことに大組織の労働運動の崩壊をみるとき、大杉や久太郎の、……すなわちその力や光は、その本当の強さを保つためには、自分で一字一字、一行一行ずつ書いてきた文字そのものから放たれるものでなければならない……という、つまり一人ひとりの生き方そのもの、日常生活そのものが自立した、奴隷根性から脱却した人間の集まりでなければなんの力にもなり得ないし、むしろ資本の側に、体制の側に乗っ取られるという状況が露呈されていると思われてならない。
このルイさんの言葉は、声高ではないがまっすぐに事象を突きさして私に届く。「真に孤独であることができる者だけが真に愛することができる」といったのは、エーリッヒ・フロムであったか。
伊藤ルイという人は、さずけられた人生のなかで、孤独である技術を磨き、屹立する個であることによって、自然を愛し、人々と連帯し、国家ではなく、丸ごとの地球を抱いているように思える。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア

DIY(終刊) 1991年12月~1992年8月
ALL REVIEWSをフォローする