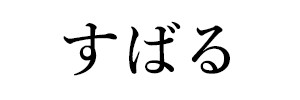作家論/作家紹介
獅子 文六『食味歳時記』(中央公論新社)、『私の食べ歩き』(中央公論新社)、『バナナ』(筑摩書房)、『愚者の楽園』(角川書店)、他
はじめて獅子文六の存在を知ったのは、かつての流行作家としてだった。加東大介(かとうだいすけ)のはまり役、愛嬌(あいきょう)いっぱいの株屋「ギューちゃん」を演じた映画「大番」(映画化四回!)の原作者と知って、へえと思ったりもした。そうこうするうち、『私の食べ歩き』を手に取った。この本はもともと昭和三十七年、『飲み・食い・書く』(角川書店)として刊行され、文化勲章をもらった一カ月後に世を去る四十四年、『好食つれづれ草』と改題してふたたび刊行、さらに『私の食べ歩き』(ゆまにて)と再改題ののち、平成十一年、中公文庫に入った。一読しておどろいた。なんでもかんでも、まあ食べるわ、食べるわ。パリの安飯屋で前菜に赤大根、仔牛(こうし)の煮込みヴォウ・ソーテ、レッテルなしの安酒。ドイツの友人の下宿で生キャベツ、焼きサーディン。大徳寺の塔頭(たっちゅう)や岐阜「角正(かくしょう)」で精進料理。小田原の新鮮なアジ。ふぐ。どぜうの丸鍋。大阪「たこ梅」のおでん。「辻留(つじとめ)」でなまこの白和え。秋田の貝鍋。伊予の鉢盛料理。京都の黄檗(おうばく)料理。ロンドンのスペイン料理。横浜「西洋亭」のコロッケやローストチキン。日本橋の鰻屋(うなぎや)の肝焼き、白焼き、いかだ。「笹(ささ)乃雪」のあんかけ豆腐。「天政」のてんぷら。東京のシナ料理。太田(おおた)の牛肉屋の牛鍋……逃さず食指を蠢かせ、「グウルマン」の自負心を発揮してかたっぱしから胃袋におさめている。じっさい、たいていのうまいもんは余さず食べ尽くしていたのではないか。酒も、からだを壊すほど飲んだ。銀座のバー「ルパン」で小林秀雄(こばやしひでお)と口論になり、表へ出ろと喧嘩(けんか)をふっかけたものの、じっさいは路上で他人と大立ち回りを演じて留置場行きになった。二度めの結婚をして三日め、署へもらい下げに行ったのは今日出海である。作家、中村真一郎(なかむらしんいちろう)の披露宴では記憶がなくなるほど痛飲し、翌朝気づくとズボンが裂けて脛(すね)に血が滲んでいた。「醜悪と恥辱に充(み)ちた泥酔」は千回以上、と随筆「泥酔懺悔(ざんげ)」に自虐的に書いてみせるほど、若いころから酒との関係は泥沼だった。
すごいかも、この食いしんぼうは、大酒飲みは。そう思わせるだけの破格の経験と知識の蓄積があり、自慢話はとうに織りこみずみ、筆にまかせて食べもの話をぐいぐい書き連ねてゆく技にいやおうのない説得力があった。「シャンパン談義」など、その真骨頂のひとつではないかしら。シャンパンは口説酒(くどきざけ)だと断じたあと、つづけて。
僕は外国にいる時は、安ホテルの洋服簞笥(ようふくだんす)の中に、いつも、シャンパンの小壜(ドミ・ブータイユ)を投げ込んで置く。そうして、宿酔(ふつかよい)した朝に、コーヒーの代りに、グッとやるのである。酔覚のサイダーと迎え酒の効用を、一本にして兼ねるもの、シャンパンを措(お)いて、奈辺(なへん)にあらんや。気分たちまち爽快(そうかい)となって、勉強したり、遊んだりする勇気が出る。たいへん贅沢(ぜいたく)のように聞えるが、その頃、邦貨換算小壜一本九十銭ぐらいである。一週間に一本ぐらい飲んだって、どうにかなるではないか。
気障(きざ)である。自慢げである。それに、シャンパンどころか、外国旅行さえとんでもない高嶺(たかね)の花だった昭和三十年代に、外国の「安ホテル」だの「小壜を投げ込んで」だの、読まされた読者は反応のしようもなく、はァそうですか、と黙るほかなかったろう。しかし、いま読んでも古びず、それどころかすんなり通用するところにセンスのよさがある。ふと伊丹十三(いたみじゅうぞう)『ヨーロッパ退屈日記』(昭和四十年刊)を思い出すが、それよりだんぜん早いのだから、やっぱりぐうの音も出ない。シャンパン話はさらに止まらず、シャンパンは味で飲むのではなく雰囲気で飲む酒である、小壜を飲むのが気が利いている、足りなければ小壜を二本飲めばよい……恐れ入ります。
じつのところ、三年におよぶパリ暮らしで味わったフランス料理は、獅子文六の味覚の下敷きになった。イタリア料理もロシア料理もドイツ料理もうまいけれど、と前置きして、フランス料理をこう評する。「西洋料理の本筋というのか、王道というのか、地方的なウマさでなく、正々堂々とウマイのである」。なるほど、自分の舌できっちり核心をつかんでいる。ワインは、赤ならボルドーのなかでもサンテミリオンかメドック、白ならブルゴーニュのプーイ(ピュイイ)やシャブリ。食通であることにはてんで興味がないとあちこちで繰りかえし書くのだが、じっさいの趣味嗜好(しこう)はどまんなかの王道をゆく食通ぶり。
しかし――。『私の食べ歩き』を読むうち、わたしは首をひねることになった。あれれ、世間には「洒脱(しゃだつ)な食味随筆」として知られているけれど、獅子の食べ心地はちょっと妙なのだ。うまいものを次から次へと列挙してみせられるのに、へんだな、たいして食欲をそそられないのです。それに、皮肉や諧謔(かいぎゃく)の地雷をあちこちに置いて食欲を阻む様子は、酒脱とはほど遠い。たとえば吉田健一の食味随筆を読んでいるとき、しだいに官能がとろとろと刺激されてとろけそうな疼きを覚えるあのなまめかしさが見つからない。もっとも、杉浦明平(すぎうらみんぺい)が『カワハギの肝』でなかばくやしがって「わたしのように、何とか手に入れようとあくせくするものにとっては、別世界の人間のように見えても仕方あるまい」と書いたように、「生産にも製造にも一切タッチせず、ほとんど無関心で、出来上がって奉献されたものを百二十%享受する」吉田健一は、今様(いまよう)のお殿様にちがいなかったのだけれども。または、おなじ大酒飲みの草野心平(くさのしんぺい)。詩人草野心平が食べものについて書くときの、生の息吹に直接訴えかけてくる躍動感、日々の営みに根づいたリアリティもうすい。かといって、小島政二郎が『食いしん坊』で描きだそうとした人間関係の気配もうすい。やっぱり獅子文六は、険しい谷間でひとり咆哮する特異な存在なのである。
おいしそうな匂いが漂っている気がして、食欲に火をつけてもらおうと期待いっぱいで近づいたのに、なかなか生つばを湧かせてくれないのだ、この獅子は。でも、もったいぶってお預けを食わされているのではない。理由はだんだんわかってきた。なにより獅子文六じしんにそのつもりがないのです。食べものの味は書いても、思うところはべつの場所にある。その複雑で狷介(けんかい)な思考回路にこそ、つねに一筋縄ではいかない獅子文六らしさが充満しているのだった。
わずか三行で、獅子文六の文章の本質をあざやかに切り取った人物がいる。鶴見俊輔(つるみしゅんすけ)である。『自由学校』『やっさもっさ』など「伝記文学として、私は、獅子文六の作品をたのしんで読んできた」と共感をあらわしたうえで、『山の手の子 町ッ子』の解説に書く。
なかなか文学にふみきれなかった獅子文六がその道に入ったのは、フランスにゆき、フランス人を妻として日本にもどってきてからである。彼がフランス文化から得たものは、モラリスト(自分を除外しない人間観察者)の方法である。
自分自身の仔細な観察にうらづけられた批評。これが獅子文六が小説や随筆に持ちこんだ手法であり、最大の特色だと鶴見俊輔は看破している。だからこそ、食べものを扱っても、味わいそのものが熱心に描かれるのではなく、するどい観察眼がもたらす批評があちこちに顔をのぞかせた。じっさい、モラリストの名にふさわしく獅子文六ならではの箴言(しんげん)は『食味歳時記』のあちこちに見つかる。
とにかく、戦後の日本人は、外国の料理なら、何でも大歓迎。外国料理というより、外国そのものを、食いたいのだろう。(「キントンその他」)
片貝(かたかい)の人は、イワシの真味というものを、知ってるのだろう。イワシという一つの魚に限って、非常な食通なのだろう。他の魚では、その真味に、到達できないのだろう。
変ったものばかり漁(あさ)るのが、食いしん坊の道ではないと、思い当るのである。(「実る」)
老人と冬は、ウマが合うのかも知れない。食物に味が乗るばかりでなく、何か、心が落ちついて、静かに、ものを味わうことができる。(「鍋」)
要所要所で獲物をきっちり仕留める。ただし、仕留めたところでやめておけばよいものを、ひと声吼えないと気がすまない。なにしろ、すっかり食欲が衰えてしまったと老齢を嘆きながらも雑誌「ミセス」に連載した『食味歳時記』、その最終回の締めくくりのしょっぱさときたら。「さて、一年間、長々と、書き連ねたが、なにが好きだの、かにがウマいのと、人に語ることが、あまり、意味のあることとは、思ってない。/一人で、自由に食ってれば、いいのである」。なんだか啞然(あぜん)としてしまう。さんざん好き放題を書いておきながら、最後の最後にきて否定してみせる。素直に心情をさらけだすと損をするとでも思っているのかしら。煙幕を張りめぐらせるのが癖になっている。相手がシュウ・クリームでさえ、この調子だ。
誰しもいうことだが、初めてシュウ・クリームを食った時の驚異というものは、震天動地的なものである。こんなウマいものが世の中にあるかと思う。羊羹(ようかん)、最中(もなか)、饅頭(まんじゅう)のたぐいは、弊履(へいり)のごとく、蹴飛(けと)ばしたくなる。私らの父兄が、自由民権思想に初めて接した時にも、恐らくシュウ・クリームと同様な、魅力を感じたに違いない。
ところが、どうだろう、近頃、他家を訪問してシュウ・クリームなぞ出されると、主婦の趣味のほどを疑いたくなる。あんな、バカバカしい単純な菓子はないと思う。これに反し、京都虎屋の羊羹、東京空也(くうや)の最中なぞとくると、その味の微妙さといい、典雅さといい、実に比較にならん高級の菓子たるを知るのである。
捨てて置けば、日本人は、みんなこういうふうになるのである。しかるに、シュウ・クリームを排撃せよとか、シュウ・クリームは醇風美俗(じゅんぷうびぞく)に悖(もと)りとか――いや、誰もそんなことをいってやしない。(『私の食べ歩き』「故郷横浜」)
けっきょくなにが言いたいのかよくわからない。しかし、獅子文六ならではの狷介さは、じつによくわかる。シュウ・クリームという新しい味をさっそく扱うことでひと足早く時代に先駆け、そのうえで最先端を揶揄してみせる。おれはぜんぶわかっているぞ、ちゃあんと知っているぞ。だから、女性がビアホールでビールを飲むのも歓迎したし、シテ島にある贔屓(ひいき)の“縄暖簾(なわのれん)”「ポール軒」を、パリに来た皇太子一行が訪れたと聞きつけ、ほうらみろ、と快哉(かいさい)を叫ぶ。意地と自負心満載のモラリストなのだ。ここでわたしが思い出すのが、『ちんちん電車』である。いっときは幼年から馴染んだ都電を「バカバカしくて、乗れない」と思っていたのに、戦後の東京の交通機関が整備されて国電や地下鉄が通り、町をバスやタクシーがわがもの顔で駆けまわりはじめると、都電の魅力に目覚めた。軌道の上をのんびりおっとり走る都電がなんとも上品で、にわかに愛おしい存在に思われ始めたのである。七十代になっても、相変わらずのあまのじゃくぶりがかわいい。そして、古き佳(よ)き時代の東京への郷愁にも突き動かされ、ふたたび都電に乗りながら偏愛を注ぎこんで『ちんちん電車』を綴った。
老境をむかえると、食べものを語る筆致にいよいよ独自の味がくわわった。若いころの食欲旺盛と鯨飲ぶりが災いして、五十代で胃潰瘍(いかいよう)の手術をして節制を余儀なくされ、六十代を超えると嗜好が変わってしまったと公言して憚(はばか)らなかった。若いころから何十年も一貫して愛着があるのは「ソバと鮎(あゆ)ぐらいのもの」で、豆腐さえ一時のように執心を示さなくなったとつれない。けっきょく好きになったもの、食べたくなったものは「ヒジキと油揚げの煮たの」「ゼンマイの煮たの」「キリボシの煮たの」「ナッパの煮たの」。おやおや。たしか安ホテルの洋服ダンスにシャンパンの小壜を投げこんだよね、鮎の塩焼き、たてつづけに二十何匹平らげたよね、往年の食い気はどこへ捨てちゃったの。はしごをはずされ、齧りどころをなくして拍子抜けして鼻白む。
でも、心配は無用です。不死身の獅子はなお吼える。
そんなものなら、誰にも料理ができるから、不足はなかろうと考える人もあろうが、どう致しまして、ヒジキやゼンマイやキリボシを、上手に煮て食わして貰(もら)ったことは、一度もない。細君や女中さんは、こういう料理を軽蔑(けいべつ)するから、いつまで経っても、腕前が上達するわけがない。それなら名ある精進料理屋へ行ったら、本望を達するかというと、そうもいかない。精進料理屋では、そんなオソマツなものを出さないが、特に頼んで調理して貰ったとしても、私の望む味とはならないだろう。これは惣菜(そうざい)料理であって、板前さんの腕がよければよいほど、ちがった味に外れてしまうだろう。(『私の食べ歩き』「一番食べたいもの」)
ああいえば、こういう。つくづく、やっかいな味覚の持ち主である。家庭の味もプロの味も、どっちもなぎ倒して韜晦に持ちこみながら、得意の批評におよぶ。ツッコミ役の瀬戸わんやなら、待ってましたとばかり、がぜん張り切っていじりまくるところじゃないか。
老いの境涯に接して食べものに距離感が生じた手負いの獅子には、もはやこわいものがない。あんなにばかにしていた麩が好きになったと言い、野菜料理が口に合うようになったからと黄檗料理を手放しで賞賛し、いっぽう熱い飯を水にさらしてつくる水飯(すいはん)は清浄だが厭世的(えんせいてき)と一刀両断、教えてくれた相手を「なにか気の毒な人であった」と名指しで言い放つ。それでも気がおさまらず、「暑い銀座で、ギョーザでも食っている方が幸福であり体にもよいにきまってる」(!)。わっしわっしと歩きながら周囲をねめ回し、気の向くまま四方八方をツメで引っ搔(か)いて歩く。
それにしても、思う。獅子文六は、いつ、どこで孤高の獅子になったのだろうか。みずから獅子を名乗ったせいだろうか。それとも生まれついての獅子だったのだろうか。「ドロップス」に、ずばりその答えが書かれている。
私は第三者的回想を試みるが、私の幼年時代には東京人にも地方人にもない特色があったようだ。早くいえば、私は子供の時にポルトガル人だかの調(ととの)えた洋服を着、舶来の靴を履(は)き、どこやらの領事の子供と遊び、ユダヤ人のべーカリイで菓子を食った。
なぜそういうことになったかというと、父の経営する店が、横浜の居留地にあったからである。なぜ武士であった父がそんなことを始めたかというと、父が福沢諭吉(ふくざわゆきち)の同郷で後輩で、その門に学んで甚(はなは)だしい感化を受けたがためである。(『獅子文六全集 第十五巻』「ドロップス」)
父、岩田茂穂は福沢諭吉の思想に学んでアメリカに二度遊び、一代で絹織物の貿易商店を築いた生粋の明治人だった。つまり、家庭のなかに文明開化の香りがふんぷんと漂い、まっさきにドロップスにもシュウ・クリームにもサンドウィッチにも親しんだ。小学校へ上がると、まわりはみな紺絣(こんがすり)の着物に兵児帯(へこおび)だったが、少年は外国臭のする暮らしぶりが自慢でならなかった。孤高の獅子に育ってゆく道を、すでに幼年期から着々と歩んでいたのである。父は五十歳の若さで世を去り、家業はしだいに衰退していったが、九歳の豊雄少年は強烈な自負と誇りをこころのなかにしまいこんだ。
「ドロップス」は、こう締めくくられている。
父の死んだ翌年、私は東京の小学校の寄宿舎へ入れられ、周囲の国際色を失ったと同時に、幼年から少年になった。後は東京の少年とあまり変りがない。現在の日本は私の幼年時代のような色彩に包まれつつあるが、私は一度経験したからそう珍らしくない。
たてがみひとふり、ガルル~と咆哮。戦後の新生日本を、すでに「幼年時代に知っている」……虚勢を張るというのはちょっと違う。自分で自分を偏屈なところへ追いこんでいるのである。
ところが、母の思い出を書くときだけはやわらかな腹を見せて、びっくりするほど無防備になる。母はフェリス女学院の前身にあたるアメリカのミッションスクール系の学校を出た才媛(さいえん)だが、昔気質(むかしかたぎ)の気性でのびのびと明るく、夫の死後は横浜から大森へ引っ越して女手ひとつで兄弟を育てた。横浜での幼年時代の記憶は、老年に足を踏み入れていっそう、甘やかな蜜となった。髪を丸髷(まるまげ)に結い、春着に身をあらためた母が用意する元旦(がんたん)の雑煮。長火鉢でじょうずに焼いてくれるかき餅(もち)。三月の節句の炒(い)り豆。お彼岸のおはぎ。明治三十年代につくってくれたサンドウィッチには、ハムが手に入らないからボイルドビーフをこしらえてはさんだ……とめどなくあふれる回想には偏屈ぶりがなりを潜め、そのかわり母恋いの心情が臆面(おくめん)もなく吐露されていて、どきっとする。
かんがえてみれば、苦労人なのだ。最初に結婚したマリーは心身を病んでフランスに帰国して死に別れ、あとに残された長女を懸命に育てた。また、太平洋戦争のさなか、本腰を入れて岩田豊雄の本名で朝日新聞に執筆した小説『海軍』は、好戦的な内容ではないにもかかわらず日本中を熱狂させ、結果として戦意昂揚(こうよう)させたとしていったん戦争責任を問われている。持てる力の限りを注ぎこんだ作品が戦争賛美の一翼を担った現実は、骨の髄までシャイで個人主義、合理主義の作家を打ちのめしたに違いない。そして戦後、ふたたびみずから獅子に返り咲いて書いたのが『てんやわんや』なのだった。
古本屋の棚で『バナナ』を見かけたときのことは、いまでもよく覚えている。もう二十年以上まえだ。あれが獅子文六の名前が目に焼きついた瞬間だった。それにしても獅子文六は、自分の小説のタイトルをつけるのが天才的にうまい。単刀直入、誰にでもわかりやすく、短く、たちどころに覚えられる。『バナナ』にしても、ありふれた三文字のカタカナが、いったいどんな小説なのだろうと読んでみたくさせる。こんかい『バナナ』をあらためて読んでみると、じんわりと微笑(ほほえ)ましく、うれしくなった。舞台はハイカラな港町、神戸。在日華僑(かきょう)の暮らしぶり。外車。シャンソン。若者の恋愛。夫人の火遊び。銀座。バナナの仲買。中国料理のうまいもの……先端をゆく風俗がふんだんに盛りこまれ、いやがうえにも読者の興味を引きつけて飽きさせない。テンポのよさ、楽しさ、的を射た文明評。鍛え抜いた新聞小説の手練手管が随所に繰り広げられ、六十代の流行作家が機嫌よく書いている気配が伝わってくる。物語のおしまい、決めぜりふも獅子文六の面目躍如だ。
「今晩は、神田のテンプラ屋の天丼(てんどん)でいいよ。明日の昼は、千葉田に頼んで、洋食にして貰いたいな。ロースト・ビーフの厚切りに、添え野菜を沢山つけてな。カラシも忘れずに……」
げんざい獅子文六の著作はそのほとんどが絶版で、ともすると「忘れられた作家」として扱われがちである。発表当時の新しさが、時代を経ることで逆に古くなったから、といわれる。あくまでも娯楽小説の域を出なかったから、ともいわれる。流行作家の宿命といってしまえばそれまでだが、しかし、さかんに書き綴った食味随筆ひとつとっても、文章には偏屈偏狭の衣をかぶった人間観察者の視線の鋭さがそなわっていた。だからこその狷介孤高。かんたんに食えるわけがない。
獅子の味は海千山千。それでも熱心にがじがじと嚙みしだいてみると、歯ぐきに沁みわたってくるのは明治、大正、昭和。または戦前、戦中、戦後。フランス、日本。さらに影を落とす文明開化を生きた父と母、三人の妻との間にもうけた子どもたち。そこへくわえて、自他ともに認める偏屈でやっかいな気性。まことにしわい。
ところで、気に入りの本に『愚者の楽園』がある。没年からさかのぼって三年、昭和四十一年に刊行された随筆集だ。装幀(そうてい)は杉本健吉(すぎもとけんきち)。獅子を戴(いただ)くにふさわしい風格も情趣もある函(はこ)には、赤地に白で描いた獅子像。数年まえ大阪ミナミの古本屋で偶然見つけて、いっぺんで魅了されて買い求めた。「梅」と題した一編のなかに、こんなくだりが見つかる。
そういえば、梅の木なぞがおもしろくなってくるのも、人間を見る目ができてくることに、関係があるかもしれない。地方へ行くと、年老いた郵便配達だとか、ハタ織りのじょうずなばあさんとかいう人によく会うのだが、そういう人間のおもしろ味は、梅の老木の幹の趣きと似通っている。(『愚者の楽園』「梅」)
ここでもまた箴言に出合う。わたしは思った。老いて枯れた獅子がごつい手脚を不器用に曲げて寝そべり、ときおり薄目を開けてにらみをきかせてみせる様子には、そこはかとなく梅の老木の渋みに通じる風情がありはしないか。獅子の肉は、食べるには向いていない。疾走したり、徘徊(はいかい)したり、獲物を捕らえたり、つねにみずからのためだけにある。そのさまを「ほう」と感心して愛(め)でていればいい。いずれにしても、煮ても焼いても食えないかんじ、そこにこそ獅子文六の味があるのだった。
【この作家論/作家紹介が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする