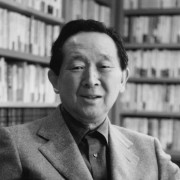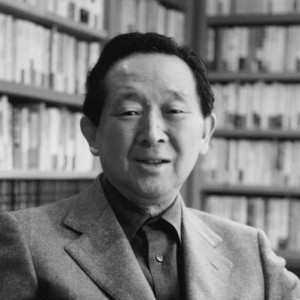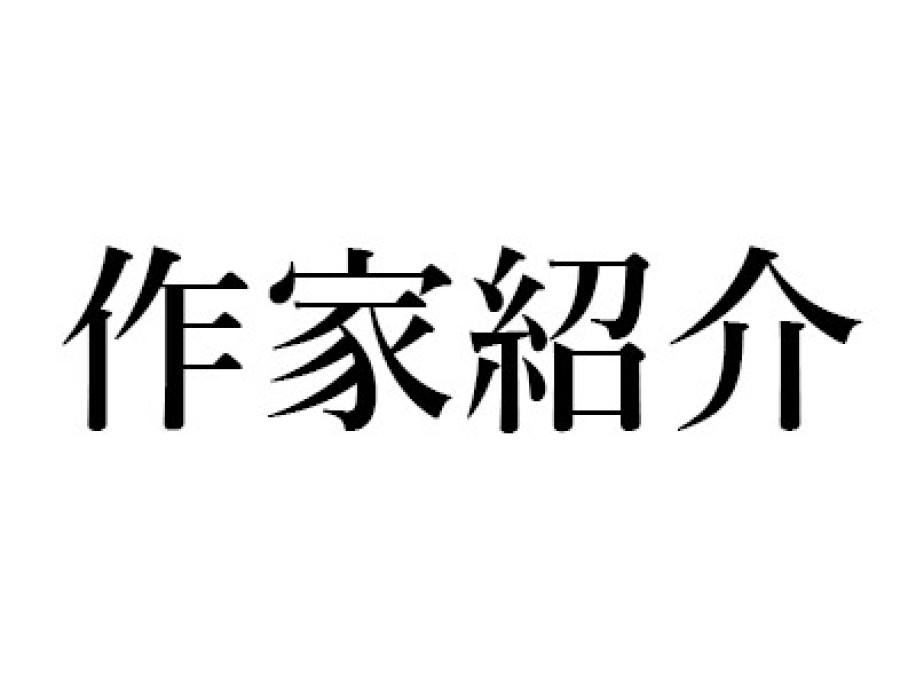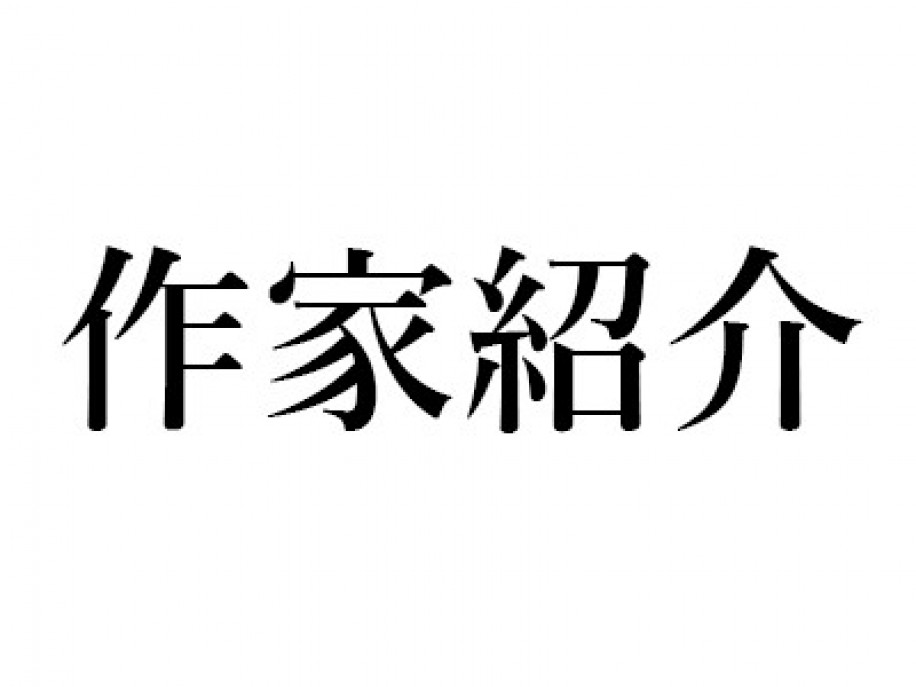金子 光晴『金子光晴詩集』(思潮社)
「一筋縄ではつかまらない」「本質が理解されているとはかぎらない」「位置は今なお決定していない」と語られているように、金子光晴は大変理解しにくい、かつ分類のむずかしい詩人のようである。
このことはひとつひとつの作品の「分りやすさ」といちじるしい対照をなしており、現代詩の理解をめぐる受容と批評の関係について鋭い問題を提供している事柄のように思われる。
短歌や俳句を日本的抒情に依拠しながら批評し評釈する場合には、決してこのような混乱が起こらないことを考慮すれば、この不思議な現象は、金子光晴の作品の質と、我が国の近代的な批評の方法とのあいだに何等かの決定的なズレが存在していることを暗示しているのではないだろうか。もしそうだとすれば、その原因を明らかにすることは、金子光晴理解にも新しい要素を持ち込むことになるのかもしれない。
考えてみると、文学作品を解説する際、私達は長いあいだ二項対立という方法論を利用してきた。それはリアリズムとロマンチシズム、自我と社会、近代と前近代、進歩と反動、等々である。そうして、このような方法が方法として社会的に(?)承認されていた背景には、芸術は社会から隔離された場所で成立するものだから、政治や経済と違って抽象的な手法で分析すべきもの、してよいものとの共同幻想が成立していたように思わせる。私小説作家がいかに現実の苦況に喘ぎ、自然主義小説が実社会の矛盾を鋭く指摘していても、それは浮世離れしている人の特殊の言説、という社会的コードを突き崩すことはできなかった。詩を、若者の表現形式とする俗論もこの中に入るだろう。
しかし、文学全体を、浮世離れしたと見る通念は、明治以後の文明開化期の、卑俗な実利主義全盛の風潮の反動として生れたのではなかったか。それと平行して、文芸批評の方は、移り変る西欧の文芸思潮を紹介することに自らの役割を限定し、その導入が、どう社会との接点を形成するかについてはほとんど無関心であったように思われる。
そのような、批評と作品の受容の社会的コードにとって、金子光晴はたしかに扱いにくい詩人なのだ。
金子光晴の作品を構成しているいくつかの性格のひとつに、両義性があるように見える。それはヨーロッパとの関係においては、親西欧であると同時に反西欧として現れ、この点で西脇順二郎や片山敏彦とは著しく異なっている。彼の西欧認識は、一九二八(昭和三)年―一九三三(昭和八)年の五年にわたる二度目の外遊によって骨格が作られたと考えられる。
リヨンの安宿で死を考えるほど窮迫し、またその前にシンガポール・ジャカルタなどの東南アジアで、旅費調達のためにほぼ二年間を送った際に、植民地の側から西欧近代主義の姿を見たことで、彼は西欧に対する、生活者と被抑圧民族の立場からの現点を獲得したのであった。〝こがね蟲〟の背景になっている、二十五~六歳の時の最初のヨーロッパ体験が、至福の感情に包まれたものであっただけに、後年、『老薔薇園』『鮫』『女たちへのエレジー』などに結晶する二度目のヨーロッパ体験は、金子光晴の世界観の形成に大きな影響があった。すなわち彼は、生活の基底に根を下ろした複眼思考を手に入れたのであり、これは、明治以後「先進国に追いつくこと」を至上の目標としてきた、我が国、特にその中での知識人達と金子光晴との隔絶を決定づける条件を形成したと言えよう。
それでは、こうした金子光晴の体験は、彼の個性、なかでも言語感覚にぶつかって、どのように醗酵し結晶していったのか。
よく知られているように、彼の女達への愛は、洗面器に排泄される尿の音や臓器・口・肛門といった器管への偏愛と一体になっている(昨今、これだけが残された唯一の〝現実〟であるかのように思い込んで、性器や糞尿や、性行為を懸命に書き立てている作品があるが、これらの詩には現実性の質料が稀薄なので、言葉は軽く、表現自体は戲画的となり、金子光晴の作品とは似ても似つかぬものになっている)。昨今の軽薄なサド・マゾ的作品に較べると金子光晴の詩は、自らが這いずり廻った地獄のなかで感得した哀しさが言葉に質量感を与えているのだ。おそらく、このような生活体験の支えがあったからこそ、彼と森三千代との関係は綿々と続いたのであったろう。金子光晴の女性擁護は、いわゆる知的エリートのフェミニズムなどとは縁もゆかりもないリアリティを持っているので、糞尿嗜好も詩のフレーズとして立ってくるのだ。
と同時に、彼は東南アジアとパリという、二つの対極的な場での生活体験で、産業社会の裏面と終末を、あるいは終末に通じる陰の部分を知覚したのであった。中世封建制のなかに地獄を見た画家達に、ボッシュとか、ブリューゲルといった人達がいるが、彼等の、怪奇でありながら極めて現実的な作品を想起させるものが、金子光晴のなかにはある。それは、近代的な耽美主義というよりは(これは『こがね蟲』の時代で終ったのだ)むしろバタイユなどの作品に通じるものであり、それでいて、その底から極めて温かい調律が立ち昇ってくるのだ。その意味では、彼は〝洗練された〟東洋の詩人でもあるのである。
このような作風を持った金子光晴が、次々にヨーロッパの思潮を紹介し、それに近づくのを〝進歩〟と思い込んでいる人々が多かった我が国の文学風土のなかで理解されにくかったのは当然であった。彼は象徴詩派にも超現実派にも人民詩派にも属しているとは見えず、しかもそのどの流派にも近いようにも思われたのである。この点については彼が、人々よりもおよそ半世紀早く産業社会=近代西欧社会の頽廃と衰退を予見し得る体験を持っていたということを、もう一度指摘する必要があるだろう。そして、このような世界に圧迫されて生きる人達は、逞しいのに哀切な存在であった。あるいは、逞しいがゆえに哀切と言った方がいいだろうか。対女性観ひとつを取ってみても、「近代」の概念にあてはめられず、さりとて「前近代」でもないところから、どうしても近代批評の枠組みにはうまく嵌らない彼の風貌が浮び上がってくるのだ。ここに、早く来すぎた青年、としての金子光晴の存在の独自性があると言えよう。
両義性という点で、もうひとつ極立っているのは、彼の日本に対する感性である。金子光晴はおそらくどの国よりも日本を嫌っていた。最初の詩集『こがね蟲』が難解な漢語を駆使した文語調で書かれているのは、フランドルの田園にあって、口語を使う訳にはいかないと感じていたからだ。これは、象徴詩派といって片づけることのできない美意識の問題を含んでいる。金子光晴が、江戸趣味の養父母に可愛がられて育った、という生い立ちも影響していよう。この処女詩集が世に出た二カ月後に東京が大震災に見舞われたことは、その後の彼の足跡を占うもうひとつの外部要因になっているだろう。
この災害は、その後の十五年戦争の結果、日本の主要都市が灰燼に帰したのと同じような、持続的で深刻な影響を当時の人々に与えたようだ。永井荷風が「明治の文化また灰となりぬ」と書きしるしたことは有名だが、この荷風の言葉は、金子光晴の感想と共に、すこし註釈を加える必要がありそうである。
というのは、本質的には、二人とも明治の文化を少しも評価していなかったのだから。むしろ、震災によって、明治維新後の卑俗な文明開花に耐えて辛うじて、生き残っていた江戸の、水準の高い文化も灰に帰していまった、という文脈に置き替えて読む必要があろう。と同時に、ようやく少しはましになるかと思われた、鹿鳴館二代目とでも言うべき文化も、これで芽を摘まれてしまったという歎きが二つながら含まれていると思われるのだ。同じ年に『東京哀惜詩篇』が発表され、『水の流浪』がほぼ完成したのは、当時の金子光晴の震災の受取り方の一端を示している。
白秋や朔太郎が、晩年になって文語の詩を書くようになったことと、金子光晴の歩みが反対になっているのも興味を魅く事柄である。結論的に言えば、彼は〝日本回帰〟をする訳にはいかない場から出発したのであった。彼は長い中断のあと『鮫』『女たちへのエレジー』で作風を確立するのだが、こうした作品の懐妊期間、彼は日本と対峙しつづけて来たのであった。この経過は彼に、間違っても日本への幻想を抱かせない、客観的な観察眼を用意させる。一九二九年、パリに向かう船のなかで書かれ、後に『老薔薇園』におさめられた文章のなかで、彼は、
「十一月十六日、ヨーロッパにはなんの魅力もない。(中略)今、この同船の人達を比較してみても、私ほど故国から完全に切り離されてしまった人間は一人もいないのだ。私には懐郷心がなくなってしまった」
と言っている。そうした金子光晴であったから、第二次大戦後の一九七二(昭和四七)年に増補版が出版された『日本人について』のなかで、
「僕らの住んでいる家は、真空の上で、祖先とも、国土ともつながっているわけではなく、ただ浮遊した存在として、微塵のように揺れているにすぎない。(中略)その徒労を心の中で承知しながら、営々としている僕ら日本人には、共通の哀れさを感じないではいられない」
と、早くも世期末の消費社会の出現を透視しているような発言ができたのである。
従来の常識に従えば、郷土意識を捨てれば、その瞬間から彼の感性はトポスを失って、思考は抽象的にまた感性はリアリティを失うはずであった。そうではなくて、脱日本を装っていれば、アンビヴァレンツな心情に陥って、日本を情緒的に非難し(高村光太郎のように)年老いれば若い頃の主張は忘れたように里がえりをするのであった。しかし、金子光晴は違っていた。ということは、彼は別のトポスを所有していたのである。こうした言い方自体矛盾を孕んでいるわけだが、それをコスモポリタンではないコスモポリタン、おっとせいではないおっとせいとしてのトポスの所有だ、と言ったらいいだろうか。この意味でも金子光晴は、詩人を二項対立という思考枠の中に置いて分類したり、その対立を観念的に止揚する手法によっては解明できない存在であったということができよう。
それでは、金子光晴の言う「さびしさ」とはどういう性格のものなのだろうか。
人の生のつづくかぎり。
耳よ。おぬしは聴くべし。
洗面器のなかの
音のさびしさを。
このフレーズが収められている詩集『女たちへのエレジー』には「さびしい」という言葉が幾度か使われている。
文明のない、さびしい明るさが (ニッパ椰子の唄)
自由。それは、国も、家も、人の仕事も心までも根こそぎうごいてゆく眺望のなかで、旗をみあげて鳴采するような、あだな、さびしい心なのだ。 (旗)
茶子の眼から
青春がうすれるのをみるのは
いちばんさびしい (茶子由来記)
こう見てくると、「さびしい」という言葉はかなり多義的に使われていることが分る。洗面器のなかに広東の女が放尿する「しゃぼりしゃぼり」という音は、生きているということそのものの「さびしさ」であり、明るさの形容としてのさびしさとは〝文明〟のある場所からやって来た自分の過去へ向かっている「さびしさ」。作品『旗』のなかの「さびしさ」とは、必死に国家とか信条などという記号にしがみついている人間の心の貧しさ、哀れさ、それを突き放しきれない自分も観察の対照に含めての「さびしさ」である。そうして、これらのヴァリエーションを貫いて、その底に流れているのは、やはり生身の肉体を持って生きて在ることの「さびしさ」である。
それは、リオンで死を想った時、
「その時も僕は、僕の寝ているベッドの下で地球がうごいているのを感じた。胸がいっぱいになったが、のどまでつまっているその感情は、悲苦ではなくて羽目を外して、世界中びっくりするような大笑いの発作の前のような気持であった」
と書いているのと同質の孤独感であった。
自分と関係なしに社会は在り、自分が死んでも地球上の数十億の人々はわめき、ののしり合い、愛し合って生き続け、地球という星はそれらの人々を乗せて太陽のまわりを自転しつづけているのだと直観した時の「さびしさ」であった。従ってこれは、対人関係から生れた淋しさではなく、存在の淋しさなのであって、故郷を失った淋しさ、というようなものでもなかったのだ。
金子光晴のこうした構えは、伝統との関係にも明瞭に現れてくる。おそらく、自分と他の詩人達との差異を念頭においてのことであろうが、
「彼等に自己の統一的発展の歴史が見られないで、かえって、日本人の年齢的変化の類型(若いうちの知識として学習された様式としての、西欧文化受容、そして見栄が衰え、客気が減退すれば年と共に日本へ回帰する―註筆者)がよみとれるのも、日本人がまだ個人がものを考える自由性にもなれていなかったことの証であろう。」(『金子光晴全集』中央公論社版 第六巻・詩人)
萩原朔太郎や北原白秋の、一見西欧的な感性が、血肉化された西欧文化、思想に基づいたものではなかった点については、同じ箇所で、
「思想の整理は学者的方法しかなかったので、芸術家といえども整理は学者的にやる以外はなく、さもなければ、無整理のまま気まぐれで、試論は、多分に感情的、衝動的になり、大局的には俗論に傾いてゆくことで納まるのだった」
と述べているのを見ても、彼が思想というものを明治以後の〝知識人・学者〟が考えていたのとは異なった位相で理解していたことが分るのである。
こうした金子光晴にとって、伝統とは主体性を放棄して身を寄せかけてゆく絶対として現れるのではなかった。ある場合には戦い打倒すべき対象として、ある場合はそのなかから魂を抜き取るべき質量として存在しているのであった。従って、伝統に反対か賛成して身を寄せ掛けるか、という物差しで彼を評価しようとすれば、金子光晴は、革命的で反伝統主義者で反戦抵抗詩人のはずなのに、何処か得体のしれない「変な爺さん」なのであった。
彼は詩人野口米次郎について「俳諧や、日本短詩の精神の沈黙の力の無限の拡がりを(外国に)紹介した功績のある人は特別で」と書いているが、こうした言及に彼の伝統への意識、定型短詩への的確な理解を読みとることができる。その点で金子光晴は伝統を否定し去ることで「近代」を手に入れようとした「荒地」などとは対極的な場に立っていたのだ。田村隆一が「飯島耕一たちが〝金子光晴〟〝金子光晴〟と騒いだことも(中略)それは荒地に対するリアクションなんだ」「荒地のグループの詩は、金子さん的なドロドロしたものを切り捨てていって成り立った世界だったわけで」と言っているのは(現代詩文庫『金子光晴詩集』解説 思潮社)、この世代に属する人の「近代」「伝統」理解の水準を示している言説であり、飯島耕一たちの金子光晴評価を、荒地に対するリアクションと言うに至っては、ひどく無邪気な自己中心的な見方と言う他はないのである。このことはまた、我が国の「伝統的」な近代派詩人にとって、金子光晴がいかに理解しにくい存在であったかを示す事柄のようにも思われる。
それでは、独立せざるを得なかった金子光晴にとって、社会とは何であり、彼は社会とどんな関係を持っていたのか、持とうとしていたのだろうか。この質問への答えは、彼の生涯の軌跡を見れば明らかなように見えるが、事はそれほど簡単ではない。というのは、金子光晴にとって、「社会」一般はなく、それは女との関係であり、日本との具体的つながりであったのだから。
かれは中野重治が言ったように、全く人情的でなく、また封建的でもなかった。人間関係が彼においては言葉どおり一対一になっていた(一九七八年九月『金子光晴読本』思潮社)から、先に「社会」という観念があって、その中で自分が孤立している、という認識は成立しなかった。社会は個々の関係のずっと背後に横たわっていたのである。従って、覚醒された自我と社会との確執という、我が国の近代文学が得意とした構図は存在せず、この問題からの逃避としての高踏派に彼は縁がなかった。『こがね蟲』以後、五年の放浪を経て、金子光晴は我が国の近代詩の風土を突き抜けた領域に到達していたのだと言うことができよう。この放浪のなかで、彼はもうひとつの発見、理想と呼ばれる観念の形態が、いかに人間の残虐な行為に正当性を与え、人間を歪めていくか、という事実を見ることができたのであった。その点で彼の理想への懐疑は、ニヒリストのそれではなく、醒めている人への慎重さに属するものであった。
十五年戦争のあいだ、金子光晴は「大東亜のために」聖戦を行うという〝理想〟に捕えられた日本の熱狂を冷静に見ていた。彼の〝反戦〟的態度は、国粋主義とは正反対の〝理想〟から(たとえばマルクス主義から)もたらされたものではなかった。大東亜共栄という理想の裏側に米・英・オランダなどと同じ植民地主義がぴったり張りついているのを見抜いていたから、個人として反対だったのである。同じ理由から、金子光晴は民主主義とかヒューマニズムにも懐疑的であった。彼は日本の敗戦後、にわかに高くなった〝抵抗詩人〟という賛辞を嫌ったと言われているけれども、それは嫌ったのではなく、安易に商標を張って騒ぐ世間の低俗性、自分が理解されていないことの苦々しさを感じていただけのことであったろう。彼は戦争中も敗戦後も金子光晴であってそれ以外ではなかった。
しかし、世間のこのような誤解も無理解も決して彼をシニカルにしたり、厭離穢土の心境へと誘ったりはしなかった。彼はつねに女性に暖かい眼を注ぎつつ突き放して眺めており、自分と異なる資質を持つ詩人達に対しても、平静で客観的であった。
なかでも、妻の森三千代や、彼女を取巻く男達に対する態度は極立って〝金子光晴的〟である。なかでも、留守中に彼女と深い関係になったアナーキストの学生の土方定一に腹を立てながらも、〝雪どけ〟(老薔薇園)という散文詩からも窺えるように、金子光晴は彼等二人を大切に扱い、ある部分では認め、森三千代を病院に訪れてヨーロッパ旅行を提案したりするのだ。四十年後に思い出しても冷静ではいられないほどの地獄をアジアやヨーロッパで見る前にも、彼は異常な忍耐強さ、優しさ、そして意地悪さ、をも見せているのである。ということは、彼の生れながらの特質のなかに人並ではないものが蔵われていたと考えてよく、これこそ彼のエロスと言うべきものであったろう。そうしてこのエロスこそ、地獄に直結することによって、死と美の秤の支点の位置に女性の存在を置き、秤が女を支点として揺れる時に聞えてくる声こそ、彼が言う「詩人の肉声」というものであった。
こう考えてくれば、彼が『えなの唄』(人間の悲劇)のなかで、
人間がうまれたといふことは いはば
世界を背負ひこんだことだ
と書いた意味が明らかになってこよう。
この金子光晴のエロスを、社会と対立し、孤立している自我という、いわば西欧近代の知のパラダイムで解明しようとすれば、読者は悪しき両義牲の中に落ちて、いわば合わせ鏡の無限空間に落ち込む結果になるに違いない。この陥弁から脱出しようとして、金子光晴を反日本的詩人、認識と覚醒の詩人というふうに規定してしまえば、彼のエネルギーであった「創造的暗黙知」は消滅し、彼自身がもっとも嫌っていた、平板な知的詩人という分類のなかに収納される小さな存在になってしまうであろう。
彼は従来しばしば言われるように、総てを意識化して捕えた詩人ではなく、むしろ自らの内部の無意識性をして自由に語らしめた詩人であったように思われる。多くの金子光晴論がそれと反対の枠組みで書かれているのは、無意識が語るものは、咨意的、否論理的、情念的で信用できないという、それこそ「近代的知」への概念的理解が根底にあったからではないだろうか。
金子光晴の場合は、無意識が作動すればするほど、日本的情念から離れるという本質を持っていたのである。それはユングの言葉を使えば、「かくのごとくある(sosein)」ことの様態なのであった。この際の主体は、社会と対立する自我と言うよりは、個我(selfst)と考えるべきものであった。個我の最も極立った特色というのは「それがもろもろの対立の結合である」(ユング)のだから。その意味では、金子光晴の近代は矛盾の自己同一体としての近代なのであった。このことを、アジアと西欧の二つながらの土壌の上に立った近代の詩人と言いかえてもよく、エロスとタナトスの美意識を体現した詩人というふうに呼んでもいいだろう。
このように、近代的知を脱構築した後で、金子光晴の諸作品に接するなら、そこには、彼の生きた時代、どんは系譜にも属しようもなかった、自由で自然な、理解しやすい詩人の姿が浮かんでくるのである。