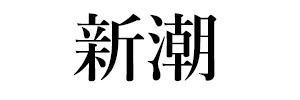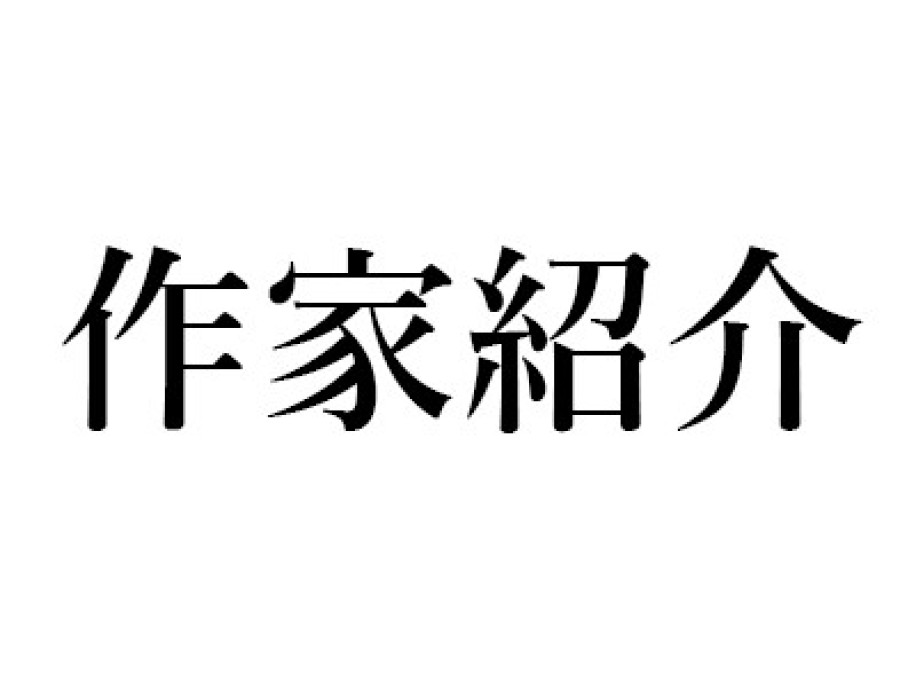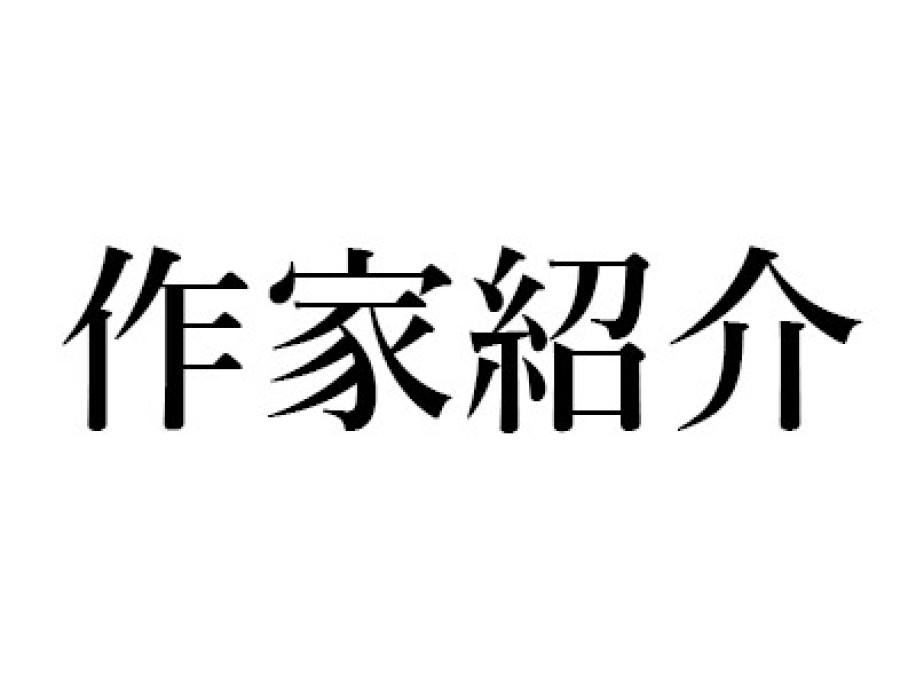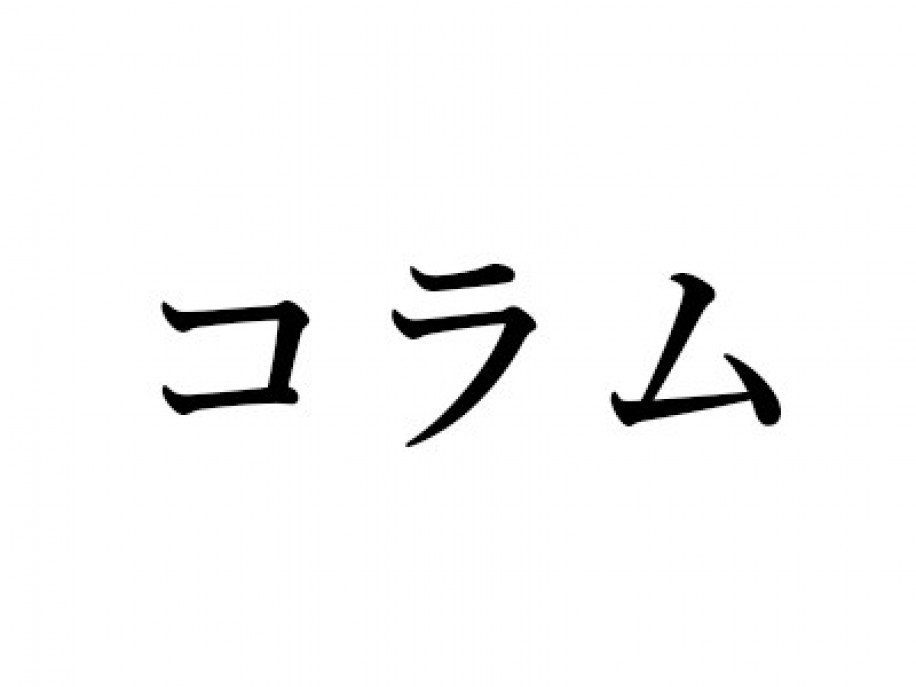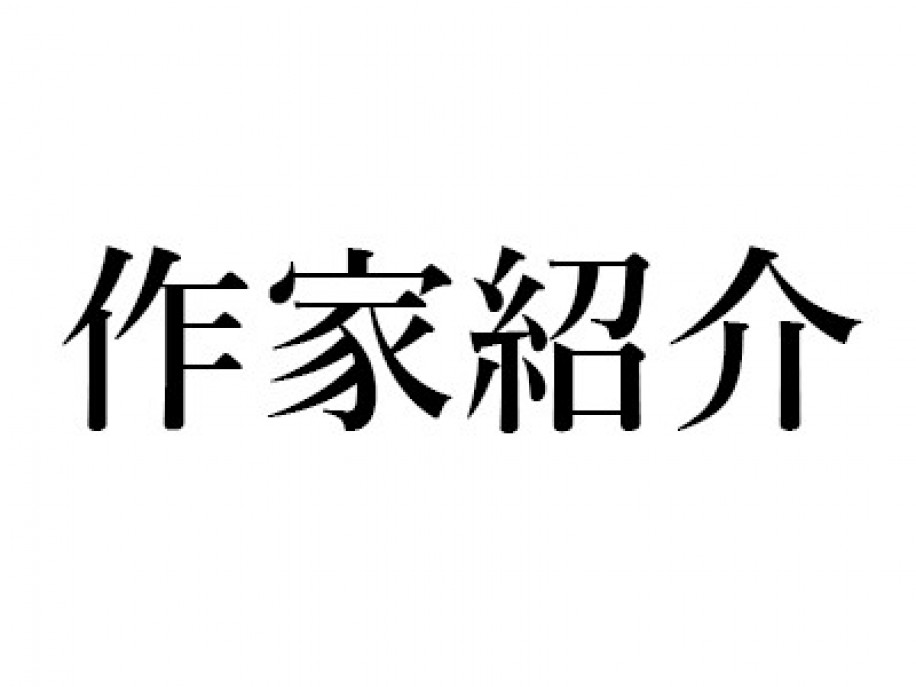作家論/作家紹介
J.L. ボルヘス『伝奇集』(岩波書店)、『不死の人』(白水社)、『ボルヘス詩集』(思潮社)、『論議』(国書刊行会)、『エル・アレフ』(平凡社)他
思考の笑い ボルヘス生誕百年によせて
十九世紀末、一八九九年生れのボルヘスは一時期、自らの生年を一九〇〇年と公言していたという。古典志向という印象が強い作家だが、二十代の初めには新奇さを求める前衛詩の運動に参加していたことを考慮すれば、新時代を感じさせる年号にこだわったとしても必ずしも不思議ではない。そのボルヘスが生れて今年は百周年にあたるため、彼の遺品を展示する巡回展や記念行事がヨーロッパを中心に開催され、八月二十六日の誕生日にブエノスアイレスで催される一連のイベントでクライマックスを迎えるようだ(ALL REVIEWS事務局注:本論考執筆時期は1999年)。
同じく今年生誕百年を迎えるヘミングウエイ、ナボコフ、川端康成にはそれぞれ『老人と海』、『ロリータ』、『雪国』のような人ロに膾炙する長篇があるが、『伝奇集』に含まれる『八岐の園』の序文や中上健次との対談で理由を述べているように、長篇を書かず短篇にこだわる彼には、そうしたポピュラーな作品はない。しかもペダンティックで難解な作家というイメージが一般的読者を遠ざけている。しかし、情緒よりも知性に訴えるその作品は少数ながら熱烈なファンを生み、作家はもとより思想家、心理学者、美術家など多様なジャンルに従事する人々を、国境を越えて強く刺激し続けてきた。此の程日本で生誕百年祭が催されたのも、ボルヘスの国際性の証と言えるだろう。また生前二度(七九年、八四年)にわたって来日しているため、親近感を持たれているということもある。
今年、故ボルヘスの夫人マリア・コダマを招いてなんらかの催しを行うというアイデアは、すでに二年前から存在していた。それを実現させるべく、昨年末に文学者、詩人、批評家、外交官、ジャーナリストらに呼び掛けて、ボルヘス会という組織がまず作られた。マリアと親交のある版画家、星野美智子氏、元アルゼンチン大使の山本學氏、一昨年秋にブエノスアイレスで彼女に会ってきた筆者の三名が世話人となり、勤務先の大学でシンポジウムを開催するということから一応筆者が代表となったものの、実際、事務局を切り盛りしてくれたのは星野さんである。最大の功績は、年末にすべり込みで日本国際交流基金に申請し、マリア招聘を実現させたことだ。三月末にオーケーが出たのを機に初めて会合を開き、具体的な話合いをした。その結果、メインとなる立教大学でのシンポジウム「迷宮を讃えて」を皮切りに、ボルヘスをテーマにした星野さんのリトグラフ展が開かれるストライプハウス美術館で連続講演会を催すことなどが決まった。さらに高橋睦郎氏の発案で、詩人による頌詩朗読、大野慶人氏の舞踏がプログラムに彩を添えることになり、準備期間が短いことや人手が足りないためにてんてこ舞いしながらも、とにかく準備が整った。あとはマリアの到着を待つだけとなったが、彼女と連絡が取れず、パリから来ることが分かったのは六月半ば。正直な所、結構冷や汗を掻いた。しかも成田で再会した彼女から、ルーブル美術館で転んで膝にひどく怪我をしたと聞かされ、もう一度冷や汗を掻いた。近くで見ると、顎にはそのとき作った青痣が残っていた。
七月一日、アルゼンチン人歌手オマール・ベルッティによるミニコンサートのときは晴れていたのに、ボルヘス原作の映画「デス・アンド・コンパス」の上映中突然激しい雨が降り出し、泡を食うが、マリアの基調講演の前に上がり、ほっと一安心。聴衆の数が予想をはるかに上回ることが判明し、急遽会場を大教室に変更するといった具合でここでもてんてこ舞いしたものの、とにかく三百人を前にマリアの基調講演が、山本空子さんの通訳付で始まった。
パソコンを使わないマリアがパリからファックスで送ってきた原稿はなんと手書き、判読不能の個所もあったが、これは山本さんが本人に尋ねたりして必死に解読した。講演のタイトルは「ボルヘスを語る」(「ユリイカ」九月号に全文掲載)。この中でマリアはまずボルヘスとは少女時代に出会い、その後師弟関係から始まった結びつきが次第に複雑になっていったことや、協力者としてごく間近から見たボルヘスの実像について語った。続いて彼の幼児期にルーツを持ついくつかのテーマに関して分析を試みたが、そのうちの分身、同一性のテーマをオスカー・ワイルドの「ドリアン・グレイの肖像」と結びつける件は、離日後訪れることになるサンタンデール(スペイン)のメネンデス・ペラヨ大学でのセミナーの前触れだったようだ。そして最後にボルヘスとブエノスアイレスのテーマを取り上げ、ボルヘスはヨーロッパ滞在によって失われた都市を作品の中で回復しようと努めたのであり、その結果、一般の人々が抱くブエノスアイレスとは異なるイメージが生れたのだと解説した。
ソフトでハスキーなマリアの声は聞く者の心を静かに揺さぶる。二十年前に初来日したときと同様少女のころの面影を残しながらも、ボルヘス夫人としての自信とボルヘス財団理事長としての責任感のためだろう、彼女はひと回りもふた回りも大きく見えた。
続いて、詩人による頌詩朗読に移り、最初に城戸朱理氏が「キリマンジャロの雪」をモチーフとする作品を、高橋睦郎氏がボルヘスの伝記に自伝を重ねたと思われるパロディックな架空の伝記を読み上げた。三人目は欠席も予想された吉増剛造氏で、「ブエノスアイレスの神話的創設」などボルヘスの詩からの引用を交えながら、朗読を通じて言葉が自立し分岐していく独特のパフォーマンスを披露した。舞台の右袖に置かれたボルヘスの肖像写真を詩人たちが意識していたのが印象的だった。
舞踏家の大野慶人氏は、「鏡と父とは、その宇宙を繁殖させ、拡散させるがゆえに忌まわしいものである」という、ボルヘスの短篇「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」に出てくる有名な一節のもじりをタイトルとする作品を踊った。最初は鏡を持って、次は父の抑圧を象徴するかのような針金製の怪獣めいた物体を背負っての踊りは、ボルヘスが作品には描くことのない深層心理を表象しているかに見え、意外性から生じる衝撃が観客を圧倒した。
詩と舞踏の余韻が漂う中、プログラムは進み、最後のパネルディスカッションへと移った。司会は筆者。冒頭は短篇集『エル・アレフ』の日本語版『不死の人』の訳者である土岐恒二氏による「日本でのボルヘス受容」と題する報告で、氏はボルヘスの先駆的紹介者である故篠田一士氏の業績と媒体となった同人誌「秩序」の役割を評価する発言を行った。「秩序」に載った篠田訳の短篇「不死の人」はその後評論集『邯鄲にて』に再録されているが、それは英文学者による英語版からの重訳の口火を切るものでもあった。
二番目は作家の室井光広氏による「ボルヘスと現代文学」で、ボルヘス論「零の力」で知られる氏は、二度目の発言でボルヘスという作家が世界的に見た場合周縁から現れていることの重要性を強調した。それは氏の関心が北欧やシェイマス・ヒーニのような詩人にあることとも関係しているのだろう。かつて図書館員だったという氏の経歴も、ボルヘスに親近感を抱く一因となっているにちがいない。
三番目の宇野邦一氏は「ボルヘス次元」と題する報告を行った。氏はエッセイ集『異端審問』所収の「城壁と書物」というテクストで語られる〈焚書〉にボルヘスが感動していることに注目し、そこから、彼にとって書物が独自の次元を構成しているとする。あらゆる書物から成る唯一の書物すなわち絶対書物の観念をボルヘスは提示するが、彼はそれを書物を支配する強力な〈主体〉として読むのではなく、その書物の連鎖と反復と増殖の中にあってそれを思考するのである。だが氏は、ボルヘスは、書物がまったく固有の一つの次元を構成することを決して忘れていないと言い、この次元がボルヘス固有の哲学、詩学と不可分であることを指摘する。これが氏の言うボルヘス次元と思われるが、しかしこれをどう定義すべきか分からないため、氏はその特徴を印象という形で素描する。氏によれば第一にボルヘスは道徳にも真理にも無関心な作家であり、第二に、ある一貫したユーモアをもつ作家であるとし、さらに第三にボルヘスの物語世界はライプニッツ的可能世界と響き合うという。
四番目の報告「ボルヘスの地図」は谷川渥氏によるもので、「学問の厳密さについて」という、現在は『全集』中の『創造者』に収められているが、初出は『悪党列伝(汚辱の世界史)』、その後ビオイ=カサレスとの共作『ボルヘス怪奇譚集』にも収録された小品を素材にしている。このテクストにはデッチ上げられた出所が記されているが、氏は一六五八年というその刊行年に着目し、そこに込められたボルヘスの意図を探ろうとする。時期的にみるとバロック全盛期にあたることからその時期を代表する思想家ホッブスと主著『リヴァイアサン』を探り当てた氏は、ボルヘスは国家イコール王の人体という当時の特徴的思想モードを暗示しようとしたと推論する。さらに、そのように仮定すれば帝国に重なり合う地図がぼろぼろになる様は王=国家の皮膚の荒廃を暗示することになるという。
このように四氏による刺激的な報告が続いた後、それを受けて二度目の発言があったが、時間の都合で議論を大きく展開するには至らなかったのが惜しまれる。最後に土岐氏が、現実世界は神が文字によって創造した物質であり、その原型は神の脳裏にあるとするヘブライズムの考え方をボルヘスが受け入れていること、そして日常的現実の一見ばらばらに見える個々の事物に新たな価値を付与し、そこに連関を見出すボルヘスの態度の根底に、事物を究極的に肯定する暖かいヒューマニズムが存在することを指摘して、パネルディスカッションならびにシンポジウムは終了した。
翌二日からは会場をストライプハウス美術館に移し、星野美智子氏のボルヘス生誕百周年記念リトグラフ展が始まる一方、土曜日毎に講演会が計四回、それとは別に城戸、高橋、吉増の三氏に四方田犬彦氏、多田智満子氏を加えた五氏による詩の朗読と大野氏の舞踏の夕が開かれた。講演会の最初はマリア・コダマに初来日のとき付添った中村健二氏や当時日本国際交流基金にいた井上隆邦氏、晩年のボルヘスを知るアルゼンチン総領事ホルヘ・ベイルス氏を交じえてのトークという形式で行われ、筆者が司会を務めた。冒頭、中村氏にシンポジウムの総括をしていただく一方、井上氏からはマリアに父親ヨサブロウ氏のルーツ探しを依頼され、わずかな情報を頼りに調べた結果、長野県のある村の出身であるらしいことを突き止めたというエピソードが披露された。マリアにはボルヘスのバロック的文体の直截的文体への変化の原因やジュネーヴの墓石に刻まれた碑文の意味などシンポジウムの基調講演では触れられなかったことを質疑応答形式で話してもらった。そしてそろそろ閉館というころ、大野一雄氏が姿を見せ、マリアのために踊ってみせるというハプニングがあった。
第二回の講演は筆者が担当し、「ボルヘスとラテンアメリカ文学」という題で話をした。彼と同年生れで今年生誕百年を迎えるグアテマラのアストゥリアスにせよ、ペルーのバリェホ、チリのウイドブロ、ネルーダ、キューバのカルペンティエル、あるいはずっと年下のパスらと比べると、ヨーロッパで文学的ラディカリズムに触れるところは共通しているが、ボルヘスの場合、学生時代に政治的ラディカリズムに触れた経験がなく、またスペイン内戦にコミットした経験もない点でむしろ特異な存在と言える。「自伝風エッセー」に述べられているように、青年時代にロシア革命に鼓舞された詩を書いたり、土着主義もしくはラテンアメリカ主義を標榜するエッセイを書いたりしてはいるが、彼は後にそれらを廃棄してしまう。オクタビオ・パスもスペイン内戦に触発されて書いた政治詩を廃棄しているが、美学的見地からそれを行ったのであり、政治への関心を失うことはなかった。
六〇年代の〈ブーム〉の世代と比較するとその違いはより大きくなる。ラテンアメリカ主義を高まらせたキューバ革命の存在が原因であり、その評価をめぐって七〇年代に作家・知識人の意見は二分されてしまうが、彼らの政治的関心そのものは保たれている。ことにボルヘスに近いところにいたコルタサルが晩年に至って政治的に先鋭化していったことやドノソが自国の社会的現実をやはり晩年に取り上げていることは、この世代と政治の結びつきの強さを物語っていると言えよう。こうした問題を含め、ボルヘスという作家のラテンアメリカでの位置づけを試みるつもりだったが、準備不足もあって、断片的報告に留まらざるをえなかった。これと関連して、ラテンアメリカ作家にとってのボルヘスというテーマも少ししか紹介できなかったので、後でその問題を取り上げることにする。
一方、ラテンアメリカに対し、アメリカ合衆国とボルヘスというテーマも十分魅力的である。ことに南北アメリカを結びつけるという発想の重要性を篠田一士氏が強調していたのを覚えていたこともあって、当日の講演を受ける形で千石英世氏にアメリカ文学とボルヘスというテーマで話をしてもらった。氏がボルヘスのホイットマン、エマーソン観やジョン・バースのボルヘス観、ポストモダン小説とボルヘスといった話題を提供してくれたので、講演の内容が立体的になったと思う。
第三回の講演は、ビデオ・アーティストの山口勝弘氏と美術評論家の日向あき子氏の対談という形で行われた。司会はNTT・ICCの副館長で昨年「バベルの図書館」展を企画した中村敬治氏が務めた。インスタレーションを中心とする「バベルの図書館」展は見逃していただけに、ビデオによる記録を見ることができたのは幸運だった。同時に、ボルヘスおよびビオイ=カサレスの作品が文学以外のジャンルにとっても刺激的であることが具体的に分かり、大いに啓発された。
第四回すなわち最終回の講演者は中村健二氏で、テーマは「ボルヘスと英文学」。氏は、ボルヘス文学の中核を成すのはバークリー、キャロル、ド・クインシーの三人であるという「大胆な」仮説を立て、ボルヘスの作品に窺える英文学的要素を具体的に指摘してみせた。
ナボコフがロシアとアメリカに跨っているように、ボルヘスもアルゼンチンとイギリスに跨っていることは常々指摘されてきたが、確かに彼の作品はイギリスの哲学や論理学から大きな霊感を得ている。たとえば初期のエッセイ集『論議』所収の「アキレスと亀の果てしなき競走」では、キャロルが好んだパラドックスをジェイムズやラッセルを引き合いに出しながら自分流に展開してみせている。ここにはラテンアメリカの要素はまったくない。
ここでひとつ気づいたのは、ボルヘスは現実の見方をキャロルからも学んでいるわけだが、だとすれば、彼が現実離れしていると評される原因のひとつはそこにあるかもしれないということだ。なぜなら、ジャン・ガッテニョによれば、「アリスの冒険からエレアのゼノンのパラドックスにいたるまで、彼(キャロル)はひたすら現実から乖離していった」(鈴木晶訳)からである。
ラテンアメリカでボルヘスについて語られるとき決まって問題になるのが、彼の描く現実、そして彼と現実との関わりである。一例を挙げてみよう。『百年の孤独』が出た一九六七年、バルガス=リョサとガルシア=マルケスが対談を行った。そのとき、インタビュアー役のリョサが、ラテンアメリカの作家の概念規定をするために、「アルゼンチン的とは思えないもの」をテーマとする逸話を書くボルヘスを敢えて取り上げ、挑発する。するとマルケスは、ヨーロッパ的な都市としてのブエノスアイレスを描くコルタサルはラテンアメリカの人間だが、ボルヘスにはラテンアメリカ的なものは見出せないと言う。そして観念的現実について書いているボルヘスの文学は逃避の文学であり、あらゆる偉大な文学は、何らかの具体的現実に基づいていなければならないとするのだ。
作家たちの多くが戦闘的ラテンアメリカ主義者となった時期である上に口頭ということもあるのだろう、このマルケスの発言はいささか思慮を欠いている気がする。しかし、それから二十一年後に発表されたバルガス=リョサのエッセイはさすがに落着いた考察となっている。「ボルヘスのフィクション」と題するその文で彼は、文学が世界の変革に寄与しうると思っていた学生時代、彼にとってボルヘスはサルトルが自分に憎悪することを教えてくれたものすべて、すなわち世界と現実から知的な博識の世界へと逃避した芸術家、政治や歴史はもとより現実すらも軽蔑し、不謹慎にも自らの懐疑主義や文学以外のすべてをにこやかな顔で蔑む作家、等々を象徴していたという。サルトリアンではなかったものの、マルケスも同様の印象を受けていたことが想像できる。だが、興味深いのは、二人ともその一方で、ボルヘスの作品に抗しがたい魅力を感じるという、アンビバレントな感情を抱いていることだ。ボルヘスが亡くなってから書かれたこの文でリョサはこの作家を努めて正当に評価しようとしている。そして周縁にいて西洋を相対化する視点を持ちえたこと、感情や具象に傾き過剰になりがちなスペイン語を刷新し、ロジックに耐えうる言語に作り換えたことなどを美点として挙げる。そして、「およそ思索ほど複雑な楽しみはないが、わたしたちはその楽しみにふけっていたのだ」(上岐恒二訳)という「不死の人」の一節を引用し、こうした文章はボルヘス自身を表現しており、この短篇がボルヘスのフィクションの世界のアレゴリーであることを指摘する。彼の短篇はどれも宝石のようであると言い、「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」、「円環の廃墟」、「神学者たち」、「エル・アレフ」をこのジャンルの傑作とみなすリョサだが、それでもボルヘスが長篇を軽視していることに対しては、『ドン・キホーテ』や『白鯨』などはいくつかの着想に収斂させることはできないとして反論している。このあたりはボルヘスと中上健次のジャンルをめぐるやりとりを思い出させる。いずれにせよ、混沌とした現実や生を知のレベルに収斂させ、あるいは廃棄してしまうというボルヘスの特徴を指摘しつつ、リョサはそれを批判しているのだ。なぜならその混沌とした現実や生こそが長篇作家の糧だからである。さらにモラリストである彼は、ボルヘスの作品に時折現れる文化的エスノセントリズムが看過できない。そしてボルヘスにとって文明とは西洋、都市、さらにほとんどの場合白人のそれを意味するところに彼の限界を見るのである。リョサの文に悪意が感じられないだけに、そこに述べられている意見はラテンアメリカの多数の意見でもあるのだろう。
一方、ボルヘスを的確に捉え、その特徴を見事に分析してみせたエッセイとして忘れられないのが、オクタビオ・パスが八十六年に書いた追悼文「射手であり、矢であり、みずから的であり」である。この文の中でパスは、ボルヘスを真のイスパノアメリカの作家とみなしているばかりでなく、その作品は「透明な完璧さと清澄な建築によって、ラテンアメリカ大陸の分散と暴力と無秩序に対する鋭い批判となっている」とさえ述べる。彼は、ボルヘスの普遍主義が「一ラテンアメリカ人の視点に他なら」ないこと、アルゼンチン人でなければボルヘスの詩や短篇の多くは書けなかったであろうことを指摘する。これは結果的に前述のガルシア=マルケスのボルヘス観への反論ともなっている。
パスによれば、「文学には二つのテーマしかない。ひとつは、人間たち、敵や同胞とともにいる人間であり、もうひとつは、宇宙そして自分自身と向き合う孤独な人間である。最初のテーマは叙事詩人、劇作家、小説家のもの、二番目のテーマは抒情詩人、形而上詩人のもの」である。もちろんボルヘスは後者に属する。一方、マルケスやリョサが前者に属することは言うまでもない。
ところで、バルガス=リョサもパスもモラリストという点では一致している。リョサの場合、その側面が強く出るためだろう、ボルヘスのウィットやユーモアを美点として挙げてはいない。一方、パスの方は、ボルヘスのエッセイの「ユーモアと節度とウィット、そして不意に発射される異常さ」を高く評価している。それらは思考から生れ、思考へと伝えられ、笑いを引き起こす。こうした笑いは第三世界的現実の中では生れにくいかもしれない。それはアメリカ的な笑いでもない。神々のそれにも似てモラルの埒外にあるこの思考=至高の笑いが受け入れられるか否かは、社会の成熟度、知性のレベル、ヨーロッパ文化の受容度など、様々な条件によるのだろう。ボルヘスのウィット、ユーモア、そして「不意に発射される異常さ」に反応して笑ったのはフーコーだった。ボルヘスを深く理解していたパスは、それらに出遭ったとき、果して笑っただろうか。
ALL REVIEWSをフォローする