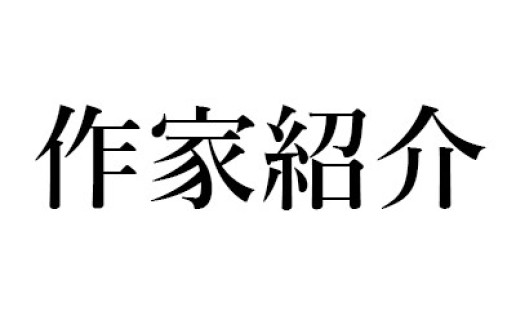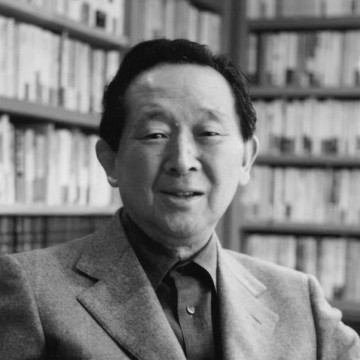
1927年3月東京に生まれる。東京大学経済学部卒。衆議院議長を務めた父・堤康次郎の秘書を経て、1954年西武百貨店入社。1963年、自ら設立した西友ストアー[現・西友]の社長に、1966年には西武百貨店の社長に就任。その後、クレディセゾン、良品計画、ファミリーマートなど多彩な企業群のセゾングループの代表となる。1991年、同グループ代表を辞し、経営の第一線から引退。
1983年にアメリカのロックフェラー系列の財団であるアジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)に対し、その日本事務所と「日米芸術交流プログラム」の設立に向けて、西武流通グループ(当時)から200万米ドルを寄附(これは当時、日本の企業体から、アメリカの非営利団体が運営する芸術プログラムに対する最大のものとなった)。以来、ACCの理事を務め、2012年からは終身理事に就任。1986年に財団法人高輪美術館[現・一般財団法人セゾン現代美術館]を、また1987年に財団法人[現・公益財団法人]セゾン文化財団を私財で創設し、2013年11月に逝去するまで両財団の理事長として活動。また、ノグチ美術館の評議員、ニューヨークのジャパン・ソサエティーの日本アドバイザリー委員、およびニューヨーク近代美術館の国際評議員を務めた。
1970年にフランス共和国よりレジオン・ドヌール(シュヴァリエ章)を、1987年に同国レジオン・ドヌール(オフィシエ章)を、また1989年にオーストリア共和国功労勲章大金章を受章。1993年にモスクワ大学名誉博士号授与。1998年に論文「消費社会批判」(1996年に出版)により中央大学経済学博士号を取得。2012年に上述のアジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)より「ブランシェット・H・ロックフェラー賞」を受賞。
また、辻井喬のペンネームで詩人および作家としても活動。1955年に詩集『不確かな朝』を刊行、以来数多くの作品を発表。詩集に『異邦人』(室生犀星詩人賞)、『群青、わが黙示』(高見順賞)、『鷲がいて』(現代詩花椿賞、読売文学賞詩歌俳句賞)、『自伝詩のためのエスキース』(現代詩人賞)、『死について』など、小説に『いつもと同じ春』(平林たい子文学賞)、『虹の岬』(谷崎潤一郎賞)、『風の生涯』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『父の肖像』(野間文芸賞)、評伝に『司馬遼太郎覚書』『私の松本清張論 タブーに挑んだ国民作家』、評論・エッセイ集に『新祖国論』、回顧録『叙情と闘争』などがある。英語をはじめ、フランス語、ロシア語、中国語、韓国語、アラビア語への翻訳作品もある。2006年に第62回恩賜賞・日本芸術院賞を受賞。2007年日本芸術院会員に選ばれる。2012年、皇居宮殿で行われる「歌会始の儀」にて召人(めしうど)を務め、同年文化功労者として顕彰される。日本ペンクラブ理事、日本文藝家協会副理事長、日本中国文化交流協会会長などを歴任。
- 著作:
 『曼陀羅華―句集』(朝日新聞出版)
『曼陀羅華―句集』(朝日新聞出版) 辻井 喬
辻井 喬森澄雄には夫人とともに旅をした時の句が多い。こんどの『曼陀羅華』を読むとそれがよく分かる。氏が脳梗塞で倒れて以後、つまり昭和五十七年九月以…
書評 『篠弘全歌集』(砂子屋書房)
『篠弘全歌集』(砂子屋書房) 辻井 喬
辻井 喬いつの頃からか、短歌は身につまされる詩型だと僕は思っている。それは長い歴史のなかで培われてきた韻律が、独特な効果をもたらすからか、僕の母が…
書評 『妬心』(KADOKAWA)
『妬心』(KADOKAWA) 辻井 喬
辻井 喬この句集を読んで、妬心とはどのような心の動きなのだろうと考えた。仲間うちの競争心に源を持つ妬心と、愛する者の心を完全には所有していないと思…
書評 『わが父波郷』(白水社)
『わが父波郷』(白水社) 辻井 喬
辻井 喬私は石田波郷に会ったことがない。作品を通じてその凝視の深さ、重さ、鋭さを享受しているだけである。しかし彼の病床俳句と言われている作品群は決…
書評 『檻: 句集』(朝日新聞出版)
『檻: 句集』(朝日新聞出版) 辻井 喬
辻井 喬鋭利な刃物で永遠を一瞬のうちに切ってみせるような詩、その時開かれる鮮やかな絵画的世界……というのが角川春樹の俳句についての長いあいだの私の印…
書評 『塚本邦雄の青春』(ウェッジ)
『塚本邦雄の青春』(ウェッジ) 辻井 喬
辻井 喬塚本邦雄 理解への手懸り「棺を覆うて後定まる」、という言葉があるが、塚本邦雄が他界した二〇〇五年六月九日から四年近い年月が経って、彼の評価…
解説