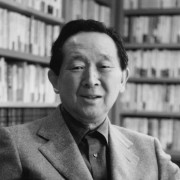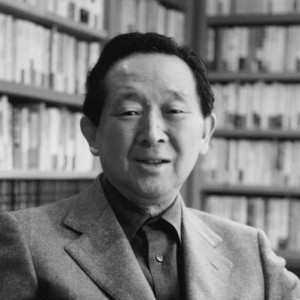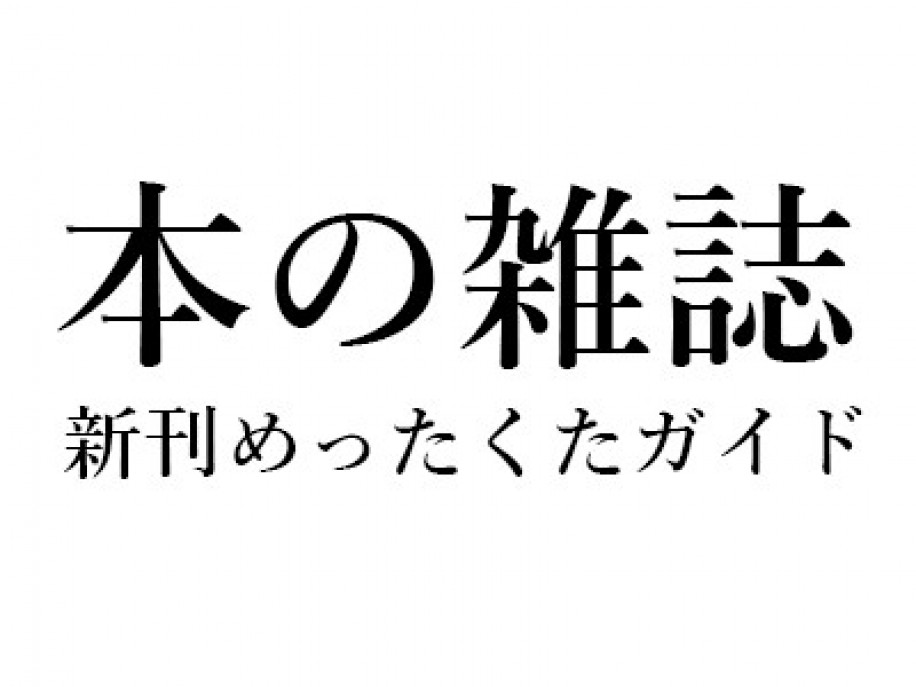書評
『檻: 句集』(朝日新聞出版)
鋭利な刃物で永遠を一瞬のうちに切ってみせるような詩、その時開かれる鮮やかな絵画的世界……というのが角川春樹の俳句についての長いあいだの私の印象だった。
詩でも小説でも、処女作や初期の仕事のなかに、その後展開されてくるであろう総(すべ)ての要素が含まれている人と、年月が経つにつれて次第に全体像が立ち現れる人と、芸術家に二つの型があるとすれば、角川春樹は明らかに前者のように私は思ってきた。
このことは、
というような初期の代表作を見れば頷けるのではないか。そこにあるのは心象に映じた光景の鮮烈さであり、それを可能にしているのは作者の現実に向かう志の直截性とでも呼ぶべきものに違いなかった。このことは、冬のかもめを捕らえて「骨になるまでの飛翔や」と表現するところにも見えているし、少年期を「晩夏の海に銃を撃つ」と言い切る自負と淋しさの交響にも現れていると言うことができる。彼の句には、いささかの感傷も詠歎もないことが哀切なのであった。
こうした作風は、彼の生きてゆく姿勢と表裏一体となっていた。そこに彼が、趣味人としての俳句作者や、職人芸の人々とは隔絶した世界を築くことが出来た理由があった。言いかえれば、信長に向かい合う人はいても、信長の首を斬り落とすことが出来る俳人は今日においては角川春樹ただ一人なのである。彼の作品世界には、いささかも世俗的な栄誉を気にしたり、宗匠になって世俗の権威者として君臨しようとする汚れはない。その意味では、角川春樹はまぎれもなく純粋であり、その純粋さは必ず過激さとなって噴出せずにはいない性格のもののように思われる。
そのような彼の、最近作『檻』は、『カエサルの地』『信長の首』『流され王』『補陀洛の径』『猿田彦』『一つ目小僧』『夢殿』そして『花咲爺』『関東平野』と続いて来た作品世界が、ひとつの大きな転換点に立ったことを示していて、その意味でも注目すべき句集となっている。
この句集について吉本隆明は「イメージと現実とを自由に交換できる方法を手に入れた」と指摘しているが、そのような方法を彼に得させたのは、『檻』という題名にも現れている一年におよぶ獄中体験であるだろう。
この句集の調べは、一見、従来の作品群に較べれば平易であり自然である。
のような句は、ごく構えずに歌われているように見える。吉本は「何かが心の中でこわれたに違いない」と言い、才気、美意識に替わって切実さが、という意味のことを述べているが、おそらく角川春樹は獄中で「我は狂気か」と想う時間を持ったことで、持ち前の過激性が肉体を獲得したのであろう。作家石原慎太郎が「肉体の天使」という作品(「新潮」一月号)で、生命がけのレースのなかで、ふと彼にだけ聞こえる音楽を聞くカーレーサーのことを書いているが、この句集『檻』のなかで彼はいつになく「秋の風眼(まなこ)を閉ぢて聞きにけり」のような句を詠んで、遠い宇宙を吹く風を、永遠を流れる時間の音を聞いているのである。それだからこそ、同じゴッホという狂気の画家を題材にしても、
といった対照を見せるのである。前の句は十五年前(昭和五十六年)の作品である。この二つの句はいずれも異なっていて連続している角川春樹の作品の世界なのである。
詩でも小説でも、処女作や初期の仕事のなかに、その後展開されてくるであろう総(すべ)ての要素が含まれている人と、年月が経つにつれて次第に全体像が立ち現れる人と、芸術家に二つの型があるとすれば、角川春樹は明らかに前者のように私は思ってきた。
このことは、
火はわが胸中にあり寒椿
向日葵や信長の首斬り落す
というような初期の代表作を見れば頷けるのではないか。そこにあるのは心象に映じた光景の鮮烈さであり、それを可能にしているのは作者の現実に向かう志の直截性とでも呼ぶべきものに違いなかった。このことは、冬のかもめを捕らえて「骨になるまでの飛翔や」と表現するところにも見えているし、少年期を「晩夏の海に銃を撃つ」と言い切る自負と淋しさの交響にも現れていると言うことができる。彼の句には、いささかの感傷も詠歎もないことが哀切なのであった。
こうした作風は、彼の生きてゆく姿勢と表裏一体となっていた。そこに彼が、趣味人としての俳句作者や、職人芸の人々とは隔絶した世界を築くことが出来た理由があった。言いかえれば、信長に向かい合う人はいても、信長の首を斬り落とすことが出来る俳人は今日においては角川春樹ただ一人なのである。彼の作品世界には、いささかも世俗的な栄誉を気にしたり、宗匠になって世俗の権威者として君臨しようとする汚れはない。その意味では、角川春樹はまぎれもなく純粋であり、その純粋さは必ず過激さとなって噴出せずにはいない性格のもののように思われる。
そのような彼の、最近作『檻』は、『カエサルの地』『信長の首』『流され王』『補陀洛の径』『猿田彦』『一つ目小僧』『夢殿』そして『花咲爺』『関東平野』と続いて来た作品世界が、ひとつの大きな転換点に立ったことを示していて、その意味でも注目すべき句集となっている。
この句集について吉本隆明は「イメージと現実とを自由に交換できる方法を手に入れた」と指摘しているが、そのような方法を彼に得させたのは、『檻』という題名にも現れている一年におよぶ獄中体験であるだろう。
この句集の調べは、一見、従来の作品群に較べれば平易であり自然である。
ひとつ世を終へたる想(おも)ひ鉦(かね)叩(たたき)
冬雨(ふゆさめ)や囚徒肩寄す鴨のごと
のような句は、ごく構えずに歌われているように見える。吉本は「何かが心の中でこわれたに違いない」と言い、才気、美意識に替わって切実さが、という意味のことを述べているが、おそらく角川春樹は獄中で「我は狂気か」と想う時間を持ったことで、持ち前の過激性が肉体を獲得したのであろう。作家石原慎太郎が「肉体の天使」という作品(「新潮」一月号)で、生命がけのレースのなかで、ふと彼にだけ聞こえる音楽を聞くカーレーサーのことを書いているが、この句集『檻』のなかで彼はいつになく「秋の風眼(まなこ)を閉ぢて聞きにけり」のような句を詠んで、遠い宇宙を吹く風を、永遠を流れる時間の音を聞いているのである。それだからこそ、同じゴッホという狂気の画家を題材にしても、
黒き蝶ゴッホの耳を殺(そ)ぎに来る
読み返すゴッホの手紙麦の秋
といった対照を見せるのである。前の句は十五年前(昭和五十六年)の作品である。この二つの句はいずれも異なっていて連続している角川春樹の作品の世界なのである。
ALL REVIEWSをフォローする