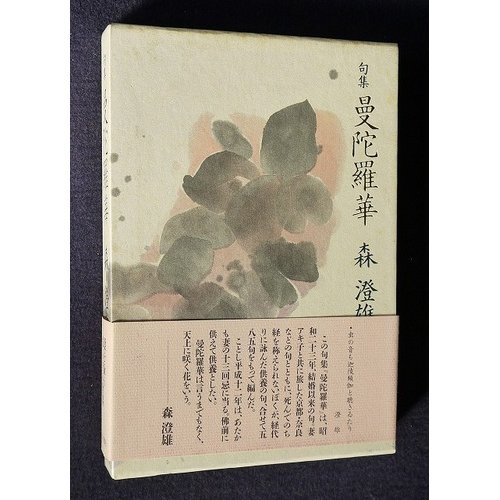書評
『ライク・ア・ローリングストーン: 俳句少年漂流記』(岩波書店)
懐かしくも惨憺たる・・・
俳人今井聖さんの、これは自伝小説であるが、ほとんど現実そのままなのであろうと想像される。私自身は、今井さんと同世代で、その青春時代を共有してきたところだから、一読、なつかしくも「痛い」ような思いを味わった。
青春は、いつも悔恨に満ちたものだが、それにしても、この痛切なまでにやぶれかぶれの青春はどうであろう。鳥取県家畜試験場の獣医で、息子に期待するところ大きく、抑圧的であった父親への反発から、ただ「俳句」という武器だけを手にして故郷と決別していく一人の少年の独立の物語が、ここに物語られている。『ライク・ア・ローリングストーン』は「転石苔むさず」という英語の諺だが、それよりも、フォークロックの旗手ボブ・ディランの歌の題名として心に刻まれている。
明治学院大学に入った「僕」は、偶然のようにして、いわゆる全共闘運動に巻き込まれていくのだが、その壮絶な運動のなかにも、結局どこか没入しきれない「僕」がいる。
それもそのはず、心の奥に「俳句」という文学の魔物を飼っているのだから、殺風景な政治運動とはどこかで決別しなくてはならないのが彼の運命であったに違いない。
そして師加藤楸邨との出会い。それもまた、微妙な懸隔を覚えて、彼は独立の俳人となっていくのだが・・・。随所に印象的な俳句を織り込みながら、本書は、世を早くした母の最期を以て締めくくられる。時に饒舌に、時に理屈っぽく、時に抱腹絶倒的に青春を辿ってきたこの本は、その巻軸に至ってしみじみとした哀感を湛えつつ終る。
抱かれし後流燈となりゆけり
享年五十五。母が煙になった。
初出メディア

スミセイベストブック 2010年9月号
ALL REVIEWSをフォローする