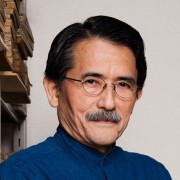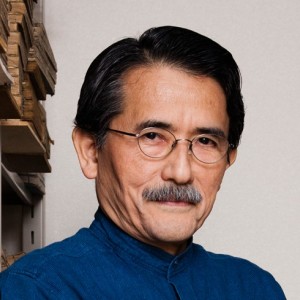書評
『増補 俳諧歳時記栞草 上』(岩波書店)
灯火親しむの候
今年は順調に秋がやってきた、という感じがする。もともと、旧暦の七夕が過ぎ、お盆が過ぎ、御先祖の御霊も常世(とこよ)のほうへお帰りになってしまうと、急に夏も老い、朝夕に秋気が忍び寄ってくる、それがわが日の本の季節の移ろいであった。じつは私の密かな道楽は、俳句を詠むことである。
そこで、歳時記はわが座右にいくつも備えて、かれこれの歳時記を読み比べたりするのは、また一つの楽しみでもある。
そんななかで面白いのは、曲亭馬琴の『増補俳諧歳時記栞草』だ。博学で考証癖のあった馬琴が、季語に簡単な注釈を付した本である。
これを繙くと、たとえば、秋の部に「色なき風」という季語がでている。日頃見ない言葉だし、現代の歳時記には出ていないようだが、馬琴の説明にはこうある。
色なき風 九月の風なり。〔新古今〕ものおもへばいろなき風もなかりけり身にしむ秋のこゝろならひに 久我内大臣
注釈はただこれだけで、句例などは出ていない。ちなみに角川書店の『合本俳句歳時記 第三版』には、この季語は出ていないが、「秋風」の項に「秋は陰陽五行説では白色であるとされ」と注釈して、
石山の石より白し秋の風 芭蕉
という句などがその例として上がる。なるほど、こうしてみると、角川の歳時記に出ている鈴木真砂女の句「秋風や旅もハンカチ白がよし」という句で、何故白が良いというのか、なんとなく解るような気がする。こんなふうに、新旧の歳時記をかれこれ眺めながら、秋風の色とはなんだろうと考えを巡らしたりするのは、まことに楽しい。
【下巻】
初出メディア
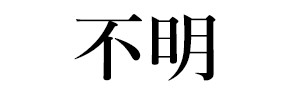
初出媒体など不明
正しい情報をご存知でしたらお知らせください。
ALL REVIEWSをフォローする