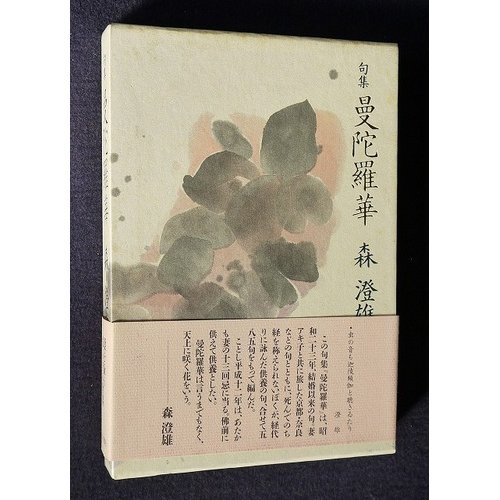書評
『わが父波郷』(白水社)
私は石田波郷に会ったことがない。作品を通じてその凝視の深さ、重さ、鋭さを享受しているだけである。
しかし彼の病床俳句と言われている作品群は決して諦念とか宗教的悟りといった色彩を帯びてはいない。あくまでも生命を愛する、生きていることを大切にし愛(いつく)しんでいる趣きなのだ。私は感動しつつそこに一種の不思議を感じる。それだけに波郷とはどういう人だったのだろうという関心が作品に触れるにつれて私を揺さぶってやまない。
そんな私の、好奇心よりはもう少し重い探し求める心に、石田修大氏の『わが父 波郷』は、なんの誇張も思い入れもない叙述の奥から、眼鏡を掛け、長身の、笑みを浮かべた俳人波郷が現れてくるような想いを与えてくれたのだった。
そのなかに、「秋の一日、私とともに埼玉の戸田ボートコースにボート競技を見に行ったことがある」という記述がある。それは東京オリンピックの年のこと、あるいはその少し後の年のことだろうか。いずれにしても、波郷が五十代になって間もなく、昭和十八年五月生れの著者が大学生の頃であったろうか。彼が高校時代ボート部にいたことが父親波郷の頭にもあったのではないかと私は思う。
この本を読む限り、波郷は自分の気持や感情を文字以外で表現することの下手な、心の優しい、父親像としては古風な日本の父親であったように思う。そうして、私がここの部分に引かれたのは、私もこのオリンピックに息子の手を引いて、なぜか閉会式を見に行ったからである。私の場合、息子は小学生であって母親に去られた後であった。
小学生と大学生の差は大きいが、この日波郷は子息に俳句のことについて何か言うつもりはなかったことははっきりしているように私は思う。波郷は「私はやるものをとめはしないが、子供が俳句をやることを望んではゐない。子供の時代まで俳句が今日の形式で残るかどうかさへ疑はしいのである」(「仰臥日記」、『石田波郷全集』第八巻 角川書店)と書いている。これは波郷のいさぎよさの現れであり、山本健吉が「俳句を作るということは、彼にとってはほとんど論理的行為なのだ」(『石田波郷―人とその作品』永田書房)と言ったゆえんであろう。彼の周辺には決して停滞した結社の風は吹かず、いつも爽やかな涼風が往来するようであったのだ。
この石田修大氏の文章は「波郷は人混みを避け、荒川の土手の上からしばらくレースを観戦して、短時間で引き上げた」と続き、
が紹介されている。
あるいは波郷は俳句のことをずっと考えていてボートの試合の入場券をもらったのを思い出し、すると息子が高校時代ボート部にいたことが記憶に蘇り、誘って出掛けることになったのかもしれない。
それから先は私の空想みたいなものだが、この叙述のすぐ前に「もちろん、酒を飲んでは母といがみ合ってばかりいたわけではない」と書かれているから、前夜にもそういうことがあり、妻が自分のことを心配して言ってくれるのが分っていながら、それだから尚更煩わしく思う我儘をつい表に出してしまった反省の色の濃い鬱屈を、ボートレースを見下す土手で解き放ちたかったのだろうか。
家のなかで波郷は我儘だったらしいがその我儘はどこか稚気を帯びていた。
そういった〝稚気〝を許すからいつまで経っても家父長制の心理構造も社会構造も変らないと、声高に主張する法律家や学者のような意見もあるだろうが、波郷の我儘はいわゆる家父長制に基づいたものではなかったと私は思う。むしろ正反対で人間的だった。その点で彼の外面(そとづら)と家のなかの顔は共通していたのである。
その人間性を支えたのが俳句だった。
言うまでもなく、芸術はしばしば人間性とは次元の違う世界に成立する。芸術家的な心理構造を持った人物が権力を持つことの恐さは、オカルト的人物が指導者になった時と共通するものがあると思う。必ず独裁が成立し、多数の犠牲者が出ることはヒットラーがそのいい例である。芸術家の生命は芸術のなかでのみ燃焼されるべきものだ。たとえ、世界最短の詩型であっても、むしろ最短であるがゆえにその燃焼は高い温度を持っていなければならないのではないか。
家のなかと、滅法褒める人が多い外側とのちょうど中間に位置して「弟子」と称する資格(?)を持っていた石川桂郎が波郷のもうひとつの側面を前掲書(『石川波郷―人のその作品』)で伝えている。
彼は波郷のことをずっと「先生」と呼んでいたが、「ある日突然に、今日から先生はやめなさい―と歩きながら、まっすぐ前を向きながらいわれた」と書く。それでもつい「先生」が出てしまうと、そのうちに波郷が彼のことを「桂郎先生」と呼び、とうとう二人の間で「先生」がなくなったというのだ。
私は短歌や現代詩の世界でも同じだと思うが、芸術創造の世界には芸術家同士の附合はあっても「先生と弟子」という関係は本来はないのではないか。様式が整っている分野で、その様式を伝授し、それを受け取る、という師弟関係は存在する。しかし、その場合でも、どこかで本人ふうが生れて、芸術家同士の関係に替るのだ。
だから波郷が「今日から先生はやめなさい」と言った時、彼は桂郎を俳人として附合う必要を認めたのである。ここには波郷のもうひとつの側面、決して宗匠ぶらない非権力的な性格が現れていよう。
もうひとつ桂郎は友人の奥さんのことを「あんな三流芸者」と評して波郷に烈火の如く怒られたこと、また仲間の俳人が戦争に征くことになってその送別会に当の仲間を殴ってしまって叱られた経験を「思い出」として書いている。この石川桂郎の話は彼の飄逸な性格を通して波郷の独特の姿を映し出しているように思われる。
こうした交遊関係を見ていくと、当時、波郷を囲む俳人、作家、芸術家の円居にはひとりの権威主義者も小道徳家もいなくて、元気潑刺、天衣無縫、気兼のない談論風発の光景が見えてくる。これはおそらく、波郷の自由な精神が自ずと作り出した性格なのではなかったかと思え、私はいよいよ一度でもいいから会っておきたかったという気持を抑え兼ねるのである。
しかし彼の病床俳句と言われている作品群は決して諦念とか宗教的悟りといった色彩を帯びてはいない。あくまでも生命を愛する、生きていることを大切にし愛(いつく)しんでいる趣きなのだ。私は感動しつつそこに一種の不思議を感じる。それだけに波郷とはどういう人だったのだろうという関心が作品に触れるにつれて私を揺さぶってやまない。
そんな私の、好奇心よりはもう少し重い探し求める心に、石田修大氏の『わが父 波郷』は、なんの誇張も思い入れもない叙述の奥から、眼鏡を掛け、長身の、笑みを浮かべた俳人波郷が現れてくるような想いを与えてくれたのだった。
そのなかに、「秋の一日、私とともに埼玉の戸田ボートコースにボート競技を見に行ったことがある」という記述がある。それは東京オリンピックの年のこと、あるいはその少し後の年のことだろうか。いずれにしても、波郷が五十代になって間もなく、昭和十八年五月生れの著者が大学生の頃であったろうか。彼が高校時代ボート部にいたことが父親波郷の頭にもあったのではないかと私は思う。
この本を読む限り、波郷は自分の気持や感情を文字以外で表現することの下手な、心の優しい、父親像としては古風な日本の父親であったように思う。そうして、私がここの部分に引かれたのは、私もこのオリンピックに息子の手を引いて、なぜか閉会式を見に行ったからである。私の場合、息子は小学生であって母親に去られた後であった。
小学生と大学生の差は大きいが、この日波郷は子息に俳句のことについて何か言うつもりはなかったことははっきりしているように私は思う。波郷は「私はやるものをとめはしないが、子供が俳句をやることを望んではゐない。子供の時代まで俳句が今日の形式で残るかどうかさへ疑はしいのである」(「仰臥日記」、『石田波郷全集』第八巻 角川書店)と書いている。これは波郷のいさぎよさの現れであり、山本健吉が「俳句を作るということは、彼にとってはほとんど論理的行為なのだ」(『石田波郷―人とその作品』永田書房)と言ったゆえんであろう。彼の周辺には決して停滞した結社の風は吹かず、いつも爽やかな涼風が往来するようであったのだ。
この石田修大氏の文章は「波郷は人混みを避け、荒川の土手の上からしばらくレースを観戦して、短時間で引き上げた」と続き、
爽やかに敗者復活に行く艇よ
が紹介されている。
あるいは波郷は俳句のことをずっと考えていてボートの試合の入場券をもらったのを思い出し、すると息子が高校時代ボート部にいたことが記憶に蘇り、誘って出掛けることになったのかもしれない。
それから先は私の空想みたいなものだが、この叙述のすぐ前に「もちろん、酒を飲んでは母といがみ合ってばかりいたわけではない」と書かれているから、前夜にもそういうことがあり、妻が自分のことを心配して言ってくれるのが分っていながら、それだから尚更煩わしく思う我儘をつい表に出してしまった反省の色の濃い鬱屈を、ボートレースを見下す土手で解き放ちたかったのだろうか。
家のなかで波郷は我儘だったらしいがその我儘はどこか稚気を帯びていた。
そういった〝稚気〝を許すからいつまで経っても家父長制の心理構造も社会構造も変らないと、声高に主張する法律家や学者のような意見もあるだろうが、波郷の我儘はいわゆる家父長制に基づいたものではなかったと私は思う。むしろ正反対で人間的だった。その点で彼の外面(そとづら)と家のなかの顔は共通していたのである。
その人間性を支えたのが俳句だった。
言うまでもなく、芸術はしばしば人間性とは次元の違う世界に成立する。芸術家的な心理構造を持った人物が権力を持つことの恐さは、オカルト的人物が指導者になった時と共通するものがあると思う。必ず独裁が成立し、多数の犠牲者が出ることはヒットラーがそのいい例である。芸術家の生命は芸術のなかでのみ燃焼されるべきものだ。たとえ、世界最短の詩型であっても、むしろ最短であるがゆえにその燃焼は高い温度を持っていなければならないのではないか。
家のなかと、滅法褒める人が多い外側とのちょうど中間に位置して「弟子」と称する資格(?)を持っていた石川桂郎が波郷のもうひとつの側面を前掲書(『石川波郷―人のその作品』)で伝えている。
彼は波郷のことをずっと「先生」と呼んでいたが、「ある日突然に、今日から先生はやめなさい―と歩きながら、まっすぐ前を向きながらいわれた」と書く。それでもつい「先生」が出てしまうと、そのうちに波郷が彼のことを「桂郎先生」と呼び、とうとう二人の間で「先生」がなくなったというのだ。
私は短歌や現代詩の世界でも同じだと思うが、芸術創造の世界には芸術家同士の附合はあっても「先生と弟子」という関係は本来はないのではないか。様式が整っている分野で、その様式を伝授し、それを受け取る、という師弟関係は存在する。しかし、その場合でも、どこかで本人ふうが生れて、芸術家同士の関係に替るのだ。
だから波郷が「今日から先生はやめなさい」と言った時、彼は桂郎を俳人として附合う必要を認めたのである。ここには波郷のもうひとつの側面、決して宗匠ぶらない非権力的な性格が現れていよう。
もうひとつ桂郎は友人の奥さんのことを「あんな三流芸者」と評して波郷に烈火の如く怒られたこと、また仲間の俳人が戦争に征くことになってその送別会に当の仲間を殴ってしまって叱られた経験を「思い出」として書いている。この石川桂郎の話は彼の飄逸な性格を通して波郷の独特の姿を映し出しているように思われる。
こうした交遊関係を見ていくと、当時、波郷を囲む俳人、作家、芸術家の円居にはひとりの権威主義者も小道徳家もいなくて、元気潑刺、天衣無縫、気兼のない談論風発の光景が見えてくる。これはおそらく、波郷の自由な精神が自ずと作り出した性格なのではなかったかと思え、私はいよいよ一度でもいいから会っておきたかったという気持を抑え兼ねるのである。
ALL REVIEWSをフォローする