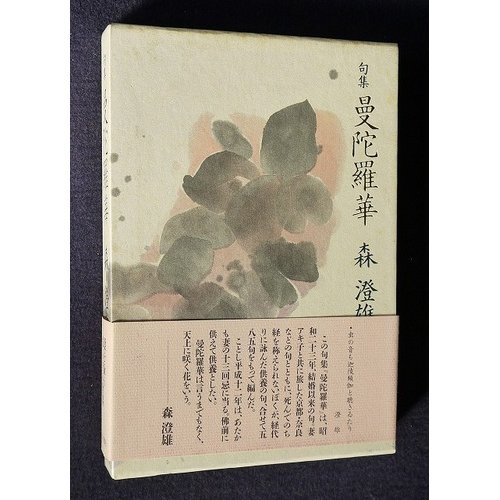解説
『塚本邦雄の青春』(ウェッジ)
塚本邦雄 理解への手懸り
「棺を覆うて後定まる」、という言葉があるが、塚本邦雄が他界した二〇〇五年六月九日から四年近い年月が経って、彼の評価は定まったとは言いにくい。しかしこれは、否定的な評価も強いから、ということではない。そうではなくて、肯定的評価の拡がりの行く先が詩全体におよび、その内容や影響力の強さがまだ定まっていない、という意味でのことなのである。彼が現代の短歌に革命的な衝撃を与えたことを否定する者はいない。
こうした短歌が可能だったのなら、僕も短歌を詠んでもいいのだ、と思った者、短歌も現代詩の詩型のひとつなのだと受取って、それ以後幾人かの若い歌人の作品集を読むようになった者も多い。しかし、「革命的」というのが、いわゆる短歌的抒情を否定した意味になるのか、モダニズム短歌の現代における再生ということなのか、などの論点になると、諸説入り乱れてという状態になり、それが「棺を覆うて」も評価が定まらないと言わざるを得ない原因になっているのだ。しかもそれは短歌の世界のなかでだけの現象ではないところに、塚本邦雄の位置付けのむずかしさがあるのである。
若い頃、塚本邦雄がウイリアム・ブレイクやアポリネールの作品に親しみ、日本の詩人ではまず安西冬衛の『軍艦茉莉』から影響を受け、敗戦後間もなく、初稿を大巾に改めた西脇順三郎の「あむばるわりあ」に大きな刺激を与えられたことは、本人も認めている。
こうした彼の青年時代の遍歴は、短歌だけを読んで歌人になった人が多かった敗戦直後の歌壇にとって異例の新人と言うことができた。塚本自身、「『あんばるわりあ』を讀んで、私は詩人にならずに歌人になつてしまつた」と言っているぐらいである。
こうした〝詩人〟誕生の独自性に加えて、塚本邦雄が育った時代が、戦争、動員、敗戦、そしてややあってからの経済の高度成長という激動と呼んでいい性格を持っていたことがあげられる。そのなかで戦時の敗戦までの四年間を、彼は海軍工廠のある呉で過していた。軍の命令によって動員された徴用工のような立場だった彼は、母親の最後を看取ることができなかった。また場所柄からいってヒロシマに落された原爆のキノコ雲も見ていたのである。
この母について、また郷里の近江について青年期の塚本邦雄は伸びやかな叙情歌としての短歌を詠んでいる。敗戦直後の時期、まだ短歌の革新者としての塚本邦雄の姿は見えていない。
一方、彼は父親とその家系については多くを語っていない。むしろ近江商人については嫌悪に近い感じを持っていたようで、このことは敗戦後かなりの期間、当時有数の商社であった(金商)又一商会に勤めていた当時の自分に対する評価と通底しているのかもしれないという気が僕にはする。彼が「初心忘るべし」というタイトルで語る時、この〝初心〟とは、ビジネスマンでありながら歌を詠んでいたその頃の自分への訣別の念も混っていたのではないかと思われる。彼が生れて間もなく他界して、当然顔も覚えていない父親についての態度ばかりではなく、彼の私的側面については謎が多い。彼の晩年の二〇〇〇年の入院手術後に訂正された出生年の二年のズレをはじめ、戦後数年間の記述については、年次が混乱し矛盾している場合が多く、この点は歌人として革新者として行動する際の明快さとは著しい対照を見せていると言っていいだろう。
言うまでもなく、総ての文学作品は作者個人と深い関連を持っている。作品に作者の生い立ちや職業の直接的な反映を見ようとするマスメディア的な理解は論外としても、幾重にも捩れたり、自己の内部でも反撥しあっている私生活との問には、多くのデフォルメがあったとしても、その複雑性において作品と作者は内的な関連を持っているものなのだ。
いくつかの作品に見られる晦渋さや私生活上の不可解さを解明するためには、まず彼の生い立ちから交遊関係などの事実を押え、人生のそれぞれの時期に対応していると思われる作品を抜き出してみること、そうした基礎作業を綿密に行うことが求められ、その意味でこの楠見朋彦氏による『塚本邦雄 理解への手懸り』は大きな意味を持っていると言うことができる。
まずはじめにこれを読むと、塚本邦雄が『水葬物語』に辿りつくまでに、長い彷徨の時期があったことが明らかになる。
次にその頃を含めて、彼が自らの経歴について誤記、あるいは乱れを見せているのはなぜかが描き出される。この件について秀れた短歌批評家であった菱川善夫は、
「まことに虚構の開幕にふさわしい人物であった」
と言っているが、それだけでは不充分なのではないかと僕は思う。なぜなら彼が目をつぶった、あるいは敢えて行った誤記は、いずれも世俗的に有利な方向への誤りだからである。年齢が長い間二歳若くなっていたのは、中井英夫が「二十代の俊英が」と書いてくれている時、塚本邦雄は三十歳を超えていてはならなかったのだし、名門彦根高商卒ではなかったらしいのに、いつの間にかそうなっているのを塚本は訂正しないままにしてしまったのである。僕はこれを、世俗的な判断に対する深い絶望と嫌悪の故ではないかと考える。この『塚本邦雄の青春』を読むとどうしてもそのようにしか思えなくなるところに、この著作の存在意義のひとつがあるのではないか。
次にこの著作から分ってくることは、塚本邦雄の才能が育った時代環境についてである。僕はこの楠見朋彦氏の本を読みながらある詩人が言った
「時代は感受性に運命をもたらす」
という言葉を想起していた。塚本邦雄に影響を与え、影響を与えられた入々を、杉原一司、下條義雄、寺山修司、船津碇次郎……と数えていくと、時代が新しい調べを歌う歌人群像を生み出しており、そのなかに塚本邦雄もいたことが分ってくる。塚本自身も例えばそのなかの一人船津碇次郎について『序破急急』のなかで、
「夭折したフランスの作家ラディゲと、杉原一司と船津碇次郎がゐなかつたら『水葬物語』は生れなかつただらう」と述べていることを楠見氏は紹介している(註参照)。更らにこの青春時代以降、短歌の世界における塚本の革新者としての活動に理解を示し、協力を惜しまなかった岡井隆の役割を明記しておく必要があろう。
こうした光景は印象派の名の下に多くの新しい若い画家、音楽家、詩人が集い、近代についての深い絶望から、アラゴン、エリュアールそしてマン・レイなど、ダダやシュールレアリスムの芸術家の群像が形成された時代の変革期を僕に想起させる。
そうして三番目に、これらの考察から『水葬物語』は突然変異のようにして生れたのではないことを僕らは納得させられるのである。このことは、彼が自らの調べに辿り着くまでにどのような彷徨を重ねたのかという事実に裏付けられて、この『塚本邦雄の青春』が説得力のある報告、物語りになっていることを示している。
確かに、時代はそれまでの抒情詩としての短歌を詠い続けることを困難にしていた。才能とは、そのような時代の性格と要請を自らの内部からの欲求として受取ることができる感受性のことだ。それを感じ得ない人達は従来の抒情性に拘泥って、塚本邦雄の歌には調べがない、などと批評するのである。
塚本邦雄の目は、いつの頃からか取り上げようとする対象、存在の周辺から、直視を不可能にする眩しい光彩を取払い、そのものとしての裸の存在と向い合うようになった。そうすることで彼は常套的で抒情的な光彩の替りに次元の違うイメージでその対象を包むことが可能になった。それを、自由になった歴史的な時間の感覚と呼んでもいいし、異次元から掴みとった衣裳と考えてもいい。その時、言葉が彼の内部から対象に向って放射される。そのことによって対象は現実の存在でありながら現実を超えた物質になる。この美学の一例を、数多く使われているピアノを使った作品のなかから三首をあげて検討してみたい。いずれも楠見朋彦氏が著作のなかで紹介している作品である。
ほほゑみに肖てはるかなれ霜月の火事のなかなるピアノ一臺
革命歌作詞家に凭りかかられてすこしづつ液化してゆくピアノ
湖の夜明け、ピアノに水死者のゆびほぐれおちならすレクイエム
この三首について『塚本邦雄の青春』の著者は自らの理解を披露している。それに納得しながらも僕は最初の作品の「ほほゑみ」は、もう見ることもできなくなった、もっとも美しい人間的な表情を指し、十一月と言うより白の色彩感覚を喚起する霜月のなかで燃えさかる赤い火と、そんななかに在っても決して鳴り出すことのない叙情の豊庫のような黒一色のピアノを置く。そのことで、短歌がもはや叙情性を演奏することは不可能なのだ、と訴えかけているように僕には思える。
『水葬物語』の冒頭に掲げられて有名な二首目の「革命歌作詞家──」の作品も、当時、流行語の感さえあった「革命」という言葉の実体の空虚さ、その偽りに気付かない鈍感さで革命歌を詠むような人物に凭りかかられては、本当の叙情を内部に持っているピアノはもう液化するしか白らの存在様式を選べないと主張しているのではないか。この一首ではじまる『水葬物語』の十首が「平和について」という章の名で括られていることは、当時の世相がいかに上滑りだけする軽さに覆われていたかを読む者に伝えているのだと思われる。しかしそれ以後、塚本邦雄が生きていた時代、世の中はいくらかでも実体を備えるようになったのだろうか。ここには塚本邦雄の、敗戦後の日本に対する深い絶望が伝わってくるように感じるのは僕だけだろうか。だから、もしそうした時代にピアノを鳴らすことができる指があったとしたら、それは水死者の掌から腐って、一本ずつ湖底へ落ちていく指しかなく、そこで演奏されるのは外国製の鎮魂歌なのだ。このピアノが磨きあげられた堂々たるグランドピアノであることは言うまでもない。
そうして、僕にそのような自由な解釈を可能にしてくれるところに、この『塚本邦雄の青春』という著作の奥の深さと実証の力があるのである。著者が「おわりに」で「本書はいわゆる評伝ではない」と述べているのは、おそらく読者に自由を与えるという意味においてではないかと僕は思う。この書は価値判断を読者に押し付けず実証的であることによって、前衛歌人、あるいはモダニズムの歌人、又は反リアリスム派というような、常套的な理解から塚本邦雄を解放してくれているのである。
それ故に、この著作を読んだ後で、もう一度『水葬物語』を播くと、「亡き友 杉原一司に献ず」という言葉の後に、フランス語でランボーの言葉が記されていることの意味が明らかになってくる。それには、
「……私はありとある祭を、勝利を、劇を創つた。新しい花を、新しい星を、新しい肉を、新しい言葉を發明しようと努めた……」
と訳が添えられていた。
(註)一九七二年に筑摩書房から出版されたこの『序破急急』という評論集の当該箇所の原文は「二十一歳で死んだラディゲと、二十五歳で没した杉原一司と、當時の『日本歌人』で私が一方的なライヴァル意識をもやしつつ、実は心醉し、然も遂に全くかかはりをもたず今日に到つた船津碇次郎がゐなかったら『水葬物語』は生れなかつただらう」となっている。(『序破急急』第四章「詞華花合」所収)。
ALL REVIEWSをフォローする