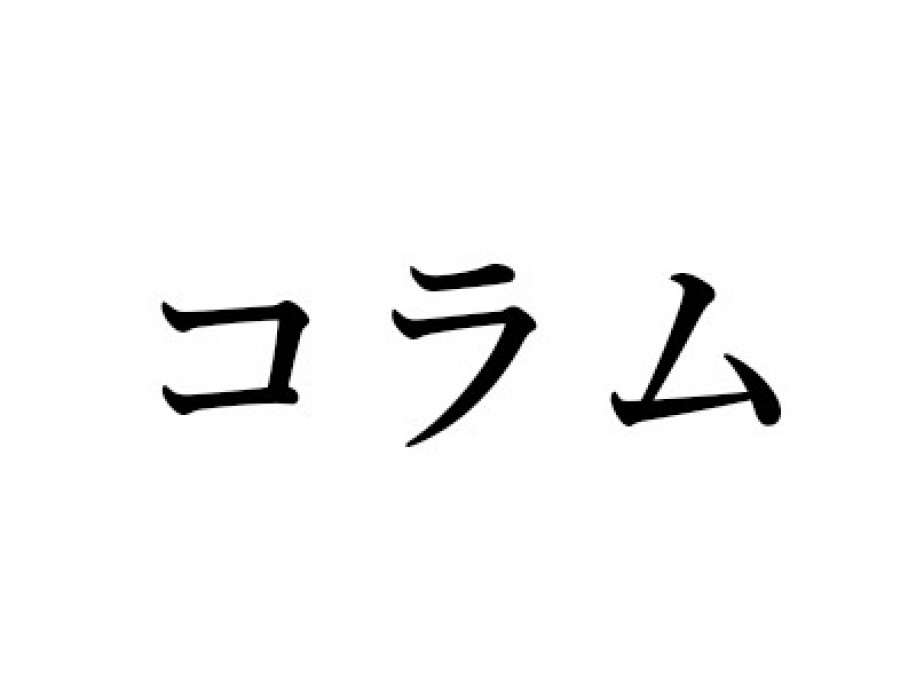書評
『人類の地平から―生きること死ぬこと』(ウェッジ)
三角測量と強靭な視線が生む「語り」
じぶんの思考がぶれかけている、淀(よど)みだしていると感じたとき、すがるようにその声に耳を傾けたくなる思索者がわたしにはいる。そのひとり、川田順造の著作が、久しぶりに立て続けに出た。まず『人類の地平から』。随想集とはいえ、一本、堅い芯が通っている。人類学者としていまの文化に対しきちんと発言しておかねばならないこと、という芯だ。川田の言葉だと、インフォーム(形にあてはめる)ではなくパフォーム(身体をとおして形にしてゆく)という、これからの知のあり方だ。
西アフリカとフランスでの入院経験から現代日本の医療を見直す。一夫多妻が福祉制度として機能している社会から高齢化社会の抱える問題を照らす。あたりまえのように子どもが働く社会からいまの教育を根本から質(ただ)す。さらには開発の、あるいは豊かさの意味、身体と道具の関係、農の心……というように、文化をめぐってつねに基本中の基本に立ちかえる語りに、思わず襟を正させられる。
その、たしかな、奥行きのある語りは、東でも西でもない南の声、そう、アフリカの生活文化からの視線を入れた文化の「三角測量」と、個別への愛着を「一般化への強靱(きょうじん)な視線」で支える「離見」(レヴィ=ストロースが世阿弥から学んだ視線)という、川田が長年にわたる西アフリカの生活経験のなかで培った構えからにじみ出てくるものだ。
その「三角測量」の一点についての研究が、『アフリカの声』だ。声、踊り、力、時、性、死、肖像、方位などを切り口とする西アフリカ文化論は、三百年にわたる西欧の奴隷貿易と、それにけしかけられた内部の悲惨な権力闘争の歴史への洞察を、厚い下敷きとしている。
最後に『人類学的認識論のために』は、人類学が現在、学科として、メタ・サイエンスとして、そして思想として試されている問題に、宗教に劣らぬ巨(おお)きなスケールをとって取り組む。「われわれ」のうんと外側に光源をとって、「われわれ」の手前を照らしてきた川田の視線は、ヒトの外との倫理的関係にまでおよぶ。
朝日新聞 2004年09月19日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする