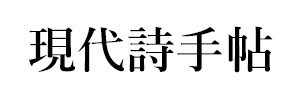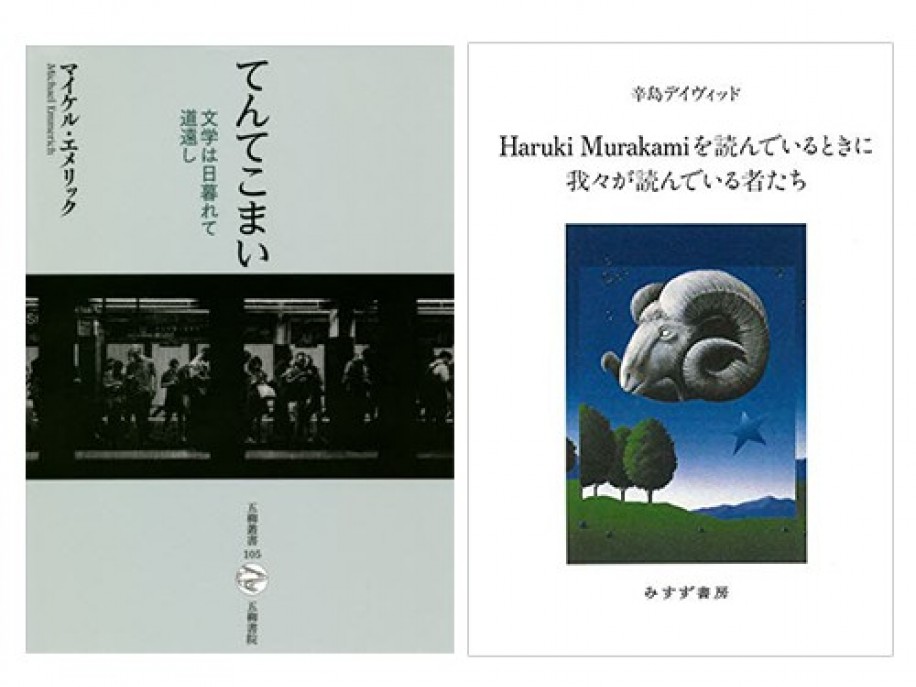書評
『詩は生きている』(五柳書院)
福間健二は不服従の人である。彼は長い経歴をもつ詩人であり、イギリス詩の研究家であり、映画とも深く関わっている人物なのだが、それ以上に彼を紹介するさいにもっとも適当なのは、その不服従な存在のあり方である。
まず彼は知識をもとに詩を語ることを拒否する。詩を死体のように扱い、分類や整理をしたり、入門書や弁護の文章を公にすることを嫌う。今日、詩は元気がない。たいがいの詩人は相当に無理をし、自分の立ち位置をかろうじて支えているというのに、その現状を見ようともしないで「詩は……であるべきだ」とご託宣を並べるのは、畢竟(ひっきょう)安全な場所にみずからの身を置いているだけのことではないか。こう書きつける福間は、日本の現代詩が日本語という単一性のなかに保護され、日本語というイデオロギーの庇護の対象となっていることに、尽きせぬ苛立ちを感じている、安全な場所に留まっていることが耐えられないのだ。
では、どうするか。世界を覆いつくそうとしている空虚と疲労に抵抗するためには、とりあえず歩き出すことだ。だが彼の歩みはひどく鈍く、足がもつれ、能率が悪い。軽快さという言葉は福間の辞書にない。彼の足取りは、かつての寺山修司のようにトリッキーで遊戯的なものでもなければ、吉増剛造のように金槌をもった漂泊でもない。かかえこむ。背負う。追いつめられる。立ちどまる。福間を特徴付けているのはこうした、およそ反二ーチェ的で、舞踏の魅惑からかけ離れた動詞である。われわれは「すれている」。敗北感と不充足感のさなかにあって、歩くたびに背骨の痛みを感じながらも、それでも長く長く歩かなければならない。
どうしてだろう。福間はいう、世界に向きあうためだと。どこか「慣らされていない、しぶとい、ごつごつした感じ」に出会うためだ。若い現代詩人の西中行久と松本圭二がすばらしいのは、彼らの詩が世界が強いてくる摩滅から奇跡的に免れているからだ。ノスタルジアでも学識でもなく、単純に現在を生きているからだ。またウェールズのロイド・ロブソンの詩が刺激的なのは、彼が言語行使の次元で、能率の悪い歩行のモデルを踏襲しているからだ。わたしも福間に紹介されて眼前で朗読に接したことがあるが、こいつはすごい奴だったね。作品全体にわたって強い吃音の痕跡が窺われ、朗読は激しい息遣いと叩きつけるかのような単語の連続で、きわめて印象的なものであった。
直線距離を選ばないこと。近道をしないこと。あえて思いきり遠回りをして、それから本来の場所に戻ってみること。本書には20世紀のイギリス詩を代表する一人であるデュラン・トマスの勉強にウェールズに滞在した福間と、ウェールズ語と英語という言語の狭間のなかで詩を書き続けている詩人たちとの間でなされた交流が、興味深く語られている、福間は直面を求める人である。彼は世界との直面を求めて、苦痛と拘泥の歩みをやめない。そして「急にたどりついてしまう」。その最初の詩論集である本書は、遠回りの後の到達の記録である。
【この書評が収録されている書籍】
まず彼は知識をもとに詩を語ることを拒否する。詩を死体のように扱い、分類や整理をしたり、入門書や弁護の文章を公にすることを嫌う。今日、詩は元気がない。たいがいの詩人は相当に無理をし、自分の立ち位置をかろうじて支えているというのに、その現状を見ようともしないで「詩は……であるべきだ」とご託宣を並べるのは、畢竟(ひっきょう)安全な場所にみずからの身を置いているだけのことではないか。こう書きつける福間は、日本の現代詩が日本語という単一性のなかに保護され、日本語というイデオロギーの庇護の対象となっていることに、尽きせぬ苛立ちを感じている、安全な場所に留まっていることが耐えられないのだ。
では、どうするか。世界を覆いつくそうとしている空虚と疲労に抵抗するためには、とりあえず歩き出すことだ。だが彼の歩みはひどく鈍く、足がもつれ、能率が悪い。軽快さという言葉は福間の辞書にない。彼の足取りは、かつての寺山修司のようにトリッキーで遊戯的なものでもなければ、吉増剛造のように金槌をもった漂泊でもない。かかえこむ。背負う。追いつめられる。立ちどまる。福間を特徴付けているのはこうした、およそ反二ーチェ的で、舞踏の魅惑からかけ離れた動詞である。われわれは「すれている」。敗北感と不充足感のさなかにあって、歩くたびに背骨の痛みを感じながらも、それでも長く長く歩かなければならない。
どうしてだろう。福間はいう、世界に向きあうためだと。どこか「慣らされていない、しぶとい、ごつごつした感じ」に出会うためだ。若い現代詩人の西中行久と松本圭二がすばらしいのは、彼らの詩が世界が強いてくる摩滅から奇跡的に免れているからだ。ノスタルジアでも学識でもなく、単純に現在を生きているからだ。またウェールズのロイド・ロブソンの詩が刺激的なのは、彼が言語行使の次元で、能率の悪い歩行のモデルを踏襲しているからだ。わたしも福間に紹介されて眼前で朗読に接したことがあるが、こいつはすごい奴だったね。作品全体にわたって強い吃音の痕跡が窺われ、朗読は激しい息遣いと叩きつけるかのような単語の連続で、きわめて印象的なものであった。
直線距離を選ばないこと。近道をしないこと。あえて思いきり遠回りをして、それから本来の場所に戻ってみること。本書には20世紀のイギリス詩を代表する一人であるデュラン・トマスの勉強にウェールズに滞在した福間と、ウェールズ語と英語という言語の狭間のなかで詩を書き続けている詩人たちとの間でなされた交流が、興味深く語られている、福間は直面を求める人である。彼は世界との直面を求めて、苦痛と拘泥の歩みをやめない。そして「急にたどりついてしまう」。その最初の詩論集である本書は、遠回りの後の到達の記録である。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする