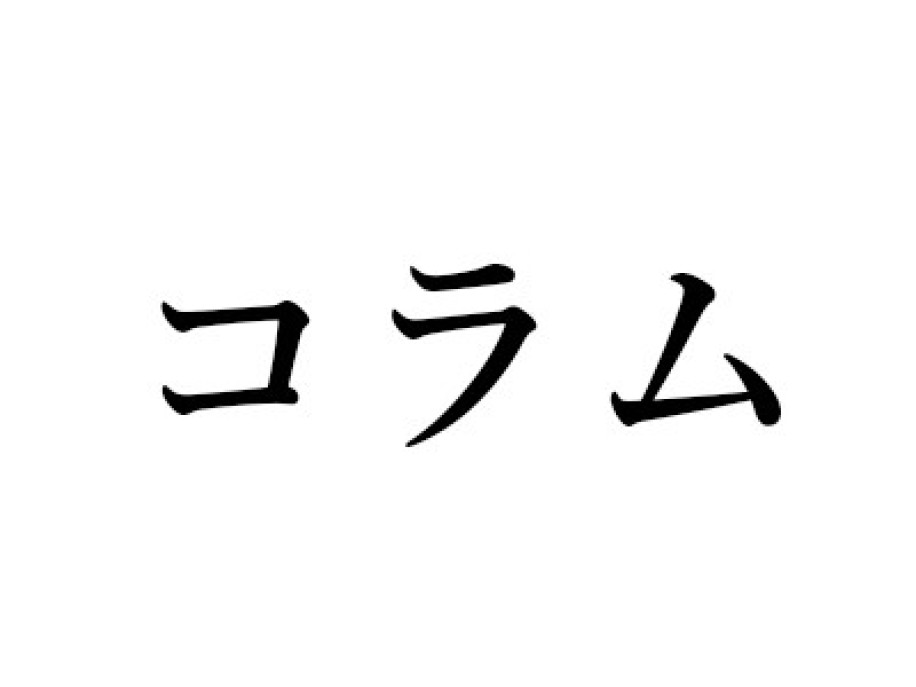書評
『黄金の驢馬』(岩波書店)
驢馬を飼おうと思っている。パキスタンから連れてくれば、2万円もしないのだという。だがその後にどうするか、まったく算段がたっていない。
驢馬を飼うにはまず一定の広さが必要だろう。臭いが原因で近所から苦情がでることもあるだろうから、まず都心では飼えない。となると田舎に引っ越さねばならなくなるのだが、そうなれば今度はこちらの仕事に支障をきたすことになる。でもいいや。とにかく連れてきてしまえば、後はなんとかなるさという気がしないでもない。人生には、結婚もしてないのにいきなり子供ができちゃったとか、突然に家族の看護をしなければいけなくなったという風に、予期せざる事件というものが往々にして起こるものなのだ。実際に目の前に驢馬が来てみれば、それなりに智恵が湧いてくることだってあるだろう。
驢馬の名前だけはすでに決めてある。ルキウスである。これは2世紀の小説家アプレイウスの長編『黄金のろば』の主人公の名前だ。高校生のときだったと思うが、わたしはこの古代ローマの物語を読んで、彼のことをすっかり気に入ってしまったのである。
ルキウスはおっちょこちょいの学生である。田舎から帝都に出てきたものの、西も東もわからず、どこかにかわいい女の子でもいないかなあくらいのことしか考えていない青年だ。ひょんなことから彼は魔女の呪文にかけられ、驢馬に変身させられてしまう。市場に連れ出されて売り飛ばされたり、ひどい苦役を強いられたり、山賊によって盗み出されたり、波乱万丈の体験を重ねてゆく。作者の言葉を借りていうならば、それはすべて運命の女神の気まぐれのなせる業なのである。だが持ち前の楽天性と調子のよさから、ルキウスはどのような困難にも屈することなく、ヘラヘラと苦境を通り過ぎてゆく。最後に彼は女神イシスの力によって、元の人間の姿に戻してもらう。そして女神様に仕える神官として生きることになる。
驢馬というのは馬に比べて、どこか劣った存在であるかのように見なされてきた。馬は高貴にして誇り高く、颯爽としている。それに比べて驢馬は背が低く、愚鈍にして頑固。農民が荷物運びのために使用することはあっても、けっして身分のある人物がその背に跨るなどということはない。その証拠に、エルサレムでローマ兵たちに捕らえられたイエスは、茨で作った冠を頭に被せられ、わざわざ驢馬に乗せられて連行されることで、周囲の群衆から辱めを受けた。セルバンテスの『ドン・キホーテ』でも、痩身で憂い顔の騎士はロシナンテという馬に乗っているのだが、その家来のサンチョ・パンサは驢馬に乗り、しかもその驢馬には名前さえ与えられていないのだ。驢馬はこうして、いつの時代にも貶められてきた動物だった。シャガールの絵画のなかで、その眼はひどく物悲しい。驢馬はどこまでも続く苦しみと屈辱に、ただただじっと耐え忍ぶことしかできない。
『黄金のろば』の物語は、こうしていつも蔑まれてきたこの驢馬という視点を借りて、人間社会を逆に諷刺してみせた連作短編集だと考えることもできる。驢馬以外にほかに誰もいないところで、人間がいかに卑小な欲望に駆られ、策略と陰謀のもとに自滅してゆくかをめぐって、さまざまに面白い話が語られる。だが同時にこれは、ルキウスという青年が、おっちょこちょいの風来坊であることをやめて、人生の真実の意味を発見するというイニシエーションの物語であるともいえる。イニシエーションという言葉は最近の日本ではすっかり評判が悪くなってしまったが、元はといえば人生の階段を双六の遊戯のように、ひとつひとつ進んでいくことと同義の言葉である。
モロッコ、パレスチナ、コソヴォ、そしてチベット。この10年の問にわたしがある共感を抱きつつ足を向けた場所では、かならずといっていいほど驢馬の姿を見かけた。どこでも驢馬は黙々と荷物を運び、ときどき悲しげな声をあげていた。ひょっとしたらわたしが出会った驢馬のなかにも、なにかの都合で魔法に掛けられたルキウスのような青年がいたのかもしれない。そう思うと、またアプレイウスの頁を捲ってみたくなる。わたしはいつになったら驢馬を飼うことができるのだろうか?
【この書評が収録されている書籍】
驢馬を飼うにはまず一定の広さが必要だろう。臭いが原因で近所から苦情がでることもあるだろうから、まず都心では飼えない。となると田舎に引っ越さねばならなくなるのだが、そうなれば今度はこちらの仕事に支障をきたすことになる。でもいいや。とにかく連れてきてしまえば、後はなんとかなるさという気がしないでもない。人生には、結婚もしてないのにいきなり子供ができちゃったとか、突然に家族の看護をしなければいけなくなったという風に、予期せざる事件というものが往々にして起こるものなのだ。実際に目の前に驢馬が来てみれば、それなりに智恵が湧いてくることだってあるだろう。
驢馬の名前だけはすでに決めてある。ルキウスである。これは2世紀の小説家アプレイウスの長編『黄金のろば』の主人公の名前だ。高校生のときだったと思うが、わたしはこの古代ローマの物語を読んで、彼のことをすっかり気に入ってしまったのである。
ルキウスはおっちょこちょいの学生である。田舎から帝都に出てきたものの、西も東もわからず、どこかにかわいい女の子でもいないかなあくらいのことしか考えていない青年だ。ひょんなことから彼は魔女の呪文にかけられ、驢馬に変身させられてしまう。市場に連れ出されて売り飛ばされたり、ひどい苦役を強いられたり、山賊によって盗み出されたり、波乱万丈の体験を重ねてゆく。作者の言葉を借りていうならば、それはすべて運命の女神の気まぐれのなせる業なのである。だが持ち前の楽天性と調子のよさから、ルキウスはどのような困難にも屈することなく、ヘラヘラと苦境を通り過ぎてゆく。最後に彼は女神イシスの力によって、元の人間の姿に戻してもらう。そして女神様に仕える神官として生きることになる。
驢馬というのは馬に比べて、どこか劣った存在であるかのように見なされてきた。馬は高貴にして誇り高く、颯爽としている。それに比べて驢馬は背が低く、愚鈍にして頑固。農民が荷物運びのために使用することはあっても、けっして身分のある人物がその背に跨るなどということはない。その証拠に、エルサレムでローマ兵たちに捕らえられたイエスは、茨で作った冠を頭に被せられ、わざわざ驢馬に乗せられて連行されることで、周囲の群衆から辱めを受けた。セルバンテスの『ドン・キホーテ』でも、痩身で憂い顔の騎士はロシナンテという馬に乗っているのだが、その家来のサンチョ・パンサは驢馬に乗り、しかもその驢馬には名前さえ与えられていないのだ。驢馬はこうして、いつの時代にも貶められてきた動物だった。シャガールの絵画のなかで、その眼はひどく物悲しい。驢馬はどこまでも続く苦しみと屈辱に、ただただじっと耐え忍ぶことしかできない。
『黄金のろば』の物語は、こうしていつも蔑まれてきたこの驢馬という視点を借りて、人間社会を逆に諷刺してみせた連作短編集だと考えることもできる。驢馬以外にほかに誰もいないところで、人間がいかに卑小な欲望に駆られ、策略と陰謀のもとに自滅してゆくかをめぐって、さまざまに面白い話が語られる。だが同時にこれは、ルキウスという青年が、おっちょこちょいの風来坊であることをやめて、人生の真実の意味を発見するというイニシエーションの物語であるともいえる。イニシエーションという言葉は最近の日本ではすっかり評判が悪くなってしまったが、元はといえば人生の階段を双六の遊戯のように、ひとつひとつ進んでいくことと同義の言葉である。
モロッコ、パレスチナ、コソヴォ、そしてチベット。この10年の問にわたしがある共感を抱きつつ足を向けた場所では、かならずといっていいほど驢馬の姿を見かけた。どこでも驢馬は黙々と荷物を運び、ときどき悲しげな声をあげていた。ひょっとしたらわたしが出会った驢馬のなかにも、なにかの都合で魔法に掛けられたルキウスのような青年がいたのかもしれない。そう思うと、またアプレイウスの頁を捲ってみたくなる。わたしはいつになったら驢馬を飼うことができるのだろうか?
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする