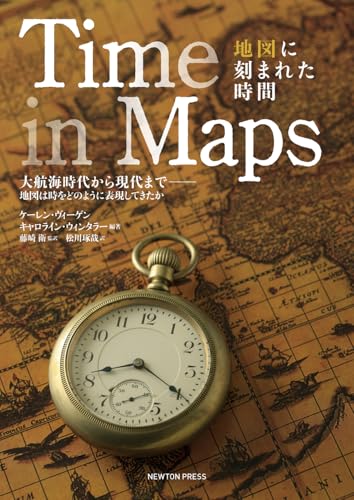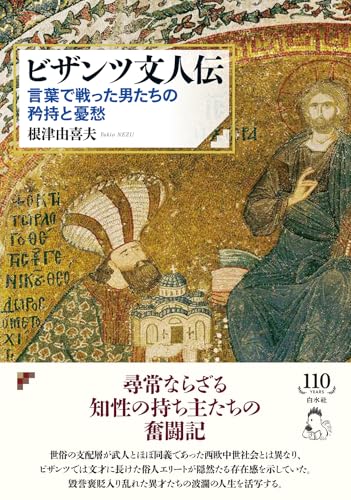書評
『ホメロス叙事詩の世界 『イリアス』『オデュッセイア』』(ピナケス出版)
「地中海文明」の理解に最適
ひと昔さかのぼれば、欧米の教養人なら誰もがためらうことなく、まず読むべき本としてホメロスの『イリアス』と『オデュッセイア』をあげただろう。もっと昔の古代にさかのぼれば、かの野望にもえるアレクサンドロス大王は『イリアス』の愛読者であった。ギリシア軍最大の勇者アキレウスにあこがれ、東方遠征途上にはトロイアを訪れ、勇者の墓に花冠を捧げるほどだった。しかしながら、わが国では、ホメロス叙事詩はそれほど親しまれていない。一度目を通したなら、アレクサンドロスのように、なんどでも読みたくなるにちがいないが。
トロイア戦争とは、ミュケナイ王アガメムノンによって率いられたギリシア遠征軍がエーゲ海を越えてトロイアを攻め滅ぼした出来事である。この戦いを古代ギリシア人たちは遠い祖先の輝かしい功業と讃えていた。
だが、『イリアス』の主題は、王の権威をふりかざす理不尽なアガメムノンに対する、若き英雄アキレウスの怒りであった。そこには上に立つ者への批判精神が目立ち、それを生み育てた土壌は、舞台となるミュケナイ社会ではなく、暗黒時代を経た新しいポリス共同体であったのだ。
この暗黒時代の介在する断絶感と距離感のせいで、トロイア伝承を基にして類を見ないほどの豊かな神話・伝説が誕生した。詩人の声に耳をかたむける人々は、暗黒時代のかなたに、神々と親しく交わる偉大な英雄たちの姿に心をときめかせたにちがいない。
実のところ、近現代人なら、幻聴・幻視に惑わされた神話の空想世界を想像しがちだが、ここには古代人が「迫真ある現実」として実感する世界があったことは忘れるべきではない。神々と人間が混在する物語は、合理精神のとがった近現代人には非現実的な虚妄の世界にしか思われない。
とくに『イリアス』にあっては、なにかと神々は人間に力を貸す。たとえば、アキレウスを助ける女神アテネが、敵将ヘクトルの弟に偽装して近づくと、兄は励まされて決意を固める。だが、決戦の最後の場面で弟は姿を消してしまうのだった。さらに、アキレウスの怒りはゼウスの計画であったが、息子ヘクトルの遺体を返してくれるようにとの父プリアモスの願いは、ゼウスの誉れを得たアキレウスに聞き入れられ、両者の和解が結ばれる。
このように、いたるところで介在する神々の所業のせいで、叙事詩『イリアス』はどこか絵空事に思われたりする。ところが、帰国譚になる『オデュッセイア』では、神々の介入があっても、地中海をさまよう知将オデュッセウスはなにかと自力で判断しようとする。故郷イタケへ帰りたいオデュッセウスの思いは死すべき人間としての希望でもあり、人間であることを自覚し、それを戦いとっていく精神でもあった。「あらゆる策略において、そなたを凌ぐ者があるとすれば、それは余程のずるく悪賢い男に相違ない――いや神とてもそなたには太刀打ちできぬかも知れぬ」と知恵の女神アテネも認める。このために、オデュッセウスは「最初の近代人」とよばれることさえあるほどだ。
本書はホメロス叙事詩の物語としての面白さ、登場人物の魅力などについて、卓越した著者の独自な解釈がちりばめられており、ことさら最適の読み物である。
ALL REVIEWSをフォローする