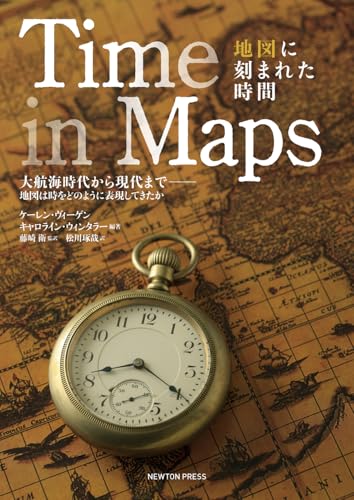書評
『世界の多様性〈普及版〉 〔家族構造と近代性〕』(藤原書店)
家族システムと心性 今世紀の古典
人類学者トッドは、評者と同じく団塊の世代に属する。かつて二五歳の新進気鋭の学者は、来たるべきソ連の崩壊を予告したのだから、驚くべき予言であった。その背景には、乳児死亡率の上昇という人口動態における異常事態をいち早く察知していたらしい。産業革命以前からイングランドの農家では核家族が大半をなしており、それに基づいて個人主義のスタンダードが生まれたと指摘されていた。この単一性モデルは指導教授であるP・ラスレットの認識でもあったが、トッドは家族システムの多様性を主張し、両者は対峙(たいじ)していく。
トッドの歴史人口学の要点は、なにはともあれ家族システムと心性との因果関係を見出(みいだ)したことにある。本書は『第三惑星』と『世界の幼少期』からなるが、前者は太陽系の第三惑星である地球における家族構造の類型の全体を見通し、後者では世界各地の経済成長の固有性と多様性を分析する。
その家族は、生物・社会における生活の単位であり、数世紀あるいは数千年にわたって存続しているだけなのだ。しかも、トッドによれば、それら家族の多様な形は類型化できる。そこには七つの家族類型があるという。
⑴外婚制共同体家族は、ロシア草原地帯、中国南部などのいずれにも適応している。
⑵権威主義家族は、大陸性のドイツ、温帯の日本などに根づく。
⑶絶対核家族は、オランダやイングランドだけではなく、数千キロ離れた合衆国でも発展している。
⑷平等主義核家族は、地中海沿岸、北ヨーロッパ平野部、東アフリカ高地で見られる。ラテン・アメリカはカスティリアの家族モデルを再生産している。
⑸非対称型共同体家族は、モンスーンの国インドにも温暖なチリにも同時に存在する。
⑹アノミー家族(近親相姦(そうかん)を禁じない)は、東南アジアの沿岸湿地帯でもアンデスの寒冷高地でも確認される。
⑺内婚制共同体家族だけが同一気候の大西洋からアフリカと中近東を経て中央アジアへと広がる乾燥地帯にまたがるが、全ての乾燥地帯がこの家族になるのではない。
こうしてみると、地理的・気候的な制約はなく、家族システムは偶然で情緒的な産物であり、イデオロギーの歴史には、人類学的な条件をふくみながらも、偶然が介入する。そこには感傷に流されない冷静な推察があった。
ところで、歴史をたどれば、家族構造は、識字率、出生率、男女格差、結婚年齢、経済成長率などを条件づけており、やがて文字の開発から人類全体がそれを習得するまで長い学習期間があり、それが人類の幼少期になるという。
例えば、これらの社会の原動力として識字率上昇に注目すればわかりやすい。市民の大部分が読み書き能力を獲得することで国民=民族が成立し、これが民主主義の条件となる。女性の識字化は出生率の低下をもたらすこともある。
このように、家族システムをめぐって、全世界規模での分布を確定し、それらの変遷をたどりながら、そこに生きる人々の心性との関係を見出すことが議論の核心となるのだ。すでに四〇年ほど以前に公刊された諸論をまとめた普及版であるが、今でも目からうろこの新知見が散らばっており、二一世紀の古典となるだろう。
ALL REVIEWSをフォローする