書評
『オレンジだけが果物じゃない』(国書刊行会)
翻訳家・岸本佐知子さんの訳したくなる作家の基準は、「小説書いてなかったらどうなってたんだろうって心配になるくらいヘンな人」なんだそうだ。スティーヴン・ミルハウザー、ニコルソン・ベイカー、トム・ジョーンズなど、岸本さんが訳してきたのはたしかに一筋縄ではいかない作家ばかりなのである。
ジャネット・ウィンターソンも岸本さんお気に入りの作家の一人。ナポレオンの遠征時代を背景に、足に水掻きがある男装趣味の娼婦を主人公にした『ヴェネツィア幻視行』(早川書房)、一七世紀の英国を舞台に、巨体で怪力の持ち主ドッグ・ウーマンと捨て子の青年の時空を超える冒険を描いた『さくらんぼの性は』(白水uブックス)、ジェンダーの問題を主題にすえた『恋をする躰』(講談社)と、すでに三作が翻訳されている。今回岸本さんが訳出した『オレンジだけが果物じゃない』は、そのウィンターソンのデビュー作。南米文学のマジックリアリズムを彷彿させる『ヴェネツィア』や『さくらんぼ』と比べると、やや現実寄りの物語になっている。というのも、これは半自伝的な作品なのだ。
主人公の少女の名は作者と同じジャネット。将来の夢は宣教師になることだ。キリスト教原理主義一派の熱心な信者である母親が、幼い頃から徹底的な英才教育を施してきたせいで。でも、実はジャネットは養子。処女懐胎を気取った母親が、孤児院から引き取った赤ん坊を”神の子”に仕立て上げるべく洗脳した成果がジャネットという少女なのだ。ところが、神の教えに微塵の疑いも抱かず成長した少女にも、世間の風は吹き寄せる。学校に通うことで初めて聖書とは異なる現実に遭遇し、とまどうジャネット。他の生徒とのあまりの違いに呆然とするジャネット。そして、恋に落ちて本当の自分を発見し、うろたえるジャネット。なぜなら、その恋の相手は同性だったから。
そうした成長を「創世記」や「出エジプト記」といった聖者の挿話に重ね合わせながら描いたこの小説が、ほば事実に即しているという点にまず驚かされる。でも、物語(ストーリー)こそ〈世界の謎を解き明かしながら、世界を謎のまま残す術、時のなかに封じ込めてしまうのではなく、生かしつづける術〉であり、歴史(ヒストリー)なんか〈手なぐさみの玩具〉で〈物語の脱け殻〉にすぎないと考えるウィンターソンが、自身の半生という歴史をストレートに語るはずもない。本筋にお伽噺やアーサー王の騎士物語、寓話などの“お話”をはさむことで、外的な事実ではなく魂の真実に肉薄するのだ。
しかも、その語り口はユーモラス。〈父は格闘技を観るのが好きで、母は格闘するのが好きだった〉という冒頭の語りから、吹き出してしまう箇所多々あり。ユーモアもまた、悲しみや怒りといった感情を心の中に〈封じ込める〉のではなく、〈生かし続ける〉ための大切な術だということに気づかされる筆致なのだ。一筋縄にはいかない作家って、やっぱイイ、すごくイイ。
【新版】
【この書評が収録されている書籍】
ジャネット・ウィンターソンも岸本さんお気に入りの作家の一人。ナポレオンの遠征時代を背景に、足に水掻きがある男装趣味の娼婦を主人公にした『ヴェネツィア幻視行』(早川書房)、一七世紀の英国を舞台に、巨体で怪力の持ち主ドッグ・ウーマンと捨て子の青年の時空を超える冒険を描いた『さくらんぼの性は』(白水uブックス)、ジェンダーの問題を主題にすえた『恋をする躰』(講談社)と、すでに三作が翻訳されている。今回岸本さんが訳出した『オレンジだけが果物じゃない』は、そのウィンターソンのデビュー作。南米文学のマジックリアリズムを彷彿させる『ヴェネツィア』や『さくらんぼ』と比べると、やや現実寄りの物語になっている。というのも、これは半自伝的な作品なのだ。
主人公の少女の名は作者と同じジャネット。将来の夢は宣教師になることだ。キリスト教原理主義一派の熱心な信者である母親が、幼い頃から徹底的な英才教育を施してきたせいで。でも、実はジャネットは養子。処女懐胎を気取った母親が、孤児院から引き取った赤ん坊を”神の子”に仕立て上げるべく洗脳した成果がジャネットという少女なのだ。ところが、神の教えに微塵の疑いも抱かず成長した少女にも、世間の風は吹き寄せる。学校に通うことで初めて聖書とは異なる現実に遭遇し、とまどうジャネット。他の生徒とのあまりの違いに呆然とするジャネット。そして、恋に落ちて本当の自分を発見し、うろたえるジャネット。なぜなら、その恋の相手は同性だったから。
そうした成長を「創世記」や「出エジプト記」といった聖者の挿話に重ね合わせながら描いたこの小説が、ほば事実に即しているという点にまず驚かされる。でも、物語(ストーリー)こそ〈世界の謎を解き明かしながら、世界を謎のまま残す術、時のなかに封じ込めてしまうのではなく、生かしつづける術〉であり、歴史(ヒストリー)なんか〈手なぐさみの玩具〉で〈物語の脱け殻〉にすぎないと考えるウィンターソンが、自身の半生という歴史をストレートに語るはずもない。本筋にお伽噺やアーサー王の騎士物語、寓話などの“お話”をはさむことで、外的な事実ではなく魂の真実に肉薄するのだ。
しかも、その語り口はユーモラス。〈父は格闘技を観るのが好きで、母は格闘するのが好きだった〉という冒頭の語りから、吹き出してしまう箇所多々あり。ユーモアもまた、悲しみや怒りといった感情を心の中に〈封じ込める〉のではなく、〈生かし続ける〉ための大切な術だということに気づかされる筆致なのだ。一筋縄にはいかない作家って、やっぱイイ、すごくイイ。
【新版】
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
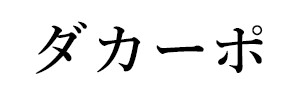
- 2002年9月18日
ALL REVIEWSをフォローする








































