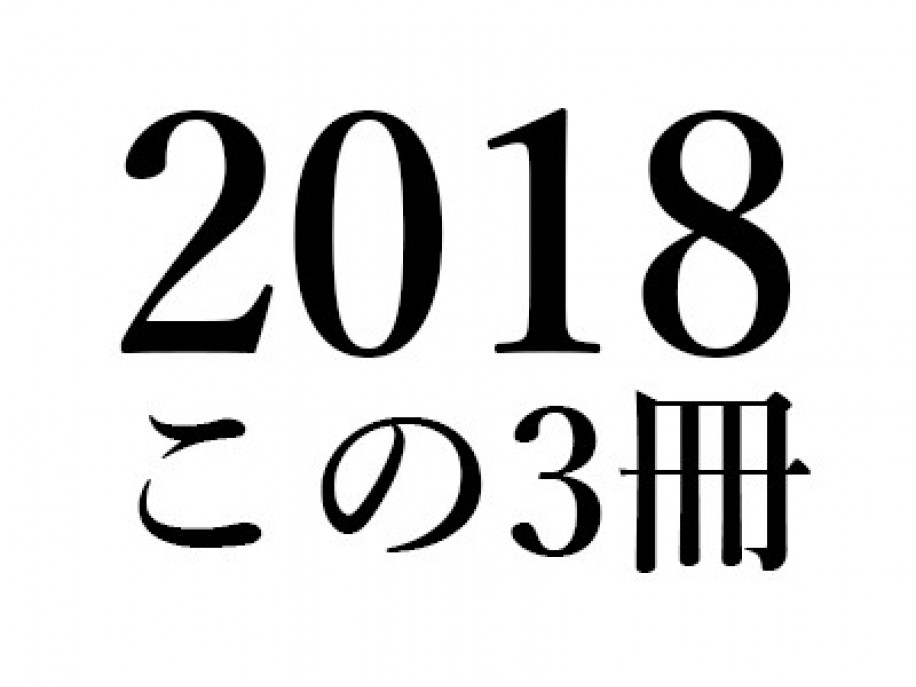書評
『いちばんここに似合う人』(新潮社)
脈打つような十六人分のパーソナル
脈打つ、というのが、この本を読んで頭に浮かんだ言葉だった。脈打つような小説、というのが。パーソナル、というのが、次に浮かんだ言葉だ。しかも二重にパーソナル。なぜ二重かというと、一つ目はまず中身。この短編集には全部で十六の小説が収められていて、そのほぼすべてが(一編だけ例外があり、「その人」というタイトルのその一編は、形として三人称で書かれている。けれど実質的には、作中で語られる“その人”よりも、誰であれ語っている“話者”の内面の方が映しだされる小説であり、その意味ではこれも、例外ではないといえるかもしれず)、一人称で書かれているのだが、全編、人の意識の内側を見せるような小説なのだ。つまり十六人分のパーソナル。長年の知己とか家族とかにも見せない(見えない)部分を、彼らは読者に見せてくれる。
一見風変りな、けれどおそらく誰でもがそうである程度にねじれた普通の人々が見せる自分と他者、自分と世界。人は、誰しもこんなにも独特で、こんなにも一人ぼっちなのだという普遍。
友人に、妹を紹介してやるとたびたび言われ、会ったこともないその妹に恋をしてしまう老人と、彼に、妹を紹介すると言い続けるもう一人の老人と、を描いた「妹」にしても、うまくいかなくなった夫婦が、ごく些細(ささい)なある経験を共有することによって、思いだす何かと、その先にたどりつく場所(抽象的な言い方でごめんなさい。具体的なことは読めばわかります。美しくてかなしい話です)、を描いた「モン・プレジール」にしても、海も川も湖もプールもない町で、三人の老人に水泳を教えた若い女の記憶をめぐる「水泳チーム」にしても、読んでいて一編ずつ虚をつかれる。これまで誰にも言わずにきたこと、あるいは忘れていたこと、がそこに書かれていると感じてしまう。リアリティの在りどころ、にぶれがないせいなのだろう。
同性愛者である若い女の子の、奔放といえば奔放な、切実で誠実で不器用で、微笑ましく勇敢な日々を綴った「何も必要としない何か」も、どう考えても名作だと思われる「子供にお話を聞かせる方法」も、とても他人事とは思えない。
これらの短編を読むと、物語はつくられるものではなく、発掘されるべきものだ、ということがよくわかる。小説は著者が書くので、著者によってつくられるものだ。でも物語は違う。
ミランダ・ジュライは物語の発掘能力に長けた作家だ。そして、そのことが二つ目のパーソナルを生んでいる。十六編全部に、著者の世界観、人間への眼差しが感じられて、たとえばきわめて性能のいいレンズ、としての作家の、息づかいがそこにいきいきとあるのだ。見る、ということ、待つ、ということ、そもそもの初めからそこにあったはずの物語が、顔をだすその瞬間をとらえる、ということ。
ミランダ・ジュライが映画監督で(「君とボクの虹色の世界」という、可笑しくもやさしい映画を撮った人です)、現代美術のインスタレーションも手がけていることと、それは無関係ではないだろう。彼女のそういう側面が、小説のあちこちをとてもいい形で光らせていて、たとえば手作りのキモノ風ローブを着た女たち(「十の本当のこと」)、たとえば駆けていく小さな茶色い犬(「マジェスティ」)といった、ストーリーの外側、消えていく景色、が見事に鮮烈な印象を残す。
ALL REVIEWSをフォローする