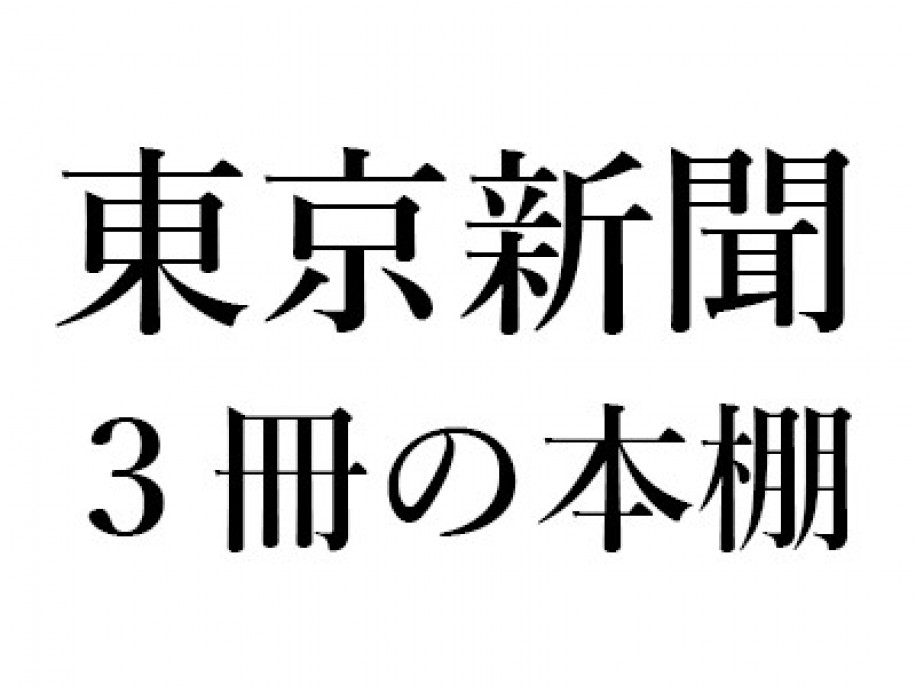書評
『デクリネゾン』(ホーム社)
感情ではなく感覚を伝える凄まじさ
古いものを持ちだして奇妙だと思われるかもしれないが、カポーティの『ティファニーで朝食を』とか、有島武郎の『或る女』とか、ジョン・ニコルズ『卵を産めない郭公』とか、マーガレット・ミッチェル『風と共に去りぬ』とか、小説の魅力と女性主人公の魅力が不可分な小説というのが確かにあって、本書『デクリネゾン』も、その系譜に連なる一冊だと思う。主人公の志絵は小説家で、離婚を二度していて、大学生の恋人と中学生の娘がいる。次々に恋をする女で、離婚も彼女の浮気が原因だった。が、悪女とかちゃらんぽらんというのではなくて、この人はこわいほど真面目なのだ。こわいほど真面目で、誠実。だからこそ、こういう生き方になってしまう。厄介。そして、小説の主人公として、きわめて魅力的だ。そんな彼女の暮らしぶりと思考のすじみちが丁寧に描かれ、感情ではなく感覚が、まるで自分のそれをむきだしにされたかのように伝わってくる。感情ならば説明も共有も可能だが、感覚は違う。それを、言語を使った肉体的な解剖みたいに小説にしてみせる金原ひとみの凄まじさ! もともとセンシュアルな小説を書く人ではあったけれど、『アンソーシャル ディスタンス』にしても『アタラクシア』にしても、最近のこの人の小説は解剖の精度が高く、言葉の奔流のいきがよくて、読んでいて陶然となる。
志絵をめぐる男たちも、作家仲間の女たちも、成長していく娘も、それぞれの時間と感覚を生きていて、どんなに大切だとしても他者だ。夫とか元夫とか親子とか親友といった言葉に規制(もしくは矯正、あるいはいっそ邪魔)されることに抗い、そういう言葉に安心(もしくは慢心)することにも耐えられず、他者とただまっすぐに向かい合いたいと願う志絵の、切実でスリリングな闘い――。
孤独や不安、守りたい相手がいることの蜜のような甘さと不自由さ、その恐怖、傷つけたくはないが誤魔化したくもないというある種の潔癖さ、といったざわざわする息苦しさに満ちた小説なのだが、だからこそときどき奇跡のように(あるいは闘う彼女への恩寵のように)訪れる幾つかの瞬間の尊さと美しさに虚を突かれる。これから読む人の喜びを奪いたくないので説明は避けるが、バドミントンとか、ヘアドライヤーとかチン横とか。ああ、こういうことがあるから人は生きていかれるのだ、と思う。
ところで、小説の魅力と女性主人公の魅力が不可分な小説には、特徴が一つある。それは時代性を抜きには語れないということで、この本にも、すみずみまで、いまという時代が新鮮な血液みたいに流れている。最近は教養小説という言葉を聞かなくなったけれど、映画や小説をめぐる解釈の差や議論や、コロナによる生活の変化やリモートの善し悪しについての考察、若者言葉に対する年長者の所感から、どんなピザの注文のし方がモテるかまで、登場人物たちがみんな実によく喋るので、この本には現代版の教養小説とでも呼びたいような側面もあり、読んでいて愉しい。さらに小説を構成する一要素としてさまざまな料理が見事な描写力で登場し、読み手の五感と食欲と妄想力を揺さぶる。その意味でもすばらしくセンシュアルな一冊なのだった。
ALL REVIEWSをフォローする