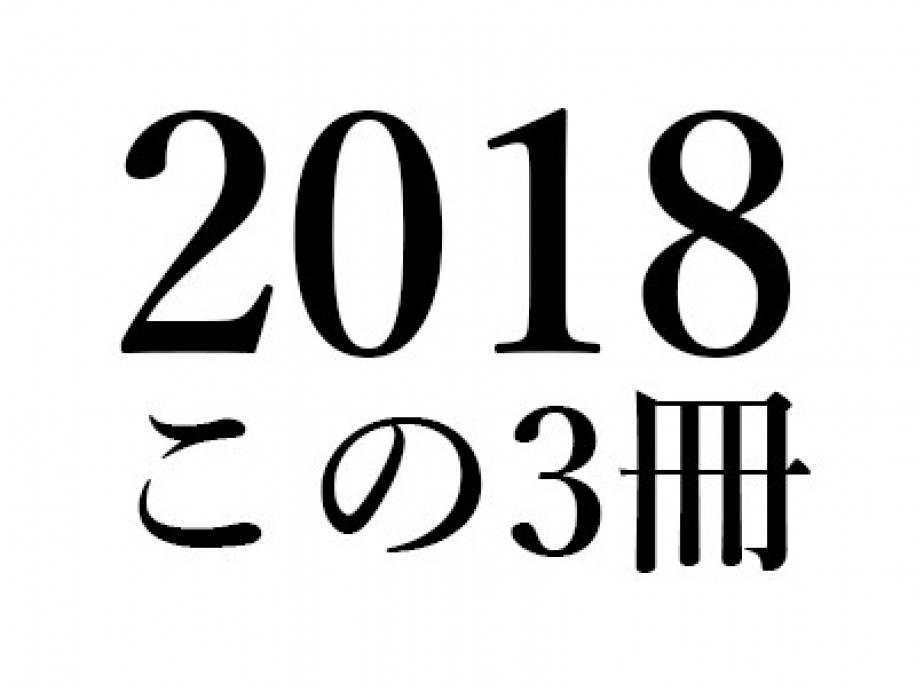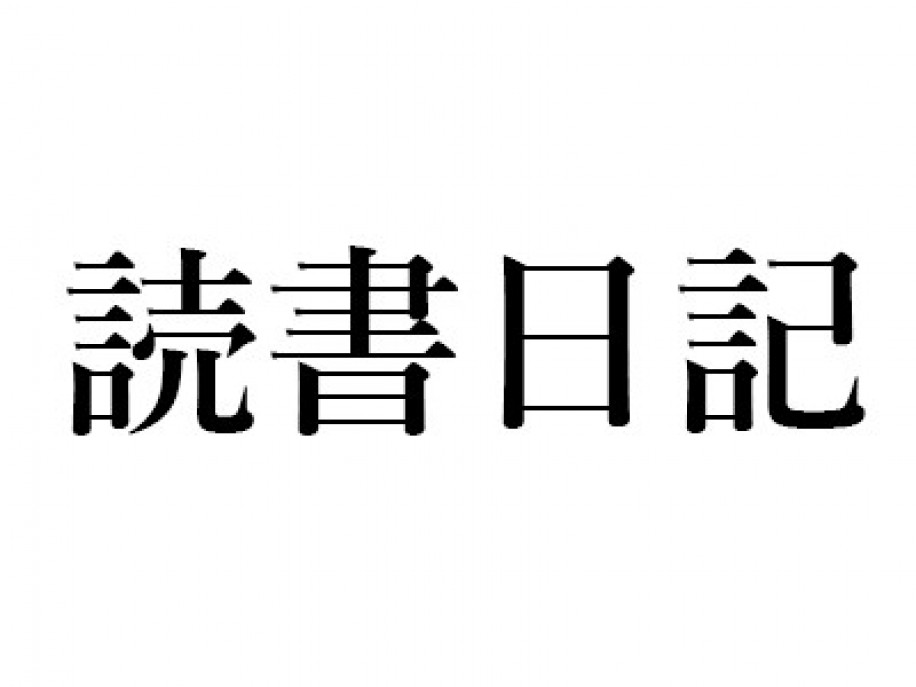書評
『ノリーのおわらない物語』(白水社)
『綴方教室』(岩波文庫)ってご存じですか?昭和初期の東京下町に暮らすブリキ職人一家の生活を、小学生の豊田正子さんが綴った作文集なんですけど、これがもう舌を巻くほど上手なんです。たとえば、近所に住んでいたきつねつきのおばさんが、毎晩のように訪ねてきて困ったことを書いた一編。
〈そのうちに、黒いかげがうすく障子にうつッたと思ったら「ヒヒヒヒ」と、のどこえで、きみ悪く笑いながら、さかいの障子をガラリと開けました〉〈おばさんは、手をだらりと畳の上について、「ねえ、おかみさん。わたしね、天国へ行きたいと思うの。オッホホ」と、又きみわるく笑いました〉〈口をあけると、きたない、みかん色のはがずっとならんで見えて、なおきみがわるいのです。電灯が、おばさんの頭の上にあって、うすぼんやりと光がさしていて、おばさんのかみの毛が黒びかりにひかっています〉
読み手にも〈きみのわるさ〉がリアルに伝わる観察眼と描写力。豊田さんはとても目と耳がいいんですよねー。世の中には子供を語り手にした小説って幾らでもありますよね。けど、ごく一部の優れた児童文学をのぞけば、豊田さんの作文と比べて、大人である作者が都合よく捏造した子供語りにすぎないんです。そしたら――、この本を読んでびっくり。だって成功してるんだもん、本物の子供語りに!
語り手は九歳の女の子ノリー。これは、アメリカからイギリスに引っ越してきたばかりのノリーが、日々の生活の中で見聞きしたことや感じたこと、考えたことを、転校先の学校での出来事を中心に綴った五四の短い章で成っている物語なんです。ちょっと面白いのが、叙述のスタイル。普通この手の小説は「あたし」とか一人称を採るものなんですけど、お話を作るのが大好きなノリーは、自分を三人称に見立てて語ってるんです。そのことによって、ところどころに挿入されているノリーが作ったお話と、ノリーが実際に体験したことが、同じくらいの現実感覚を持つことになり、それってよく考えてみると、想像と現実をごっちゃにしやすい子供の思考の特徴だったりするんですよね。
ほんの何十秒かの間に一人の男の脳裏によぎるさまざまな事柄を、微に入り細をうがつ描写で綴った究極の心理小説にして脚注小説『中二階』、テレフォン・セックスを題材にした前代未聞の電話小説『もしもし』など、海外小説ファンに人気の高い作家、ニコルソン・ベイカー。その電子顕微鏡的観察眼と、‟神は細部に宿る”式の徹底したディテール描写によって、ベイカーは文学史始まって以来の、大人の作家による完全なる子供語りに成功しているのです。子供の脳内世界は混沌としていてとりとめもないから、一貫したストーリーが流れているわけではないし、学校、お父さんとお母さんと弟のチビすけがいる家、時々家族と訪れる古いお屋敷や聖堂、それが世界のすべてだから、現実世界で何か大事件が起きるわけじゃありません。なのに、というか、だからこそ、ものすごく面白いんです。
話したいことが山ほどあるのに、能力がそれについていかないから「あのね、あのねっ」と気持ちが前のめるばかりで、話を首尾一貫させることができず、ちょっと難しい言葉を使おうとしちゃ間違って、話題があちこちに飛んでしまいがちで――。キュートな言い間違え(「朝めしさいさい」「これにて一件着陸」「煮ても立っても座れない」などなど)がちりばめられたノリーの語り(岸本佐知子さんの訳が超可愛いっ!)は、まさに子供そのもので、その語りのリズムに身を任せているうちに、なんというか、自分も子供返りしてしまうというか、そんなこそばゆい現象が起きてしまうのです。あー、ベイカーに『綴方教室』を読ませてあげたいっ。きっと喜ぶと思うんだけどなあ。
【この書評が収録されている書籍】
〈そのうちに、黒いかげがうすく障子にうつッたと思ったら「ヒヒヒヒ」と、のどこえで、きみ悪く笑いながら、さかいの障子をガラリと開けました〉〈おばさんは、手をだらりと畳の上について、「ねえ、おかみさん。わたしね、天国へ行きたいと思うの。オッホホ」と、又きみわるく笑いました〉〈口をあけると、きたない、みかん色のはがずっとならんで見えて、なおきみがわるいのです。電灯が、おばさんの頭の上にあって、うすぼんやりと光がさしていて、おばさんのかみの毛が黒びかりにひかっています〉
読み手にも〈きみのわるさ〉がリアルに伝わる観察眼と描写力。豊田さんはとても目と耳がいいんですよねー。世の中には子供を語り手にした小説って幾らでもありますよね。けど、ごく一部の優れた児童文学をのぞけば、豊田さんの作文と比べて、大人である作者が都合よく捏造した子供語りにすぎないんです。そしたら――、この本を読んでびっくり。だって成功してるんだもん、本物の子供語りに!
語り手は九歳の女の子ノリー。これは、アメリカからイギリスに引っ越してきたばかりのノリーが、日々の生活の中で見聞きしたことや感じたこと、考えたことを、転校先の学校での出来事を中心に綴った五四の短い章で成っている物語なんです。ちょっと面白いのが、叙述のスタイル。普通この手の小説は「あたし」とか一人称を採るものなんですけど、お話を作るのが大好きなノリーは、自分を三人称に見立てて語ってるんです。そのことによって、ところどころに挿入されているノリーが作ったお話と、ノリーが実際に体験したことが、同じくらいの現実感覚を持つことになり、それってよく考えてみると、想像と現実をごっちゃにしやすい子供の思考の特徴だったりするんですよね。
ほんの何十秒かの間に一人の男の脳裏によぎるさまざまな事柄を、微に入り細をうがつ描写で綴った究極の心理小説にして脚注小説『中二階』、テレフォン・セックスを題材にした前代未聞の電話小説『もしもし』など、海外小説ファンに人気の高い作家、ニコルソン・ベイカー。その電子顕微鏡的観察眼と、‟神は細部に宿る”式の徹底したディテール描写によって、ベイカーは文学史始まって以来の、大人の作家による完全なる子供語りに成功しているのです。子供の脳内世界は混沌としていてとりとめもないから、一貫したストーリーが流れているわけではないし、学校、お父さんとお母さんと弟のチビすけがいる家、時々家族と訪れる古いお屋敷や聖堂、それが世界のすべてだから、現実世界で何か大事件が起きるわけじゃありません。なのに、というか、だからこそ、ものすごく面白いんです。
話したいことが山ほどあるのに、能力がそれについていかないから「あのね、あのねっ」と気持ちが前のめるばかりで、話を首尾一貫させることができず、ちょっと難しい言葉を使おうとしちゃ間違って、話題があちこちに飛んでしまいがちで――。キュートな言い間違え(「朝めしさいさい」「これにて一件着陸」「煮ても立っても座れない」などなど)がちりばめられたノリーの語り(岸本佐知子さんの訳が超可愛いっ!)は、まさに子供そのもので、その語りのリズムに身を任せているうちに、なんというか、自分も子供返りしてしまうというか、そんなこそばゆい現象が起きてしまうのです。あー、ベイカーに『綴方教室』を読ませてあげたいっ。きっと喜ぶと思うんだけどなあ。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
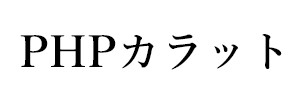
PHPカラット(終刊) 2004年11月号
ALL REVIEWSをフォローする