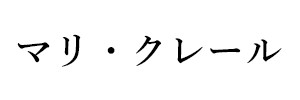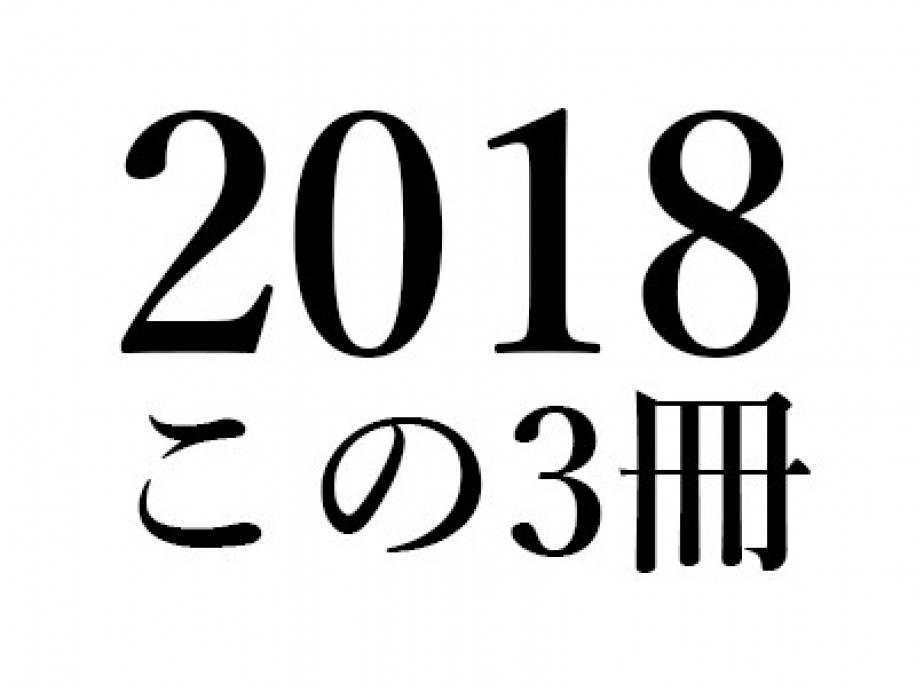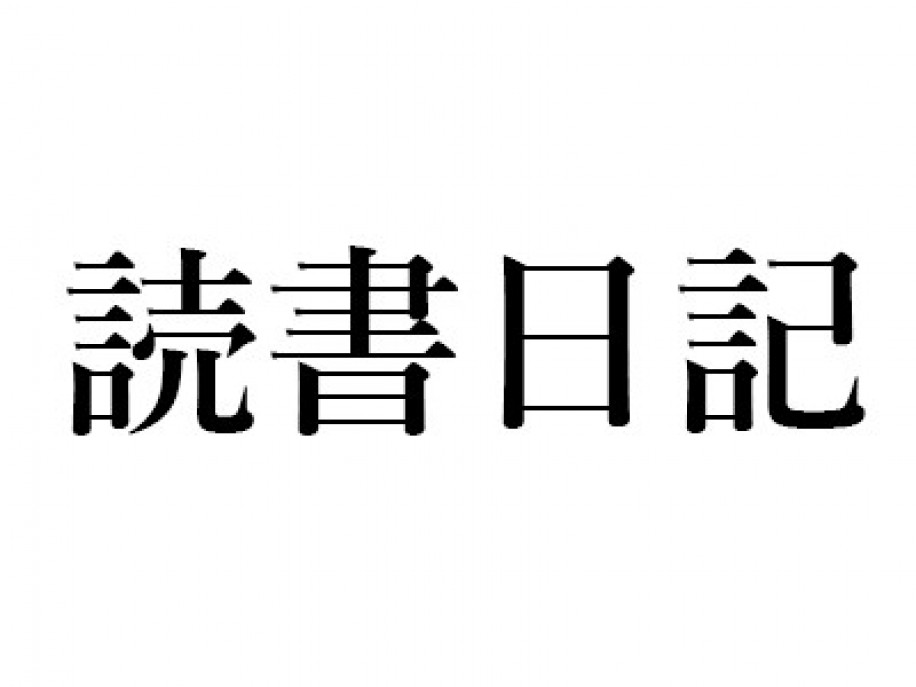書評
『中二階』(白水社)
中途半端な空間
ニコルソン・ベイカーの『中二階』は、語り手の「私」が昼休みを終えてオフィス・ビルの中二階にある仕事場ヘエスカレーターで戻るまでの数十秒を、日常の些事ともいえぬ些事に関する省察で埋めてみせた、奇妙な物語である。本書を開いてただちに目につくのは、膨大な脚注だ。小さな活字がならぶ欄外は、ときに本文を浸食しつつ勢力を増し、紙面の大半を占拠する。「行き当たりばったりで惜しげもない脚注のつけ方」に共感する語り手は、ご丁寧にも脚注の意義を説くための脚注まで設けているのだが、大切なのはむしろ欄外に目をやるタイミングである。そこだけまとめて読むべきか、本文と交互に読むべきか、交互に読むとしたら、どこで本文を中断して注に移るべきか。基準があるようでいてなく、結局のところどこから読んでも構わないこの脚注の柔軟性は、仕事中つねによそ事を考えているような「私」の態度と相似形を描いている。
エスカレーターの楽しさと安全性、ストローの歴史、レコードの溝とスケートでできる溝との関連、靴紐の耐久性と磨耗、パック牛乳の出現と牛乳配達の衰退、ポップコーン製法とその発明者、靴下のはき方、会社におけるトイレの意味、耳栓、ホッチキス、バンドエイドの糸。少年の驚きと徹底した細部への執着をもって、「私」は思うさま、脱線に脱線を重ねながら語りつづける。そのつど小出しにされる彼の素顔をひろい集めてみると、名前はハウィ、一九五七年生まれで現在三十歳の独身、妹がひとりいて、両親は離婚しているらしい。Lとだけ記され、彼の思考に登場する「頻度率」トップにランクされた恋人もいる。本文から得られるこれらのデータは、しかし次々に横滑りしていく話題にまぎれて巧みに感情を抜き取られており、語り手の過去や私生活について、じゅうぶんな情報を与えてはくれない。
その欠けた部分を補ってくれるのが、一見いらぬお喋りにしか映らない脚注の部分なのである。そこにはあたたかみのある挿話が、いくつも無造作につめこまれている。たとえばTシャツの着方に関して述べられた部分からは、少年時代の彼の姿がほんのりと伝わってくるし、ドアノブとネクタイをめぐって展開される、数頁におよぶ長大な注釈は、父親との幸福な関係を語った好短篇ともいうべき出来映えだ。ミシン目のすばらしさを称える頁に付された欄外での高揚ぶりも、世界のすばらしさを歌うホイットマンの詩のように読者に伝染する。
本文と脚注の転倒。ふつうなら寒々とした参考文献の列挙か、あらずもがなの評言ばかりならぶ「注」を、生き生きとした愉快な読み物に変容させたのは作者の手柄だろう。だがこの転倒があまりに軽やかで、あまりに鮮やかなだけに、注釈という手段に訴えざるをえない現在の語り手の姿が、かえって浮き彫りにされてしまう。おびただしい注を持ち前のユーモアで量産し、読者に内面を悟られまいとする寂しげな横顔。無駄話に戯れることが、じつは本当の自分をたえず隠蔽していく恰好の逃げ道だということを、彼はなかば承知しているのではないだろうか。
なにも存在しないはずのところに無理やりつくられた中途半端な空間、一階でも二階でもなく、エレベーターも停止しない不自由な場所。それが中二階だとするなら、本文でも余白でもない脚注とは、いわば書物のなかの中二階であり、逸脱を旨とした中二階的哲学の実践の場である。たしかに「哲学の実践に最も適した人生の場面は、今日という日の諸君の生活の有り様なのだ!」と述べるマルクス・アウレリウスの言葉ほど、語り手にふさわしいものはない。たとえその哲学が、自己を絶えず分散させずにはいられない孤独な生活から、しばし逃れる彌縫策(びほうさく)にすぎないとしても。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする