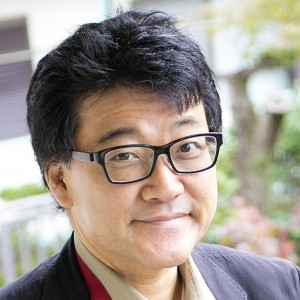書評
『さくらんぼの性は』(白水社)
ジャネット・ウィンターソン(Jeanette Winterson 1959- )
イギリスの作家。第一長篇『オレンジだけが果物じゃない』(1985)が、イギリスでその年の最優秀処女作に与えられるホイットブレッド賞を受賞し、さらにBBCでドラマ化されて一躍脚光を浴びる。『ヴェネツィア幻視行』(1987)も高い評価を獲得し、『さくらんぼの性は』(1989)もベストセラーとなった。そのほかの著作に『恋をする躰』(1992)、『永遠を背負う男』(2005)などがある。introduction
思考が短絡するぼくは、『さくらんぼの性』をフェデリコ・フェリーニの映像で読んでいた。そう、主要登場人物のドッグウーマンに、「フェリーニのアマルコルド」や「女の都」などに出てくる生命力に満ちあふれた重量級の女性たちをスーパーインポーズしているのだ。また、主人公ジョーダンが行きつく街の、どことなくチープな質感が、フェリーニが銀幕に映しだす世界のようである。おなじイギリスの現代女流作家でもうひとり、ぼくがフェリーニ的だと思うひとがアンジェラ・カーターで、こっちは単純に『夜ごとのサーカス』と「フェリーニの道化師」というつながりだ。ウィンターソンもカーターも想像力に大胆さとキメ細かさを併せもっている作家だから、やっぱりフェリーニ的といってもそう外れじゃない……と思う。▼ ▼ ▼
空想のなかの街がある。ボストン、マドリッド、チューリッヒ、バンコック、シンガポール、香港。地図で見たときに思い描いていた街並み、到着する寸前までゆっくりと膨らんでいたイメージ。だが空港に降りたとたん、架空の街はすうっと消えていく。とたんに押しよせる、異国の色彩、匂い、ざわめき。現実の温度に圧倒されながら、トランクを引きずってクルマを探す。旅はいつでも、そんなふうにはじまる。
現実の街に失望しているわけではない。それどころか、およそどの街も、ぼくの想像がおよばないほどの魅惑を秘めている。大きな街路から細かい路地まで合わせた距離の膨大さ、おびただしい戸口や窓の数、見知らぬ略号・標識、まるで迷路だ。その迷路を経めぐりながら、ふと空想の街を思いだす。あれはなんだったのだろうか。もうひとつの旅、ありえたかもしれない旅。
『さくらんぼの性は』で、主人公のジョーダンがたどるのも、そんな“もうひとつの旅”である。
僕は気がついたのだ。僕の中には、見えないインクで綴られていて、現実に押しやられ、ちょうど夜ごと窓からはばたいて、朝、服も履物もぼろぼろにして戻ってきたときには何も覚えていないあの十二人の踊る王女のように、いつも僕を置いてどこかへ飛んでいってしまうもう一つの人生があると。
ジョーダンはテムズ川で拾われ、象すらぶっ飛ばす大女ドッグウーマン(彼女は犬を育てては売って糧を得ている)に養われた。ときは十七世紀の半ば、おりしもピューリタンの勢力が台頭しつつあるころ。成長した彼が王室の庭師の職を得たのもつかの間、チャールズ王はクロムウェルの軍に捕えられ、ジョーダンも船乗りになって国外へ脱出するはめになる。いや、ピューリタンからの逃亡というよりも、もともと彼のなかには旅への衝動がひそんでいたのだ。ドッグウーマンは「あの子は水から来たのだから、いずれまた水が取りもどしにくるのははじめからわかっていた」と言う。
航海は長い期間におよび、ジョーダンはさまざまな異国の風物を目にするが、どの土地にいっても彼は満たされない。海のうえ、船がかすかに軋み、同室の相棒が寝息をたてている。そんな夜、ジョーダンは街のことを想う。
その街では、人々の言葉が空高くあがり、厚い雲となってたれこめる。だから掃除人がモップやブラシで言葉を拭いさらなければならない。ジョーダンはこの街で知りあった女性の掃除人から、木箱に閉じこめたソネットをもらった。
あるいは、こんな街もある。恋の猛威に三度もたてつづけに襲われた街。生き残ったのは、僧侶と娼婦だけ。ふたりは、今後この街では恋を禁じることに決める。彼と彼女は体力が許すかぎり交わりつづけ、ふたたび街を人でいっぱいにすることができた。だが、街を訪れたジョーダンがギターをかきならしたため、ふたたび恋の疫病が蔓延してしまう。
ジョーダンは、街全体が踊っている銀の都も知っている。最初はほんのかすかな振動だったのが、しだいに大きくなり、やがて重力から解放され、空を漂いながら踊りつづけている街。十二人の王女は夜ごと、この天空の都に踊りにでかけたものだ。しかし、王女たちの夜遊びはとうとう王様に知られてしまい、怒った父君によって鎖につながれた彼女たちは、十二人の王子のもとにひとりずつ娶られていった。その後それぞれに数奇な運命が待ち受けているのだが(それは王女一人ひとりがジョーダンに語って聞かせてくれる)、けっきょくは十一人の王女が一緒に暮すことになる。
その王女たちがいま住んでいるところも、かなり奇妙な街だ。住民は一夜のうちに自分の家を壊し、別の場所に建てなおす。街全体の戸数は一定なのに、ひとつとして前の日とおなじ場所に建っている家はない。
ところで、十二人目の王女はいったいどうしたのだろう? じつは、彼女こそジョーダンが追い求める〈真実〉なのだ。名前はフォーチュナータ。
一方、真実などわざわざ捜しもとめる必要のない人物もいる。ジョーダンの育ての親ドッグウーマンだ。彼女の論理は単純明解である。王党派の説教師に「目には目を、歯には歯を」と言われれば、ピューリタンたちの目玉をえぐり、歯を引っこぬいてしまう。兵隊たちが銃で打ってもへいちゃら。胸で弾を受けとめ、「か弱い女の着るものを台なしにするなんざ、紳士のすることじゃないね」と凄む。若いころ、一度だけ男とつがったことがあるが、力を入れたとたん、男を体のなかに吸いこんでしまった。そのときは、かなてこで男を引っぱりだしたのだという。
ジョーダンが旅する街は精緻なカルヴィーノの世界を連想させるが、ドッグウーマンのたくましい活躍はラブレーのガルガンチュアばりだ。彼女は息子のジョーダンをとても愛しているが、彼が遠い旅に出たからといって涙にくれるわけではない。彼女の愛は、そんなにヤワなものではないのだ。彼女には躊躇も後悔もない。どんな権力にもひるまない。ドッグウーマンにとっての真実は、すべて彼女の内にある。
ジョーダンとドッグウーマンの個性は時空を越え、現代にあらわれる。船に憧れ海軍に志願する青年ジョーダンと、意識のなかに大女が住みついた女性化学者(彼女は環境汚染を黙認する体制に孤高の闘いを挑んでいる)。現代と十七世紀がオーバーラップしてゆくクライマックスは、ジョーダンが探していた王女フォーチュナータとふかく関連してくる。そして、ジョーダンはドッグウーマンのもとに帰り、現代のふたりも運命的な出会いを果たす。しかし、ジョーダンの「もうひとつの旅」は? 彼は求めていた目的地にたどり着くことができたのだろうか?
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする