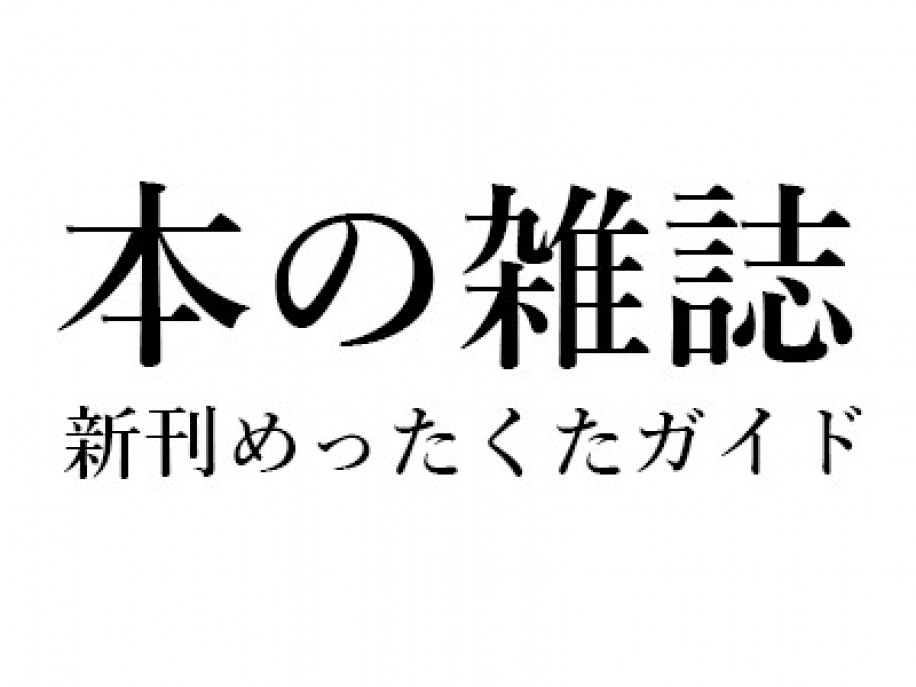書評
『豚の死なない日』(白水社)
「もののけ姫」あるいは万人の感動
宮崎駿(みやざきはやお)の新作「もののけ姫」は当然のことながら予約をいれ、公開早々見にいった(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1998年ごろ)。「ナウシカ」も「ラピュタ」も「トトロ」もそうやって見た。宮崎教の信者としては当然の行為であろう。予告編が終わり、「もののけ姫」がはじまるとあちこちから拍手が起こった。レース前のファンファーレが鳴るだけで拍手がわく最近のGIレースの競馬場のようだ。思わず、わたしまで拍手しそうになった。さて、もちろん「もののけ姫」はたいへん感動的であった。北の地の果てに住む若者アシタカは勇気があり、山犬に育てられた少女サンは美しく健気で、自然を代表する荒ぶる神々たちには人間と戦う理由があり、またエボシ御前を代表とする人間たちにも森を切り拓き自然を破壊する理由がある。悪も善も純度一〇〇%どころかせいぜい三〇%がいいところでジコ坊のように善悪の彼岸のような登場人物も現れ、シシ神は滅び、その結果自然は蘇るが、それは太古のそれとは異なる人間化された自然なのだというメッセージのあたりでマルクスを思い出してしまうのはわたしが古い人間だからだろうか。そういうわけで、一度映画を見たら頭にしみついてしまう主題歌をできる限りの高音を駆使して歌いながら(「♪はりつめた弓の ふるえる弦よ 月の光にざわめく おまえの心♪」)帰途についた。家に帰っても興奮さめやらず、ああいうのを万人が感動する映画というのだろうか、それにしても万人が感動するといっても中には感動しない人もいるだろうに、あっさり感動してしまう自分は万人さんなのだなあと考えていると眠れなくなった。電気をつけて机に向かうと、『豚の死なない日』(ロバート・ニュートン・ペック著、金原瑞人訳、白水社)があった。帯によれば「全米150万人が感動した大ロングセラー」で「第43回青少年読書感想文全国コンクール課題図書」なのである。なにを隠そう、わたしは必ず「課題図書」を読むことにしている。感動的なものが多いからだ。わたしは「もののけ姫」の余韻にひたりつつ『豚の死なない日』を読んだ。主人公は十二歳の少年で、貧しい家に育って家の仕事を助け、お父さんは病気気味で、唯一心を許していたペットの豚を生活のために殺さなければならないのである。おお……これって、豚を鹿に替えると『子鹿物語』そのものではないかと思ったが、そんなことで感動の量が減るはずもなく、クライマックスの豚のピンキーを殺すシーンでは絶対泣くだろうと思っていたらほんとうに全米150万人と共に泣いてしまったのだった。それにしても『豚の死なない日』や「もののけ姫」はなぜそれほどまでに万人を感動させるのか。第一に考えられるのは、どちらも無垢な動物が可哀そうな目にあうからである。それを見て、無垢な少年少女が傷つくからである。
もしかしたら、それは遠い昔、人が自然に対して無力だった頃、荒ぶる神さまを宥(なだ)めるため動物を殺して差し出したことを無意識のうちに思い出させるからだろうか。そして、もう一つ気づかれるべきなのはこういう物語では主人公の少年少女がたいてい肉体労働に従事していることだろう。自然を失った人間が唯一自然と交感できるのは労働を通してなのだと書いたのはやはりマルクスだった。労働は厳しいが、そこには失われた自然の痕跡があることを人に思い出させるはずではないか――かつて肉体労働を十年やり現在は精神労働(?)に従事しているわたしはそう思うのである。
少年少女には「心の教育」より労働の機会が必要なのかもしれませんね。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする