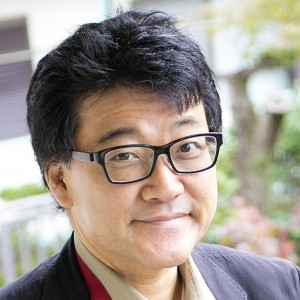書評
『世界の終わりのサイエンス』(早川書房)
トマス・パーマー(Thomas Palmer 1955- )
アメリカの作家。長篇『密輸人』(1983)でデビュー。これは、マイアミを舞台にコカインの密輸に携わる人々を描いた作品で、第一級のクライム・ノヴェルとして高い評価を得た。『世界の終わりのサイエンス』(1990)は第二作にあたる。いまのところ、パーマーの出版された小説はこの二作だけのようだ。アマチュアのナチュラリストとしても熱心な活動しており、Landscape with Reptile(1992)という著作もある。introduction
早川書房は、ぼくがずっとお世話になっている版元である。SFブランドはもちろん、それ以外でも面白い作品がたくさん出ている。とくにエンターテインメントとも主流文学ともつかない領域で、不思議な味わいの傑作を紹介してくれるのがありがたい。ただ惜しむらくは、そういうジャンル無用の作品が、往々にして評判にならぬまま埋もれてしまうことだ。思いつくままにあげると、ルードルフ・ブラウンブルグ『アフリカ夢の飛翔』、クリストファ・フランク『モルテル―愛の寓話―』、モーリス・ポンス『マドモアゼルΒ』、ロベール・メルル『マドラプールに消えた』……。ここに紹介するトマス・パーマー『世界の終わりのサイエンス』もそんな一冊だ。オフビートの不条理劇と思いきや、サム・ライミはだしの即物的恐怖が画面いっぱいに飛びだす。ちょっと類がない。▼ ▼ ▼
最初は日常のほんの片隅の、ふとした違和感。それが大きな異変につながっていく。たとえば、雨のなかをクルマで走りながら、ふと横を見ると、一か所だけ陽があたって輝いているところがある。光のなかにムラがあり、近づいても最初はちょっとした汚れのようにしか見えない。しかし、その存在を感じ、またぎ越したとき、あなたは別な世界へ転移してしまう。それが境界線だ。
『世界の終わりのサイエンス』の設定は、サイエンス・フィクションが常套としてきた「次元の裂け目」「異世界への門」と、ほとんどおなじものだ。ただし、境界線はただ現実世界と異世界、日常と非日常を区切っているだけではない。物理的意味であると同時に、登場人物の精神の亀裂、そして物語の断層に相応している。
主人公のプールは最初、それとは気づかずに境界線を越えてしまう。迷いこんだのは、見知らぬ個室である。飾りのない白い壁、黄緑の絨緞、最低限の家具、ドアのむこうには廊下があるが、それは部屋をぐるりと取りかこみ、出口はひとつもない。サムと呼ばれる監視人がひとり、毎朝どこからともなくあらわれ、晩にはどこかへ帰っていく。トマス・M・ディッシュの短篇「リスの檻」にそっくりな状況だが、その不条理はやがて解消される。プールは監禁されていたのではなく、どうやって出たらいいかを知らなかっただけなのだ。いまいるのは、この個室だけの閉じた世界であり、外は存在しない。別世界につづく境界線だけが、ただひとつ出口なのだ。
境界線はだれにでも見つけられるものではなく、ある種の素質が要求される。そのうえ、能力があるからといって、自由自在に操ることができるわけではない。ひとたび境界線を越えてしまうと、後戻りすることは困難。断片化した小世界が無数にあり、ひとつの小世界で一生を終える者もあれば、移動を繰りかえす者もある。プールがもともと暮していた〈現実〉は、もっとも大きな小世界だ。移動者のほとんど(全員?)は、プールと同様〈現実〉の住人だったのが、ある日突然、境界線を越えてしまったのである。分断された小世界を統括するためにパンロゴという一種の治安警察が組織されているが、無数にある世界を行きかう略奪者はとても防ぐことができない。
パンロゴは、プールに特殊な能力があると信じている。というのも、彼が最初に移動した個室のような狭隘な小世界は、これまでに存在が確認されたことがなかったからだ(彼は移動したのではなく、意識せずに自分だけの世界を創りだしたのかもしれない)。サムの助けにより、プールは境界線を見いだすすべを習得する。そして、彼の特異性が証明される。境界線を越えたプールが到着したのは、もといた世界、つまり現実の世界だったのだ。不可能とされていた「後戻り」に成功したのである。
妻のカーメンと赤ん坊のリュサンダ。変わらない日常が帰ってきた。疑問は残る。なぜ彼だけが現実に戻ることができたのだろう。しかし平和な日々は長くはつづかず、ふたたび彼は、知らずのうちに境界線を越えてしまう。それは恐ろしい遍歴のはじまりだった。
何回か転移を繰り返すうちに、現実と似た世界にも出会う。戻ってきたのだと喜び、家に入る。居間には娘を膝に乗せたカーメン、妻の兄ジョジーがテレビに見入っている。プールは微笑み、部屋に足を踏みいれる。歓迎を期待しながら。だが、彼の姿を見たジョジーは、野球のバットを降りあげ、プールに殴りかかる。どうしたんだ。バスルームに追いこまれた彼は、洗面台の鏡でその理由を知る。濡れた新聞紙のような顔には茶色の斑点が浮きだし、喉元の大きな裂け目から筋ばった肉がのぞいている。プールは死人だった。
抑えたトーンで語られていたストーリーに、B級ホラーまがいの派手なシーンを、こともなげに挿入してしまうあたり、このトマス・パーマーという作家、ふつうのセンスじゃない。不条理と心理的葛藤がこの作品の主旋律だとしたら、そこに通俗的なサスペンス、スリラーという伴奏を巧みに組みあわせることで、独特の響きを創りあげることに成功している。
その響きは、プールの能力の核心が明らかになるにつれ、大きなうねりへと高まっていく。死者として転移したプールはその世界で死を迎え、また別な小世界に転移する。今度は生身として。そうした経験を幾度か繰りかえし、彼はふたたび現実の世界へと戻ってくる。彼はそれまでの経験を妻に話すが、信じてもらえるはずがない。だが、精神科医のワクスマンは、プールの話がただの妄想ではないことを見ぬく。「別な世界はたしかに存在している。(普通の人間が)そこに入りこめないのは精神の緩衝装置のようなものがあって遮蔽効果が働くからに違いない」と、ワスクマンは言う。プール本人は、自分がありふれた生活(唯一の現実)にあこがれていると思いこんでいる。しかし彼のなかには、そこから逃げだそうという衝動が隠れていたのだ。そして、その分裂が破局の引金となる。ワクスマン邸のポーチに、かつて見たこともない鮮明な境界線が出現したのだ。だれの目にも見える輝きが。
プールの心の葛藤にむいていた物語の焦点が、いきなり境界線のスペクタクルへと切りかわる。この作者ならではの大胆な展開だ。主人公(典型的なアメリカ中産階級)の精神のメタファーとして、境界線を理解させたそばから、パニック映画のようなスペクタクルで境界線を“出現”させてしまう。メタファーがひとつの「意味」に固着するまえに、物語の調子をすばやくシフトさせる。残るのは、ザラついた余韻。悪夢のなまなましい感触。
境界線はまばゆい光を放って破裂する。そして物語は、現実と小世界をめぐる息づまるサスペンスと、プールと妻の心理劇を往復しながら、クライマックスにむかう。現実の基盤がゆらいだとき、境界線のむこうから、なにかが侵入してくる……。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする