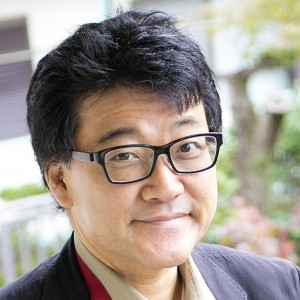書評
『ユニヴァーサル野球協会』(白水社)
ロバート・クーヴァー(Robert Coover 1932- )
アメリカの作家。The Origin of the Brunists(1966)が、もっともすぐれた処女長篇に与えられるウィリアム・フォークナー賞を受賞。第二長篇『ユニヴァーサル野球協会』(1968)と短篇集Pricksongs & Descants (1969)によって、バース、バーセルミ、ピンチョンらと並ぶ、先鋭的なアメリカ文学の書き手として注目されるようになる。そのほかの著作に、『女中(メイド)の臀(おいど)』(1982)、『ジェラルドのパーティ 』(1986)などがある。introduction
ウェブをうろうろしていたら、「ユニヴァーサル相撲協会」というのを見つけてのけぞった。そういう名前のコンピュータゲームを開発した人がいて、試験公開中でダウンロードもできる。わが家の家訓ではゲームとギャンブルが御法度なので、残念ながらプレイできないのだが、なんだか楽しそうだ。開発者によれば、『ユニヴァーサル野球協会』を読み、作中の野球ゲームに刺激を受けて相撲版をつくったのだという。このひとは、この小説の面白さをただしく理解していると思う。もちろん、『ユニヴァーサル野球協会』について、フィクションであることの自覚性とか、マジックリアリズムのアメリカ的展開とか、いろいろ言うことはできる。しかし、読者を引っぱっていく小説のエンジン部分は、主人公が考案した野球ゲームそのものの魅力だ。▼ ▼ ▼
「仮想現実」ということを、ときどき考えてみたりする。
この言葉そのものは、ヴァーチャル・リアリティの訳語として発明されたらしい。ヴァーチャル・リアリティと聞くと、ぼくなどはすぐにゲームや映像アミューズメントを思いうかべてしまうが、技術開発の歴史をたどるなら、軍事や宇宙開発での利用が当初の眼目だったのだという。だから、現実と区別のつかない仮想世界を構成しようというものではなく、あくまで遠隔操作などをおこなううえでの使い勝手が重要視された。そもそも、ヴァーチャルという言葉は「本物や実際とは異なるが、効果としてはそれと同等な」くらいの意味で、「仮想」というニュアンスはない。
しかし、ヴァーチャル・リアリティという言葉が日本に輸入され、マスコミでさんざんに取り沙汰されたときは、もっぱら臨場感や仮想性ばかりが強調されていた。なかには「現実というのは唯一無二のものじゃなくて、テクノロジーで幾通りも構成可能なものなのだ」みたいな、ずいぶん先走った論調もあった。その考え方はまちがっていないけれど、ぼくが知りたいのはそんなことではない。ヴァーチャルやシミュレーションという論議から、くるりと振りむいて「この現実はどうなんだ?」と問いたい。しかし誰に訊けばいいのかがわからない。
現実が真実か仮想かなんてのは、けっきょくは瑣末な問題だろう。それよりもずっと切実なのは、いったいだれの現実なのかということだ。
何者かが操作している現実。フィリップ・K・ディックは、その生涯を通じて、この主題を飽きることなく繰りかえした。あるいは、何者とも特定できないなにか――政治、歴史、神話、自動的なシステム――が現実を動かしているという認識。これは六〇~七〇年代のアメリカ文学が共通して持っていた強迫観念であったし、それはいまだに解消されていない。
ピンチョン『競売ナンバー49の叫び』やバース『やぎ少年ジャイルズ』とほぼ同時期に、ロバート・クーヴァーは『ユニヴァーサル野球協会』を発表している。しかし、超時代的あるいは神話的な小説空間を紡いだピンチョンやバースと、クーヴァーのこの作品とではだいぶ毛色がちがう。
主人公はさえない中年会計士ヘンリー、彼を取りまく日常もきわめて平凡。なにかが現実を操作しているなんて気配すら感じられない。操作しているのはヘンリー自身だ。ただし、現実をではない。彼が操作するのはサイコロだ。
自分で考案した野球ゲーム。八チーム一リーグで、すでに第五六年度を迎える。選手一人ひとりに個性が付与されているばかりか、毎年引退と入団によってメンバーの新陳代謝もある。野球殿堂入りする者、協会の役員として留まる者、愉快な酒場を開いた引退選手もいる。ゲームそのものは、選手の過去の実績に応じたハンデと、三つのサイコロがもたらすの偶然を組みあわせて進行するのだが、その過程でさまざまなエピソードが生まれる。「ブロックのやつはぽっと出の若造だったが、実力でエースの座をつかみ、長いことBクラスに低迷していたパイオニアズを二位に引きあげた」「ジェイクはかつて、一試合五個の二重殺(ダブルプレー)を完成させた立役者(キー・マン)なのだ。その記録はいまなお破られていない」といった具合。
このゲームに興じているときのヘンリーは、まさに目の前で白熱のプレーが演じられている気持ちになる。ぎらつく太陽のもと、ビールで喉を潤しながら観戦している観客のひとりだ。
これこそが仮想現実ではないか。
いままさに世紀の瞬間。新人(ルーキー)デイモン・ラザフォードが完全試合を達成しようとしている。最後の打者、デイモンが投げる(ヘンリーがサイコロを振る)。三塁ゴロ、矢のような送球が一塁へ、アウト。踊りあがるヘンリー。大記録! デイモン・ラザフォード時代の到来だ。
しかし次の試合、とんだアクシデントが起こる。二度続けて一・一・一の出目のあと、デイモンに打順が回ってきた。連続一のゾロ目の次は、大事件一覧表(エクストローディナリイ・オカーランス・チャート)が適応される。次のサイコロも一のゾロ目。一覧表(チャート)はデッドボールによるデイモンの死亡を告げる。このときからヘンリーの人生は狂いはじめる。
ヘンリーが手を伸ばせば出目は簡単に変わる。ひとつのサイコロをひっくりかえすだけのことだ。しかし彼にはできない。自分のつくったルールなのに、自分が操作しているゲームなのに、いや、だからこそ、ヘンリー自身がルールに拘束されてしまう。ユニヴァーサル野球協会は、ほかのだれでもない彼だけの現実なのに、思いのままにならない。ああ、デイモン、十年にいっぺん出るか出ないかのスタープレイヤーよ、とりかえしのつかないことになってしまった。いっそのこと、こんな野球ゲームなどやめてしまおうか。
デイモンの死に打ちのめされたヘンリーは、会計士の仕事もろくに手につかない。遅刻や失敗の連続で上司からは大目玉をくらうし、同僚ルーの慰めも煩わしいばかり。そんなどん底のなか、ヘンリーは気持ちを入れかえてリーグの建てなおしを図ろうと試みる。ところが、興味本位のルーをゲームに参加させたために、とんだ茶番試合が展開されることに……。
あらためて言うまでもないだろう。仮想現実はコンピュータ技術の進歩によってもたされたものではない。人間はどんなものからでも仮想現実をつくりだせるのだ。そう、サイコロが三つあればいい。ただし、いったんできあがった仮想現実は、スイッチを切れば消えるようなヤワなものではない。
この小説は、虚構にのめりこむのもほどほどにという教訓ではない。作者クーヴァーは「人間はフィクションによって生きているんです。そうするしかないんです」と言う。そう、だれもが、それぞれのユニヴァーサル野球協会のオーナーなのだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする